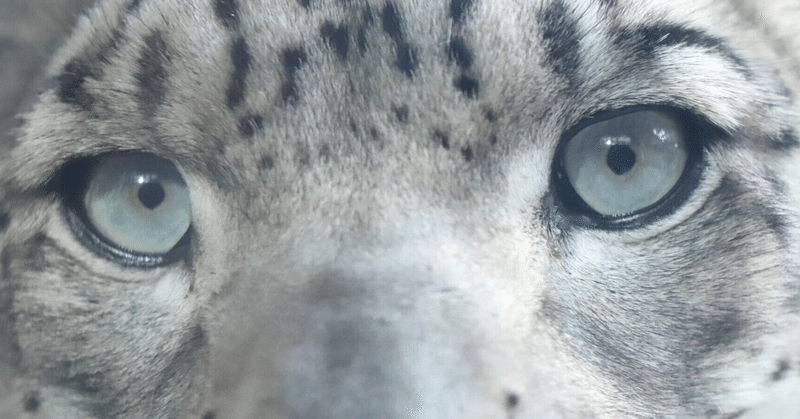
鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎
鬼太郎誕生ゲゲゲの謎を観た。
感染症の流行やらなんやらですっかり遠のいた映画館。ひさびさに足を運んだ。
あまりなじみのないタイトル。行くかどうか本当に迷ったのだが、結果として行って損は無かったように思う。
一番懸念していたのが、男性二人のキービジュアルでアニメ作品であることから、女性向け作品なんじゃないだろうかというところ。
個人的な話になるが、わたしは本当に男性キャラクターというものに興味がなく、その辺をメインに(しかもコテコテに)据えられるとちょっとなあ……と思っていた。
それが「アニメ」であることでまたその可能性が高まる。
ちょっとこの辺は偏見半分なのですが、最近の日本のアニメ作品ではそういう「ウケ」というか刺さる層に露骨に媚びていて、ストーリーよりもそのキャラクターを見るためのイメージビデオであることが多くなっている気がする。というかなんならアニメに限らずほとんどの作品がそうなってしまっているんじゃないかと思うときすらある。
キャラ萌え先行でストーリーはそれに付随し、時に破綻していても構わない、と。
いや破綻にも良い破綻と悪い破綻があると思うが、「筋が通っているか」というところが分水嶺になるのではないかと思う。
質が悪いのは「それでも売れてしまう」ことで、売れているからといってそれが(わたしにとって)良い作品かどうかは、結局見るまでわからない。
さて、映画に話を戻すが、この映画はそういう「悪い」キャラクター映画ではなく、しっかり丁寧に作られた作品だった。
まずもって鬼太郎は50周年にもなる歴史の長いアニメIP。しかも長らく子供向けとして制作されている。
それがここにきて大人向け、しかも別に今の大人(今作のメインターゲットであろう40台以下あたり)はそこまで鬼太郎に思い入れがない。最近流行りのリバイバル狙いもしにくい。にもかかわらずPG12で子供層をぶっちぎって大人向けの作品を作るからにはかなりの覚悟と真摯さを作品に費やさなければ到底成功しないだろう。
しかしこの映画は、子供だましをせず丁寧に描くことでそれを成しえ、大ヒットを記録することになった。人々の心に響いた証左に他ならない。
まず冒頭の雨のシーン。
行った映画館の音響が良かったのか、もしくは最近の映画はみんなそうなのかどうかわからないが、「雨音」の層だけで3層はあったように感じた。
背景のような遠い雨音、自分の傘に落ちる音、そして近くで跳ね返る水滴の音。
それがそれぞれのスピーカーから立体的に聞こえてくるので、否が応でも「雨の中にいる」感覚になる。
序盤でこういう入り込むためのステップをうまく挟み込んで誘われると、見る側も映画の世界に入り込みやすい。
大画面や画的な迫力、美しさにあまり興味のないわたしが映画館に行って観てよかったと感じた最も大きなポイントだった。
龍賀家や哭倉村のあたりは王道モチーフで、ある程度説明を省ける分妖怪やらのこの映画の独自要素にフォーカスを当てやすかったと思う。
それでも妖怪やらの設定はやや複雑で混乱しやすかったが、完全に「わけがわからない」状態ではなかったし、ふんわり分かっていれば良いことだろう。これはすごいことだと思う。
何せほとんどの登場人物を、わたしたちは「知らない」はずなのだ。
それであれだけの人数を出すとどうしても説明やテンポが悪くなってしまう。そこを既存の馴染みあるモチーフに入れ込み、その舞台の中で今回の主役を活躍させるのは上手い手法だと感じた。
(ただし若い人には良くわからなかったという層もあったようなので、この辺は個人差によるか)
唯一惜しかったのは共闘がほんの少ししかなかったところだ。
今作は二人の男性のバディもの、という魅力があるのに、方やフィジカルな幽霊族。方や太平洋戦争の生き残りとはいえ、普通の人間では後れを取ってしまう以上、荒事が片方に寄ってしまうのは仕方ないのだが。
妖怪アクションについては余すことなく魅せてくれるのに、銃を構えるシーンがほとんどなかった。
協力関係の強さは申し分ないだけに、もう少し「人間にしては」という感じで背伸びをし、肩を並べる二人の姿が見たかった。
というか、キービジュであんな銃を持って血まみれなんだから、観る前はもっと容赦なく頭の一つや二つ、いやもっとたくさん吹っ飛ばすのを期待していた。これは残念。まあ「人間」だから仕方がないのだが。
ここからはネタバレになるが、景気よく血も出るしグロテスクな表現もあり、ホラー演出は中々。
特に終盤の子供の身体に年寄りの頭を載せるのは醜悪さと違和感が桁違いで、ややギャグ演出に片足を突っ込んでいるものの、それでも気味の悪い演出として秀逸だったと思う。
最期まで爺の顔だったので、良くも悪くも胸糞の悪さは軽減されていたが、子供(の身体)を殺す展開だったからか、どうしても時貞氏の結末の演出がマイルドになってしまったのではないかと思う。ちょっとここだけニチアサの解像度だったのが残念でもあり、ホッとしたりもした。
故に時ちゃんについてはさらっと肉体も精神も殺されてしまって(気持ちとしてはそれで良かったのだが)割と不完全燃焼だったものの、一番最後のオチできちんと昇華してくれたのは、さすがの丁寧さに感心した。
さて、彼は「忘れないで」と言った。
この作品は「生きること」「未来に繋ぐこと」を伝える作品だったと私は思う。
彼が「忘れないで」いてほしかったのは、彼だけではない。
たくさんの、大人のせいで未来を、そして生きることを奪われた子供たち。
そのすべてを、いま生を享受しているわたしたちは忘れてはいけないと思う。
この作品は戦争についても触れているし、作者の水木氏の戦争体験やそれを経ての人生観についても、日本にいれば耳にすることがある。
簡単に人の命が踏み躙られる時代。
そしてその時代と隣り合わせだった時代。
それが今作の舞台だ。
一歩間違えれば戻ってしまう。そんな危うい時代。
それでも戻らなかったのは、生きていた人の多くが未来を見ていたからだと思う。
作中ではたくさんの人が死ぬが、主要人物では(おそらく)左目を損傷して死んでいることが多かったと思う。
彼女の殺し方なのか、あるいは作品に込められたメッセージか。
(次女と水木についてはわざわざ目を狙って殺そうとしていないので、後者だろう)
そしてこれは外ならぬ「目玉」の親父の過去の話だ。
彼は人型だったにもかかわらず、良く知られるのは目玉の二頭身の姿だ。
そんな図体でありながら、彼は父としてアドバイスをしたり、子を守り、導く姿の方をわたしはよく知っている。
彼がそうできるのは、多分その目で「未来を視てる」からなんだろう。
海外では右目は太陽で未来を、左目は月で過去を暗示するという。
これが日本では逆で、左目は未来を暗示するそうだ。
黄泉から帰ってきたイザナギが左目を洗って生まれたのが天照大神だから、左目は太陽で未来のメタファーということらしい。
左目を潰された彼らは、みんな未来を見ておらず、今、そして自分のことだけのために行動し、他者に害を及ぼし殺された。
傷を残しつつも、確かに左目に光を残した水木。
右の光は奪われても、左の光を微かに残していた母。
隠されていても左に炯眼を宿す父は、そして左目そのものとなり、最愛の子とともに往く。
未来を見通す強さとして。
道を指し示す導として。
命とは継ぐもの。
そして、繋げられてきたもの。
「忘れないで」
過去の悲しみを、過ちを、痛みを。
繋げて前に進むことが、そしてそれを伝えることが、「生きる」ということだから。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
