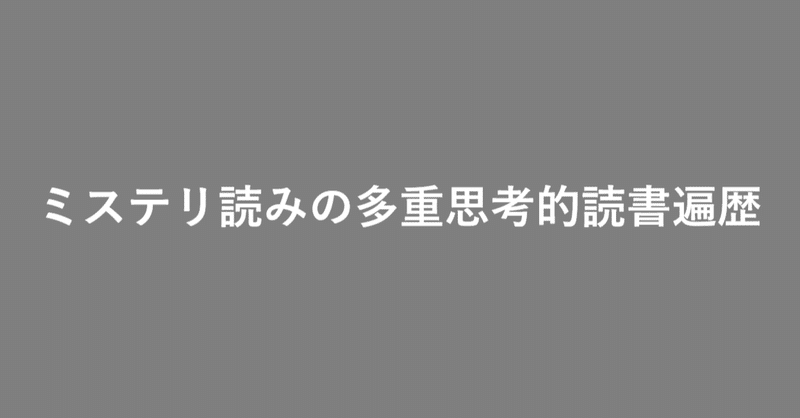
ミステリ読みの多重思考的読書遍歴(1)by 大阪のミステリファン
僕は人狼などの正体隠匿系のゲームが好きなので、ミステリ評でもそのような用語を使うことがよくあります(確白など)。分からなければご自分で調べて下さい。また三津田信三の『十二の贄』、ピーター・トレメインの『翳深き谷』、麻耶雄嵩の『貴族探偵』(とりわけ収録短編「こうもり」)に関してネタを割っています。知らない人は読了の上、お読みください。
2021/5/23 死の一義的不確定性について
今日はジョルジ・アマードの『老練な船乗りたち』(水声社)を読む。この本には二つの物語が入っているが、一つ目の「キンカス・ベーホ・ダグアの二度の死」というのがミステリに接近させて読むことのできる現代文学である。「自分の弔いは、てんでんに自分でやったらいい。できないことなんてないさ」というのが皮肉が効いている。もし悲惨な死に方をしたとしても、その死に様をどうこうしようにも、自分ではどうすることもできないではないか!?ある者の死について混乱した見方、混沌とした状況が示された上で、死体の二つの見え方に関して読者の前に丹念な描写とともに提示されていく。まず一つは尊厳もなく浮浪者のように死んでいった死体の有り様であり、もう一つは立派な腕を持つ葬儀屋の手によって尊厳が取り戻された洗練された死体の有り様である。筋だけ追うとこれは弔いの話であるので大袈裟には葬りたくはない(費用も掛けたくない)が、きっちりと弔いたいという上での折り合いの付け方、落としどころの見出し方という物語とも見てとれるが、それは同時に遺族や葬儀屋の側から見た一方的な見方でもある。言い換えると遺族や葬儀屋による死者に対する働きかけという観点からは確かに弔いということになるのであろうが、第三者的に見れば一つの死体が全く別人に見えるという事実をも内包しており、むしろ「同じ死んだ人とは見えないほどだった」という死者に対する印象操作の可能性(!)のほうが思考の本線という思いもしてくる。遺骨収集に代表されるように死体に対する執着には枚挙に暇がない。逆に云えば死体さえ上がっていれば、それを逆用しそこに印象操作を施すことなど何の造作もないことなのだと気付かされる。極めて重要な意味を持つ二つの死である(笑)。それと同時に死者側から敢えてこの話を蒸し返し捉え直した場合には、自分の死の印象を一義的に確定させることなど、とてもではないができるものではない、ということも暗に示しているとも云えようか。
2021/5/30 ロジカル・ミステリの盲点
今日は三津田信三の『十二の贄』。死相学探偵シリーズの第5作目に当たる。ホラーとミステリを融合した著者お得意のシリーズであり、本作はロジカル&クリティカルな要素が非常に濃い。遺産相続による金目当てという、これ以上ないほど分かり易い情の介入する余地の少ない設定にまず目を奪われる。一応雰囲気を盛り立てるため、黒魔術やら黄道十二宮やらの道具立てはあるものの、全てはミスディレクションの目的に奉仕していると読んだほうが正着かもしれない。初七日で読み上げられた遺言状の内容は衝撃的なもので、これ以上人工的な意匠と設計が施されたものもないのではないか。内容はと云えば半分は悠真へ、そして残り半分は残りの相続人に十二等分される。そして血を血で洗うかの如く相続人の十三人の生き死にによって遺産相続分が変動するという特殊条件が図らずも付されており、有利な条件にあった悠真が誘拐され生死不明の状況になって、事態は混迷を極めていく。第一の犠牲者である初香でさえも、それが主目的なのか、はたまた口封じなどの巻き添えの犠牲者なのかが分からず、犠牲者が次々と増える始末である。ミステリ的には誘拐犯と殺人犯を同一人物だと見せ掛けておいて、初香殺しの現場の状況の奇妙さから(とりわけ手紙の置かれた場所のおかしさから)、手紙を書いたのが殺人犯ではなく実は誘拐犯であり、その連携の無さから実は別人であったと捻り出す推理過程が秀逸である。しかし監禁によるアリバイ創出という誘拐犯からの思いがけぬ利益付与に気付いた殺人犯がそれを逆用して巧妙に同一人物と偽装した方法はかなり上手かった(偽の解決である第一の被害者=犯人はEQなどの古典の作例に倣ったものと思われる)。相続人全員に死相が出現しており、結構皆殺しの型に嵌めるのが容易でありそうな状況でありながら、読み手の推理を巧く逸らす工夫はかなりのもの。真犯人の設定に関しては類例は多いものの、探偵視点からの死視から免れる状況にあったこと、相続的に有利な状況にあって(遺産目当てであれば)犯行を行うほどの積極的な理由の見辛いこと、視点人物=犯人でよくある微妙なアンフェアぎりぎりの絶妙とも評せられる巧妙な心情描写など、よく出来ている点が多かった。まあ、状況的な確白位置が最黒位置というのはミステリ的には常套手段なので、今更評することもないかな、とも思うが。文庫版330頁の「これが黄道十二宮による遺産相続殺人だった場合、三番目に殺されるのは自分だということを、悠真は理解していた」という仮設定の描写は厳密にはフェアプレイに即しているかと云われると微妙かと思う。仮定のことを考える積極的な理由が見当たらないしね、どう見ても。これは作者側の都合だよな。
2021/6/6 探偵視点の情報とそれを利用したミスディレクション
ピーター・トレメインの修道女フィデルマ・シリーズを読む。今回は上下巻の『翳深き谷』を手に取った。物語は丘陵を進み、連峰の頂を越えてラズラの領地に入るところから始まる。ラズラが領主として治める土地をグレン・ゲイシュといい、文字通り異教徒の地である。峡谷の隘路に入ったときに他なる信仰を抱く者に恐怖を感じるくだりがあるが、キリスト教と異なる宗教を信仰しているからといって過度に恐れるのは偏見であるという旨の発言をフィデルマがワトスン役のエイダルフにする辺りから、もう伏線が既にスタートしていると後から振り返ればよく確認できる。いにしえの神々の信仰が残存する象徴がまさに「禁忌の谷」であり、三十三人の祭祀的な虐殺がまさに事件と大きく関連していると錯覚させる算段となっているのである。これは探偵が要は世界の外側からやってきたということに起因している。この作品ではキリスト教徒と異教徒との視点の違いや偏見もそうだが、探偵視点での情報により二つの大きなミスディレクションを人工的につくっている。まず一つがオーラがラズラとそっくりの双子の妹であるという点である。これに関しては文庫版上巻の127頁に既に記述がある。「オーラは彼(勿論ラズラのこと)の妹だとの知識があるフィデルマには、誰がラズラかを、もちろん、一目で見分けられた。二人は、それほどよく似ていたのだ。」この作品の巧妙なところは博覧強記、頭脳明晰で名高いフィデルマが「一目で見分けられ」るようなラズラとオーラの誤認をまさかする筈がない、という視点のバイアスを読者の側に植え付けさせている点にあるといってよい。双子に関わらず非常に顔貌や背格好が似ている人物が二人いる場合、見間違いを起こさせるということはミステリ的には当たり前にあることである。しかし、それは証言の誤認が通常第三者(被害者でも犯人でも況してや探偵でもない)から提出されることを前提として仕掛けられるものであり、探偵自身が間違うことなど無謬性の原則からいっても本来あってはならないことである(無論迷探偵なら話は別であるが)。その点で云えばある意味本作は探偵小説の禁じ手を一つ犯しているのである。もう一つは薬草治療の点についてである。マルガとクリーインとのつながりに関しては情報として透けてしまうと、探偵であるフィデルマが早々と真相に辿り着いてしまう為、巧妙に隠蔽されているのであった。クリーインとマルガが親子関係であることはこのコミュニティでは公然の事実であったのだが、フィデルマにはかなり後になるまで知らされることはなく進んでいく。一種の叙述トリックのように読者視点としても情報伏せの進行が採られている為、読者も容易に気付くことが出来ない(因みに探偵が知り得た情報が読者に提示されないのはそれこそアンフェアであるが、そもそもハナから探偵が知り得ないのはアンフェア足り得ない)。文庫版上巻の176頁にマルガについて「魅力的な娘」、「あのように若くて、薬草治療師」という事件の原因に関する核心めいた情報が提示されるものの、事件と関連付けて考察するのは難しい。クリーインの記述についてもそうだ。187頁に「(クリーインが)娘と一緒に薬草を摘みに行く約束をした」と書いてあるのに、その娘がマルガだとは読者は何故か思わない。この世界の住人で薬草治療師と云えばマルガであるにも関わらずである。何故ならばここでのクリーインは単なる「よく太った来客棟の召使い」でしかないからである。この本全体に云えることとして偏見を糺すように同時に偏見を読者に植え付けるというようなことをやっていて、その方法がとても巧妙であるのだ。この本で印象的なシーンと云えば、身分が低い者の身分差がある場合、社会的地位の異なる場合の結婚についてクリーインがフィデルマに訊く場面が挙げられる(上巻258頁から)。クリーインはそのことについて尋ねるのは自分のためではない、知り合いのためである、と嘘を吐くが、フィデルマはクリーイン自身が結婚という成り行きにならないと考えるのは偏見であると自分を戒める。この状況自体が二重の偏見、ミスディレクションとなっているのである(フィデルマはクリーインの嘘を見破ったが、要するにその方向性が異なっていたということ)。その後の場面で更に追い打ちを掛ける。フィデルマはエイダルフにマルガの薬を試したか、と訊くとエイダルフが「(クリーインが)私を殺す気に違いない。でも、これを飲めば治るって言うのです。自分は、薬草治療師を手伝って、よく薬草採集に従いていくから、良い薬草を知っているんだ、とか言ってね」と憤慨する。フィデルマはこれに対して「早く、まともなお頭(つむ)に戻って頂戴。」と窘めて偏見を糺すのであるが、この対人バイアスこそがミスディレクションとして優れた有効打となっていることは言うまでもないであろう。探偵は無謬である。その無謬性で以て読者に対して出てきた探偵が偏見を指摘しているのであるから、間違っているのは偏見を抱いたエイダルフの側であって、罷り間違ってもフィデルマが擁護したクリーインが悪玉である筈はなく、よってクリーインは犯人足り得ないとなるのが当然だと考えるのが自然な読み筋であろう。そしてもっと云えばこれまでも頼りに然程ならなかったエイダルフというシリーズ通してのバイアスもよく効いているように思う。エイダルフの二日酔いの描写などヘタレそのものだしね。
2021/6/20 偶然じゃないし自殺じゃない!
今回はシリル・ヘアーの『自殺じゃない!』再読。成程『自殺じゃない!』とは凄いタイトルである。帯の惹句には「クラシックの芳醇な香り漂う、英国風ヴィンテージ・ミステリ」とあるが、まさに皮肉の味が極まった英国風の事件の様相を始めから呈している。最初のくだりで「これぞ夢にみたホテル」(11頁)、「イギリスの田舎のホテルにいささか幻想を抱きすぎ」(12頁)とある筈なのに、レナードという名の老人にとっては「思い出の場所」(18頁)であり「このホテルが旅の終点であるのをうれしく思って」(18頁)いるという。この感傷的に語る老人が今作での犠牲者である。状況は睡眠薬の飲み過ぎという自殺の様相を呈し、検死審問でも自殺との評決が出た。しかし、残された遺族は納得しない。何故なら自殺だと保険金が下りないからである。ここから先の筋はかなり地味そのものである。親族会議に作戦会議、要するに家族で話し合って関係者に話を訊いていくばかりの展開となっていく。関係者に話を訊いていくばかりで、本当に埒が明くのかって普通思ってしまうものであるが。しかし、本作の面白いところはホテルに宿泊していた客に怪しい容疑者候補が何人もいたことだろう。これはもう完全に偶然じゃない!もう作者の意図通りに人工的に造られた状況だとしか思えないのである。だが、所詮はアマチュア探偵団であることの限界も相俟って、次第に手詰まりになっていく。その上運の悪いことに生前被害者と偶然会っていた当のマレット警部が遺族の素人探偵団の調査に対して力を貸すことに拒絶反応を示してしまう。もしもこれが殺人事件であったなら、警察の仕事は犯人を特定し犯罪の立証を行うことだが、素人探偵団としては誰が犯人かまで特定する必要はなく、あくまでも自殺ではなく保険会社からお金を受け取る権利があることを主張することなので、齟齬が生じているのである。被害者家族のスティーヴンははっきり言う。「誰かを有罪と証明するのは僕の仕事ではありません。唯一関心があるのは、父の遺産として保険会社から金を受け取る権利があると証明することだけ」(78頁)であると。調査も手詰まりになり、警察の理解も協力も得られないとあっては流石に解決は無理なのかと半ば諦めムードが漂う中、思わぬところからマレット警部が関心を示し始めるのである。詳しくはここではネタを示唆するため省略するが、いずれにせよマレット警部が捜査に乗り出す雰囲気づくりの状況設定がよく出来ている。実際の警察の捜査でも似たようなことがあるかは寡聞にして知らないけれど、推理小説としての内部論理的な説得力があるのは事実であろう。そのことはマレット警部の独白「これは証拠はないが、仮説としては成立するな。まるで道理にあわない仮説だが。」(241頁)に端的に示されている。そこから先はやや急ぎ足で急転直下の解決となるが、真相も英国的な皮肉に充ちたものとなっていることに異論はなかろう。
犯人のムーヴ、状況のつくり置き、素人が探偵っぽいことをする面白さなど様々な興味を惹く点が挙げられる本作であるが、僕はこのマレット警部再登場のくだりの自然さと、倫理小説としての素養、リテラシーについて書きたいと思う。マレット警部再登場については先ほど書いたばかりであり、如何にもマレット警部が捜査に乗り出していこうとするくだりの流れと展開が自然に見えるのが素晴らしい。よく一度解決された事件を蒸し返し再度捜査する流れになる推理小説をよく見るが、展開が無理筋だったり「そんなことでいくらなんでも警察が重い腰を上げようとするか?」と些か疑問に思ってしまうものが多い。その点マレット警部が探偵寄りの創造的な警察官であることを差し引いて考えてもこの小説は非常に良く出来ていると思う(詳しくは書かないが各自見つけて欲しい)。もう一つはこの時期の推理小説に特徴的なエシカルな観点についてである。とりわけ倫理逸脱的な傾向を帯びそうになると、一転してノーマルな側に引き戻そうとするところが英国文学に在る要素でかなり好きなのである。分かり易いのはスティーヴンとアンが保険金を受け取るための方向性を巡って兄妹喧嘩をするくだりであろう。妹のアンを偽善者だと罵るスティーヴンに対してアンは「お兄さんと話していると胸がむかつくわ」(60頁)と突き放す。これだけだと何でもない場面であるが、このあと「こうして聡明で慈愛に満ちた二人の成熟した若者は(中略)自分の行為を大いに恥じたのは言うまでもない」(60頁)というから物凄い。何故ならキャラクターが成熟した大人であるから、倫理が逸脱したまま留まる筈はなく、羞恥をおぼえて引き返すべきであり、事実そうなるのである。これはもう完全に英国文学の世界であろう。クラシカルな英国の推理小説を読むとほぼ英国文学と接続的であることがよく確認できるが、この点最近の評論ではあまり取り上げられないようである。このたぐいの要素は良くも悪くも現代の(特に新本格以降の)推理小説には殆ど見られなくなってしまった。僕にはそのことが残念でたまらないのだが、どうであろうか。
2021/7/13 叙述系最高峰のアイディアと複数作に跨る伏線が凄すぎ
現場に行くけど推理はしない、という安楽椅子探偵を丁度裏返しにした設定で話題を攫った麻耶氏の『貴族探偵』シリーズ。探偵役とワトスン役の関係性に鋭い批評を投じるという、麻耶氏特有の問題意識が色濃く表れた問題作にして、今となっては彼の代表的なシリーズともなっている。そんな中最も注目を浴びたのが短編「こうもり」で、最早それは単体で〈「こうもり」トリック〉という固有名詞で語られるほどに絶賛されるに至ったと記憶している。アイディア的には手垢に塗れたアイディアを三つ複合することにより、全く新しい機構を構築することに成功しており、お見事としか言いようがない。これを説明するためにはまず手品のタネを最も単純化して語る必要があるであろう。この作品では叙述トリックと逆叙述トリックとを重ね合わせることによって驚異のマジックを生み出しているが、まず外形的に叙述系を抜きにして考える。一言で云えば替え玉トリックである。伏線も単純で「名前を騙って無銭飲食を繰り返していた奴」(122頁)というものである。この作品は一言で云えば、読者視点と登場人物視点との情報量の違いを明確にトリックに織り込んでいるのであるが、ひとたび犯人視点からこの事件を考えてみた場合には単純なアリバイトリックを仕掛けたというのみである。しかし、そこに人物の誤認と見掛け上の一人二役(見掛け上の一人二役、というのは説明のために考案した造語であるが)を成立させることにより、人数の誤認を惹き起こしている点において前例のない独創的な仕掛けが決まっているのである。このような先鋭的なアイディアを編み出したきっかけは何であるのか、僕ら凡人には分かる筈もないのだが、それを成立させるための準備があまりにも周到であり入念である。予行演習と当日とのランチの場面を考える。まず第一に読者にはそこにいることが明示されている貴生川の存在が、登場人物視点ではいないことになっている仕掛けを繙いていこう。視点の採り方の差異によって、存在=非存在(=非在)である筈は勿論ないのだが、これが所謂逆叙述トリックである。すなわち読者には透けさせ、登場人物の眼にはそう映らせないというものである。これが違和感なく成立するためにはターゲッティングされた人物の誤認誘導が成立している必要性があるのだが、そのために絵美のパートナーを貴生川自身であると読者に誤認させる前提を踏み台として置いている。つまり登場人物視点に立てば大杉に扮した貴生川(もっと云えばその時点では貴生川ではなく大杉)一人しかいないことになっているのだが、読者視点だと地の文の貴生川と会話の中の大杉先生が二人いることになっているのだ。論理的に気付くことができる要素はテーブルの描写であり、それが四人掛けのテーブルであることから、予行演習日と同じくそこには四人しかいないことが明白であり、フェアプレイにも則っている。ここで物凄いのは絵美のパートナーが貴生川であり、ひいては貴生川が貴族探偵その人であると思わせるその遣り口である。貴生川は高級ジャケットを羽織っており、知的な風貌をのぞかせてもいて(139頁)、その人物特徴は丁度読者視点では貴族探偵を思い起こさせるのに充分である。「貴生川敦仁が、絵美に寄り添って話し込んでいる」(139頁)や「絵美は貴生川とほとんど身体がくっつくほど密接して座っていた」(140頁)という一連の描写から絵美と貴生川〈読者視点では貴族探偵〉とがまるで恋人どうしの関係にあるように細工されているが、作者である麻耶氏がそれだけでは足りないと思ったのか前作(第2作)の106頁に貴族探偵がイニシャルKであることを匂わせる伏線を置いているのが巧い。K=貴族探偵であるならば、それが貴生川であろうと読者からすればそう思うからだ。しかし、作者の肩を過剰に持つ訳でもないけれど、K=貴族探偵=貴生川であることを明確に否定する伏線も実は存在している。それはコーヒーの好みのくだりである。第1作の「ウィーンの森の物語」(「こうもり」は第3作目)において「シロップは抜きでフレッシュだけで(つまりはノンシュガーで)お願いします」(40頁)とあるのに対して、「昨日もそうだったが、よほどの甘党らしく、ソーサーにはシュガーの空袋が三本載せられている」(152頁)とあるではないか。前者が貴族探偵、後者が貴生川の描写であることは明白なので、貴族探偵と貴生川が別人であることはこのことから明らかである筈なのだが……。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
