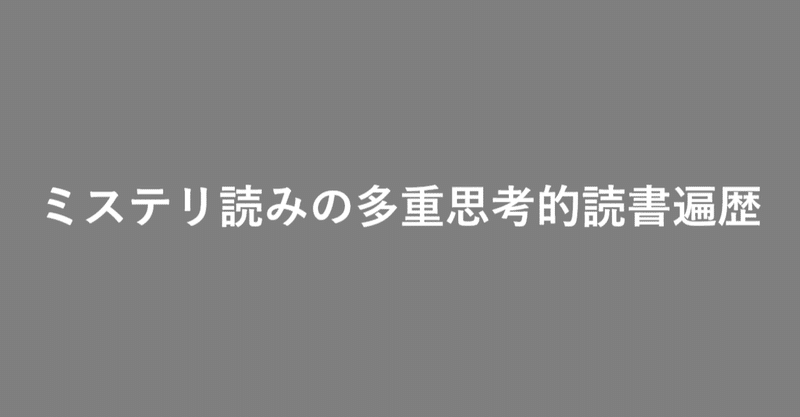
ミステリ読みの多重思考的読書遍歴(2)by 大阪のミステリファン
大阪のミステリファンです。今回は前回に引き続いて第2弾を提供させていただきます。
久住四季の『トリックスターズD』、綾辻行人の『迷路館の殺人』、米澤穂信の『夏期限定トロピカルパフェ事件』、梓崎優の『叫びと祈り』、そして山口雅也の『キッド・ピストルズの最低の帰還』のネタを割っています。知らない人は読了の上、お読みください。
2021/8/8 叙述トリックを成功させる状況設定のつくり方
今日は注目の若手作家、久住四季の『トリックスターズ』シリーズからシリーズ最高傑作との呼び声も高い『トリックスターズD』(メディアワークス文庫版)を読む。前幕というまえがきのある設定、そして前2作を作中作にした凝った構成、それに作中人物にこの現実こそが実は小説なのではないか、と言わしめるなど総体的にメタ的要素が俄然強くなっている。これはメディアワークス文庫版のあとがきによれば、綾辻行人氏の〈館シリーズ〉を多分に意識しているとのことで、実際こちらも3作目ということで『迷路館の殺人』との類似性が色濃く見られる。只これまでの『トリックスターズ』などと比較するとメタレヴェルでの仕掛けが存在することを読者に予想させる出だしと構成を採用している点、叙述トリックの存在を大いに匂わせており、その分フェアにつくられているとも云える。米澤穂信の『折れた竜骨』を思わせるような特殊魔術ミステリという設定も面白い(ここでは『召喚』魔術)し、魔学をロジカルなものと置いているのもミステリ的咀嚼に感じられ有意義であるが、一番の肝はやはり叙述トリックの仕掛けであると思う。この作品では暗転するまでの現実世界と暗転してからの憑依させた人物の特定が問題となる世界の二つが峻別されている訳であるが、勿論トリックの大きな幹は語り手存在の誤認にこそある。召喚魔術の効果によって憑依が起こり、自分が何者であるのかの記憶を失くしているという設定がまず目を惹く一つ目のファクターであって、一人称語りにおける語り手自身の語り(要は自分が何者か)の省略に関するハードルをいとも簡単に下げてみせているのには驚いた。従来の方法だと会話文を多くするなどして、自分に関する記述を意図的に極力抑えるなどといった作為の必要性が生じて結果違和感が生じがちとなる傾向にあるが、この作品ではそもそも自分が何者かということを知りようがない(そもそも疑いようがない)状況が出来しているため自然に記述できるのだ。そして勿論二つ目のファクターこそがこの作品の肝である一人称語りの人物が別人物だと誤認している状況を生み出すに至る、他の登場人物の当該人物に関する誤認を惹き起こす状況設定、つまりは作中作のメタを使った誤認方法なのである。作中作との類似性から一人称語りの人物を別人物と誤認するといった仕掛けなのだが、作中作(虚構)と作中現実が錯綜する状況のつくり置きによって、読者視点だと全く違和感なく受け取られるようになっている点が秀逸である。巧いのは読者には一人称語りによってフェアに真相を提示しているのにも関わらず(「しかし現実には、ぼくは事件解決どころか、そもそも捜査になど参加していない」(メディアワークス文庫版89頁))、作中作というメタ的設定や、現実と虚構の境目が曖昧になるという設定の存在によって、違和感を寧ろ取り込んでしまう緩衝剤のような機能を構成そのものが果たしている点が頼もしい。憑依体の正体に関しては結構状況的にバレバレなところはあるが、棟内からの脱出を目指すサスペンスのように一度見せ掛けておいて、結界の中に閉じ込めた目的を別に設定していたという二段含みの真相が秀逸。視点人物(と思われていた人物)が実は結界の外に居たという極めて重要な事実は、上述の叙述トリックの視点人物の隠蔽がなければ、読者視点すぐに透けてしまうことから、叙述トリックと状況設定とががっちり手を取り合っていることがよく確認できると思う。叙述トリックのための状況設定が、裏を返せば状況設定のための叙述トリックにもなっているのだ。
あと以上の点に更に付け加えるならば、綾辻行人の『迷路館の殺人』との類似性としては性別誤認トリックの存在が挙げられる。それも構成的に物語の外縁でそれが明かされる点も似ていて、その辺も含めて『迷路館の殺人』のオマージュであることを強く意識していることを窺わせるものだ。只上着のスーツを伏線に使うところは、『迷路館の殺人』とは大きく異なっていて、事件の核心(首切りの論理)と大きく関わっていた犯人絞り込みのための属性の隠蔽という要素が強かった『迷路館の殺人』のほうに性別誤認トリックの使い方の巧さという点では軍配が上がるなあと思ってしまうのは自分だけではない筈であるが、如何か。
2021/8/22 〈日常の謎〉からの意外性溢れるホワットダニット
今日は米澤穂信の『夏期限定トロピカルパフェ事件』。これは小市民的なひと夏の思い出づくりなのか。確かに外形的にはスイーツ・セレクションをめぐっての〈日常の謎〉系統のミステリではある。しかし、本書は山田風太郎の連鎖式ミステリの諸作、つまりは連作短編のように一旦見せ掛けておいて、実は全く異なる構図で描かれた長編が立ち上がるという試みに挑戦した作品でもあるのだ。その上で各短編を読んだとしても、実に良く出来ているのが本書の凄いところ。まず最初の「シャルロットだけはぼくのもの」にしてもティッシュを使わざるを得なかった真相の土台となる、「何故ハンカチが使えなかったのか(別のことに使われたのか)」という準備が実に用意周到に出来ている。ここでのミステリ要素だけを抽出しての素晴らしい点は二点あると僕は考える。まず一つ目は別のことでハンカチを使ったことの隠蔽、これには倒叙形式という〈日常の謎〉系統ではあまり見かけることのない叙述形式が最大限に活かされている。またもう一つはハンカチ以外のものが使われなかった(或いは使えなかった)という論理の定めであり、とりわけ紙ナプキンに関する枚数の描写には本当に恐れ入った。続く「シェイク・ハーフ」では「半」の字(正確には漢字の「半」に見える文字)に関するダイイング・メッセージもののような展開がなされていくが、実は字ではなかったという真相よりも、その字ではなかったという事実に気付くきっかけが本格ミステリ作家ならではの着眼点で唸ってしまった。鮎川哲也だったか本格とは謎(トリック)の解明よりもそれが割れるときのきっかけにこそアイディアが必要とされるという旨の発言があったと記憶しているが、確かにこの作品における字ではなく図であった、という真相が割れる瞬間の構想など最たるものだと思った次第である。
只本作の肝は一見すると〈日常の謎〉系統の作品に途中まで見えていた景色が、あることを経て一変してしまう構図の変転にこそあると思う。誰もこのような事件性の高いものが起こり得るとはこの本を開き始めたときに思い付きようもないのだから。その上で述べると小佐内さんの甘いものに関する特別縛りとまでも言える拘りをロジックに織り込み、「小佐内さんは自分が誘拐されることを、知っていた」(199頁)→「誘拐計画そのものが小佐内さんの誘導によるものだった」(212頁)という真相暴露後の何段ものロケット打ち上げが素晴らしすぎると感じた次第である。それを導くのが「小佐内さんを信じ抜く」というこの創作世界のみで通用するある種の特殊論理であり、特殊論理の積み重ねによって論理展開、そして画の変遷までも可能にしている点が秀逸であると思った。ある意味ではこれは近年流行のSF的設定のミステリに近いアイディアのようにも思えてくるのであった。各々の短編に伏線の地雷をばら撒き、長編の趣向に奉仕させる。何とも愉快壮観な秀作である。
2021/9/19 異世界の風貌における特殊論理
本日は梓崎優の作『叫びと祈り』。国内の各種ミステリ・ランキングで軒並み上位に喰い込むなど業界における評価も高かったと記憶している。さて、本作で強調されるべきは異世界での異形の論理である。そしてその設定を可能にしたのが、異国をありのまま表現する語彙力の確かさと表現の引き出しの多さである。勿論異国情緒性といった雰囲気が先行してあるタイプの作品ではなく、その土地の特性による動機の創出や特殊状況の設定にこそ、力量が発揮されているとは云えようが……。
1作目の「砂漠を走る船の道」からしてミステリーズ!の新人賞を受賞した秀作。整然と隊列を組む砂漠のキャラバン、という設定は同調性論理が極めて重視される状況として極めてユニークであり、その長が死ぬところからその組織論理に微妙な罅が入り、疑心暗鬼になっていく展開もとてもスムーズであると感じた。容疑者が数少ない状況で何故殺人を犯すのか、という謎が徐々にクローズ・アップされてくるが、その解決として隊の人間以外に別の人間がいてその人が犯人、皆殺しを狙ったものなので全員が揃っている状況で殺すのが最適など様々な推理が出てくる。中には事故と自殺のキマイラ、なんてものもあったが、少々捻りすぎかと思う(推理マニアでないと発想できない)。真の解決は人を死体にして完全にモノとして扱い、それを道しるべとして利用した、という倒錯した論理であり、砂漠のキャラバンという特殊な状況を見事に活用した解決だと評することができようか。塩を道しるべとして犠牲にできないという人の死体を活用しないといけない裏付けもよく練られている。(ラクダの)メチャボに関わる叙述トリックについては、長の後継者にするつもりなのか、という旨の発言がやはり気になり、ラクダであれば後継者になることは(通常は)ないと考えるのが妥当なので、整合性の観点で問題になってくると思われる(仕掛け自体は面白いけど)。
2作目の「白い巨人」もスペイン風車を巡る推理合戦が堪能できる見るべきところの多い作品。風車伝説に現代の消失事件を重ね合わせて謎を生み出している。解決は多重解決でロースンの某短編を思わせる逃げ込んだ風車を間違えた説、そして兵士の気力、頑張りと使命感が存分に試される風車の羽根にしがみ付いてやり過ごした(笑)説が出た後、風車伝説そのものがフェイクであったという、前提が大きく覆される真相が示されて度胆を抜かれる。構図が大きく反転する話が個人的に好きなのもあって、この大胆な仕掛けにはかなり驚かされたが、思考の道筋上有効なところはあったとは云え、風車伝説が現代の事件と直接の関わりを持たなかったという点がたいそう衝撃的である。長編だとたまにこの返し方は見られるものの、短編でやられるととても意外に感じられる。風車伝説で考慮された要素が現代の事件を考えるに至っては推理の役に立たなかったものの、強引に両者を結びつけようとする作者の振る舞いにこそ、笑いを浮かべるではないだろうか。
3作目は霧に包まれる修道院を舞台にした幻想性の高い一作で、腐敗しない遺体という有り得ない状況を作り上げ、紙面上での奇跡を現出させようと試みている。思考の過程などは他の短編より緻密さに欠け、どちらかというと幻想味溢れる雰囲気で読ませる作品のように思われてならないけれども、リザヴェータ様の遺体を入れ替えたとすると辻褄が合うが、その状況は不可能であった点から、そもそもリザヴェータ様の遺体がなかったとする不在論が出来してくる展開が凄まじい。「人間がひとり、目を閉じて横たわっていた。」(創元推理文庫版156頁)という生者を死者に見せ掛ける叙述トリックが効果的に用いられ、見事に手玉にとられてしまうが、最後にカーの某長編を意識したオカルトオチ、つまりはリザヴェータが本当に復活していたのだ、というミステリ構造そのものの成立を危うくするラストも超弩級のインパクトを放ってあまりあるものだ。
続く4作目が異様で凄まじい動機が披露される個人的にベストだと思える傑作「叫び」。この本の興味深い点は1作目の砂漠のキャラバンの話も共通するところだが、我々の常識と如何に違って見えても、その社会では常識であるかもしれぬ、という斬新な見方の転換にこそあると思っている。4作目の設定はエボラ出血熱のような症状が蔓延し、絶滅に瀕してしまった南米アマゾンの秘境にあるという先住民の村。どう見ても全員の死亡がほぼ免れ得ないという状況下で何故か連続殺人が起こるというものである。死を目前に控えた人物を敢えて殺す必要があるのか、というテーマは病死だけでなく刑死や戦死など他でも見られるものだが、殺人が不必要な状況下での殺人の解決として最も有り得ると思われる、死に方の違いが問題(苦痛度の違いetc.)であったのだ、が大胆に否定されるくだりがお見事すぎるのである。これをどう解決するのかと思えば、病による死という不確定な状況を変えるための殺人―即ち最後のひとりになるという栄誉のための殺人であったという理由が、歴史に名を刻むというカルト的な動機で物凄いのだ。この場合は設定の勝利といってよく、通常のクローズド・サークルと違って皆殺ししても犯人が生き残ることを前提としておらず、文化を継承するための子孫も繁栄させることが不可能であるという終末論的な世界観がこの一見不可解な状況を可能足らしめていると思った次第である。
この作品集の掉尾を飾るのは「祈り」。病院かサナトリウムのような場所で謎解きのためのゲームが始まるといった内容で、始まりは何が起こるのか予想も付かないが、実際にこの中では変化球だとおぼしき一編だ。一つ名探偵論として無理矢理にでも考えるのだとすれば、予兆めいたものは多分にあり、最初の1作目では完全に解決できた探偵役が、徐々に方向性を見失っていく過程(4作目では推理が完全に誤り、正答に到達できない)が作品集を通じて示されていたことで、名探偵救済のための物語として解釈することが可能となっているのかもしれない。いずれにせよ、正しいも間違いも、答えがあるもないも、全てひっくるめて物語というより大きな構造(メタ的な枠)のなかに吸収されていくかのような感触をおぼえることは確かであり、それだけでも特異な作品として記憶のなかに刻まれるように思われるのであった。
2021/11/7 パンク=マザーグースの待望の帰還
本日は山口雅也の『キッド・ピストルズの最低の帰還』である。副題に『パンク=マザーグースの事件簿』とあるとおり、今作はマザーグースてんこもりの中身で、まさにマザーグースに捧げるオマージュ作品と呼んでも差し支えないほどである。作者の気合いの入り様は一作目に『駒鳥(コック・ロビンのほうが通りがいいか)の死と埋葬の哀歌』を持ってきていることからも感じ取れる。ご存じのように黄金時代にはイーデン・フィルポッツがハリントン・ヘクスト名義で『だれがコマドリを殺したのか?』(1924)を書いているし、同年にフィリップ・マクドナルドが『鑢』を発表している。S・S・ヴァン・ダインの『僧正殺人事件』が世間的には有名であろうが、他にも後の時代になるとエリザベス・フェラーズの『私が見たと蠅は言う』(まんまやんタイトル)なんかがあり、枚挙に暇がない。本作に話を戻ると、流石はパラレルワールド、世界観などは野放図でやりたい放題な感じがしないでもないが、目撃証言を巧みに心理誘導するものであり、操りの構図の上になされたとするのが真相となっている。これだけだと単なるアリバイもの、推理の誤誘導に他ならないが、その操りの構図に加えて、禅と弓道に神秘性を求めるロビン卿の心理状態―『自分が命中させた』と考えることで楽になりたい―が加わってあたかも不可能犯罪もののような様相を呈しているところは秀逸。最初否定していたのに途中でやったと証言を変えたくだりも心理の移り変わりを巧みに捉えており素晴らしい。元々西洋と東洋の弓術の比較、その歴史などの薀蓄がカットバック的に挿入されていることもあり、事件そのものと違和感なく溶け込んでいるのも見事であった。
2作目で扱われている童謡は「ゴータム村の三利口のお椀の舟」。童謡と違って『ゴータム海洋パラダイス』にある水中ハウスという設定に変えてあるのがまずミステリ的に作り変える準備かと思った次第である。珊瑚礁地帯という非日常的リゾート描写も素晴らしく雰囲気を盛り立てる。加えて水中ハウスの構造が半球状で巨大なマッシュルームに見えるなど、非日常の極みのような形をしている。勿論その形自体意味があるのだが……。手掛かりや伏線はなかなか気が利いていて(注意深く読めば気付くのだが、それだけフェアだとも云える)良いと思ったが、容疑者の失言に基づく気付きというつくりはいただけない。現実の事件では犯人側の瑕瑾から絞られてしまうという展開はあるのだろうけど、ミステリはやはりロマンの一種と僕は思っているので、こういう手の遣り口は好きではない。もう少し好ましい書き方はなかったものか。その一点が惜しまれる佳作。
3作目は怪しげな教団に動物愛護団体が絡む不可能犯罪もの。「セント・アイヴスの道」という童謡をミスディレクションに用いて一本道での不可能な芸当を成し遂げている。三次元方向へのアイディア、つまりは空への脱出という解決自体は見慣れたもので新奇性はないのだが、袋の本来の目的が砂であったという驚きの真相が用意されている。猫のトイレなどの納得できる見解があるだけにこれはかなり意外。更にすり替えを強調するために見せておかねばならない子供を隠してしまっていた不都合の理由も素晴らしい。トラックの幌に見せ掛けて実は球皮であったという隠蔽の手段が秀逸。探偵役の側がトリックを仕掛けるというプロット上の意外性も炸裂し、満足すべき逸品に仕上がっている。
4作目は「三匹の盲目の鼠」という有名曲を用いた作品。音そのものを凶器としたミステリは前例がある上、あからさまにライヴ・ハウスでの音楽バンドをテーマにしている性質上、ある程度のことが透けてしまうのは致し方ないところか。個人的には超低周波音をモティーフにしたことの是非よりも、耳栓をしていた伏線にくだらなさと練り込みの薄さを感じてしまった。綿屑が落ちていたくだりはあまりにいただけない。聴こえないようになっていた仕組みが、もう少しこなれたものであれば、また感想は違っていたように思われる。最悪耳栓であってもいいが、それが何か変わった意外性のあるモノであれば驚きようがあった筈であるからだ。
最後は「安息日生まれの子供」をモティーフに使った超能力を有した子供たちが集まっている研究所が舞台のSFミステリだ。超能力を前提とした世界線ではあるものの、その扱われ方は非常に捻くれており、興味を惹く。死の予期(或いは予知)というのが事件の根幹に関わりを見せているが、サンデイがマンデイとして入れ替わりで死ぬくだりも特殊能力との関連性を暗示している点が面白く、事件の構図自体「何が問題となっているのか?」を巧妙にすり替えて隠蔽しているところがよく練られているなと唸った。全体的に玉石混淆という水準の作品集ではあったものの、概ね楽しめたように思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
