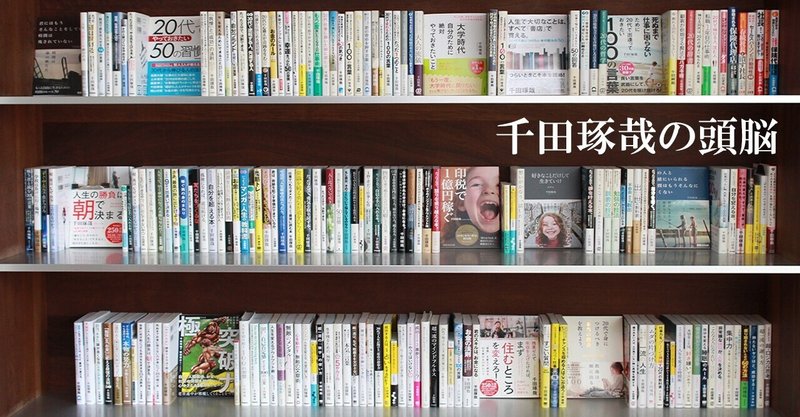
【千田琢哉の頭脳】Vol.0411(2010年3月21日発行のブログより)
実力主義、成果主義がもてはやされてうちの会社もその流れに乗って人事制度を再構築してきました。もちろんそれによる一時的な恩恵もそれなりに受けました。しかしここにきてどこか歪が生じており、パフォーマンスもよろしくありません。業績不調もあってかなり社内がギクシャクしており、今一番の悩みの種です。結果オーライでは組織に生きる生身の人間には限界があるのでしょうか。ちょっと弱気になっています。
(静岡県・会社経営・Kさん・男性・36歳)
コンサルタントで大切な能力に仮説構築力というものがあります。
仮説構築力とは根拠ある仮の見通しを立てる力です。
仮の結論を立てる際に当てずっぽうではいけません。
根拠が大切になってきます。
仮説は間違ってもいいのです。
「なんだ、あの先生が立てた仮説は間違っていたじゃないか」
というのはその発言が間違っているのです。
仮説が間違っていたとわかったらすぐさま別の仮説を打ち立てていきます。
その仮説も間違っていたらまた次の仮説を打ち立てていきます。
大切なのは仮説があっているか否かではなくて、
仮説⇔検証の繰り返し
です。
世の中に出たらいかにこの仮説・検証の回転率が速くできるのか、
が仕事能力と深くかかわってきます。
最初から正解を出すことは求められていません。
なぜならそんなラッキーはいつまでも続かないし、
偶然に過ぎないからです。
偶然の単発ではなくて10年後20年後も使えるスキルでなければ
意味がありません。
正解か否かなんてどうでもよくて、
なぜそう考えたかの根拠こそがすべて
だということは憶えておくといいでしょう。
野村監督は頭脳派の名監督として有名です。
野村監督は古田選手に配球の指示の質問した後に
それが合っているかどうかなんて一度もアドバイスしたことが
ないそうです。
「なぜそう考えたのか」
その一点のみを聞いていたとのことです。
結果オーライになる風潮がありますが、
結果オーライの人も組織も続きません。
結果主義の人や組織は必ず行き詰ります。
それよりは結果は3割バッターでいいから、
なぜそう考えたのか、決断したのか、の根拠が大切なのです。
クイズ番組でもこの人頭いいな、という人が必ずいます。
毎回優勝はしませんが、毎回上位です。
しかも長い間レギュラーとしてテレビに出してもらえます。
その人たちの共通点は正解率の高さではありません。
その人がまったく知らない問題が出された時に
どう考えてその答えが出たのか、の納得感なのです。
もちろん不正解です。
でも正解よりも不正解の方が説得力があって面白いのです。
優秀なビジネスパーソンやコンサルタントがまさに同じなのです。
事実よりも説得力があるのです。
これは事実よりも仮説構築力の方が大切だということではありません。
常に事実の前では頭を下げるべきです。
でも例外なく仮説構築力が優れている人は常に事実に対して謙虚です。
事実とのギャップを楽しみながらでなければ、
仮説構築力は磨かれません。
古畑任三郎も刑事コロンボもよく間違えます。
自分の仮説とかけ離れた事実とのギャップを繰り返し楽しみながら
ある瞬間にバーンと核心に迫っていくのです。
これが仕事を楽しむということです。
...千田琢哉(2010年3月21日発行の次代創造館ブログより)
↓千田琢哉のコンテンツ↓
🔷千田琢哉レポート
文筆家・千田琢哉が書き下ろした言葉を毎月PDFファイルでお届けします。
🔷真夜中の雑談~千田琢哉に訊いてきました~
文筆家・千田琢哉があなたから頂いたお悩みに直接答える
音声ダウンロードサービスです。毎月1日と15日発売!
“毎月1回の飲み代を、毎月2回の勉強代に”
🔷千田琢哉公式チャンネル
「3分の囁き」千田琢哉の独り語りをYouTubeでお楽しみ下さい。
