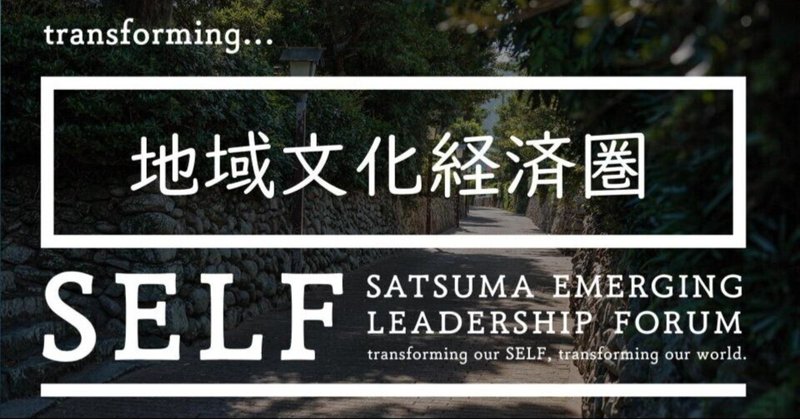
地域文化経済圏 × Transformation:鹿児島ー沖縄という小さな共同体の再生~文化を礎に島(シマ)の可能性を探る~
わたしたちが高度成長期において「便利さ」と引き換えに手放してきた相互扶助的な「共助」の復権が叫ばれる中、人口減少社会という新しい時代における小さな共同体のあり方はどのように進めて行けばよいのだろうか?
鹿児島の甑島、奄美大島、そして沖縄という島から見たコミュニティ(=シマ)の可能性を探ります。

ヤマシタ ケンタ
鹿児島離島文化経済圏 発起人
東シナ海の小さな島ブランド株式会社 代表取締役
Shimamori Inc. 代表取締役
甑島生まれ、37歳2児の父。高齢化率52%を超える人口1,000人の村を拠点に「東シナ海の小さな島ブランド株式会社」や「Shimamori Inc.」など創業。耕作放棄地の再生から空き家の改修、公共施設等の小さな拠点づくりに取り組む。”懐かしい未来の風景をつくる”集落デザインカンパニーとして山下商店甑島本店、オソノベーカリー、FUJIYA HOSTELなど地域密着型の18事業を運営している。その他、島嶼地域における共創社会の実現を目指す、鹿児島離島文化経済圏や日本の水産業に新たな選択肢をつくるFISHERMANS FESTを監修。
比屋根 隆
株式会社レキサス 代表取締役
Ryukyufrogs 創設者
株式会社うむさんラボ 代表取締役
沖縄県那覇市出身。沖縄国際大学在学中に起業。レキサスではITを軸にオリジナルサービス開発にこだわり、連続した新規事業創出やスタートアップの立ち上げを実施。2008年に県内学生を対象に次世代リーダーの発掘・育成プログラム「Ryukyufrogs」を創設。2018年には株式会社うむさんラボを始動。沖縄や世界を豊かにする人財や事業の創出、起業家支援、そのエコシステムやコミュニティを育む活動を行う。
麓 憲吾
有限会社アーマイナープロジェクト 代表取締役
NPO法人ディ!(あまみエフエムディ!ウェイヴ) 代表理事
奄美大島 奄美市出身。島のアイデンティティ形成や人口減少を課題としつつ、フロントマンやイベントパフォーマンスなどの非日常的/直接感化(関係づくり)に限界を感じ、メディアやコミュニケーションによる日常的/間接感化(環境づくり)を探求し活動しています。音波(音楽)や電波(ラジオ)を伝い、島の空気屋として磁場と島心を培っています。また、奄美の生活文化(芸術文化ではなく)としてのシマ唄・八月踊り・音楽文化の奄チュアスタイルを守り、次世代へつなぐことの深さを広く伝えていくことをミッションとしています。
陶山 祐司
株式会社Zebras and Company 共同創業者/代表取締役
Tokyo Zebras Unite 共同創設者
一般社団法人ドラッカー学会 理事
(1) 社会性と経済性の両立、(2)ステークホルダー全体への貢献、(3)長期的な価値創出拡大を行う「ゼブラ企業」の普及に取り組む。元々は経産省でエネルギー政策、電機産業政策に従事。その後、VC/新規事業のコンサルタントとして、100億円超を調達した宇宙開発ベンチャーやIoTベンチャーの事業戦略策定、資金調達、サービス開発、営業の支援や政策提言等を実施。2018年に独立、SIIF(社会変革推進財団)におけるインパクト投資の促進や、ガバメント・リレーションズの普及に従事。2021年にZebras and Companyを共同創業。

経済と文化をどうつなげるのか
陶山:みなさん、よろしくお願いします。早速ですが、山下さん、すごい何か喋りたさそうにされていますね。(笑)
山下:では口火を切ってお話しさせていただきます。実は、このセッションの打ち合わせをこのメンバーでしたときに、経済ってそんな簡単なテーマじゃないよねみたいな感じで、陶山さんに言われて背筋が伸びたんです。それで、そもそも「経済」とは何なのかな?と、改めて考え直しました。経済って誰のために、何のためにあるのかをまずは、考えなければいけないなと思いました。
少し話は変わるんですが、昨日、SDGsの項目に「文化」の項目がないっていうのを山極先生から伺って、ちょっと衝撃的だったんですね。僕らは島の中に暮らしているから、島らしい生活文化みたいなものって当たり前にあるもので、それは絶対に大事にされる、尊重されるべきものだと思っているんですよ。
でも、グローバルな話になると、あれ、僕らの文化って何だろうと。SDGsの項目にない「文化」と今回のテーマである「経済」をどう繋げればいいんだろうとなって。
でも同時に、もしかしたらこの繋がりってすごく大事なことかもしれなくて、生活文化を大切にしている沖縄を含め、鹿児島の島々が、これからの世界を牽引するトップリーダーになっていく可能性があるんじゃないかなっていう可能性もぼんやり感じました。

陶山:めっちゃいいですね。それでいうと、地域文化経済圏っていうテーマは最初から決まっていたんですけれど、顔合わせをして喋ったときに、経済圏っていう言葉がやっぱり経済中心に回ってるように聞こえるから、そこはなんか違和感があるよねという話をしましたね。
経済圏っていうので見てしまうと大切なものを見失ってしまうけど、経世済民、つまり「世をおさめ民をすくう」という意味で言うと、社会と生活を支えるということでの経済と、コミュニティをどう成り立たせるかという観点の経済という双方の意味合いがありますよね。
山下:少し関連するような話で、自分の今の活動の原点となる一つのストーリーがあります。島の港の真ん中に江戸時代に島津家が作った防波堤があって、その上がったところにアコウの大木があったんです。その木の下にいつも夕方になったら、どこからともなく集落の人たちが集まって夕涼みをしながら、たわいもない話をしたり、なんとなくそこに集まって無言で夕日をみんなで眺めたりしていました。
でもその場所が水産業の発展のために港湾工事の整備が行われ、しかも建設会社に務める父親がそこの現場監督になり、その工事によってその土地の文化や風景、暮らしの時間みたいのが全部失われてしまいました。その時の私にはその矛盾を自分ではどうすることもできなかったという経験があります。
だからこそ、歌とか踊りとか島の中にある生活文化が、どういった指標やルールがあったら経済が発展する中で維持継続できるのかみたいなことをいつも考えています。お金にならないという理由で切り捨てられないような、島らしい経済のあり方はどうしたらいいんだろうとずっと考えています。
島の芸能がプロ化することによって失われるもの
陶山:さっきから比屋根さんが何か言いたそうですが、どうですか。
比屋根:島の伝統芸能の後継者って育てられてるのかというのをちょっと聞いてみたいなと思ってですね。沖縄でもこの問題は切実です。

麓:そうですね、先ほどアマチュアリズムが大事だってお伝えしたんですけども、プロフェッショナリズムとも、どちらにも役目があるなと思っています。島では元ちとせがデビューして活躍したことによって、親が子供に島唄を習わせたいということで、習っている子がものすごく増えたんです。伝統文化の裾野が広がったわけですね。
陶山:やはり元ちとせさんの影響は大きい?
麓:そうですね。子供たちにとっても何か価値観が変わったんじゃないかなと思います。都会から評価されることによって島唄の価値が大きく変わったように見えて、子どもたち自身も伝統文化にたずさわることがアイデンティティになるというか、一つ何か武器を持ってるというかそういう感覚があったんじゃないですかね。
陶山:なるほど。山下さんはどうですか。
山下:僕はまさしく唄とか踊りの担い手の一人として今集落にいるんですけど、生活文化って集落で暮らす中で自然に教えられるというか、集落に生まれ育ったらそれを歌ったり踊ったりするのが当たり前のように教わる環境にあります。
そんな中、先日、雨乞い踊り保存会の歌い手の先輩が、事情があって急にやめてしまったんです。集落の歌とか踊りって楽譜があるわけじゃないので、引き継ぐにも音程がわからないんです。これはこれで、次の課題だなと思いながら、託し方にも託され方にもすごく悩んでいるところです。

比屋根:沖縄本島のいわゆる伝統芸能をされてる方々の現状としては、跡継ぎがいない。みんな高齢化していて、見にきてくれる方々も同世代なので、このままいったら伝統って繋げないし、かといって、若い人に来てくださいと言っても、あるいは観光客来てくださいっ言っても、興味を持ってもらえそうにアピールできない。
別の課題としては、経済がそこに紐づいていないんですよ。だから、沖縄本島だと観光客の方々にちゃんと高いお金を払ってでも見たいと思わせるようなイノベーションを、後継者を育てながらやらないといけない。そこに対してちゃんとお金が回るようなビジネスモデルを作らないといけないなっていうふうに思ってるんです。その点、ほかの島の方はどうなのかなと。
麓:奄美だと唄者(うたしゃ)と呼ばれる唄が得意な人が集落にいて、そのひとたちは生活の中で作業をしながら唄うとか、お酒を飲みながら唄うとか、そういう感じのアマチュアリズムの世界で世代をつないできました。
それがいつからか島でも居酒屋さんとかに唄者が呼ばれるようになったんです。それが週末だけじゃなくて、平日も呼ばれるようになって。そうなるとみんな疲弊していったんですよ。島の唄者は唄で食べているのではなく、生業があってその合間に生活の一部として唄も唄っている。だから、そういったところをちゃんとマネジメントする必要がある。
観光ビジネス業界の人は、地元の島唄で飯を食える子供たちを育てようみたいなことになっちゃうんですよ。要はプロ化ですよね。
やっぱり生活文化の唄と踊りなので、それをこの後も継続できたらいいなというように考えています。

陶山:伝統が商業化されて商品化されてっていうところ。難しいテーマですけど、結局ビジネスもコミュニケーションなわけじゃないですか。
だから、この文化はこれだけ価値があるんだと、だからこれだけ払ってくださいというのもありだし、島の人の紹介で来た人だったら、別にタダでもいいですよみたいなこともやっていいはずなんじゃないかと思うんです。経済と地域文化の保全との間にどんな思想を持たせるかみたいなところな気がするんですよね。
会場から:それはちょっと違うと思うんです。さっきアマチュアリズムを強調されてらっしゃいましたけど、生活文化っていうのと伝統文化ってのは全く違う。歌を歌ってお金をもらう行為自体が、島唄という本来の文化から逸脱していることで、だからこそ価値があるっていうのと、10万円出せばそういう価値は手に入るって話は全然違うと思います。
麓:ありがとうございます。アマチュアリズムっていうことが、クオリティがないということではないんですよ。ただ、島唄は、島の時間や空間の中で生まれた感情を歌にしているので、知人に歌いに行くぐらいまではいいと思うんですけど、全然関係のないところに自分の時間を割いてそこに行くのであれば、対価が必要なんだろうなというイメージはあります。
なので、観光業者だったり、飲食店が何かしら利益を得たときに、その利益が、歌い手側にフィードバックするようなシステムができたらいいなとは思います。
陶山:ありがとうございます。おっしゃってることももっともだなと思っていて、まさにそこも含めて、どんなあり方がいいんだろうねと。僕はどちらかというと左脳が強い人間なので、合理的に考えがちなんですけど、そこに本来は揺らぎがあるべきだし、やっていく中で、やっぱ違うよねってこともきっとあると思うんですよね。そういうのが対話できるようなコミュニティだったりとか、コミュニケーションみたいなものがうまく続いていくといいなっていうふうには、思いました。

離島から見た薩摩
陶山:ありがとうございました。では、少し話を戻して、このセッションの一つのテーマであり最初に司会者の方から振っていただいたのもあるんですが、離島から見た薩摩をどう見るかっていうところも聞いてみたいなと思うんですがどうでしょうか。
比屋根:あんまりそこに問題意識とか、視点を持ってないっていうのが答えです。境界線がないというか逆に何か一緒にできるといいな、しか考えてないです。
過去いろいろあったのかもしれないけど、未来に向かってっていう思いがあります。薩摩と琉球の歴史も昔あった話ではありますが、でも今日本が世界に果たす役割、ていうのもあると思うんですね。その中で日本の中でもさらに縮図である離島、鹿児島には明治維新をしたという歴史もあって。その中で我々が日本をある意味新しい形でリードしていく、東京の資本主義とは違う形で、新しい文化経済のあり方を提唱しながら、国内や世界中からたくさんのファンが、応援していくために僕らは何をしましょうかっていう話がすごく大事かなと思ってるし、可能性があると思ってます。
陶山:ありがとうございます。山下さんどうぞ。
山下:そうですね。薩摩という言葉を変革の記号として人々が集うことで薩摩会議も起きてきていると思うんですね。過去にこだわるわけではないんですが、明治維新を支えたお金は、どこから来たのかを考える人があまりに少ない。
明治維新という日本を近代化させた事件を起こした人たちの資金源はどこから来たかということを、もうちょっと考えた方がいいかなとは思います。
陶山:もうちょっと言うとどんな感じですかね。

山下:いろんな島々を当時の薩摩が統治していく中で、島々の畑や田んぼを全部サトウキビに変えていきました。島民は自分たちの食べるものもままならない状態でサトウキビを作らされました。それは砂糖地獄と呼ばれています。そんな風にしてサトウキビに変えていったのは、砂糖が金になるからです。
一方で、幕府が鎖国してた時代も、薩摩は琉球王国を通して密貿易をしたり、甑島や奄美大島を通じてイギリスにも密入国したりしていました。そういったような裏と表を使い分けるために時の為政者たちにうまく利用されてきた側面があるのが島なんです。世の中が変わっていくときの、その影の部分に島の存在があったと思うんです。
明治維新最高、薩摩藩すごいっていうのがここでは表に出るけれど、その一方で裏側には島々の人の涙や苦しみもあります。だからこそ、次の150年を考えたときに、やっぱりこの島的なものが、次は世の中を変えていく。あえてそういう言い方をさせてもらいますが、虐げられていた琉球と薩摩の島々の人が声を上げることに未来の価値があるんじゃないかっていう意味で、薩摩会議で自分たちも一緒になって参加しようと考えています。
陶山:ありがとうございます。麓さんどうぞ。

島の役割あるいはポジショニング
麓:自分たちが奄美大島で暮らしてて、アイデンティティを形成する上で、相対的な何かがないとアイデンティティって生まれなかったと思うんです。本当に長い間、鹿児島に対しても、沖縄に対しても、私達はどうあるべきかっていうのを祖先を含めて考え続けてきたと思います。ようやく自分たちでしっかりとアイデンティティの輪郭が見えてきた感触はあります。対等にコミュニケーションを取れるための発展の段階があったのは島にとってすごく大切なことだなというふうに思っています。
島々が薩摩に対して思いがあるように、他の奄美群島や全国の島々が奄美大島に対して思っていることもあると思うんです。そこで、リーダーシップっていうか、どれだけチームをまとめられるような環境や、風土を作るかっていうこともすごく大事だなと思っています。
すごく個人的なことなんですけども、私は音楽プレーヤー(ドラマー)だったんですが、やっぱ環境作りだなと思ってプレイヤーをやめたんですよ。そうやって活動する中で、プレーヤーに対して共感もあれば、ジェラシーもあるんですが、そのときに本気で裏方に徹するっていう立ち位置を確保することによって、その場をまとめられたという経験がありました。やっぱり島の側が環境作りに挑むっていうところの覚悟みたいなものがあると、国や世界全体の動きにとっていいんだろうなと思います。
陶山:ありがとうございます。ちょっと今のところでもう一つ聞きたいなと思ったのは、自分がそのプレーヤーだったじゃないですか。そこから環境作りに移ろうと思ったきっかけとかはありましたか。
麓:実は、最初の頃は仲間だったり先輩たちとイベントをやってたんですね。そうするとだんだんお客さんが増えてきて、利益性が出てきたんです。最初は趣味の延長でやってたんですが、だんだん利益が入ってくると利益分配して…みたいになってきたんです。
そのときに、あれ、なんか違うなと。何かイベントで利益があるんだったら、それをちゃんとフィードバックして環境作りすべきなんじゃないかなというふうに思い始めたんです。それで先輩に生意気に意見したりしましたね。(笑)
陶山:なるほど。イベントで利益が出始めたときに、何となく違和感があったわけですね。
麓:そうですね。お金のやり取り的なことがあったりして疎遠になることもあるわけですよ。ところが、本気でリスク背負ってやっていくという姿を見せると、ちゃんと数年後にその先輩たちと再合流できるという。覚悟が伝わるという感じですかね。
煩わしさの向こう側にある絆
山下:今の再合流の話で思い出したんですけど、麓さんにその話を、もう8年か、9年前くらいに新婚旅行で奄美大島に行ったときに伺いました。その時は、僕の悩みを聞いてくださったのですが、
「賢太が今、地域とか島のことを想って色々やってるとは思うんだけど、お前をいっぱい嫌ったり、よく思ってない人たちもたくさんいるだろう。でも、5年、10年、20年経ったときに、島を想う賢太の行動が正しいってことがわかるから。」ってまず肯定してくれて。その上で、「今お前のことを嫌ってる人たちが20年後に、ずっと応援してたよ頑張ってるねって近づいてくる瞬間がある。そのときに、お前が何というか。これが本当の地域作りだ」って言われたときがあって。重たい宿題をもらったなと思ったのを覚えています。
もしそうなったら、いやあのとき僕のことをいじめたんでもう絶対嫌です!って言うか、おかげさまでありがとうございますというかで本当に地域の未来が変わってしまうと思ったのを思い出しました。
麓:島は煩わしさの向こう側に絆があったり、心地よさがあったりっていうのがあるので、自分の器とか、その愛情の内訳とか、そういったことを本当に内面的に測られるというか。大変ではありますが、これを解決していくと関係が好転していくっていう感覚がやっぱりちょっと面白いですよね。
陶山:めっちゃ面白いっすね。元々は、人の生活ってきっとそうだったんだろうなという気がしています。でも文明が進んで都市化していく中で、そういう感覚での人間関係ってなかなか形成されにくくなっている気もします。
僕も妻とは喧嘩しても一緒にはいますけど、そうした深い関係じゃないところでも、嫌なことがあっても関係を築いてきたからこそ、新しい面白い文化が生まれてきたし受け継がれてるし、今後も受け継がれてくるんだろうな、そういうところにすごく可能性があるんだろうなっていうのを今の話を聞いてても感じました。
山下:なんか小さな共同体っていうのは自分たちの好きな人とコミュニティを作っていくっていう話じゃないっていうことです。好きでも嫌いでも、年齢も性別もいろんな多種多様な人たちと、制約がある中で、本当のダイバーシティがそこにある。
陶山:そうですよね。本当のダイバーシティって、女性を一定数入れましょうとか外国人入れましょうとかっていうそういう甘い話じゃなくて、もう本当にイライラして夜眠れないぐらいの中で、でもそこで一緒にいると、何か生まれることがあるし、自分がそれで変わっていくことがあるっていうことですよね。
山下:なんかそのときにどうしても今ここにいる人たちだけでは解決できない未来もやっぱりあると思うんです。
全てが自分たちで解決できればもちろん良いですけど、そうじゃないからこそ、この海域というところで鹿児島から沖縄へ向けてこの会議で手を取り合うことで解決できる、新しい未来に向かっていける可能性が僕はあるんじゃないかなと思っています。これまでは事務的に誰かの思惑によっていろんな線が引かれてきたけれども、海は繋がってるわけですよね。
船で行こうと思えば、今から沖縄に行くことができるし沖縄からここに来ることもできる。それをなんかどっかで制限制約があるからできないって思い込んでるけども、これからの時代はそこをとっぱらって、この海域で何かチャレンジしていくようなことあってもいいんじゃないかなと思います。

これからの連携に向けて
陶山:いいですね、面白そうですね。名残惜しくはありますがあと残り5分になりましたので、最後に一言ずつコメントをいただいてもよろしいでしょうか。
比屋根:まずは、お二人の島に伺いたいなと思いました。何が一緒にできるのかっていうのを、現場に行って一緒に同じ時間過ごさないと見えてこないので、まずは行きますっていう話ですね。それで何か一緒に取り組んで、また来年薩摩会議でこんな進展がありましたっていうことを共有できたらいいなと思いました。どうぞよろしくお願いします。
麓:150年後に向けて環境や社会が変わっていくことは時代に合わせて大切なんですけど、共同体に生まれ、他人ごとを自分ごとに思うような愛情の島心というのが、ずっと150年後も変わらずあったらいいなと思います。Give and Giveというようなイメージで未来に臨みたいです。
陶山:ありがとうございました。賢太さんは最後にもっていこうかなと思うので(笑)、僕も少しだけ話したいなと思ったことで言うと、もっと跳ぶということも面白いと思うんですよね。
今の時代、「グローバリゼーションは跳ねる」という言葉のように、今後、人や情報は横に広がるんじゃなくて、まさに島から島へ跳んで、こっちに来て、次はあっちに行ってというように、直接つながっていないところでも跳ねて離れたところに行ったりするようになるのも面白くなりそうだなと思ったので、自分も島に行きますという宣言と、自分も何かやりたいなと思いました。
では最後に賢太さん。

山下:ありがとうございます。そうですね、やっぱり島っていうと、どこかで島だからできないんだとか、島では叶えられないんだとかいうできない理由を探しがちです。だから島を離れて働くとか、そういうのがこれまで当たり前にあった島という中で、なんかやっぱりそれを逆転させていきたいなと思います。島だからできるんだし、島じゃないとできないんだっていう感覚。
そういう世界を作るために自分たちが何をしたらいいのかということを考えています。今生きている私達が手を取り合ってできることとして、例えば、お金がないからできないっていうのを未来には無くしたいんです。
お金だけがあってもできないことがいっぱいある。物だけあってもできないこともある。だから共同体をもう一度自分たちで作り直す中で、できない言い訳をなくしていく。島こそが自分たちのこの夢を叶える場所なんだっていうような子供たちをどんどん育てながら、そういう思いや島心もお金も文化も巡っていく。
そういう世界をこの鹿児島と沖縄その先に台湾があったり、海域っていう中で、挑戦とか人を思ったり、何かそういったものがいっぱい生まれてくる世界を今から始めてたら、いいかなって思っています。なので、僕が言い訳をしないために、皆さんの力をいっぱい借りて何かやっていきたいと思いました。
比屋根:いいですね!台湾も巻き込みましょう。巻き込んで、何か新しい取り組みができたらいいなって思ったので。私がつなぎます。次回は鹿児島から台湾までのつらなりでお話しするということをコミットで。
山下:はい、わかりました。(笑)
陶山:皆さん来年の薩摩会議ぜひ楽しみにしててください。この後、登壇者とぜひ、名刺交換とかしていただければと思います。1時間半、皆さんご清聴いただきありがとうございました。
(ライター:竹下 愛華 校正:SELF編集部)
「あ、鹿児島っておもしろい」そう感じたら、ぜひサポートをお願いします^^ おもしろい鹿児島を、もっと面白くするための活動費として使わせていただきます。
