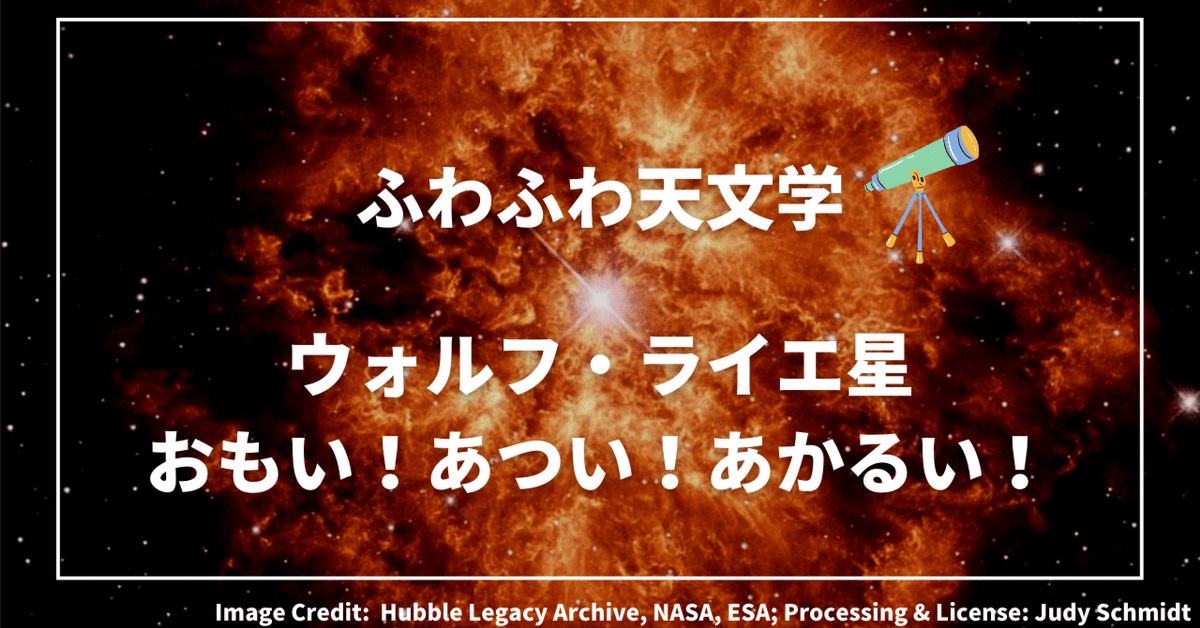
【ふわふわ天文学】 ウォルフ・ライエ星
みなさん、こんにちは、こんばんは、アストロアカデミアです。
とにかくざっくり天文学の世界を覗きたい人のための【ふわふわ天文学】
今日のテーマは「ウォルフ・ライエ星」!
忙しい人のためのウォルフ・ライエ星
ウォルフ・ライエ星は、
重い星が進化した 熱くて あかるい 星
です。
とりあえず、ウォルフ・ライエ星ってどんな星なん?って聞かれたらこう答えておけばOKでしょう。
もうちょっと時間がある人の場合は
ウォルフ・ライエ星は、
「重い星が進化した 熱くてあかるい星で、その光が特徴的なんだよね。」
と伝えておきましょう。特徴的ってなんだよと思ったそこのあなた、天文学の世界へようこそ。
ウォルフ・ライエ星の歴史
約150年前の1867年、シャルル・ウォルフとジョルジュ・ライエ によって奇妙な星が発見されました。この星は、発見者2人の名前をとって「ウォルフ・ライエ星」と名付けられました。

ウォルフ・ライエ星のプロフィール
おもさ(天体の質量)
誕生したときの質量が 太陽の25倍よりも大きい星 がウォルフライエに進化すると考えられています。
温度(天体の表面温度)
典型的な温度は、30000 - 100000 K(ケルビン)です。太陽:6000 K 、シリウス:25000 K なので、これらとくらべてもかなり温度が高いですね。あつそう。
明るさ(天体の光度、等級)
天体の光度は太陽の3万倍から100万倍、等級にして15等ほどあかるい天体なんです!
ウォルフ・ライエ星の特徴
先程から、”特徴的”や”奇妙な星”と言ってごまかしてきたウォルフ・ライエ星 一番の特徴はその スペクトル(*1) です。
ふわふわ天文学 ではとにかくその違いを知ってもらうために 普通の星(太陽)のスペクトルとウォルフ・ライエ星のスペクトルをくらべてみてもらいましょう。

左の太陽のスペクトルは、土台となる曲線に何本も溝が入ったような形に見えますね。この溝のことは天文学では 吸収線 (*2) と呼ばれるものです。
一方で、右のウォルフとライエがはじめて見つけたウォルフ・ライエ星の一つである HD191765 のスペクトルです。おわかりいただけるだろうか?
ウォルフ・ライエ星は、何本もピンとたった線が支配的に見えますね。この線は天文学で 輝線 (*3) と呼ばれるものです。ウォルフ・ライエ星は恒星の中で、輝線が支配的なスペクトルを示す特異な星だったのです。
この原因は、ウォルフ・ライエ星の恒星風に関係しています。詳しく解説したいところなんですが、このさきはゴリゴリ天文学の方にお預けにします。
まとめ

ウォルフ・ライエ星をさらに知りたい人へ
では、なぜウォルフ・ライエ星は輝線が支配的なスペクトルを示すのでしょうか?
また、ウォルフ・ライエ星はどのように進化してきて、どのように死んでいくのでしょうか?
ここからさきは、【ゴリゴリ天文学】ウォルフ・ライエ星 でまとめたいと思います。お楽しみに。
注釈と雑談
*1 … スペクトル
天体からの光はさまざまな色の光の重ね合わせで出来ています。天文学では、光を色ごとに分けたものをスペクトルと呼びます。
*2 … 吸収線
光源と観測者の間に、低温の物体があるとき、その物体によって特定の色(=波長)の光が吸収されてできる線を吸収線といいます。
*3 … 輝線
輝線は、原子や分子によって放たれる光でそれぞれに特定の色が決まっています。このあたりは詳しく別の記事で解説しますね。
ウォルフ・ライエ星は人気が高いようで、いろんなところで使われていることにこの記事のために調べていて気付きました。いくつか書いておきます。
遊戯王カード:星風狼ウォルフライエ/Stellar Wind Wolfrayet
能力にも結構ウォルフ・ライエ星らしさがあって面白い。

競走馬:ウォルフライエ
名付け親はどこで知ったのかとても気になります。
競馬はまったく詳しくない自分でも知っているディープインパクトの子どもだそうです。はやそう。

いつも note のご愛読ありがとうございます! 一人でも多くの方に宇宙を楽しんでもらえる活動を続けられるよう、ご支援よろしくおねがいします。
