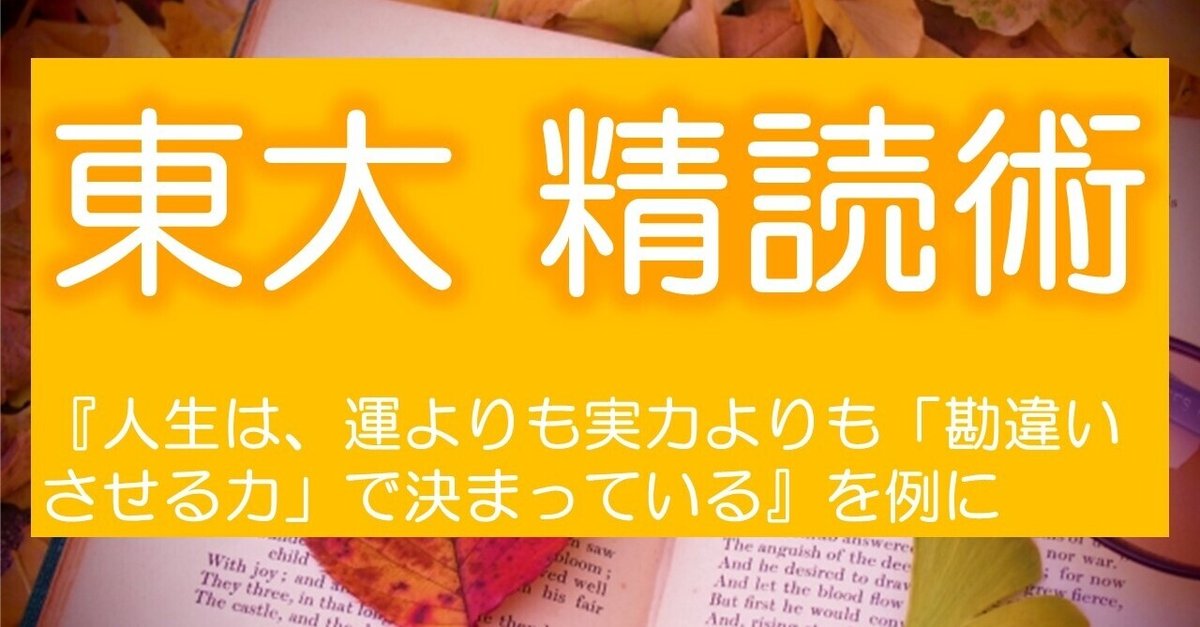
東大精読術✨ー『人生は、運よりも実力よりも「勘違いさせる力」で決まっている』を例に
・本記事のおすすめ度は★★★ 3/3
パラフレーズやディスコースマーカーをあまり意識をしたことのない方には、参考になるかもしれません!
・本記事は5915文字で、約10分で読めます。
今回は、実用書やビジネス書の内容を
しっかりと身に着けるための
読書メモ・読書方法についてハックしていきます。
東京大学の入試の現代文は、
その良問っぷりが有名です。
やどかりも現代文の対策をする中で、
文章を正確に読み解く方法を試行錯誤してきました。
文章を正確に読み解く方法の中でも、
社会人になってからの読書で実践している部分を
お伝えしていきます。
なお、社会人読書と入試と違うところといえば、
具体例も丁寧に拾ってメモするところです。
社会人読書では現実でアウトプットする必要があるためです。
▮ 書籍紹介
今回は、この書籍を例にとって説明します。
『人生は、運よりも実力よりも「勘違いさせる力」で決まっている』
– 2018/8/9(著者:ふろむだ)
やどかりは、💰貧乏性💰のため、次の方法で読書をしました。
①Kindleサンプル版をダウンロード
→「はじめに」の部分の画像をスクショできる
→読書メモに挿入できる
②図書館で借りる
→「はじめに」の部分以降は紙で読む

▮ 東大精読術まとめ
これから説明するポイントは、4つです。
・目次に紐づけてメモを取ろう
・キーメッセージは、パラフレーズに着目して見つけよう
・「はじめに」のメッセージは、すぐ立ち返れるように脳のワーキングメモリに格納しておこう
・広義のディスコースマーカーでつながりを取りこぼさない
目次に紐づけてメモを取ろうキーメッセージは、パラフレーズに着目して見つけよう「はじめに」のメッセージは、すぐ立ち返れるように脳のワーキングメモリに格納しておこ
う広義のディスコースマーカーでつながりを取りこぼさない▮ 目次に紐づけてメモを取ろう
まずは、書籍の宣伝文言をドキュメントの冒頭にコピペします。
ここを読んで、グーグルドキュメントにコピペします。



目次URL↓ 紀伊国屋書店なんかは詳細な目次があることが多いです。
コピペした目次は四角い箱内に入れるのがおすすめです。

挿入した四角い箱に、目次のテキストを挿入します。
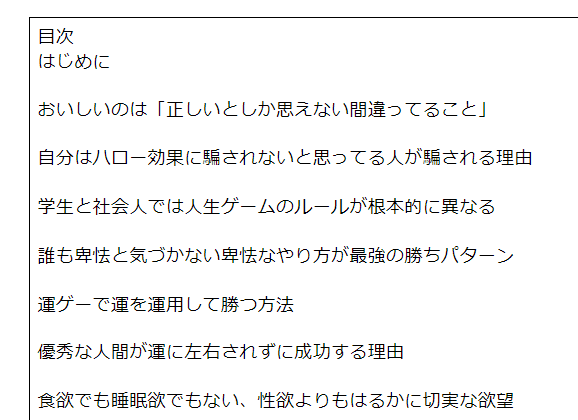
その次に、もう一度同じ目次をコピペします。
それぞれの目次の中に、メモをつけ足していくイメージです。
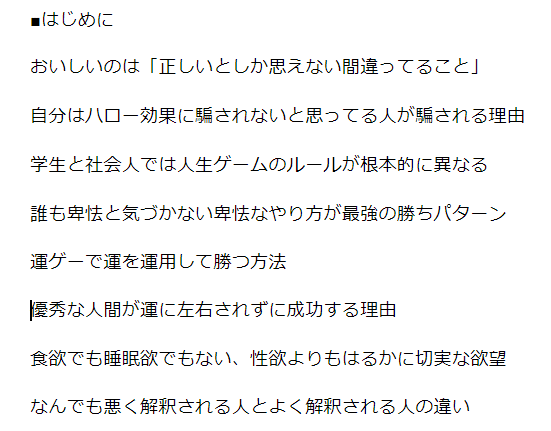
次に、そのペーストした目次を全て選択します。

この状態で、標準テキスト>見出し1をクリックします。

そうすると大きな文字になり、見出しとして認識されます。

ドキュメント編集欄の横に「ドキュメントの概要を表示」という、
リストの形をしたアイコンがあります。

これをクリックしましょう。

そうすると、各行が見出しになり、各見出しにジャンプできるようになります。

▮ 「はじめに」の読み方
「はじめに」の部分は、これから論を展開するに当たり重要なテーマが記述されています。
そこで、ネチネチとロジックを追いかけましょう。



で、このように「人は無意識のうちに人の評価を書き換える仕組み」について記載したのち、
筆者はさらに具体例を出しています。

なので、この部分で追加された具体例は、
読書メモの「同様の研究は山ほどある。」という部分に戻り、追記していきます。


このすぐ後には、こういった具体例の総括として、
「思考の錯覚」「錯覚資産」というキーワードを出しつつ、
「プラスのイメージを引き起こすもの」が、「全体的に優秀」と錯覚させる
→ このような錯覚は、資産として機能する
と述べています。
ここは本書のキーメッセージとなると思われるので、蛍光ペンや太字を使って、しっかり目立たせます。
👉なぜキーメッセージになると思われるかは、次の章で!
本書ではこの後、このキーメッセージに紐づけられる具体例や、このキーメッセージに即した生き方に関して論を展開することが予想されるからです。

実際、この後、
「プラスのイメージを引き起こすもの」が、「全体的に優秀」と錯覚させる現象
=ハロー効果
と説明した上で、
ハロー効果に騙される理由について、
1つの章を割いて説明していきます↓
![]()
さらには、筆者が「もう一つのポイント」として付け加えている点があります。
錯覚資産は掛け算で威力が増大する+複利で増える
ということ。これに関しては、筆者がどのように論を展開していくのかあまり想像がつかないけれど、
筆者自身が「もう一つのポイント」としているので、
本論で迷子にならないようにするためにも、しっかりとメモしておく。

さて、ここまでメインメッセージをしつこく追いかけてきました。
追いかけるだけでなく、それを記録・可視化しています。
そうすると、「はじめに」以降を読み進めていくにあたりやることは、
「はじめに」で筆者が展開したポイントに逐一立ち返る具体例や論理の展開が、「はじめに」で筆者が展開したポイントとどのようにつながるか逐一検討するということになります。
▮ キーメッセージの見分け方
→パラフレーズ
物を書く人というのは、
キーメッセージがまず頭にあって、
そのキーメッセージを伝えるために、
・研究結果や事例などの具体例を出したり
・キーメッセージを展開させたり(その理由や結果の考察など)
して、ボリュームを膨らませるものです。
そして、キーメッセージは、様々な言葉を使って
何度も何度も言い換えます。
キーメッセージを”カルピスの原液”とすれば、
この原液を何度も再利用して、
その濃度を変えながらも、
たくさんの飲料を生産します。(分かりにくいな)
例をみてみましょう。
やどかりは、本書のキーメッセージを次のように読み取りました。
「プラスのイメージを引き起こすもの」が、「全体的に優秀」と錯覚させる(「思考の錯覚」)
→ このような錯覚は、資産として機能する(「錯覚資産」)
その理由は、後半部分(「錯覚資産」の部分)について、
何回も言い換えながら説明しているからです。

■「はじめに」のメッセージは脳のワーキングメモリに格納
さきほど、「はじめに」の章で付け加えている点があります。
筆者が「もう一つのポイント」として、
以下の点を挙げていました。
錯覚資産は掛け算で威力が増大する+複利で増える
案の定、その後の章でこのポイントについて説明がなされていました。
具体的には、錯覚資産が”複利で増える”という点について。

図は、同書P189より引用。
筆者の説明を参考にすると、
・錯覚資産が十分に大きければ、たいして実力がなくてもかなりの成果が出る
・環境に恵まれているから、成果が出るというのもある
→錯覚資産はすべてのループの通過点になっている
このループが回るので、錯覚資産と実力は、相乗効果で雪だるま式に増えていく
「はじめに」で説明されていた
錯覚資産は掛け算で威力が増大する+複利で増える
という点について、
より解像度の高い言葉や図を用いながら
論を展開しています。
P189あたりにこの話が出てくるので、
「あ、これは『はじめに』に書いてあった、錯覚資産の掛け算・複利についての話だな」
と繋げる💡には、
「はじめに」に記載されていたキーメッセージを
脳のワーキングメモリに入れながら
読み進める必要があります。■広義のディスコースマーカーでつながりを取りこぼさない
筆者は、A「美しき敗者と醜悪な勝者、どちらになるべきか?」という章で、次の3点について記載しています。
✅人間は、「バランスの取れた総合的な正しい判断」ではなく、
「一貫して偏ったストーリー」に説得力と魅力を感じる。
✅「一貫して偏ったストーリー」
:「シンプルでわかりやすいこと」を断定しよう
✅そうすれば主張が受け入れられて、錯覚資産が育つ
その次の章は、
B「有能な人と無能な人を即座に見分けられるのはなぜか?」
というタイトルのもと、
「一貫して偏ったストーリー」が受けられることについて
より論を敷衍しています。
”好き”な技術には、
・メリットがあり
・リスクが低い
と評価しがちであるという実験をもとに、
人間の頭の中では、トレードオフはない
トレードオフ:メリットがあってもリスクがある、等
と述べています。そして、大事なパラグラフを引用します。
これは、先ほどの党派性の話につながっている。
人間の直感は、なんであれ、敵か味方に分けて、世界を認識しているのだ。
この実験は、「技術」という、一見無機質なものですら、人間の脳内では、敵か味方に分かれるということを示している。自分が敵とみなした技術は、リスクだらけで、メリットなんてほとんどないし、味方とみなした技術は、リスクは低く、メリットだらけなのである。
P290-291から引用
太字にさせてもらいました。
これは、先ほどの党派性の話につながっている。
この”先ほどの党派性の話”というのが、
A「美しき敗者と醜悪な勝者、どちらになるべきか?」
という章で述べられた3点です。
✅人間は、「バランスの取れた総合的な正しい判断」ではなく、
「一貫して偏ったストーリー」に説得力と魅力を感じる。
✅「一貫して偏ったストーリー」
:「シンプルでわかりやすいこと」を断定しよう
✅そうすれば主張が受け入れられて、錯覚資産が育つ
注意すべきは、
B「有能な人と無能な人を即座に見分けられるのはなぜか?」
この章には、以下のようなキーワードが一切出てこない点です。
・「一貫して偏ったストーリー」
・錯覚資産が育つ
さらには、一見タイトル上の関連がありません。
A「美しき敗者と醜悪な勝者、どちらになるべきか?」
B「有能な人と無能な人を即座に見分けられるのはなぜか?」
しかし、実際には、A章>B章が補足という関係となっています。
✅Aの章は、錯覚資産に関するメインの主張を述べている
=ポジションを取れ
✅Bの章は、人間の脳は敵か味方かでしか判断できないと述べている
✅Aの章>Bの章
Bの章は、Aの章での主張を敷衍し、根拠づけている
そのことを読み取れるのが、
これは、先ほどの党派性の話につながっている。
という部分です。
本書では、この部分は太字にはなっていません。
これは、先ほどの党派性の話につながっている。
しかし、この1文が、
前の章(A章)と後の章(B章)の関係性を示唆する重要な一文になっているのです。
ディスコースマーカーとして機能しているといえるでしょう。
注意なのは、ぼーっと読んでいると、
・人間の脳は敵か味方かでしか判断できないと述べているという話
・錯覚資産のためにポジションを取ろうという話
の2点がつながりません。
独立した知識として納得し、インプットしてしまいます。
しかし、それではやはり、学びの取りこぼしがあります。
人間の脳は敵か味方でしか判断できない(B章)
↓
「一貫して偏ったストーリー」に魅力を感じる(A章)
↓
「一貫して偏ったストーリー」は錯覚資産を作る(A章)
というように理解してこそ、論の流れを追えているといえます。
■やはり行間を補う必要がある
「思考の錯覚のまとめ」という章では、
これまでに解説した認知バイアスについて
手短にまとまっています。
・感情ヒューリスティック
・利用可能性ヒューリスティック
・ハロー効果
・デフォルト値バイアス
・認知的不協和の論理
・一貫して偏ったストーリーを真実だと思い込む
・置き換え
利用可能性ヒューリスティックは、
次の3つのポイントを説明する
”思考の錯覚”となります。
✅人間の直感は、思い浮かびやすい情報だけを使って、判断をする
✅だから、人の「思い浮かびやすさ」をコントロールすることで、自分に都合のいい思考の錯覚を起こさせる
✅具体的には、連絡をとっていなかった友人と食事にいこう、現場での成果を具体的にアピールしておこう
しかし、この3つのポイントを説明する章では、
利用可能ヒューリスティック
という用語は一切出てきません。
「思考の錯覚のまとめ」という章で
利用可能ヒューリスティックの定義が書いてあります。
利用可能ヒューリスティック:脳がすぐに利用できる情報、すなわち、「思い浮かびやすい」情報だけを使って、答えを出す認知バイアス
この定義をみて、それより前の章
「幸運を引き当てる確率を飛躍的に高くする方法」
で説明していた認知バイアスが
利用可能ヒューリスティックなのだなあ
とつなげなければいけません。
なお、利用可能ヒューリスティックの
具体例として挙げられていたものを
蛇足として解説します。
あなたは検査の結果、陽性だった
大腸がんの人の98%は、この検査で陽性になる
大腸がんじゃない人の2%は、この検査で陽性になる
この場合に、あなたが大腸がんである確率は高いだろうか?
陽性ということは、図でいうと黒の面積にヒットしたということ。
ということは、大腸がんである確率は高そうである。

しかし、「大腸がんじゃない人とそうでない人の全部の数」という情報を加えて判断しなければ正確な答えは出ない。
全体の面積も考慮しないといけないのだ。

そうすると、”大腸がんじゃない人がたまたま陽性になった”という面積の方が大きいことになる。
今回検査の結果は陽性だったが、
たまたま投げたダーツの矢が、
”大腸がんじゃない人がたまたま陽性になった”
というゾーンに当たった確率の方が高い。
しかし、人間は、直感的に陽性である確率の方が大きいと思ってしまう。
「大腸がんじゃない人とそうでない人の全部の数」には想いは至らず、
「大腸がんじゃない人とそうでない人が陽性になる割合」だけに着目してしまうから。
このように、
人間の直感は、思い浮かびやすい情報だけを使って、判断をするということがいえます。
その後筆者は、だからこそ、
人の「思い浮かびやすさ」をコントロールすることで、自分に都合のいい思考の錯覚を起こさせることが大切だと論を進めます。
具体的なアクションとしては、
連絡をとっていなかった友人と食事にいこう、現場での成果を具体的にアピールしておこうということです。
▮ 東大読書術まとめ
目次に紐づけてメモを取ろうキーメッセージは、パラフレーズに着目して見つけよう「はじめに」のメッセージは、すぐ立ち返れるように脳のワーキングメモリに格納しておこう広義のディスコースマーカーでつながりを取りこぼさない▮ 編集後記
・思考の錯覚に陥っていることに気づきにくい
・思考の錯覚に陥っていると理解したとしてもなお錯覚してしまう
といった文脈で、ミュラーリヤー錯視が紹介されていました。
上の線と下の線、どうみても下の線が長く見える…
錯視と知ってもなお、長く見える…
ということでやどかりは、線の右端に定規をあてないと
線の長さが同じであると受け入れられませんでした。

皆さんはいかがですか?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
