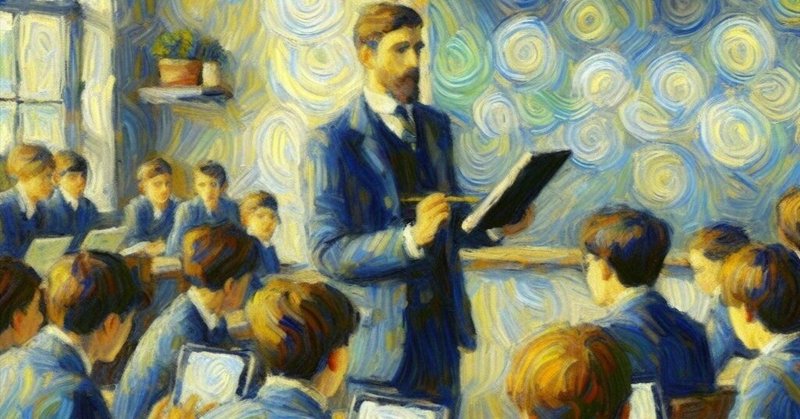
沖縄県立総合教育センター令和5年度 長期研修研究報告会
3月5日(火)〜3月8日(金)の日程で、沖縄県立総合教育センターにて長期研修研究報告会が行われます。
ありがたいことに、今年度は現場を離れて1年もの間、勉強する機会を頂くことができました。(本当に現場の先生方には心から感謝です・・・。)
その集大成となるのが、今週の研究報告会です。
普段は、日々の授業準備や校務に追われ、なかなか腰を据えて研究を進めることができませんが、長期研修に出たことによって、じっくりと一つのテーマについて研究することができました。
教職について今年で9年目になりますが、これは初めての経験です。
GIGAスクール構想の大きな作用
私の研究テーマは、今話題の「デジタル・シティズンシップ」です。
令和元年に始まったGIGAスクール構想により、日本の全小中学生に一人一台ずつ、タブレット端末が整備されました。これが「1人1台端末」です。
教師にとっては、1人1台端末が整備されたことによって、日々の授業を劇的に変化させるものであり、生徒にとっては、「学び方」そのものを大きく変える強力なツールでもあります。
まさに、学校教育において「ゲームチェンジャー」のようなものです。
GIGAスクール構想の(ほんの少しの)反作用
その反面、どの学校でも1人1台端末を起因としたトラブルが起こっているのではないでしょうか。
教師からしてみたら、一番手っ取り早い解決策は、1人1台端末の使用を禁止したり、取り上げたりすることです。
ただ、本当にそれで良いのでしょうか?
多かれ少なかれ、子供たちは、社会に出た時にICTツールを活用することになるはずです。その時、ICTの正しい使い方について考えた経験がなければ、大きく踏み外してしまうのではないかと考えます。
例えば、車を運転する人であれば、「アクセルをどれくらい踏めば、車がどれくらいスピードが出るのか」を体験的に理解しているはずです。
これは、ある程度車を安全に運転できるまで、教習所の敷地の中で練習を繰り返し、さらに公道でも横に指導官についてもらって何度も練習を繰り返した事による賜物です。
もし、運転のやり方もろくに知らずに、いきなり公道に出たら、きっと取り返しのつかない事になるはずです。
子供たちに自分ごととして考える機会を
私は、ICTも車も同じようなものだと思っています。
正しく使えば、とても便利な物ですが、誤った使い方をすると他者を傷つけるものになりかねません。
だからこそ、学校では子供たちがICTの活用方法について、自分ごととして考える機会が必要だと思います。
大人が一方的に管理するのではなく、ICTを活用する中で、時には踏み外したり、失敗したりしたって良いと思います。
むしろ、学校は教習所の敷地内のように安全に失敗できる場でもあります。
生徒会活動を軸としたデジタル・シティズンシップの醸成
このような思いから始まったのが私の研究です。
本実践では、生徒会活動を軸として、生徒の自治的な活動を展開していきます。
その過程では「生徒と教員の対話」や「生徒同士の対話」を推進し、協働的にICTの利用に関する納得会を創り上げていきます。
その具体的な手立てが「『1人1台端末ガイドライン』の策定」です。
私の所属するIT教育班の報告は、三日目の3月7日(木)に行われます。
拙い研究ではありますが、子供たちと一緒に創り上げた実践です。
よろしければ、以下のURLから報告をご覧になってください。
http://www.edu-c.open.ed.jp/post-12.html
また、本実践が少しでも同じような課題を抱えている学校の力になれるよう「1人1台端末ガイドライン策定支援マニュアル」を作成しました。
興味のある方は、是非、以下のリンクからご確認されてみて下さい。
https://kyosys.open.ed.jp/multidatabases/multidatabase_contents/detail/10/1383ca91f0cae8fbbe22254f9f84f184?frame_id=16
今後は、この場から少しずつではありますが、私の学びを発信していきたいと考えています。
私の勉強したことが、少しでもみなさまのお役に立てば幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
