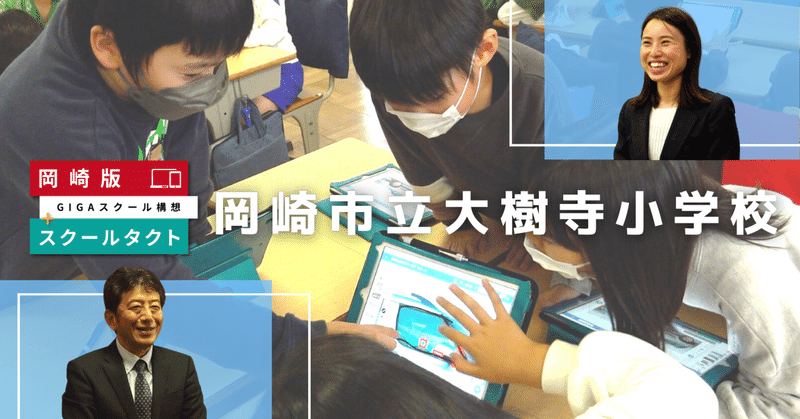
つながり合う安心感とともに、遊び感覚で学べる授業を目指して
「岡崎版GIGAスクール構想」の柱の一つである「学び方改革」に基づき、全ての子供が楽しく参加できる授業を目指す愛知県岡崎市立大樹寺小学校。
大樹寺小学校では、学び合いにつながるチーム学習に加えて、クラス全員で学ぶ体制づくりのツールとしてスクールタクトを活用しています。
チーム学習を取り入れた授業風景、先生方のインタビューは以下の動画でもご覧いただけます。
実際にどのような実践がなされているのか、そしてその背景にある思いについて、校長の坂元干城先生と2年生担任の安藤友紀先生にお話をうかがいました。授業の様子とインタビューを通じ、新たな指導法やそれを受けた子供たちの変化、先生方が目指す学びのあり方について迫りました。
楽しみながら学べる授業を実現したい
徳川家康ゆかりの地ということから、「家康学習」というユニークな学びを1年生から6年生まで実施している岡崎市立大樹寺小学校。同校の校長坂元干城先生は、授業づくりにおいて3つのことを大切にしてほしいと先生方に伝えています。
「私は授業を核にして学校をつくることを大事にしています。そして、その授業づくりの中では3つポイントを設けています。1つ目は、子供に正解を求めない授業を実践してほしいということ。2つ目は、チーム学習によって子供たちの参加度を上げること、そしてその土台となる心理的安全性を担保してほしいということ。最後に3つ目が、ICTを活用するということです。
これからの時代は一層デジタルの活用が重要になっていきます。新たなツールですから慎重に活用をしていかなければいけない側面もありますが、未来の社会で生きていく子供たちを育てていくためには避けては通れない道具だと思うのです」
坂元先生は2020年に岡崎市全校にタブレットが配布された際に「これからの時代にICTは必要だ」と思う半面、「どう使っていけばよいだろう」と悩んだ時期もあったといいます。そんな中、前任校の教員が「こんなものがありますよ!」と坂元校長に紹介したツールが、スクールタクトでした。
「スクールタクトのWebサイトで、子供たちが学んでいる動画を見てピンときました。実際に事例として掲載されていた福島県の新地小学校へ直接連絡をして、私に声をかけてきた教員ともう一名で視察に行く機会をつくってもらいました。二人は2日間視察を終えると、校長室に駆け込んできて、スクールタクトを使った際の子供たちの様子について目を輝かせて報告してくれました。あまりの勢いだったので、急だけれど今日の夕方全職員集めて研修会をやろうと伝えて、新地小学校の視察結果を報告してもらったんです。そうしたら、多くの先生たちが驚いたようで。研修会が終わっても解散せずに車座になって、対話が続いていました」
ー坂元校長先生は前任校から現任校に移っても、スクールタクトの活用を続けています。どのような効果を実感しているのでしょうか。
「教員にとっては、これまでノートの回収後にしかわからなかった子供たちの学習進捗がリアルタイムでわかるようになったという点が大きいでしょう。他にも、ワークシートを作ったり配布したりする手間が減り、圧倒的に楽になりました。子供たちにとっては遊び感覚で学べる良さがあります。友達の意見を見て参考にしたり、話し合ったりしているうちに結果的に学ぶことができている。私は、小学校段階では遊びと学びの境界がないような状態が理想ではないかと思っています。スクールタクトは、遊んでいるうちに自然と学べるような授業をつくる道具の一つではないでしょうか」
授業時間を効果的に使うことができ、子供たちの思考力や表現力を伸ばすことに時間を使うことができることも大きな利点だと感じているといいます。
「以前はクラス全員の考えや回答を共有する時間を授業内で取ることは難しい状況でした。しかし、現在はスクールタクトの共同閲覧モードを使えばすぐに共有できます。効率的に時間を使って、子供たちが思考を深めるための時間を確保できるようになったことはとても大きなポイントでしょう。これからの子供たちが生きていく社会では、情報は簡単に手に入ります。たくさんの情報を詰め込むことではなく、得た情報を組み合わせたり、そこから深く考えたりして、判断することこそが求められます。スクールタクトをはじめとしたICTをうまく活用して、子供たちがいろいろなことを考える時間を授業の中で作っていく、そんな授業実践を増やしていきたいと思っています」

「みんなで勉強をしている感覚」が持てる授業を目指して
大樹寺小学校で2年生を担当する安藤友紀先生は、「個人で考える時間を取った後に、チーム学習で話し合う時間を設けている」といいます。それはチーム学習は子供たちに自信を持たせる大きな意義を感じているからです。
「1人で考えた後に挙手するように促しても特定の子しか発言しないというケースは多いでしょう。1人で考えた後にチーム学習をすることで友達に『一緒だね』『すごいね!』と言われると、自信を持つことができます。友達同士で話し合えることで、すごく子供たちの自信につながっているのではないかと感じています」
スクールタクトはチーム学習のタイミング以外でクラスの友達が何を書いているのかを確認する際に活用しているといいます。以前はノートに自分の意見を書いて隣同士で見せ合ったり、プリントを配布したりする授業が多かったという安藤先生。スクールタクトを使うようになり、「短時間でさまざまな活動ができるようになり、丸つけや成績管理も楽になった」と語ります。さらに、子供の変化も印象的だったといいます。
「以前、勉強が苦手で字を書くことも億劫で、授業中はよく寝ているような児童と接したことがありました。しかし、その子がスクールタクトを使うようになると、すごく楽しそうに授業に臨むようになったんです。板書とノートの学習ですと、書くことが苦手な子はそれだけで面白くなくなってしまいます。この子の場合には、タイピングやゲームが得意だったこともあり、遊び感覚で授業に臨めるようになったのだと思います。どんどん自信をつけていく様子が印象的でした」
スクールタクトの効果は実感しつつも、すべての学びでICTを活用すればいいというわけではないと、安藤先生はいいます。
「特に低学年の場合には、鉛筆で書く練習をした方がいいことやタブレット上の画像ではなく実物を見た方がいいようなこともあるでしょう。子供たちの理解を深めるためにはどんな方法が最適なのか、教員側は常にそのことを考え続けなければいけないと思っています。低学年でもびっくりするほどにICTを使いこなしていますが、ただ、使えればいいということではありませんよね。どんな課題提示をし、どうICTと組み合わせていくかを検討することは重要な教員の役割だと思っています」
ー安藤先生の目指す授業に対して、スクールタクトはどのように貢献しているのでしょうか。
「『みんなで勉強をしている』という感覚を持てるメリットが大きいと思っています。スクールタクトの画面で、他の子の考えを見ることができるので、ゆるやかにつながり合っていると思えるのではないでしょうか。教室での学びから弾き出される子がいないんです。友達が常に隣にいてくれるような雰囲気で、協働的に学ぶことができていると思っています」
誰一人取り残さず、楽しい学びを実現する。そんな授業を目指して、安藤先生の取り組みは続きます。

安藤友紀先生 2年生算数(三角形と四角形)の授業
(スクールタクトを用いた活動を太字で記載)
【導入5分】
■教員
・前回の授業までに学習した、三角形と四角形の定義を確認
・学習課題を引きだすために、三角形や四角形が隠れている写真を提示。児童に写真から三角形や四角形を見つけるよう伝える
■児童
・教室前の画面に投影し、発表児童はペンタブレットを使いながら自分の画面上で発見した図形を囲んでいく

【展開① 15分】
■教員
・スクールタクトに写真を配信(道路標識、自転車などの写真)
■児童
・スクールタクト上で三角形と四角形をマークしていく

【展開② 10分】
■教員
・「お友達の描いているのも見てみる?」と声をかけて共同閲覧モードにする
■児童
・黙々と取り組む子や他の子の回答を確認する子など個別に学習を進める
【展開③ 5分】
■教員
・「話し合い体形にしてください」という投げかけのもと、チーム学習をスタート
■児童
・チームで話し合いながら、お互いの気づきを共有する

【展開④ 10分】
■教員
・「気づいた部分を発表してください」と伝える
■児童
・前の画面に投影し、発表児童はペンタブレットを使いながら自分の画面上で、発見した図形を囲んでいく
■教員
・「歪んでいても四角形といっていいか、チームで話し合ってみよう」と投げかける
■児童
・各チームで意見を発表
【まとめ 5分】
■教員
・「振り返りを書きましょう」と伝える
■児童
・スクールタクトに振り返りを記入
遊ぶように学ぶ授業を目指して
今回は、授業を核にして学校をつくることを大事にし、子供たちが安心感と自信を持って学校生活を送れることを目指す、岡崎市立大樹寺小学校をご紹介しました。
続編として次回は、個別で考えたり学びを深めたりする時間と、チームで学び合う時間の両者を大切にした授業を行う、岡崎市立南中学校の取り組みをご紹介します。
それではまた。
学びとマナビが、ひびき合う。
スクールタクトでした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
