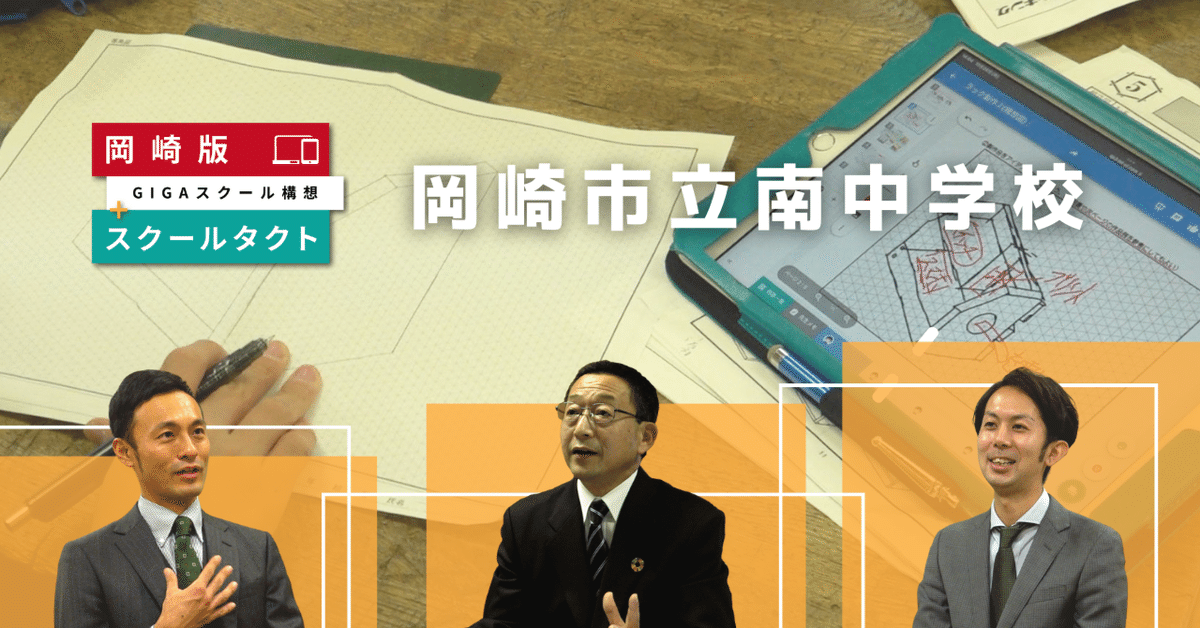
全ての生徒にスポットライトがあたり、一人ひとりの『我がこと』となる学びを
「岡崎版GIGAスクール構想」の柱の一つである「学び方改革」に基づき、生徒一人ひとりが学びに主体的に関わることに重きを置き、多様な教科や授業外活動でスクールタクトを取り入れている愛知県岡崎市立南中学校。
個別で考えたり学びを深めたりする時間と、チームで学び合う時間の両者を大切にした授業が行われています。そこでは、ICTで生徒の学びの履歴を残し、振り返りを行うことも重視されています。
南中学校の授業風景、先生方のインタビューは以下の動画でもご覧いただけます。
同校の取り組みの詳細について、校長の加藤有悟先生、技術科の手島憲人先生、英語科の安藤翔太先生にお話をうかがいました。実際の授業とインタビューから見えた、個で考えていく力、多様な考えに触れながら他者とともに課題に向き合う力、それぞれの力を育てていく学びの実践をお伝えします。
全ての生徒が主体的に授業に関わるきっかけに
岡崎市立南中学校は校訓として「明朗にして自由 健康にして溌剌」を掲げ、重点努力目標として「学びの南中」「コミュニケーション能力を育てる南中」「自主・自立の南中」「健康・安全な南中」「教職員も幸せな南中」の5つを設定しています。
加藤有悟校長はこれらの同校の伝統の上に、「教育目標として『一生幸せ教育』というテーマで教育活動を進めている」と語ります。ここには、「生徒が生涯にわたって幸せに生きることができるような基盤を中学校で作りたい」という思いが込められているといいます。
同校の重点努力目標の一つである「学びの南中」の中では、特に生徒一人ひとりが学びに主体的に関わることを大事にしています。その施策の一つとしてICTの活用を進めています。
「英語科では教科書も電子版が配付されていますし、電子黒板を使ったピクチャーカードの表示などICTを効果的に取り入れています。スクールタクトの共同閲覧モードを使った学び合いも多くの先生方が実施している状況です。先日は、社会科の研究授業として、中部地方の地理学習で『田原市は農業日本一に返り咲くことができるか』をテーマに学級全体で話し合いを行いました。その授業では『できる/できない』の立場に分かれて話し合いをしたのですが、生徒一人ひとりがスクールタクトに意見を書いて読み合い、その上で話し合いをしており、学び合う効果を実感できました」
また、授業だけでなく生徒会活動で「本日の議題」としてみんなで意見を書いて出し合うといった活動にも使われています。
「スクールタクトは教科の授業から学級活動、生徒会活動、部活動など活用の幅は広いです。生徒間の情報共有に利用でき、しかもその中身も文字情報、写真情報、手書きの情報、音声記録などあらゆるデータが共有可能。私は校長として先生方のさまざまな活動を見ているのですが、多様な表現方法があることで、学習の厚みが出ています。また、生徒の学びを保管するポートフォリオとしての機能も期待できると思っています」
何よりも、生徒一人ひとりが学びに主体的に関わることに価値を感じていると加藤校長先生は続けます。
「共同閲覧モードを使うことで、全ての生徒にスポットライトがあたることで、一人ひとりが『我がこと』として、いろいろな活動に取り組めます。まさに主体性の育成につながっていくのではないでしょうか。自分が書いたことはみんなに見てもらうことができる。置き去りにされないことで、自分もクラスの一員だという意識を高めていけるように思います。
生徒にとっては『自分の参加度が高まる』『自分のことをちゃんと見てもらえる』『より“個”が大切にされる』そういう授業や活動にできる可能性があると思っています。教員にとっては一人ひとりの生徒の学習進捗や意見を把握することができる、そしてより良い助言や支援ができるようになっていくのではないでしょうか」
加藤校長先生は、今後も学習定着度なども押し測りながら、発達段階に応じて生徒の能力を成長させていく鍵としてICTを活用していく方針です。

個別最適化を実現しながら、学び合いを取り入れる
同校に赴任して2年目の手島憲人先生は技術科の授業を担当する中で、個別最適化とチーム学習を実現したいと考えています。
「私は個人のペースで自分の課題を解決していけるような個別最適化された技術の授業をしていきたいと考えています。そういった意味で、スクールタクトに作業の工程や道具の使い方のポイントを簡潔に全て載せておいて、あとはタブレットを見ながら自身で作業を進めていけるようにしています。授業を欠席した場合でも、前回のスクールタクトを開けば何をすればいいかわかるようになっています。そして、作業に行き詰まったらグループの生徒に助けてもらう。その重要性も体感してほしいです」
今回見学をした「ラックを作るために等角図(※1)を描く」の授業では、まさに生徒個別の学習と学び合いが組み合わされた授業となっていました。そのねらいを手島先生はこう語ります。
※1 製図の際に用いる図法のひとつで、物の形状を斜め上から俯瞰した図。
「授業で物作りしてく上で大事にしたいのは、それぞれの生活の中で問題を見つけて、それを解決できるような作品を作ることです。本単元では、まず生徒たちが生活の中から『片付かない』などの問題を見つけて、それを解決できるようなラックを考えていきました。
しかし、自分一人で考えているだけでは想像していたものにならないケースもある。例えば、『マンガを片づけたいということだけれど、そのスペースに入るかな?』といったチームメンバーの指摘にハッとすることがあるんです。客観的な視点により、自分一人ではなかなか気づけない問題を炙り出すことができるんです。そういった意味で、他者と関わってお互いにアドバイスする時間も非常に重要だと考えています。対話する中で出てくる言葉もあると思うので、4人で1テーブルでのチーム学習の時間を設けています」
手島先生は「個」で考えることを大切にしながらも、それだけでは限界もあると考えています。自分の学習をサポートするツールとしてスクールタクトの共同閲覧モードも活用しています。
「最初は個人で考えてほしいのですが、どうしても手が止まってしまう生徒はいます。そのため、ある程度個人ワークの時間を設けたら共同閲覧モードにします。なかなか前に進めない場合には、他の生徒のアイデアを見て『真似をする』ということでもいいと思うんです。また、授業の最後には自分がどこまで作業が進んだかをチェックシートと写真とともにスクールタクトへアップします。クラスメートの振り返りを見て自分のペースを調整することにも役立てているのです。最後は完成させる必要があるので、他の生徒の進捗を確認しペース配分していくことも大切でしょう」
手島先生はスクールタクトを使うことで積極的に発言をする生徒以外にもスポットライトが当たる可能性があると感じているといいます。
「発言することは苦手だけれど、描くことや作ることは得意な生徒は少なくありません。そういう生徒の作品を大画面に映して、具体的に褒めることもしています。また、『いいね』を押してみようと呼びかけることもあるので、生徒間でも見てもらえてうれしさが芽生えているかもしれませんね」
手島先生は今後、スクールタクトの機能が多様になり、いっそう授業で使いやすくなることを期待しているといいます。
「例えば、図形が3Dで出てくるような機能ができると、技術科としてはとてもありがたいですね。そしたら、製図ではなく立体上で組み立てられるような授業もできるはず。そんな時代がきたら、ICTを使った学習ならではのメリットをより実感できるようになるでしょう」

手島憲人先生 1年生技術(ラック制作)の授業
(スクールタクトを用いた活動を太字で記載)
【導入 10分】
■教員
・教室前の画面にこれまでどう木材を切ってきたかを投影。授業のねらい(めあて)として「等角図で自分の作りたい作品を描く」を提示。「ラックを作ることで生活の中の片づけたいものを書いていきましょう」と投げかける
■生徒
・個人でスクールタクトに、「充電コードをきれいに収納したい」「机の横にものが散らばりがち」「マンガ置き場がほしい」といったそれぞれの課題を記述していく
【展開① 10分】
■教員
・「チームでシェアしてみよう」と投げかける
■生徒
・それぞれの課題をシェアし、自分の棚に活かせそうな視点をメモしていく
■教員
・「メンバーの話を聞いてアイデアが広がっているようなので、さらに広げるために共同閲覧モードにします」と伝える
■生徒
・スクールタクトの共同閲覧画面を見ながら、活かせそうなアイデアを自分のメモに書き加える

【展開② 10分】
■教員
・「自分の課題を解決し快適になるラックのアイデアスケッチをしてみましょう」と投げかける
■生徒
・フリーハンドでペンタブを使ってアイデアスケッチを描く

【展開③ 10分】
■教員
・「近くの人同士でお互いのアイデアスケッチを見合い、置きたいものが置ける棚になっているか確認しよう。もっとこうした方がいいというアドバイスがあれば教えてあげてください」と声かけをする
■生徒
・「二段ラックにしてたくさん置けるようにした」「マスキングテープを挿して置いておけるように輪投げ型の部品をつけた」といったそれぞれの工夫を話し合う
【1コマ目まとめ 10分】
■教員
・「アイデアスケッチを等角図にしていきましょう」と伝える
■生徒
・個人作業で実寸の2分の1の大きさにして等角図を描く
■教員
・生徒の席の間を見て回り、個別に指導しながら「まずはこの線から描くとわかりやすいね」「125mmはcmに直した方がわかりやすくない?」などアドバイスをする
■生徒
・手が止まっている子に対して自然に「ここはこう描いた方がいいんじゃない?」といった教え合いが生まれる
<2コマ連続授業のため次授業へ作業が続く>

アウトプット重視の授業によって自立した学習者を育てる
同校に赴任して2年目の英語科の安藤翔太先生は、5年程前はインプット中心の学習を行っていたといいます。しかし、現在は生徒が主体的に動くアウトプットを重視した活動的な授業を展開しています。
「以前はフラッシュカードで単語を覚えさせたり、教科書を何度も音読したりする授業を行っていました。しかし、次第に自分自身の授業に疑問を抱き始めます。「『果たして、私の授業では社会に求められている力をつけることができているのだろうか?』と思ってしまって。考えあぐねていく中で、目的・場面・状況に合わせて自分の意見や考えを言えるようにすることが一番大事なことではないかと思い至り、とにかく自分で表現できるようにする力をつけたいと思うようになりました」
授業が大きく変わったのはICTの普及のタイミングだったといいます。
「私が授業を転換できたのは、GIGAスクールでタブレットが一人一台導入されたことが要因として大きかったです。英語では、タブレットがあれば、録音し聞き返すことやプレゼンテーション資料を作ることができます。こんなにいい『アウトプットができるツールはないな』と、強力な武器を手に入れたように思いました。英語で重要な『聞く(リスニング)』『話す(スピーキング)』『読む(リーディング)』『書く(ライティング)』の4技能をバランスよく育成するのに有効なツールだと感じました」
安藤先生はアウトプット中心の授業とすることで、生徒たちが英語の楽しさを感じる機会をより多く創出できると考えています。
「一番大事にしたいことはすごくシンプルで、『英語で話すことは楽しいな』と生徒たち全員に感じてもらうことです。それに加えて、英語が得意になった子には、その力をどんどん伸ばしていってもらい、グローバルで活躍するようになったらそんな幸せなことはありません。コミュニケーションや自分を表現する楽しさを味わえる授業にしたいと考えたときに、スクールタクトは助けになる存在です」
また、安藤先生は生徒たちの学びの記録としてもスクールタクトは有効だと考えているといいます。
「スピーキングテストの際に動画を撮って、スクールタクトにあげるような活動をしました。そうすると記録としても残せるので自分で後で見て振り返り、自己評価に活かすことができます。前よりもできるようになっていたら達成感を覚え、『できた』と感じると、楽しさも味わえるでしょう。自分のパフォーマンスを見ることに対しては、抵抗感を感じる子もいますが、『どこが良かったのか』『何が足りなかったのか』を振り返ることは成長していくためには大切な機会です」
安藤先生はそれぞれの生徒の学習進捗の把握がスムーズになったことにも手応えを感じているといいます。
「これまでのプリントやノートでの学習の場合、全部集めてパッと見てまた返すという煩雑な工程が余儀なくされていました。しかし、スクールタクトの場合は授業中でも、授業直後でも、生徒の取り組みを確認して理解度を推し量ることができます。生徒把握がスムーズにできることになったことで、次の打ち手も講じやすくなりました」
安藤先生は、今後、自身の目指す教育のあり方についてこう語ります。
「私は、自立した学習者を育てたいと強く思っています。『言われたからやる』『先生から指示されたからやる』ではなくて、生徒たち自身で『課題は何か』『今、自分に足りないものは何か』を考え、それに向けて、行動やアウトプットをしていく力を付けさせたいと思っています。現在、授業でチームの中で助け合いながら、それぞれの課題をクリアしていく様子が見られるようになりました。多様な仕組みやツールを活用しながら、自立した学習者への道をサポートしていきたいと考えています」

安藤翔太先生 2年生英語(比較の表現)の授業
(スクールタクトを用いた活動を太字で記載)
【導入 10分】
※教員の指示はほぼすべて英語で実施
<Review>
■教員
・本授業の目標「比べる表現を使って表すことができるようにしよう」を伝える。授業の流れ「<Review>→<Key Sentence >→<New Word>→<本文Check>→<本文音読>」を黒板に示す。比較表現を使って、ペアで話し合ってみようと投げかける
■生徒
・ペアを変えていきながら比較表現を使った会話を暗唱する
■教員
・スクールタクトのスライドを見るように促し、比較表現を使って文章にするよう伝える
■生徒
・スライドを見て、スクールタクトに記述していく

【展開① 10分】
<Key Sentence >
■教員
・デジタル教科書の動画を見せてヒアリングさせ、チームで聞き取った内容を話し合うよう伝える
■生徒
・チームで話し合う
■教員
・解答をデジタル教科書で音声を流して確認
■生徒
・解答を復唱する
【展開② 5分】
<New Word>
■教員・生徒
・教室の前に置かれた大画面に穴埋めとなっている英文を表示。音声を流して、穴埋めの内容を生徒たちが聞き取る
【展開③ 10分】
■教員
・個人で音読をするように伝える
■生徒
・起立して教員の発音に倣い、個人で音読。終わった人から着席
■教員
・「話せるようになったものを今度は書いてみよう」と英作をするよう伝える
■生徒
・スクールタクトに比較級を使った表現を英作する

【展開④ 5分】
<本文Check>
■教員
・チーム学習を再開
■生徒
・チームで自分が書いた英作の内容をシェア。書けていない生徒はこのタイミングで加筆修正。シェアが終わったチームは音読を練習

【展開⑤ 5分】
<本文音読>
■教員・生徒
・クラス全員に音読をするよう伝え、読み上げる
【まとめ 5分】
<本文Check>
■教員
・2つのスライドを提示して、比較を使って表現するよう伝える。答えは一つではない問題なので、生徒は既習の知識を組み合わせて解答を考える。例えば、「時計とお金のイラスト」を並べて、「Money is more important.」などの表現を導く。スクールタクトの共同閲覧モードに切り替えたことを伝える
■生徒
・クラスメートの記述も参考にしながら自身の解答を作成する
生涯にわたって幸せに生きられる基盤づくりを
今回は、全ての生徒にスポットライトがあたることで、一人ひとりが『我がこと』として、学びに主体的に関わることを目指す、岡崎市立南中学校をご紹介しました。
続編として次回は、市の構想に先駆け、約5年にわたり生徒たちが主体的に学び合うグループ学習を推し進めてきた、岡崎市立竜南中学校の取り組みをご紹介します。
それではまた。
学びとマナビが、ひびき合う。
スクールタクトでした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
