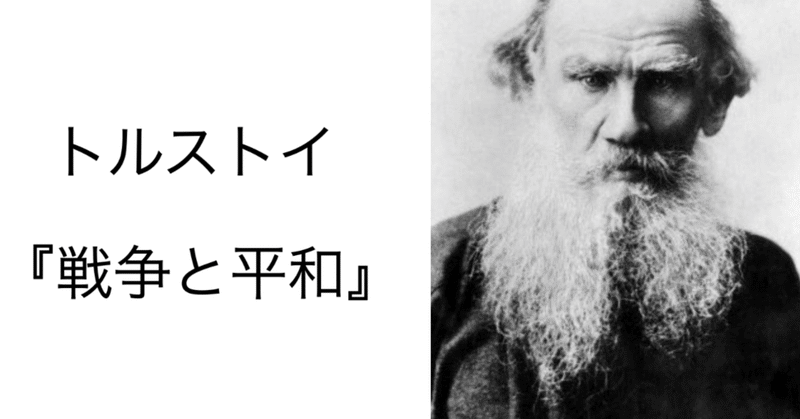
トルストイ『戦争と平和 第三部第一篇』読書会(2024.2.16)
2024.2.16に行ったトルストイ『戦争と平和 第三部第一篇』読書会のもようです。
解説しました。
私も書きました。
憲法にとらわれない民兵組織による国防は歴史的標準である
フランス革命によってブルジョワ階級を政権に組み込んだフランスは、ブルボン王朝に通じる周辺王国の反革命的介入を阻止すべく国民皆兵制を整備した。これが、ナポレオンの大陸軍(グラン・ダルメ)のはじまりである。ナポレオンの出世は、門閥にとらわれない実力主義によって可能になったのであり、彼の勇敢な部下も、同じく実力主義によって組織されていた。これが世界最強の大陸軍を支えていたのである。
フランス式の教育を受けたアンドレイやピエールは専制君主制のロシアの近代化が必要だと思っていた。読み書きもままならない農奴を抱えた地主貴族が支配者層とあっては、ブルジョワ的産業資本は育たないし、国の生産力もあがらない。
ナポレオン戦争の本質は、先に近代化した貿易大国のイギリスと、本来は農業国家でありながら革命によって急進的な近代化を遂げたフランスとのヨーロッパ大陸における覇権争いであった。
ロシアは、先に述べたとおり、地主貴族の支配する農業国で、自国の産業基盤が弱く、工業製品をイギリスからの輸入に頼っていた。イギリス・フランスと比べても近代化の後進国であった。スペランスキーが近代的改革しようとしたが守旧派に邪魔され頓挫した。
ナポレオン軍の侵攻に徴兵で対処するか、義勇兵や民兵組織で対処するか、方針が定まらない。皇帝と国民の合意もないまま、あいまいな封建的な権威によってモスクワには挙国一致体制ができあがる。
全然話は変わるが、三島由紀夫の結成した「楯の会」は、民兵組織である。日本国憲法の私生児である自衛隊で日本を守るのは無理ということで、ここは一つ、民兵に頼ろうと、三島先生は考えたそうである。三島先生の考えは、意外や意外、モスクワ陥落後に、民兵隊を組織したデニーソフやドーロホフなみに骨太で、なおかつ反動的あった。
(引用はじめ)
ヨーロッパ諸国の軍事制度を研究した者は、むしろ戦前の日本の国軍一本化がむしろ異例であることを知つてゐます。正規軍以外の各種の軍隊の並立のうちに発達してきたヨーロッパ軍事制度の歴史に鑑み、日本の戦前の軍事制度に関する常識を、戦後の平和憲法下の特殊事情を考慮して、一ぺん徹底的に考へ直し、真に有効な現代的方途を発見してゆかなければなりません。
現に戦時中も、総力戦体制と称しながら、軍の権力構造を保持するために、知識人や行政上経営上の指導者をも一兵卒として召集し、無理な一本化を急いだ弊害のみを助長させた教訓は近きにあり、むしろ、戦争末期は市民軍の養成を別途に推進すべきであつたのであります。
— 三島由紀夫「祖国防衛隊はなぜ必要か?」 (ウィキペディアの『楯の会』より引用)
(引用おわり)
アンドレイもピエールも「まずは隗より始めよ」で、自身の領地の近代化に取り組んだ。アンドレイの改革は、ナポレオンの侵入で頓挫、ピエールは、領地経営の才に乏しく、成果をあげられなかった。
それでも、彼らは、少なくとも専制君主制を、穏やかに立憲君主制に移行していかなければ、ロシアの未来は暗いと危機感を抱いている。近代化を推し進め、ロシアの国力を強化しなくてはならない。でなければ、ロシアに勝利したナポレオンが、イギリスとの覇権争いに終止符を打った暁には、ロシアはフランスの衛星国として分割統治されてしまう。その衛星国の支配者は、ナポレオン一族にとって代わられるだろう。
そうなれば、ますますロシア固有の文化は破壊され、アンドレイやピエールが反感を抱く、リーザ的なもの、エレン=アナトール的なもの、つまりは、おフランス直輸入の享楽的個人主義とそれに伴う道徳的退廃によって、ロシアの魂は徹底的に蹂躙されつくすだろう。
祖国戦争の背景には、分割統治されるかもしれないロシアへの危機感が隠されている。
第三部第二編に描かれる「ボロジノの戦い」では、ロシアの民族的ファナティシズムが玉砕行為となって炸裂する。
(おわり)
読書会のもようです。
お志有難うございます。
