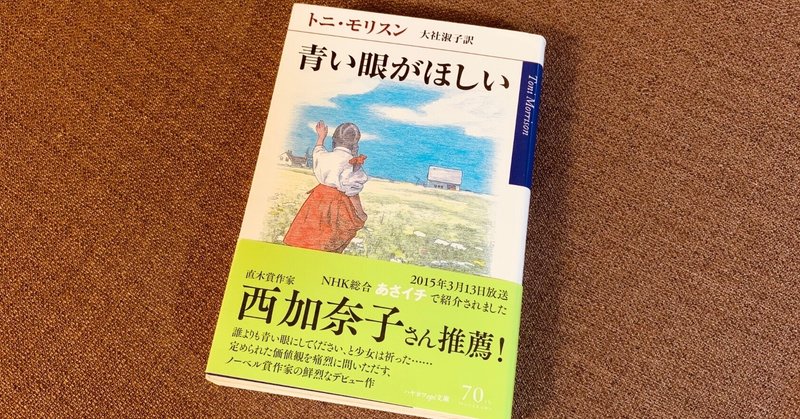
【読書録】『青い眼がほしい』トニ・モリスン
今日ご紹介する本は、トニ・モリスン(Toni Morrison)の小説『青い眼がほしい』(原題は "The Bluest Eye" )。私が読んだのは、ハヤカワepi文庫版(大社淑子訳)。
トニ・モリスンは、ノーベル賞作家。アフリカ系アメリカ人の女性作家としては初めての受賞だったという。この作品『青い眼がほしい』は、そんな彼女のデビュー作。1970年の作品だが、広く世界で読まれるようになるには、25年もの長い期間がかかった。
この作品の舞台は、1930年代のアメリカ中西部。主人公は黒人の少女、ピコーラ。黒人差別の時代に彼女を襲った悲劇と彼女の悲惨な人生についての物語だ。しかし、この作品は、白人対黒人という単純な構図を超越して、さまざまな問題を浮き彫りにする。社会に植え付けられた差別的価値観がもたらす、集団心理。それに影響される人間の、嫉妬、優越感、劣等感、嫌悪感といった、醜い感情。そんな感情に突き動かされての、残酷な言動。それがさらに他人やコミュニティに及ぼす影響。
以下、私の特に印象に残ったくだりを引用しておく(ネタバレにはご注意ください。)。
**********
それは、クリスマスと人形の贈り物から始まった。大きくて、すてきで、特別な贈り物は、いつも大きな青い眼をしたベビードールだった。おとなのたてる、にわとりに似た声の響きから、わたしがいちばんほしがっているのはその人形だと、彼らが考えていることがわかった。わたしは、人形とその外見にまごついた。どう扱ったらいいのだろう? 人形の母親のふりをすればいいだろうか?
わたしは、白いベビードールをこわした。
しかし、人形の手足をばらばらにするのは、本当の意味で恐ろしいことではなかった。本当の意味で恐ろしいのは、同じ衝動を小さな白人の女の子に移すことだった。白人の女の子にたいしては何も感じないで斧をふるえるような気がしていたが、実際に斧をふるいたいと思うときだけはさすがに無関心ではいられなくなった。わたしからすべり抜けてしまったもの、白人の女の子がほかの人たちの上に織り出す魔法の秘訣を探りだすこと。人人(※原文ママ)が彼女たちを見て「まあ、かわいい」と言うのに、わたしにたいして言わないのは、どうしてなのか。路上で彼女たちに近づくときの黒人女の目づかい、彼女たちを扱うときの独占欲の強い、やさしい触れ方の理由を見つけること。
(・・・)わたしのこの眼がちがっていれば、つまり、美しかったとしたら、わたし自身もちがっていたはずだ、という考えが、ピコーラの心に浮かんだ。
青い眼にしてくださいと、毎晩かならず彼女は祈った。熱心に一年間祈った。一年たって少し落胆はしたが、望みを捨てたわけではなかった。こんなにもすばらしいことが起こるには、長い、長い時間がかかるものだから。
こういうふうにして、奇蹟だけが自分を救ってくれるという強い確信に縛られていたので、彼女は決して自分の美しさを知ろうとはしなかった。彼女はただ、見えるものだけを、つまり、ほかの人々の眼だけを見て暮らした。
「黒んぼやーい。黒んぼやーい。おまえのおやじは裸で眠る。黒んぼやーい、黒んぼやーい。おまえのおやじは裸で眠る。黒んぼやーい・・・・・・」
彼らは、犠牲者がどうすることもできない事柄、つまり彼女の肌の色と、おとなの寝癖についての憶測という、理不尽なことにかけてはひけをとらない二つの侮辱の種をもとにして、即席の歌をつくりあげていた。自分たち自身が黒人であることと、自分たち自身の父親も同じようにくつろいだ癖を持っていることは、この場合、問題ではない。最初の侮辱に激しい勢いを与えているのは、自分たち自身の黒さにたいする軽蔑だった。彼らは、自分たちが難なく育てあげてきた無知、みごとに学び取った自己憎悪、入念にもくろんだ無力感のすべてをすくいとり、長い間、心のくぼみで燃えていた火のような軽蔑の円錐形のなかに吸い上げてーさましー憤激したくちびるからこぼしながら、通り道にあるものすべてを焼きつくそうとしているように見えた。彼らは犠牲者のまわりで、病的なバレエを踊っている。彼らは、自分たちの慰みのために、この哀れな娘をいけにえにして、焔を上げて燃えている穴に突き入れようとしていた。
(・・・)わたしたちは人形をこわすことはできたが、この世のモーリーン・ピールたちに出会ったとき、両親や叔母たちが出す蜜蜂のように甘い声、仲間の眼に宿る服従の色、教師たちの眼に浮かぶへつらうような光をこわすことはできない。この秘密は何だろう。わたしたちに欠けているものは何だろう。どうして、それが重要なのか。それに、そうだから、どうだというのか。
(・・・)彼女は子供に、黒人とニガーの違いを説明した。このちがいは簡単にわかるのよ。黒人はきちんとしていて静かだけど、ニガーは汚くて、大声で話しますからね。
(・・・)わたしたちはみんな(中略)彼女の上でからだを洗ったあと、とても健康になったような気がしたものだ。わたしたちは、彼女の醜さにまたがったとき、ひどく美しくなった。彼女の素朴さがわたしたちを飾り、彼女の罪がわたしたちを神聖にし彼女の苦痛がわたしたちを健康で輝かせ、彼女の不器用さのおかげで、わたしたちは自分にユーモア感覚があると思ったものだ。彼女は口下手だったので、わたしたちは雄弁だと思い込んだ。彼女の貧しさのおかげで、私たちは気前がよくなった。彼女の白昼夢さえ、わたしたちは利用したー私たち自身の悪夢を鎮めるために。彼女はこういうことをわたしたちに許してくれたので、わたしたちの軽蔑を受けるのにふさわしいものとなった。わたしたちは、彼女を犠牲にして自分たちの自我をみがき、彼女の弱さでわたしたちの性格に詰め物をし、自分たちは強いという幻想を抱いて、あくびした。
(・・・)愛は、けっして愛する以上にはならない。よこしまな人々はよこしまに愛し、はげしい人々ははげしく愛し、弱い人々は弱く愛し、おろかな人々はおろかな愛し方をするが、自由な人間の愛が安全なことはかつてない。愛する者に捧げる贈りものがないからだ。愛する者だけが、愛の贈りものを持っている。愛される者は、愛する者のぎらつく内なる眼の光のなかで、裸にされ、無力にされ、凍らされる。
(・・・)ここの土は、ある種の花には合わないのだ。ここの土はある種の種子を育てようとしないし、ある種の実は結ばせない。そして、土地がそれ自身の意志で殺す場合、わたしたちは黙認して、犠牲者には生きる権利がなかったのだという。
**********
主たる語り手のクローディアは、黒人の少女。子どもの目を通して語られる出来事の描写は、あまりに生々しく、痛ましい。
自分が周りから愛されないのは、美しいと評価される白人が持つ「青い眼」がないからだ、という少女の思い込み。原題の "The Bluest Eye" を直訳すると「最も青い眼」だ。眼が青ければ青いほど美しいと考えた少女の、この "Bluest" という一語に込められた強い羨望を思うと、やるせなくなる。
そして、黒人同士の間でも、優劣をつけようとする発想。他人が自分よりも劣っていると考えることによって、自分自身の存在価値を見出そうとする子供たち。なんと悲しく、愚かなことだろうか。
現在の私たちにも、こういった心の動きがないと断言できるだろうか。世間が良しとする基準から外れているという理由で、自分を価値のない人間だと思ったりしていないだろうか。自分に自信を持ちたいために、無意識のうちに、自分より劣った他人を探し、差別的な眼を向ける誘惑に屈してはいないだろうか。そして、集団において差別的な意識を黙認したり、差別的な言動に加担したりしてはいないだろうか。
なんとも強烈で衝撃的な作品だが、人間の性を知るために、全ての人に勧めたい本だ。
ご参考になれば幸いです!
私の他の読書録の記事へは、以下のリンク集からどうぞ!
サポートをいただきましたら、他のnoterさんへのサポートの原資にしたいと思います。
