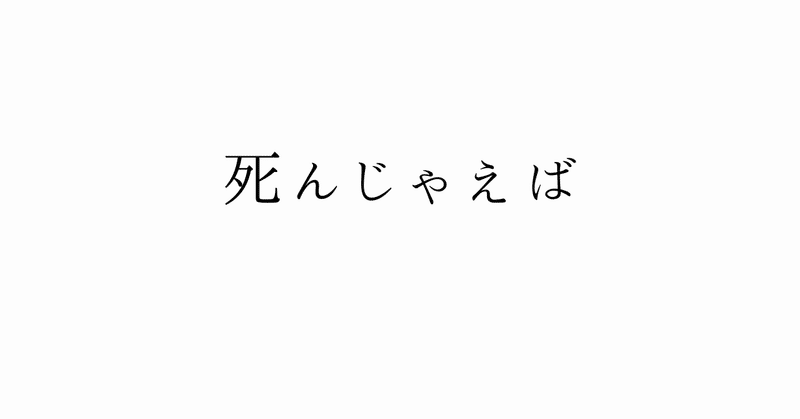
短編小説『死んじゃえば』
『じゃあさ、死んじゃえば?』
チャイムが鳴り終わって、亜季は私に向かってそう言った。
退屈な授業中、私と亜季でこっそりとメモの交換をしていた。
"人生ミスったわ"
"わかる"
"大学とかムリ"
そこまでいって、チャイムが鳴った。
担任が、宿題を忘れるなとか身だしなみがどうとか言っているけれど、皆はいつも通り無視していた。
私達もご多分に漏れず、担任の話を無視して、お互いの椅子の背を向かい合わせて馬乗りになった。
「亜季はどうするの?」
「私も未来と同じ。だから、そろそろ潮時かなぁって」
"未来"というのは私の名前だ。
ミライ、なんて美しい響きだろうか。よくもまあ、こんなにも仰々しい名前を付けてくれたものだと思う。
私の両親は、父が「貴史」母が「美智子」という、至って普通の名前だった。
そして、その娘の私が"未来"。
いわゆる"キラキラネーム"という程では無いけれど、やっぱりなんだか、ちょっと大袈裟だと思う。
未来とか、将来とか。そういう前向きな言葉は、カッコつけすぎていてダサいって、前にテレビでコメンテーターが言っていたのを思い出す。
その点、今目の前に座る亜季はカンペキだ。
当たり障りのない無難な名前。誰の目にもつかずにやり過ごせるくらいには目立たない。そんな名前。
亜季の背後の窓の隙間から流れ込むそよ風が、枝毛ひとつ無い美しく長い黒髪をかすかに揺らした。
筆のように綺麗にまとまった毛束を、指先で弄りながら亜季は言った。
「未来が逝くなら、私も逝こうかな」
悪戯っぽい、キュッと目尻の上がった猫目をこちらに向ける。亜季のお得意の表情だ。大抵は、何か悪巧みしたような口調とセットの演出だった。
「その顔やめてってば」
それを見て、私は思わず吹き出してしまう。
亜季は幼なじみだ。幼稚園の頃からずっと一緒で、家も近い事もあり、家族ぐるみで仲が良い。
そんなお互いの両親も、もうとっくにこの世を去っているのだけれど。
「まあ、それならそれでいいんじゃない?とりあえず担任に言っておきなよ」
亜季は表情を戻してそう言った。
「うん。じゃあ、早速行ってくる」
そう言って私は立ち上がった。「いてら〜」と亜季が手を振る。
軽く手を振り返すと、亜季はスマホを取り出して弄り出した。画面が青くなったのが見えたから、きっとSNSで、また誰かの愚痴を投稿するのだろう。
ザワザワした教室を出る。廊下を隣の組の生徒達が流れて行く。次は体育らしく、皆体操服に着替えていた。
その流れに逆らって、階段を降りる。踊り場に差し掛かると、担任と女子生徒が立っていた。
話し相手は、同じクラスの岡田さんだった。
担任は、降りてきた私に気が付くと「おう、未来」と言って、教科書を抱えていない方の手を上げた。
担任は三十歳だけれど、それよりもだいぶ老けたように見えるのはきっと、白髪まじりの洒落っ気のない髪型のせいだろうか。それか、目元にたっぷりと皺を寄せて笑う表情のせいかも知れない。
私が担任と岡田さんの目の前で立ち止まったから、二人は不思議そうな顔になった。
「未来ちゃんも、先生に話があるの?」
岡田さんが、少女アニメの主人公みたいな高い声でそう言った。
「うん」
私は彼女とは大して仲良くもないので、素っ気なく返した。嫌いというわけでは無いけれど、好きにもなれない。岡田さんはそんな子だった。とても、良い子なんだけれど。
「どうした、未来」
次に担任が聞いてきた。わざとらしい、人を気にかけるような顔で。
「そろそろ、人生を終わらせようと思いまして」
私がそう言うと、途端に、担任は目を丸くした。それもまた、わざとらしいリアクションだった。
そのまま岡田さんを見やって、今度は私を見た。それを何度か繰り返す。
メンドクサ...。そう思ったが、もしかしたら口にも出たかも知れない。
すると担任は、大袈裟に咳払いを一つして言った。
「未来、お前もか。岡田も死のうとしてるらしいぞ。...今月は二人か」
そして肩を竦めるポーズをした。
岡田さんが、申し訳なさそうな苦笑いをこちらに向けた。なので私も同じような顔をしたつもりだけれど、多分出来ていない。
「まあ、最近世の中もつまらないからな。先生もそろそろ飽きてきた頃なんだ。とはいえ、後任がなかなか見つからなくてね。ほら、『今は教師不足』だってこの間話しただろう?だから中々"引退"出来ないんだ」
そんな話いつ聞いたっけ、と思う。どうして教師という人は、私達がいつもしっかりと自分の話を聞いていると思えるのだろう。
それに、教師不足って言ったって、そんな事情、死んじゃえばアンタには関係ないのに。どうしてそこまで気にかけるのだろうか。
大人ってよく分からない生き物だ。と思った。
「という訳でな、若いうちに決断できるお前らは偉いぞ。社会に出たら、死にたくてもなかなか死ねないんだからな」
担任はそう言うと、私達の肩を叩いた。叩いたと言うより、手を乗せて体重をかける、の方が正しいかもしれない。手が乗った方に重心がズレてバランスを崩しそうになる。
そして、馬鹿みたいに高笑いを上げながら私達に背を向けて階段を降りていった。途中で、思い出したかのように振り返り「了解」と言って、親指を立てながら下手くそなウィンクをした。
「未来ちゃんは、いつ逝くの?どこでするの?」
ボケっと誰も居なくなった階段を眺めていたら、岡田さんが声をかけてきた。
「うーん、まあ、無難に飛び降りかな。楽だし」
よく考えずに答える。
そういえば、方法はどうしよう。岡田さんは決めているのだろうかと思って聞くと「私はクスリで」と返ってきた。
クスリとは、恐らくアレの事だろうと思った。
政府推奨の、安楽死用のクスリ。
最近、SNSで「あのクスリは激痛が伴う」とか「天国に行けない」とか騒がれている。
もちろん悪質なデマである事は皆分かっているはずだけれど、それでもちょっと抵抗がある人もいるらしく、政府が、デマの注意喚起や専門家の説明を、テレビとかチラシ、動画サイトの広告などで必死に広めているところだ。
仮に、もしもそのデマが本当だったら、ウチの両親はちょっと可哀想だと思う。ウチだけでなく、亜季の両親も。
私達の両親は、四人で仲良く逝った。
二年くらい前、私の母が大好きだった大きな枝垂れ桜の下にビニールシートを敷いて、最後の花見だと言って、四人は缶ビールでクスリを飲み込んだ。
川の字に一本足した形で四人は横たわった。
四人は幸せそうな顔をしていた。次第に、少しずつ瞼が閉じて行って、やがて完全に閉じた。
それを私と亜季で、眺めていた。
「今見てるドラマ、せめて最後まで見てからにすれば良かったのにね」
亜季がそんな事を言って笑っていたのを思い出す。
私の母も、仕上がっていない編み物があったし、父も組み立て途中のロボットのプラモデルを放ったらかしにしていた。
母も父も確か「死んだら関係ない」みたいな事を言っていたような気がする。
それを聞いた私は、それもそうだ、と納得したのだ。
だけど、それを亜季に言うと
『私は、何かを中途半端に残して死ぬのは嫌。見てないドラマとか、天国で観れないのも嫌だな』
と言っていた。
天国か。本当にそんなものがあるのだろうか、と私は疑っていた。
もちろん、そんな事を口に出したら袋叩きにあう。それに、SNSに書き込んだりなんてしたら、身元を特定されてヘイトスピーチがなんとかの罪で警察に捕まってしまう。
だから、私は心の中で、密かに思っているのだ。
天国があるなんて、証拠はあるのだろうか。誰かが実際に足を運んで、存在を確認してきたのだろうか。
一度、幼い頃に母に尋ねたこともある。天国って本当にあるの?
そしたら、母は私を目一杯叩いた。痣がいくつも出来るくらい、何回も叩かれた。その時に、これは聞いてはいけない事なんだと、悟ったのだ。
多分、これはどこの家庭でも当たり前なんだと思う。前にテレビのコメンテーターの、ベストマザーが何とかって肩書きのおばさんが言っていた。
『子どもの躾、特に死後の世界に対する疑問は、早い内にしっかりと矯正する必要があります。そうしないと、大抵はろくな大人に育ちませんから』
殆どの大人は、そんな疑問を口にしないと言う。偶にニュースで、過激思想の人が捕まったというニュースを聞くことがあるけれど、母はそれを見る度に「頭のおかしい人」と言っていた。
その日の学校を終えて、亜季と一緒に帰宅した。
「ひまわり」に着くと、それぞれの部屋に別れた。亜季はこの後、溜まったドラマを見るらしい。私は荷物を置いて、寮母さんの部屋へ向かった。
寮母さんは、"高田さん"と言って、とても優しくて面倒見のいい中年女性だ。
朝、脱いだパジャマとか、読みっぱなしの漫画とか、色々と散らかして出ていった私の部屋は、帰ってきた頃にはいつも綺麗に片付いている。
高田さんの部屋に行く途中で、中庭で中腰になっている彼女を見つけた。花壇で何か作業をしているようだった。
「高田さーん」と、少し遠目から声を掛ける。すると彼女は振り返り、小さなスコップをこちらに掲げて笑った。
「おかえり、未来ちゃん」
「ただいま。何を植えてるんですか」
傍まで行って、高田さんの後ろから花壇を覗き込む。そこには無数の小さな葉っぱが植えられているのが見えた。
「これはね、ネモフィラの苗だよ。見たことある?小さな青い花が沢山咲くんだよ」
ネモフィラ...名前は聞いたことはあるけれど、どんな花だったっけ。思い出せない。
「うーん、見た事ないかもです」
「そうなの?今はこんなに小さな葉っぱだけどね、春になると一面、可憐な花が咲くんだよ」
高田さんはそう言って、小さな花壇を包み込むように両手を広げて見せた。
可憐な花、と言われてもよく分からなかったけれど、ちょっとだけ興味は湧いた。
「へぇ、見てみたいです、ネモフィラ」
だからそれは、本心から出た言葉だった。
それを聞いた高田さんは少し嬉しそうに笑った。
「五月くらいになるかねぇ。未来ちゃんに見てもらうのが楽しみだわ」
「あの、高田さん、明日私死ぬんです。だからネモフィラは見れないです、すみません」
私は、ちょっと申し訳ないなと思いながら、今日決めた事を伝えた。
「あら、そうなの?なーんだ、残念。一昨日も二階の奥の皆口君がね、"吊り場"で首括ったのよ」
「皆口君って、あのエリートの」
「そうそう。あの皆口君。一番頭のいい大学行くって聞いてたからさ、ちょっとビックリしたわ」
皆口、そんな子が居たなと思い出す。
寮の二階は男子部屋フロアになっていて、その一番奥の部屋に住む、県内一の進学校に通う皆口君は、無口な子という印象だった。
偶に寮内ですれ違って、こちらから挨拶をしても、毎回必ず無視される。私の横を通り抜けた時に見えた彼のメガネが、やたらと分厚かった事だけは印象に残っていた。
彼のようなエリートは、国が指定する"特待生"として、国家維持の為、最低でも三十歳までは生きるように推奨されているらしい。
だけど、あくまでも推奨なので、強制でも無いらしい。
特待生が逝くという話はあまり聞いた事が無いので、意外だった。
しかも、人気がない吊り場を選ぶなんて。
天才には、天才なりの苦悩があるのだろうか。
高田さんが「意外だねぇ」と独り言のように呟く。
ふと、気になったので聞いてみた。
「高田さんは、いつ逝くんですか」
すると彼女は、腰に手を当てて「うーん」と唸った後、言った。
「私は、今は寿命を全うしてみようかなって思ってるよ。というより、花ばっかり植えてると、そんな暇もなくなるのさ」
「....たしかに」
まあ、腑に落ちる。確かに、植物はしょっちゅう面倒を見てやらないといけないし、季節が変わるごとに植える花の種類も変わる。
花が好きって、大変なんだなぁと思った。
「趣味があるとね、人生がちょっとだけ楽しくなるんだよ。私も何度か、そろそろ逝こうかなぁって思った事もあるけど、花壇に向かってるとさ、そんなこと忘れちゃうんだよね」
「そういうものですか」
「そういうものだよ」
その後、自室に戻る途中で、寮に併設された"自死エリア"を見て回ることにした。
寮を出て、駐車場を横切ると、そこに刑務所みたいな高い塀で囲われた場所がある。
重々しい鉄扉を開けると、また刑務所みたいに、寮のワンルームと同じくらいの広さの檻がいくつか並んでいた。
ここに来るのは初めてだった。
端から檻を眺めていく。一番手前が、皆口君が使ったと思われる、吊り場だった。
上から太いロープが垂れ下がって、輪っかを作っている。その下には、木で作られた、私の膝くらいの高さの踏み台が倒れていた。
檻に入る扉の横に、なにやらポスターの様な紙が貼ってあるのが目に入った。
"自死の際は、必ずこちらにお電話を!!"
"◯◯ー◯◯◯◯ー◯◯"
"◯◯自死管理事務局"
そう書かれた下に、喉にロープが巻かれた犬が、ニッコリと笑いながら受話器を耳に当てているイラストが描かれていた。
こういうのって、どうしていつも動物なんだろう。もしかして、犬や猫も自死をするのだろうか。
そもそも、人生が退屈とか、動物はそういうことを考えるのだろうか。
いくつか檻を通り過ぎる。鎖で繋がれた拳銃が置かれた檻や、縦に長いドラム缶みたいな穴が地面に埋まっていて、傍に重りの様な物が置かれている檻もあった。
死に方の多様性、確か首相のおじさんがテレビでそう言ったのを覚えている。
昔は、吊り場しか無かったらしい。
一番奥まで行くと、上に登る階段があった。
おそらくここが"飛び降り場"だろう。
一番上まで登ると、崖みたいになっていて、下を覗き込むと、真っ黒なコンクリートの床が見える。
結構、高い。この高さなら、難なく死ぬ事が出来そうだと思った。
明日、私はここから飛び降りる。
そう思うと、少しだけ、足が竦んだ。
死ぬのが怖いんじゃない。高い所から落ちるのが怖いんだ。きっとそう。きっと。
飛び降りさえすれば、そんなことはどうでも良くなる。怖いのは、一瞬だけ。
そう、自分に言い聞かせた。
翌日、いつも通り学校に行った。
授業の合間、教室の隅で大人しく座る岡田さんに近付いた。
「岡田さん」そう声をかける。
彼女は、私を見上げて、控えめに「未来ちゃん」と言って微笑んだ。
この子は、ちょっと前の少しの期間、虐められていた。
きっかけは、担任の言葉だった。
『お前らは、何歳まで生きる予定だ?お前らみたいな平凡以下の人間は、無駄に長生きしても退屈なだけだぞ』
そういった途端、クラス中から笑いが起こった。
それを聞いていた私はムカついて、反論しようとした、その時だった。
右斜め後ろから、椅子が倒れる音がした。振り向くと、岡田さんが立ち上がっていた。
『どうした、岡田?』
『退屈だろうが平凡以下だろうが、それでも、他人の人生の価値を量る資格なんて、誰にも無いと思います!』
普段は気の弱い岡田さんが、こんなに声を荒げたのは初めてだった。
『どうしたー岡田、そんなに怒ることでもないだろう』
冗談みたいな口調で言った担任の顔は、笑っていなかった。
それだけじゃない。クラス中が、私を除いて、岡田さんに冷ややかな視線を送っていた。
彼女は、身体を震わせながら泣いていた。
その日からだった。彼女に対する陰湿な虐めが始まったのは。
だが、虐めはすぐに終わった。
『人を虐めるようなやつは、クズ人間だ』
朝のホームルームで、担任が言った。
きっかけを作ったのはお前だろう、クズ教師。
私はそう思いながら聞いていた。それに、あの時と同じ人間が吐いた言葉だなんて、到底信じられなかった。
私が岡田さんの代わりになってあげれば良かったと、今はそう思う。
彼女よりも気の強い私なら、もっと担任に反論出来たし、虐めも、ただやられっぱなしじゃなくて、やり返して、一泡吹かせることだってできたはず。
彼女に手柄を取られた、私はそんな風に思っていた。
「岡田さんは、どうして逝くの?」
彼女を見下ろして、努めて優しい口調になるように聞いた。
答えは、何となく予想できたけれど。
「もう、この世界が嫌になっちゃったの」
彼女は、やっぱりそう答えた。
「私達って、頭のおかしい人だよね、きっと」
だから、私はそう返した。
察してくれたのか、彼女はニコッと笑って、小さく頷いた。そして、言った。
「こんな世界、未来も希望も無いよ」
放課後、いつもと同じように、亜季と並んで夕方の街を歩いた。
「亜季はさ、私が居なくなるの、寂しい?」
さっきコンビニで買ったカフェオレにストローを刺して、ズズズ..と音を立て飲みながら歩く亜季を見て言った。
亜季はストローから口を外すと、不思議そうに首を傾けた。
「なんで?」
「いや、なんとなく」
「寂しいなんて、考えたこと無かったな。だって、すぐに会おうと思えば会えるんだから」
そう言って、亜季は空を指さした。
「亜季」
「なに?」
「もう、今夜私は死ぬ。だから、親友のアンタには言っておく」
「どうしたの、なになに?」
私が立ち止まると、亜季も歩みを止めて、私の目の前に立った。
ゆっくりと深呼吸して、私は言った。
「私は、この世界をクソッタレだと思ってる。命の価値を軽く見て、天国なんて物を盲信して、ちょっとでも人生に嫌気が差したら死んじゃえばいい。そんな常識がまかり通ったこんな世界、クソ狂ってる」
「なにいってー」
「私は『頭のおかしい人』でもなんでも良い!私からしたら、皆の方が頭がおかしい!どうしてそんなに簡単に死んじゃうの!?どうして天国があるなんてわかるの!?あったとしてもさ、どうしてこの世界で、もっと大切に生きようって思わないの!?」
「...」
「私は!お父さんとお母さんが逝った時、ほんとはめちゃくちゃ泣きたかった!悲しかった!でも亜季はヘラヘラ笑ってた!どうして!?家族が死んじゃったんだよ!?どっちが頭がおかしいの!?」
止まらなかった。気が付くと、亜季は俯いて黙り込んで、私はボロボロと涙を流していた。
「おかしいよ...こんな世界...」
そう言って、もう、次の言葉が出なくなった。
これが、間違いなく、私の本心だ
「...今のは、聞かなかった事にする、ごめん」
亜季はそう呟くと、とぼとぼと歩き出してしまった。
これが、私と親友との、最後の会話だった。
亜季、私の言葉をどう受け止めただろう。
きっと、SNSの裏垢で、私の事を貶すんだ。
口汚い言葉で私を罵って、顔の見えない取り巻きに同情を貰って、心底安心するのだろう。
あの子はそういう子だって、私は知ってる。
勝手に親友だって思って接していたけれど、それは家が近いから、親同士が仲良いから、それが理由。
私は、亜季が人生を辞めるって言い出したら、本当は悲しいのに。
もう、親友辞めようか。
ーいつから世の中はこうなってしまったのだろう。
ーこの世界って、いったい何なのだろう。
階段を登る。
色々と考えたけれど、やっぱり、これでいい。
さっき、自死管理事務局に電話をかけた。
事務的な内容を簡単に伝えられて、三十秒ほどで通話は終わった。
この後、処理業者がやってきて、私の遺体を片付けてくれるらしい。
崖の淵に立つ。
顔を覗かせると、吊り場の檻の中が見えた。
丸いロープと、木の足場が、寂しく月明かりに照らされている。
皆口君。君は、何を思って首を吊ったんだろう。
私と同じで、この世界に絶望していたのかな。
君とは会話をした事が無かったけれど、君の気持ちは、何となく分かる気がするよ。
私達は、世の中から見れば"頭のおかしい"人間で、社会に出てもきっと、虐げられて生きていくしか無いんだ。
私達の居場所なんて、どこにも無いんだ。
それと天国なんて、無ければいいのにと思う。
このまま死んで、無になれたら、それが私にとって最良の結末だ。
ネモフィラ、スマホで調べてみた。
青くて小さな可愛いお花。
可憐、と言う言葉の意味も、ちょっとだけ分かった気がする。
ああ、あの小さな花壇に咲くネモフィラ、見たかったなぁ。
でも、もうこの世界で生きていくのは勘弁だな。
さあ、このクソッタレな世界におさらばしよう。
私は、心の中で宛もなく手を振って、崖から飛び降りた。
終
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
