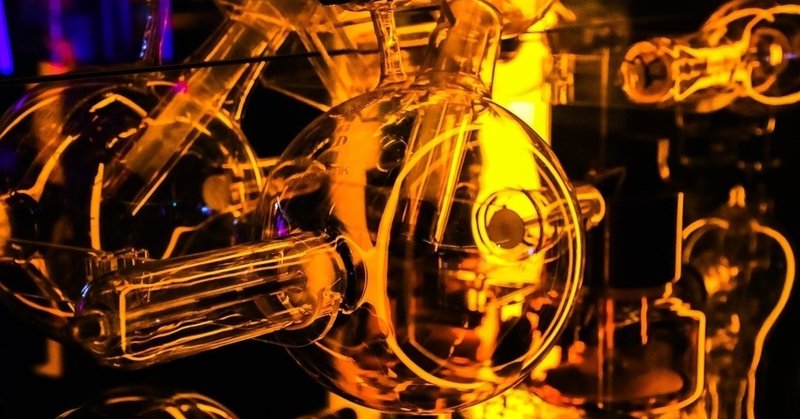
ⅡⅤクリエイターアワードの最終選考
ⅡⅤクリエイターアワードの小説部門の最終選考作品に選ばれまして。
まぁ、もう結果が出たのでぶっちゃけますけど、受賞はしませんでした。
ⅡⅤクリエイターアワードは、第1回のテーマが、記憶喪失・性別不明のVtuber「アメノセイ」の「過去」を書くとううものでして。
クリエイターアワード、やってみない?って誘われて興味を持って応募したのですけど、それがなんと締切の半月前。12月から募集していたアワードの、3月の締切半月前くらい。
そこからロケットダッシュで書いたものが、最終選考まで残ったのがある意味すごいな……となりました。
もちろん、手を抜いて書いたわけではないですし、何と言うか「ギリギリのロケットダッシュ状態じゃなければ絶対に出なかったタイプの切れ味」はあったな……多分12月の時点でのんびり書きはじめたらこれはできなかっただろうという方向性の作品になっていたので、これも運命かな……みたいな気持ちになります。
だらだら書いていたら、絶対微妙な出来になったと思うんだよね……。
むしろ、8割くらい内臓をちぎってはなげるような話がよく最終選考に残ったな? ということの方が衝撃で……。
いや、別にグロではないんですけど、アメノセイの設定をできるだけ全部盛ろうと思って、それでいて締切まで時間が迫っていたのでコンパクトにまとめようとした結果、な、内臓の話に……何故か……なったんですよねぇ?
モツをちぎってはなげ、ちぎってはなげ……。
(いや、実際ちぎってるわけではないので、グロ苦手な方も本当に安心してください……)
何なんだって思います? 私も思う!
なんで内臓の話書いたのかな??
君はどう思う???(聞かないで)
いや本当に、どうして「そうだ内臓の話にしよう!」って思ったのか、3月の私に問いただしたいですよね。アマゾンの奥地にまで探しにいかないとダメかもしれない。
最終選考まで残ったので、ポートフォリオに書いてもいいですよね……書きますね……。
割と真剣にお仕事を募集しているので(限界女芸やってるくらいなのでお察しですが私はめちゃくちゃ貧乏です!!!)この機会に興味をもってくださって、あまつさえ依頼してみたいと考えてみた貴方はぜひ仕事依頼からお問い合わせください。
あと、友達にネタだしやっちまえとイイ笑顔で言われたので、残念賞をくれる方はAmazonの奥地(ほしいものリスト)で何か恵んでください!我ながらこれは酷いな!
※ほしいものリストのタイトル通り、元々は自分が買いたいものをリスト化して、定期的に追加しては買ったものを削除するという覚え書き用に作ったリストですので、特に何も送らなくても大丈夫ですからね!
※むしろこの欲しいものリストを見る価値は「どうしてここまで?」という無駄に細かいコメント芸です。
まぁ、そういうわけで残念ながら受賞しなかったわけなんですけど、テーマがテーマだけに完全オリジナルにわざわざ書き直すのもなぁ、と思いますので、最終選考作品をこちらに載せようかと思います。
何かしっとりしたタイトルつけたけど、おおむね内臓の話だぜ!
********************************
『僕ら』が送る『君』への矢
雨が降っている。
天気が悪いと、身体が重くなるからいけない。
「そう思うよね? どうだろう。いつもじゃない? 確かに」
交互に意見を述べていると、ちょうど点滴を替えに来た看護師が怪訝な顔をして僕を見た。
いつものことなのだから、いい加減に慣れて欲しい。
「その一人会話、いつもやっているのね」
「ひとりじゃないです。二人います」
「二重人格なのねぇ」
「違います。違います」
子供の戯言とでも思っているのだろう。実際、僕は一人だ。対外的には。
だけど、別に二重人格ではないし、イマジナリーフレンドと話しているわけでもない。たまたま脳みそが一つだっただけで、僕の中には元々二人分の人間が入っているのだ。
僕には心臓が二つある。心臓だけではない。身体のいくつかの臓器が二つあって、その内片方が形成不全。原因は、双子の片割れがきちんと分離されなかったことによる。
本来だったら、身体の一部だけ結合したシャム双生児のようになるか、腕や足など本当にごく一部の器官だけが余分にできたりするのだというけど、僕らは何故か一人の人間の中に二人分が詰まって生まれてきてしまった。
その結果、僕はずっと病院に住んでいる。心臓やら何やらがたくさんあったところで、その分強くなったりはしない。むしろ、形勢不全の臓器が負担となって、常人よりはるかに身体が弱い。本当に、病院の中庭までも歩けやしない。
僕は、恐らく大人になるまでは生きられないだろう。
雨が降るだけで、手首を持ち上げるのもおっくうになる身体。うんざりするほど、思い通りにはならない。
「VR持ってきてください」
「体調悪いなら、大人しく寝ていなさい。もう手術まで日がないんだから」
「持ってきてください」
「……もう、仕方がない子ねぇ」
中年にさしかかった歳のこの看護師は、僕のことを手のかかる反抗期の息子か娘だと思っているようだ。ちなみに、息子なのか娘なのか、僕も知らない。一人に二人分の弊害なのか、僕には性器にあたる器官がない。つまり、どちらでもない。
色々な意味でイレギュラーだから、こうして病院で『保管』されているわけだ。僕は親の顔も知らない。何も知らない。僕は、特殊な症例を研究するためのモルモット。それ以上でも以下でもない。人間だと思われていないかもしれない。だとしたら、この看護師はだいぶ僕の人権を尊重している。何せ人間扱いだ。
「身体が動かせないんだから、VRくらい楽しませてよ」
「はいはい」
雑な返事をして、看護師はヘッドギアを僕に被せてくれた。
ヘッドギアを通して見る世界は、簡素で何もない病室とは違って、カラフルな色が溢れているサイケデリックなワンルームだ。その気になれば、ルームのデザインはすぐに変更できるし、映像を見たい時は部屋を丸ごとスクリーンのように使える。仮想現実はどんなことだって簡単にできてしまうのだ。
バーチャルの世界に没入してしまえば、現実の身体のことは忘れられる。それに――。
『やっと、別々になれた』
『やっぱ交互に話すのは無理があるって。ただでさえ、息が切れるのに』
『でもさぁ、声に出さないと虚空に向かって会話するヤバいヒトにならないかな? そっちと、今の独り芝居状態、どっちがマシ?』
『うーん…………』
目の前には、鏡に映したように同じ外見をした人間がいる。
黒髪のショートヘア、青い瞳。いつもと違うのは、入院着ではなくて、球体を繋ぎ合わせたような不思議な黒いジャケットとショートパンツ、青いぴったりとしたタイツを身につけていること。当然ながら、これはこの世界だけのアバターだ。
僕もセイの格好の青い部分を赤くしただけで、ほとんど同じ格好をしている。このアバターは、セイが二人お揃いになるように作ったものだからだ。
『でも、交代制にした時は混乱したよね?』
『だって、アメがちゃんと交代前のことを教えてくれないから……』
『セイだってちゃんと教えてくれなかっただろ? セイがテキトーなことを言ったから、つじつまが合わなくて大変だったんだ。手から寿司を出すようになりたい話なんて、何でしたんだよ。おかしくなったのかと思われて、検査の種類増やされたんだぞ』
『VR内なら寿司を手から出せるかもって話ならしたけど』
『ほんっとーに何でその話になったのか、全くわからなかったんだよ……』
バーチャルの世界では、僕らは一人じゃなくて二人になれる。
アメは僕で、セイが君。どちらがどちらでもいいのだけど、セイはどちらかというと人見知りで、あまり表に出たがらない。出たら出たで、変なことを言うし。
アメは『雨』ではなく、『天』と書く。セイは『晴』。二人合わせたら『アッパレ』だ。
戸籍上の名前は別にあるけれど、少なくともVRの場では、そう。
VRを使えば、いくらでも病院外の人間と交流を持てるけれども、僕らはずっと閉じられた二人だけの世界にいる。
僕らは二人で一つ。一つから二人になるためにここにいる。だから、他の人間は必要ない。
『どうして神様は、僕らに二人分の身体をちゃんと作ってくれなかったんだろう』
『さあ、意地悪だったんじゃない?』
『せめて脳みそが二つあれば、二人いるってわかってもらえたのになぁ』
僕らは心臓やら何やらが二つあっても、脳みそはひとつきりだ。だから一人しかいないと思われている。だけど、僕らは物心ついた時からずっと、自然に二人分の意識があったし、自由に入れ替わりすることができている。
――細胞記憶、という言葉がある。
フィクションでよく使われるネタだ。臓器移植を受けた人間が、ドナーの記憶がフラッシュバックしたり、ドナーの感情に振り回されたりする、という話だ。医学的な根拠はない、ただの都市伝説でしかないけれど、僕らは自分たちがそういったものなのだと信じている。
僕らの場合は、二人分の臓器と一緒に、二人分の記憶が育っていったのだと思う。脳みそではなく臓器で、僕らは二人分の記憶を持っている。少なくとも、僕らはそういう風にとらえている。人格は心臓に宿るとも言うし。
とはいえ、個々の存在を証明する根拠があるわけでもなく、僕らは結局外では一人としてしかカウントされない。VR世界だけが、僕ら双子の聖域だ。本来こう生まれるべきだった僕らの、理想の姿なのだった。
僕らは病院から出たことがないから、VRの世界でもインドアだ。この部屋を出ることはない。外の世界を知るのは、基本的にネットに転がっている動画から。いくつか、動画配信サービスを使えるように手配をしてもらった。基本、病室から動けない僕に、わずかばかりの同情と温情をいただいたわけである。
もらったものは、便利に使わせていただく。僕らは体調が許す限り、だいたいこの部屋で二人、動画を見て過ごすことが多かった。
特にセイは、音楽が好きだ。ヒマさえあればずっと音楽を聴いているし、歌っていることもある。それに飽きた時は、大体配信されているTVドラマや映画を観る。
『この前さ、こっちで昔のテレビ番組見たでしょ。あの……なんだっけ。ジダイゲキ』
『ああ、何かこう……本当に古いヤツだったね』
変な髪形のサムライ・ガイが、カタナソードを振り回して戦う古式ゆかしいチャンバラ・アクションだ。この前、古典リバイバルシリーズを延々と見ていた。どんな設定でも、気が付いたら刀を振り回して一件落着するので、安心感が半端ない。僕もセイも割と好きなジャンルだ。
『あれやってみたいんだよね。あの、オンミツって人がやってたの! 手紙を括り付けてシュバってヤツ。かっこいい!』
セイが何のことを言っているのかよくわからなくて首をかしげていると、「これ!」と画像をだしてくれた。古びた『ナガヤ・アパートメント』の壁に、カツン、と矢が突き刺さる。その先に、紙で書かれた手紙を結び付けている。
『……矢文だっけ?』
『そう、それ! 今度伝言がある時は、矢文残しておいてよ』
『手紙はともかく、病院のどこに矢があるの?』
『VRの中なら何でもできるよ。かっこよく伝言して!』
『VRの中なら、そもそも伝言をする必要がないだけじゃ?』
『あ、そっかぁ……』
表に出る時は交代制。大体アメである僕が出ている。セイは人見知りだし、かっこいいもの、歌うことが好き。かっこよくなれない、重くて苦しいあの身体が好きじゃない。歌うことだってできないし。
セイはVR世界にいた方が、のびのび暮らせる。だから、基本的には僕が表。
必然的に、僕が辛い部分をほとんど担当することになるけれど、それについては別にかまわないと思っている。
セイが楽しそうにしているのを見るのが好きだ。セイには辛い想いをしてほしくない。
僕には、セイを守る以外にやりたいことがない。表に出ていることが多い分、セイよりも好奇心や意欲は低いのかもしれない。
何もできない、やれない現実に慣れてしまって、セイのように色々やってみたいとは思えない。そしてセイとは違って、僕は他人と話すことにはさほど抵抗がない。基本的に、他人のことなどどうでもいいからだ。
親の顔は覚えてもいないけれど、主治医以外の顔ぶれは度々変わる。メインで世話をしてくれる看護師だって、今の中年女性で四代目くらいだ。面倒なので名前も覚えていない。
だから適材適所ということで、本当にたまたま僕がメインで『表』に出ているだけなのだ。最初からVRの世界で生まれていれば、気楽に暮らせたのだろうか。最初からデータだけの存在だったとしたら。こちらが『リアル』でも僕は構わないのだけど。
人間だって、元をただせば遺伝子情報の塊でしかないのだし、『心』は脳細胞の間を伝わっていく電気信号だ。心臓を動かすのも電気。VR空間を構成するデータの塊の中に信号で構成されたアバターと、電気信号で動かしているリアルの人間。どれほどの違いがあるのか、僕にはよくわからない。
――よく、わかりたくない。
アラームが鳴って、メッセージウィンドゥが立ち上がる。
『薬の時間だって』
『ええー、僕、アレ嫌いなんだよね』
『僕だって好きではないけど……行ってくる』
『…………たまには代わろうか?』
『そう言って代わって、いつも僕が普通に飲んでいる薬を不味いって吐きだしたことあるの、忘れた?』
『あ、あー……』
『薬飲み終わったら呼ぶから、待ってて』
『もう今日はVRやらせてもらえないよねぇ』
『看護師がいる間は、会話するのはやめておこうか……何か変に思われてるみたいだし』
脳みそも一つ、口も一つ。見た目はただの人間なのに、二人分詰まっているせいで生きづらいことこの上ない。
『ところでさー、昼間あの看護師さんが言ってたけど』
『うん?』
『手術、って何のこと? 僕が引っ込んでいる間に、何か話あったの? またどっかダメになったりした?』
『…………そんなとこ』
僕はさらりとそれだけ言って、VR空間から退出した。
意識は追いかけてこない。薬が飲み終わるまでは、セイは出てこない。
「ログアウトしました」
そう呟くと、ヘッドギアを外してくれた。看護師ではなく、往診にきた主治医の方だ。
「あんまり長時間使うと、脳が疲労するから、ほどほどにしなさい」
「はい」
「それと、手術日は予定通り、十日後だ」
「はい」
義務的に返事をする。点滴の交換、投薬、体調の検査。毎日朝晩と繰り返されるこの日課には、ほとんど僕しか表に出ない。セイはこの主治医が苦手なのだ。
僕もそれほど好きではない。主治医と言っても、僕らの身体は治るものではないのだ。どちらかというと、彼は僕らを研究している医学者というのが正しい。僕らという貴重な検体を、なるべく長く存続させて、多くの研究結果を残すのが目的。死んだ後には、きっとこの身体を綺麗に解剖してくれるだろう。
「今度の摘出は心臓だ。今まで以上に身体への負担が大きい。なるべく、体力を浪費しないように生活しなさい」
「……はい」
表面上はしおらしく返事をする。もちろん、聞いてやるつもりはない。
――心臓に心が宿るのなら、今度の手術でセイは死んでしまうかもしれない。
あるいは、もしかすると死ぬのは自分の方かもしれないけれど。多分、表に出ている機会が多い自分の方が、この身体の主体となっている。だから多分、残るのは自分の方だ。
今までにも、何度か二つある臓器の片方を摘出する手術を行っている。その度に、セイが表に出られる時間が減っていく。セイには、自分は苦い薬や痛い注射が気にならないから、人見知りがないからと言って聞かせて、交代回数を減らしているけれど――実際には、交代することができないのだ。手術で臓器の片方を摘出するごとに、この身体における「セイ」の部分が減るごとに、それは顕著になっていった。
「君は以前に、心臓に双子の兄弟の人格がある、と言っていたね」
「……それは、手術に関係ありますか」
もう何年も前、僕らはこの主治医を気まぐれに信じてみようと思って、僕とセイに関する仮説を話してみたことがあった。結果は「医学的根拠がない」とのこと。
解離性同一性障害か、ストレス性の人格障害か、カウンセリングに何度も付き合わされて、僕らはすっかり嫌になってしまった。思えば、セイが主治医をはっきりと苦手に思うようになったのは、この一件のせいであったように思う。
主治医は、あまり愛想のない人だから、余計に怖く見えるのだろう。今も、石像のようにカチコチに硬い表情で僕を見ている。心の内が全くわからない。もしかしたら、あの看護師が一人芝居状態の会話をしている様子を、主治医に伝えていたのかもしれなかった。
「手術には関係ないが、君のメンタルケアの面で考慮する必要がある」
「メンタルケアですか……不要な心配です。大丈夫です」
結局、この人の中では、僕は僕でしかなく、セイのことは僕が作りだした架空の人格でしかないのだろう。僕には証明する手立てはないし、心臓を摘出すれば、その手術が成功してもしなくても、セイは死ぬ。
僕と一緒に死ぬか、僕より少し早く死ぬか、する。
「実は、知り合いの研究者に、人格をAIに移植する被験者を探しているんだ。君が良ければだけど、受けてみる気はあるかい? AIになったところで、今のところ記憶を引き継げるわけではない。性格や口調、趣味、嗜好などは引き継げるところまでは調整が済んでいるらしい。君の人格をベースにした、全く別の人格がデータとして構築されるというだけだが……」
――この人は、どうして今更こんな話を、僕にするのだろう。
手術をしても、しなくても、僕はそれほど長生きできない。病院から出ることもできない。摘出された臓器は、研究のために使われるサンプルになる。延命をしながら解剖実験をされているだけだ。
そんな僕へのあわれみか、僕の中に『もう一人いる』という認識も、今更ながら研究対象にしてみる気になったのか。
この流れで、この話をすることは、そういうことなのだろう。
僕はこの世界に興味がない。ずっと病室の中だし、病院の庭先に出たのも、最後はいつだったか思い出せない。少し外出するだけでも、様々な面倒がまとわりつくから、VRの世界にこもっている方が、よほど心身に安全で健康的だ。
僕の世界には、この病室と、セイしか存在していない。
少なくとも、セイは今度の手術で消える。僕の世界からは、消える。
人格をAIにする、ということは、セイにそっくりなデータが生まれるということで、いずれにしても、セイは死ぬ。僕の中でも、VRの世界でも。VRの世界のセイは、あくまでアバターとして別個に存在している風に演出しているだけで、本体は僕の中にあるからだ。
そのAI移植が、どういう技術なのか僕は知らない。僕の中にある、セイの人格だけ、綺麗に切り離して移植できるかなんて、見当もつかない。
「……明日まで考えさせてください」
「ああ、そう答えておこう」
主治医が去った後も、しばらくセイを呼ぶことができなかった。
真っ白い壁と天井に囲まれた、ベッドの上。僕らに許された世界の中。
VRの世界なら、何でもできるのに、この世界だと僕らは身体を起こすのにすら人の手が必要だ。かっこいいことなんてできない。歌う事すらできない。小さな声で、一つの口で二人分の言葉を紡ぐだけ。
窓の外では、まだ雨が降っている気配がする。
止む様子はない。
◆
VRの世界はいつも平和だ。
セイは今日も上機嫌で、配信サイトを巡って覚えてきたらしい歌を、のびのびと口ずさんでいる。
脳は共有しているのだから、僕だってその歌は知っている。セイが得た知識は、僕にもわかる。わざわざセイの行動を記憶から掘り起こしたりはしないだけだ。
だけど、セイの感情全てを共有しているわけではない。セイがどうしてその歌が気に入ったのか、僕にはわからない。
僕には、自分の好みと呼べるようなものがなかった。セイが好きなものが、僕の好きなもの。セイが嫌いなものは、僕にはどうでもいいものだ。
『セイ、この部屋を出ようか』
ふと、思いつきで言ってみた。VRの世界に居座ることは難しい。看護師か主治医に見つかって、強制ログアウトをされたら一瞬で終わる儚い夢だ。それでも、どこまでも遠い場所に行きたい衝動が、僕の中にふと湧いて出た。
『え? なんで? 二人きりなの飽きた?』
当然、セイにはわけがわからなかったようだ。僕は苦笑して、セイの手を取る。アバターとアバターが触れ合ったところで、重みすらないのだけど。
『いや、僕はセイがいればどこでもいいよ。むしろ、セイの方が心配だ。人見知りなんだから。焦って言わなくてもいいこと言ったりするし』
『手から寿司のことは忘れてよ〜』
セイは頭を抱えて嘆いたけれども、慣れない人と話して焦ったにしろ、手から寿司の話はなかなか出てこないと思う。
そのままのことを言ってやろうとして、だけどセイが続けた言葉を聞いて、やめた。
『僕だって、アメと一緒ならどこにだって行きたいよ。こっちなら、二人でいられるし……アメがこの部屋を出たいって言うなら、喜んでいくよ』
急に、意識がリアルの世界に、引きずり戻されたような気持ちになった。
セイは、人見知りで、主治医や看護師と話すのが苦手。この閉じられた世界で僕と二人きりでいるのが、一番の幸せなのだと思っていた。
だけど、本当に二人きりで閉じこもっていたかったのは、僕の方じゃないのか?
セイを表に出さないようにして、この部屋に閉じ込めていたのは、僕の望みじゃないのか?
だって、僕の世界には病室とセイしか存在していない。
セイがいなくなったら、僕は――。
『アメ……僕はね、アメとずっと一緒にいるよ。死ぬまで僕らは、二人でひとつでしょ?』
『うん……』
セイがいなくなる。僕らはいずれ片方になってしまう。
一緒に死ぬか、別々に死ぬか。それだけ。死ぬときは一人だ。
僕らは一蓮托生だけど、別個の人格で、死んだらそこで終わり。
その先はない。天国なんて、僕は信じていない。
セイは、本当はどこにだって行ける。このVRの世界の中でなら。
本当は、セイはもちろん、僕だってどこにでも行けた。行かなかっただけで。僕に付き合ってくれていただけだ。
僕がいなければ、セイはVRの世界で自由になれた。VRの世界なのに、こんな狭い部屋に閉じこもっていたのは、僕のせいだ。
『どうしたの、アメ』
『……何でもない。行きたいところを考えておいて』
『うん、そうする!』
無邪気に笑うセイに別れを告げて、僕はVRルームからログアウトした。
そしてヘッドセットを外すと、ベッド脇に置かれたタッチパネルを操作して、主治医にメッセージを送る。
「嘘をついてごめん、セイ」
僕らは、同じ場所には行けない。
同時に死ぬか、別々に死ぬかはわからないけれど、少なくとも今のようにずっと二人でいることはできない。
だから――。
「君は自由に、好きなところに行って、好きな歌を歌って」
◆
タブレットの画面に、自分と同じ顔をした人間が写っている。
アメノセイという名前。バーチャル空間に来る前の記憶がなく、自分の性別すらわからない。ちょっと人見知りだけど、カッコいいものと歌うことが好き。
『君とはあまり似ていない人格になったね』
「僕じゃないですから」
主治医の見解に、僕は短くそう答えた。
『君の双子の片割れかい?』
「そうです。貴方が存在を信じなかった、僕の片割れです」
『君も言うようになったね』
言いかえすとは思わなかったのだろう。主治医の声には、苦笑の色が見えた。
「もう、セイに気を使う必要はなくなったので」
『自主性が見えたのはいいことだ』
果たして、どうだろうか。やや疑問が残る。わざわざ、そこに突っ込んで聞いたりはしないのだけど。
僕の心臓はもう、ひとつしかない。だから、セイはもう、僕の中にいない。
手術をするたびにただの人間に近づいていく僕の身体は、機能面ではただの人間に程遠い。しばらく無菌室の住人だ。
主治医の声も、無菌室の向こう側から、スピーカー越しに聞こえてくる。
「AIに移植された人格は、記憶まで引き継げない。このセイ君も、君の中にいたセイ君とイコールではないよ」
「もちろん、わかってますよ。いいんです、セイの一部でも存続するなら、僕はそれで」
そんなこと、AIに人格移植する前に、散々繰り返し確認したことだ。
「バーチャルの世界は永遠ではない。少なくとも、人間の寿命よりははるかに短い」
それもまた、すでに何度も聞かされている。
今更、何を言いたいのだろう。そもそも、この話を持ってきたのは、主治医の方ではなかったのか。心臓に人格が宿る話を蒸し返したのも、彼だ。
結局、彼は僕の中に双子の片割れがいたことを、信じていなかったのだ。実際、出来上がってきた彼、あるいは彼女を見て、僕とのあまりの差異に驚き、もしかすると本当に双子の心を持っていたのかもしれない、と信じられたのかもしれない。
多重人格にしろ、それが兄弟の人格であったにしろ、自分の手術によってそれを殺したという事実が、彼に今更のような質問をさせているのかも、などと推測する。良い研究結果が得られただろうか、と意地の悪いことを考えた。
セイが結局僕自身から生まれたものなのか、僕とは別個の存在だったのかは、結局神のみぞ知ること。そして僕は、神様を信じていない。だから僕にとってはもう、どうでもいいことだ。
セイが僕を忘れても、セイから生まれたものが存在しているなら、それでいい。
「VR世界は永遠じゃないかもしれないけど、きっと僕よりは寿命が長いでしょう?」
手術をしなければもって半年、手術をしても二年生きられるかどうか。バーチャルの世界が崩壊するより、この体が限界を迎える可能性の方がずっと高い。
「だから、いいんです。僕は少し違った形でも……二度と僕の中に戻ってこなくても、セイが楽しそうにしているならそれで。それに、僕は『アメノセイ』に一方的にコンタクトを取ることはできますから」
「そうだったね。君にはアクセス権がある」
アメノセイが存在するバーチャル空間は、他にもAI人格や、アバターを使ってバーチャル世界の住人として生活をする人間がたくさんいる。トークをしたり、歌を歌ったり、商品の宣伝をしてお金を稼いでみたり、ゲームを実況したり、思い思いのことをして、自由に配信を行っている。
今のところ、アメノセイにアクセスする権利をもっているのは、AI移植を行った研究所の関係者と主治医、そして僕だけだ。稼働実験中だから、仕方がない。
「アクセス権、僕以外の人にもフリーにできますか?」
『君はそれでいいのかい?』
「いいです。それに、セイからお願いされていたので、矢文を送らないと」
『…………ヤブミ?』
「矢文です。ジダイゲキに出てくるやつです。VRなら、その辺は簡単に作れるので。メッセージを送る時は、矢文にするんです」
『どうしてそんなことを』
「かっこいいからですよ」
それ以上の意味はいらない。
きっと、アメノセイはかっこいいと言ってくれるだろう。
僕の身体は二人分でひとつ。二人分のうち一人分を削ったところで、一人の人間として完全にはならない。だから僕はこのまま、病院で緩やかに衰弱して、そう遠くない未来に死ぬ。
だから、その前に、アメノセイにもっと色々な世界を見て欲しい。
矢文にしたのは、何もセイがかっこいいといったからだけが理由じゃない。普通にメッセージを送っても、意外性がないからだ。矢文なんて時代錯誤な方法を、わざわざVRの世界で使ってみたら、きっと面白がってマネする人がいる。
そうなれば、きっと、色々な人からアメノセイの元に矢文が届くだろう。
近い未来、僕が本当にいなくなってしまった後も、届き続けるだろう。
「楽しみだね、セイ」
そこにいるけど、もうどこにもいない、僕の片割れ。
『泣いているのかい』
熱い、熱い滴が溢れて、頬を伝う。
「雨のせいですね」
塩辛い雨が、僕の顔に降っている。
今日が快晴なことくらい、天気予報で知っている。無菌室でも、配信されているニュースくらいは見られるから。無菌室の中で、雨が降るわけないことだって知っている。
『アクセス権のことは、明日にでも可能にしよう』
そういって、気を使うように主治医は去っていった。
雨が降る。雨が降る。心の中から外へ、塩辛い雨が。アメの雨。
矢を放とう。
初めのメッセージは何にしよう。歌をうたってみない? 動画を見せて欲しい。
いや、それよりもまず、伝えるべきことがある。
『最初の指令:VR世界を探検せよ』
これでいい。これくらいがちょうどいい。
すでにいなくなった僕と、すぐにいなくなる僕から――。
何も知らないままで、新しい世界へと駆けだす『君』に放つ、餞の矢だ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
