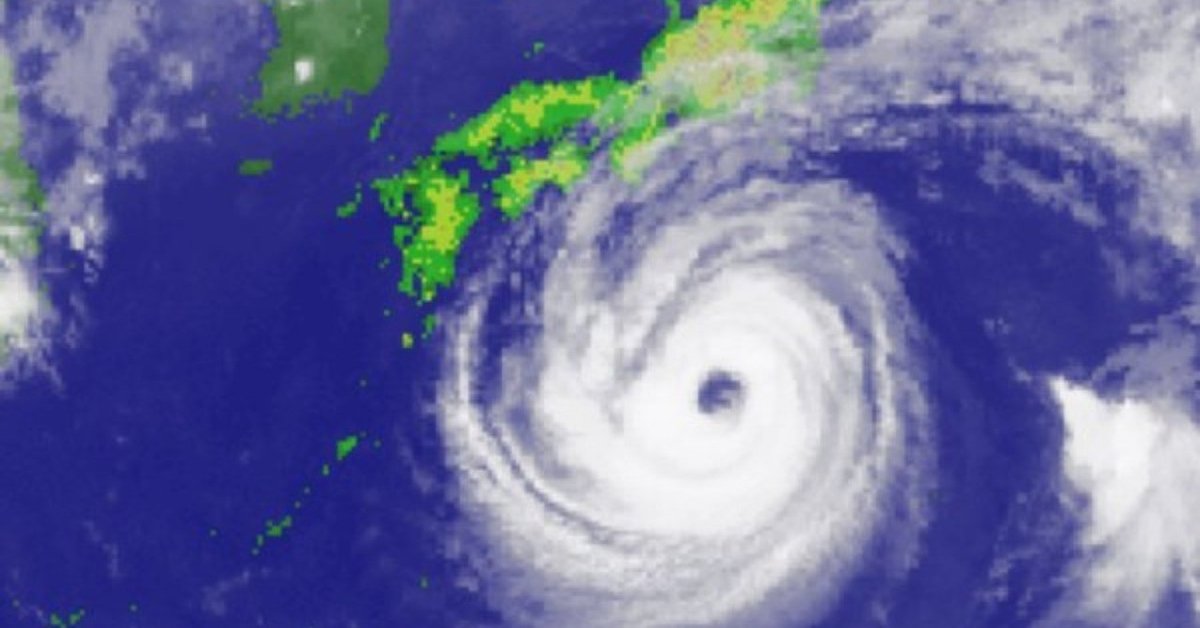
台風のリテラシー(2013)
台風のリテラシー
Saven Satow
Sep. 17, 2013
「時速百キロの風速と、樹木や家を倒した風圧を利用し、台風のもたらしてくれる膨大な雨量を活用して、風圧は動力に、雨量は電力に利用したならば、私たちの生活はどれほどゆたかになるだろう。もしこのことに成功したならば、台風は恐るべきものではなく、逆に私たちに利益を与えてくれる貴重な資源にかわり、災害は絶無になります」。
松下幸之助
気象庁は台風を4桁の数字を用いて識別しています。左2桁が発生した西暦年の下2桁、右2桁がその台風の生まれた順番です。2013年9月13日に発生した台風18号は、気象庁内では、「1318」と呼ばれます。
ただし、台風の命名法は国際的には異なっています。1997年に開催された台風委員会で台風の名称にはアジア名を用いることが採択され、2000年から実施されています。これはアジア各国の政府が組織した委員会です。政府が提案した名前を委員会がリストにまとめ、その掲載順に従って台風に与えるのです。海外のニュースはこの名前で報道します。台風18号の正式名称は「マンニィ(Man-Yi)」です。なお、1997年にチベットで発生した地震は、英語で、”1997 Manyi Earthquake”と呼びます。
台風は日本にとって身近な気象現象です。『源氏物語』の第28帖を「野分」と言いますが、これは台風の当時の呼び名です。気象予報士もメディア上で丁寧に説明していますから、大まかな理解はしていることでしょう。今回の台風は雨による甚大な被害をもたらしています。台風に伴う降水域は、主に、陸雲とレインバンドと呼ばれる降雨帯です。ただ、台風が接近する季節は日本列島に梅雨前線や秋雨前線が存在している場合が少なくありません。これにより、遠くにあるのに、台風が広い地域に豪雨をもたらしてしまうのです。
けれども、台風に関してわかっていないこともあります。実は、台風の発生理論がいまだに確立していないのです。
台風は熱帯低気圧の地域名です。正確に言うと、北緯0~60度、東経180度よりも西側の太平洋上で発生する熱帯低気圧を指す名称です。台風は大半がこの海域で生まれます。そこでここを台風発生海域、もしくは台風海域と言います。年平均27個ほど発生します。ただし、気象庁は、最大風速が秒速1.2m以上の場合、台風ではなく、弱い熱帯低気圧と呼んでいます。
台風は水温27度以上の熱帯の海洋上で生まれます。けれども、どこでも発生するわけではありません。また、低緯度帯で発生して、中緯度に向かいますが、高緯度にまで達することはありません。日本列島は台風経路に位置していますけれども、北海道は例外となっています。さらに、冬季は台風海域だけで生まれます。
台風は移動することで被害地域を広げます。ただ、熱帯低気圧に自ら動く力はありません。この点はしばしば誤解されています。地球の球面効果であるベータ効果によって、北半球において、無風の中であっても、熱帯低気圧が発生すると、北上するのです。しかし、この効果だけでは経路の説明ができません。背景風が要るのです。
台風は、北太平洋高気圧の西の縁を回って北に進路をとることが多くあります。北太平洋高気圧は季節によって変化し、台風の進路もそれに連れて移動する傾向が認められます。熱帯低気圧は亜熱帯高気圧に伴う気流に流されると考えられるのです。
台風は冬季にも発生しますが、数が少なく、日本列島に来ることもありません。この時期は北太平洋高気圧が弱いからとされています。夏から秋にかけてこの高気圧は発達し、台風の発生数も増え、列島に達するようになります。
日本列島上空には偏西風が吹いています。日本に接近すると、台風はこの気流に流されて東向きに進路をとります。ただ、沖縄付近に転回点があり、東から西向きへと転換します。この転回点は背景風が弱いのです。台風の停滞や迷走はここで起きます。
台風の被害をめぐる報道に接すると、中心に対して偏りがあることがわかります。熱帯で生まれた際の台風は雲の分布が円形ですが、中緯度帯に入ると、暴風圏が中心の東側に偏ります。これは南北の気温差によるものです。台風の発生する熱帯の気団は温度が一様です。しかし、中緯度帯には乾いた空気の亜寒帯の気団が控えています。渦巻きの東側から熱帯の湿った空気が北上すると共に、西側からその乾いた空気が南下します。渦巻きの西側の積乱雲の発達が抑制され、暴風圏が東側に偏るのです。
進路の東側に南や南東に開いた湾では、強風による海水の吹き寄せ効果が大きくなり、高潮災害よりも厳しい被害につながります。台風は低気圧ですから、海面を押している大気の圧力が下がります。それによって海面が吸い上げられたところに強風が吹くので、高潮が発生します。かつてTVレポーターによる港湾の傍からの生中継がありましたが、あれは本当に危ないのです。
台風一過も同じ理由です。台風の西側から北よりの風が吹きますから、乾いた空気が運ばれ、13年9月17日の東京のように、通過後に青空となるのです。
熱帯低気圧のエネルギー供給は気化熱です。この潜熱の解放には高い海面温度が必要です。緯度が高くなれば、それが下がり、台風も衰えていくのです。ところが、北海道まで北上すると、中心気圧が再び下がり、温帯低気圧化し、甚大な被害をもたらすことがあります。南北の温度差が大きすぎるため、台風によって低気圧が発達するのです。積乱雲に頼ることなく、渦が強化されます。
気象学では蒸発熱(気化熱)と融解熱を合わせた「潜熱」という概念を用います。ただ、あまり一般的絵はないと思われますので、ここでは気化熱も混えて使います。
日本が古来より台風に悩まされるのはこうした自然や地理の条件に起因しているのです。台風は暴風雨により被害が複合的な災害です。洪水や土砂災害、高潮、風害を短期間のうちに広範囲にもたらします。台風は日本に被害と教訓を最も与えてきた災害の一つです。
ところが、その台風の発生理論は未確立のままです。台風は積乱雲によって構成されています。しかし、積乱雲は一般的にどこでも発生します。積乱雲だけでは台風は生まれないのです。台風には渦巻きがあります。積乱雲と渦巻きの結びつき、すなわち積乱雲が渦巻きの配置をしたものが台風です。けれども、その発生がよくわからないのです。
強い渦巻きなら観測できます。しかし、それは台風に成長した際に認められる状態です。積乱雲が渦巻きに配置された時に、「台風の目」として渦が見えてくるのです。そうなると、熱帯低気圧と無関係の理由で弱い渦巻きが生まれていることになります。弱い渦巻がどのようにして積乱雲を巨大な渦状に集めるのかをうまく説明できないのです。
台風は反時計回りを示します。北半球では高気圧は時計回り、低気圧は反時計回りです。気圧によって渦が反転するわけではありません。高気圧は地球の自転速度より速く、低気圧は遅いのです。
時速50kmで並走している2台の自動の一方が時速60kmに加速したとします。いずれも前進しています。けれども、時速60kmで走るドライバーからは、時速50kmの自動車が後退しているように見えるのです。
発生理論は未確定ですが、台風の発達のメカニズムは1960年に解明されています。積乱雲が中心部で発達し、渦巻きを強化する過程を「ㇱスクメカニズム」と呼びます。「ㇱスク(CISK)」は「第2種の条件付き不安定(Conditional Instability of the Second Kind)」の略語です。「第2種」とは奇妙な名称ですが、孤立した積乱雲の発生メカニズムを「第1種」にしたためです。
台風は、構成する渦巻の特徴から、3層構造として捉えられます。台風の目は地上から高さ12~18kmですので、16kmを想定しましょう。地上から高さ1kmまで風が周囲から集まる境界の層、1~10kmまでは同心円状の風が吹く層、10~16kmまでは風が吹き出す層です。第1層は地上摩擦の効果のため、地衡風平衡が成り立ちません。風がスパイラルして中心部に流れこみます。
台風は、中心からある半径まで、それに比例して風速が大きくなります。そこを超えると、風速がゆっくりと小さくなります。最も風速が速い半径を「眼の壁雲」と呼びます。台風の目はその内側を指します。目の半径は10~100kmくらいです。
熱帯低気圧の周辺から集まった空気は壁雲の半径で積乱雲の内部にとりこまれて上昇します。水が水蒸気に変わる時、周囲から熱を奪います。気化熱を得た空気は暖かくなります。壁雲の積乱雲の上部から吹き出す空気の一部は目の内部に入り、下降流を形成します。この潜熱解放後の空気は暖かいので、目の気温が高く、地上気圧は中心で最低になります。風は気圧の高い方から低い方へ、気温が高い方から低い方へそれぞれ流れるからです。目の内部に積乱雲ができないのはそのためです。
台風の発達にも空気の上昇・下降と渦巻が関係しています。「エクマン境界層」と呼ばれる渦巻きの下層では、周辺部から空気が集まり、上昇します。これを「エクマン収束」と言います。それが飽和状態に達すると、周辺部から下降します。渦巻き本体内部に弱い鉛直面の循環が生まれることになります。積乱雲は背景に上昇流があって発生します。上昇する渦巻きが存在するなら、その中心部で積乱雲が生まれやすいことになります。他方、周辺部は下降流ですから、積乱雲の生産が抑制されます。
積乱雲の発生自体は不規則でも、そこに渦巻きが入りこむと、できやすいところとできにくいところが生じます。この組織化を通じて中心部の潜熱が解放され、エクマン収束で生まれた上昇流が強まります。空気が周辺部から中心部へさらに集まるので、角運動量保存則によって渦巻きが強化されます。この過程が正のフィードバック機構として働き、熱帯低気圧は台風へと発達するのです。
従来、一般市民は天気予報の情報を知るだけで十分です。けれども、今は経験したことのない気象現象がしばしば起きています。それは想像を超えているということですから、積極的にその対象について考えることが求められます。そうであっても、慣れが生じたり、他人事に思ったりすることは避けられませんから、そのための方策も専門家の間で検討されています。情報の受け手として送り手と認識を共有している必要がありますので、一般市民は仕組みを知っておくべきでしょう。台風の予報や報道を認知するには、そのリテラシーから理解することが不可欠です。
台風の発生理論は未確立ですが、その発達メカニズムはわかっています。それには潜熱の解放が大きな働きを果たしています。海面温度と台風の関連が報道されても、「暖かく湿った空気」程度で、その潜熱解放に言及されることはあまりありません。しかし、ここがポイントです。海面温度が上がれば、水が水蒸気になりやすくなります。台風の原動力である潜熱の解放が起こりやすくなるのです。海面温度が高いことは、台風の規模の大きさや勢力の維持を示唆します。海面温度は台風リスクの指標と認識できるのです。地球温暖化は海面温度の平均温度を上昇させますから、異常気象をもたらす一因と考えられるわけです。
台風18号による被害も映像によって伝えられ、その恐ろしさを被災地域以外でも認識されています。可視化は事象を直観的に把握させます。けれども、3・11以降、未経験の事象に遭遇することが珍しくありません。海面温度の上昇は台風のリスクを高めますが、それは今後のまだ見ぬ被害の原因となる危険性があります。未知を生きることが前提である時代には、うかれて能天気ではいられないのです。
〈了〉
参照文献
木村龍治他、『身近な気象学』、放送大学教育振興会、2010年
PHP研究所編、『松下幸之助発想の軌跡』、PHP研究所、1982年
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
