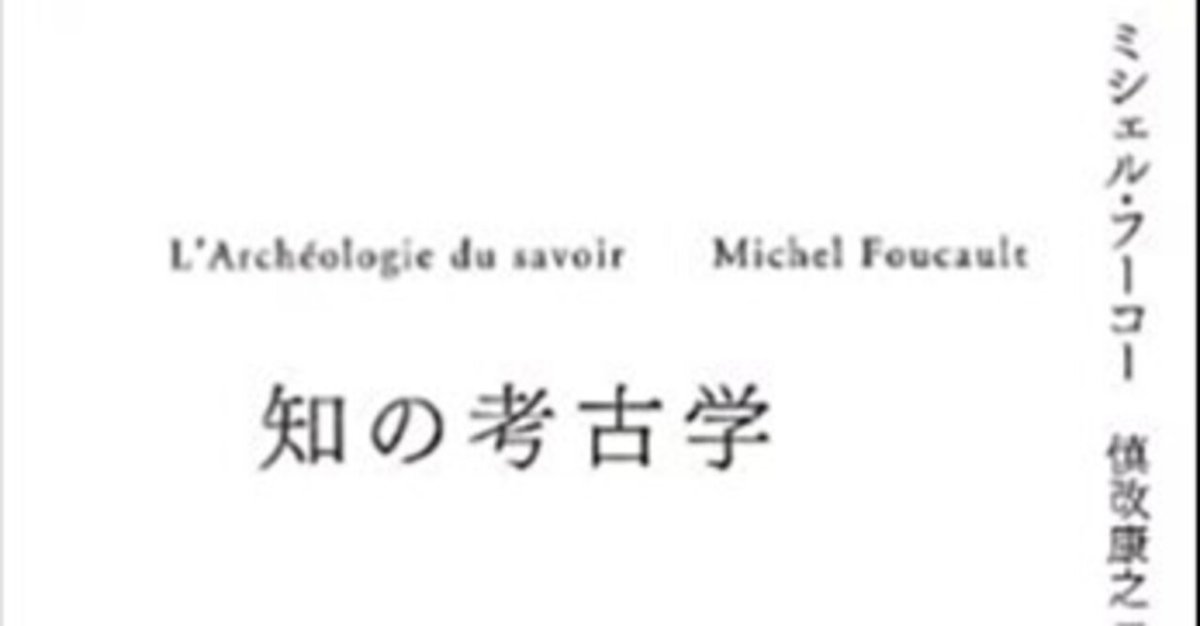
知の考古学を超えて(2013)
知の考古学を超えて
Saven Satow
Nov. 21, 2013
「書くことは最大の悩みの種だった」。
ミシェル・フーコー
ミシェル・フーコーは歴史研究において「知の考古学」を提唱している。従来の歴史研究は文献史料を解釈して過去を再構成することである。しかし、その後、史料の相互関係を問い、時間的なつながりを捉え直すことへと移行する。その史料を成り立たせている社会の潜在的構造を明らかにすることが歴史研究だとフーコーは考える。科学的言説や科学的思考の定義に関する知識の潜在的グリットの地層を掘り起こす。これがフーコーのアプローチである。
すべての文献史料は、その時代の思考様式から生まれるので、等価である。序列もつけず、起源も問わず、理念の規定もせず、それらの史料を照らし合わせることで、その社会における諸関係を顕在化させる。同じ発言内容であっても、社会における出来事や発話は、関係や環境などによって働きかけて形成されている。歴史の総体を把握することは難しい。さまざまな断片を照らし合わせて、その時代や社会に生きるあるある人がなぜあえてそのようなことを言わなければならなかったのかを明らかにする思索である。史料を研究すれば、それを生み出した社会構造を明らかにできる。
それは権力を政治史ではなく、社会氏から捉えることを意味する。権力は制度や習慣などの諸関係のネットワークである。それは必ずしも明示的ではない。知の考古学は暗黙の権力を見出す方法である。
しかし、フーコーの考古学理解は古い。発掘と年代特定が考古学ではない。今日の史学は考古学的アプローチが不可欠である。近代史や現代史にも用いられている。考古学は文献史学を相対化し、言葉ではなく、物から歴史を考察する。フーコーが言葉から物を解釈するのに対して、考古学は物から言葉を考えるのであって、両者の認識の方向は反対である。
フーコーは1984年に亡くなったのだから、現代考古学の発展を知らない。しかし、考古学が文献史料のない時代や社会における思考様式も取り扱ってきたのであり、言葉を相対化する術を持っていることに気がついて然るべきである。彼は「考古学」を援用しながら、言葉が思考様式の現われとしているのは我田引水と言わざるを得ない。
その時代の社会の暗黙知が言葉に表象されるとは限らない。言葉は抽象的・一般的な物事を表現することができるが、物はそれが困難である。その際には省庁を利用せざるを得ない。言葉で「幸せ」と言うのは容易だが、それを物で示すには、関係する人たちの間で共有されるコンテクストに基づいて象徴化する必要がある。また、物は具体的・個別的であるので、そうした問題を探究する場合、言葉よりも強みがある。言葉の考察だけでは捉えきれない思考様式がある。
考古学的認識から文献史料を読む時、それは新たな理解を提供する。相対化しているために、その読解力は主に文献研究に携わった人よりもはるかに精度が高い。
考古学にかかれば、ゴミや排泄物、死体も史料と扱われる。また、遺体の状況からどのように取り扱われたかや食器の傷により当時のマナーも解明できる。考古学には大きく次の四つの意義がある。
文献史料のない対象を扱うことが可能である。経年の過程で文献史料が失われる場合も少なくない。また、現存する史料がある特定領域について語っているにもかかわらず、他のものがない場合、それを一般化してしまう危険性もある。
文献史料に記されていない、もしくはなじまない対象を検討できる。日常生活や庶民の暮らし、暗黙の常識などは文献史料に記されることはあまりない。
文献史料からイメージしにくい対象を吟味できる。文献史料より受ける印象が実際の事物のそれと異なる場合がある。都市構造や建築土木の構造物などの空間感覚は文献史料を読むだけでは認知するのが難しい。また、武器の破壊・殺傷能力や船舶・車両の性能なども考古史料でないと確認できない。
文献史料の作成者の視点に規定されない考察が行える。文献史料は意図や目的に基づいて執筆・編集される。それを承知して批判的にテキストに向かったとしても、作成者の視点に拘束されてしまうことがある。
こうした四点が考古学的アプローチの利点である。具体性・個別性の考察に強いことがわかる。
付け加えると、今日の考古学はデジタル技術を駆使している。都市や構造物の場合はコンピュータ・シミュレーションによって再現でき、3Dプリンタによって模型をつくれる。立体の考古史料はX線CTによって内部構造を視覚化する。3Dデジタイザによって表面を測量、3Dプリンタによってレプリカを印刷する。平面史料は赤外線解析を行って制作過程を視覚化し、デジタル・スキャナによって複写する。いずれの史料でも、組成は元素が発する固有の放射線を解析することで特定できる。紙などの2次元史料は顕微鏡で組成を確認することもある。
X線CTや3Dプリンタ、デジタル・スキャナはさまざまな場面で利用されている。しかし、考古学では、まさにそれでなければならないものとして活用されている。なお、X線CTは医療用の5倍の解像度を持つタイプが使われている。
デジタル技術は考古史料のコピーの作成を容易にし、その利点は二つある。一つは拡大縮小が自在であるため、全体や細部の検証が容易になる。もう一つは実際に手にとれるので、使用や加工、組み立てによる実証実験が行える。
歴史研究は考古学的アプローチの積極的な導入により具体性の考察を拡張している。これはフーコーの知の考古学では弱かった方向性である。その点では知の考古学は越えられている。
フーコーの姿勢には、全般的に、抽象性指向が認められる。フーコーは、権力を所作ではなく、歴史的に形成されてきたと暴露するが、そこにとどまり続け、よりよい社会の構築のための方策を提案することをしない。彼は社会が精神障がい者を排除してきた歴史を明らかにしながら、処遇はどうあるべきかについて具体的に語らない。そうした提案をすることが権力の誘惑だと回避する。彼にすれば、今日の哲学は、具体的な権力をジャーナリズムが監視するとすれば、抽象的なそれを行うことになろう。
フーコーからは現代社会における権力に対抗する生き方を読み取れる。権力の研究やポストモダンの議論に手頃な方法や解釈を提供し、フーコー産業と呼べる状況が知的シーンに生まれている。けれども、歴史研究によって現代の思考様式を相対化し、それをよりよい社会を構築するために具体的に生かす姿勢はない。これは彼の時代の思考様式の一つである。フーコーによってフーコーを読み直す。もうそういう嗜好様式の時代を迎えている。
〈了〉
参照文献
本田光子他、『博物館資料保存論』、放送大学教育振興会、2012年
ミシェル・フーコー、『知の考古学』、中村雄二郎訳、河出書房新社、1995年
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
