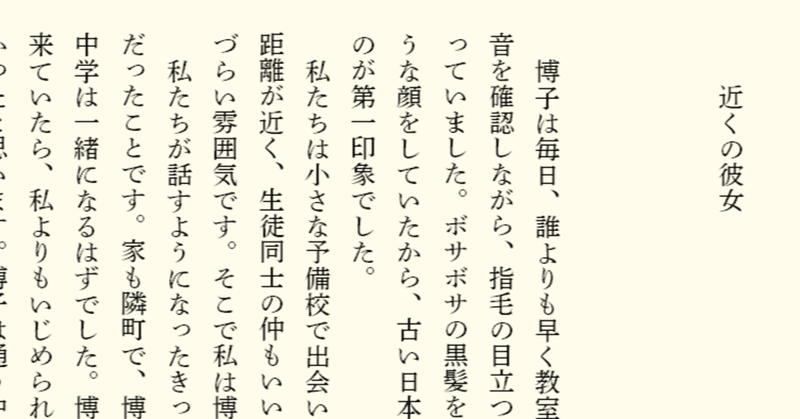
近くの彼女(第12回六枚道場参加作品)

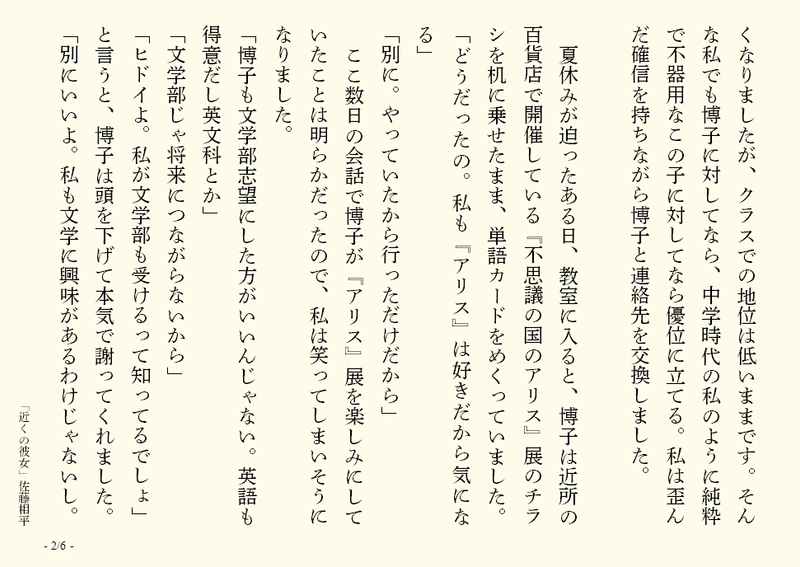




「近くの彼女」 佐藤相平
博子は毎日、誰よりも早く教室に来て、小さな声で発音を確認しながら、指毛の目立つ手で単語カードをめくっていました。ボサボサの黒髪を長く伸ばし、能面のような顔をしていたから、古い日本人形みたいだなというのが第一印象でした。
私たちは小さな予備校で出会いました。先生と生徒の距離が近く、生徒同士の仲もいい一方で、ぼっちだと居づらい雰囲気です。そこで私は博子を友達に選びました。
私たちが話すようになったきっかけは最寄り駅が一緒だったことです。家も隣町で、博子が受験をしなければ中学は一緒になるはずでした。博子があの荒れた学校に来ていたら、私よりもいじめられていたことは間違いなかったと思います。博子は通う中高一貫の進学校でも友達がいないようでした。彼女はそのことを必死に隠そうとしていましたが。
私は高校では上手く立ち回り、いじめられることはなくなりましたが、クラスでの地位は低いままです。そんな私でも博子に対してなら、中学時代の私のように純粋で不器用なこの子に対してなら優位に立てる。私は歪んだ確信を持ちながら博子と連絡先を交換しました。
夏休みが迫ったある日、教室に入ると、博子は近所の百貨店で開催している『不思議の国のアリス』展のチラシを机に乗せたまま、単語カードをめくっていました。
「どうだったの。私も『アリス』は好きだから気になる」
「別に。やっていたから行っただけだから」
ここ数日の会話で博子が『アリス』展を楽しみにしていたことは明らかだったので、私は笑ってしまいそうになりました。
「博子も文学部志望にした方がいいんじゃない。英語も得意だし英文科とか」
「文学部じゃ将来につながらないから」
「ヒドイよ。私が文学部も受けるって知ってるでしょ」と言うと、博子は頭を下げて本気で謝ってくれました。
「別にいいよ。私も文学に興味があるわけじゃないし。国語の成績が一番いいから国語の先生にでもなろうかなってだけだから。教職は安定してそうだしね」
私は百人一首から和歌に興味を持ち、文学部を志望していました。国語教師になるというのは親を納得させるための理由です。だけど、中学時代に『新古今和歌集』の技巧的な世界の素晴らしさについて語り、からかわれるようになった嫌な思い出があるので、博子にも本当の理由は言わずにいました。
「博子は経済とか経営とか商学部志望だよね。将来はどうするの」
「銀行か商社。でも留学してMBAをとって外資系企業で働くことも考えている」
「へー、すごいね」
そんな派手な世界は向いてないでしょ。私は呆れてしまいました。きっとメガバンクの重役らしい父親の影響だったのだと思います。階段の踊り場でうずくまり、怯えながら電話をする博子の姿を、私は何度も目にしました。
博子は誰よりも熱心に勉強していましたが、成績が伸び悩んでいました。そのストレスのせいか体調を崩し、さらに勉強が遅れるという悪循環に陥っていたようです。十一月には一週間も授業を休むことがありました。
博子が復帰した次の日の授業後、先月の模試の結果が返されました。私は予想よりも点が取れていないことに動揺し、三者面談が不安になりましたが、隣にいた博子の結果を盗み見て安心しました。得意だった英語さえ私よりも点が取れていません。
帰りの電車で私は「模試はどうだった。私は全然ダメ。この時期の模試で七割取れないのはヤバいよね」と、わざと聞きました。
「まあ、いつも通りだった」
「流石だね。私も博子みたいに英語が得意だったらなあ」と追撃すると、博子は黙ってしまいました。もうやめよう。そう思った瞬間に、隣に立つ博子の肌の白さが目に入りました。先週休んだからだよね。車窓に勉強疲れで荒れた私の肌が映った気がしました。
「グローバルに活躍したい博子にとってはあんなの簡単でしょ。お父さんも期待してるんだろうなあ」
「もう、やめて」
震えた声でした。私はやり過ぎてしまったと焦り、別の話題を振ってみましたが、博子は壊れたように何かをつぶやくだけで応じてくれません。怖さを感じながら、私は駅で博子と別れました。
次の日から博子は予備校に来なくなりました。どうやら学校にも行っていないようです。私が連絡してみても返事はありません。心配にはなりましたが、私は自分の受験勉強で忙しく、博子のことをだんだんと忘れてしまいました。
受験が終わり、私はある国立大学に進学し、四月からは一人暮らしをすることが決まりました。やっと親から離れられる喜びを感じる一方で、いい思い出なんて無いはずなのに地元を離れることに寂しさを感じた私は、近所を散歩するようになりました。
その日は駅の普段使わない出口から歩いてみることにしました。緩やかな坂を上り切ると商店街に出ます。小規模ですが活気があり、お肉屋さんからするコロッケのニオイが懐かしいです。通り沿いに植えられた桜の木は、蕾が膨らみはじめています。町を出る前に咲いてくれないかな。そんなことを考えながら歩いていると、向こうから青いコートを着た人が近づいてきました。博子でした。春の日差しの中、死人のような顔をしています。全ての感情を失い、凍りついた表情です。博子は虚ろな目を一瞬だけ私に向けると、何も言わずに横を通り過ぎて行きました。
英語を教えながら小説を書いています/第二回かめさま文学賞受賞/第5回私立古賀裕人文学賞🐸賞/第3回フルオブブックス文学賞エッセイ部門佳作
