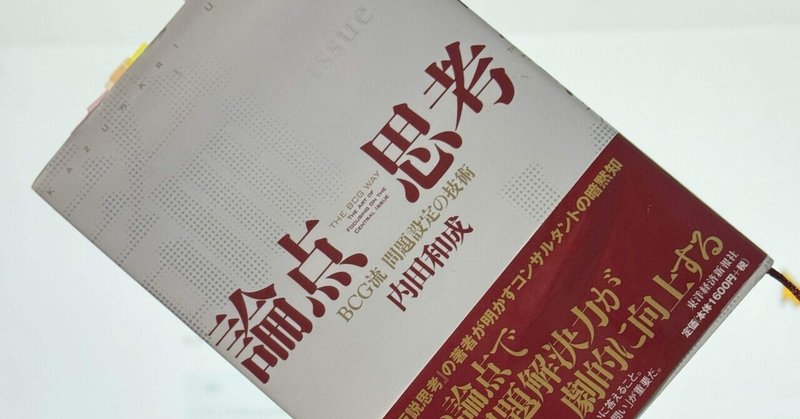
#216 再読「論点思考」正しい問題解決は正しい問いの設定からと自分を戒めた話
こんにちは!けーたです。
本日は、「論点思考」を再読してやっぱり問題解決の一丁目一番地(最近この言い方は通じないらしい)だなと改めて思いましたので、本の気づきなどをまとめて投稿いたします。
どうしてこの本を手に取った?
「論点思考」は基本的に自分が困った時に戻る場所としている本です。
そこに戻って来ているという事は、、、そうです。仕事でちょっと困っているのです。
困り事のレベルとしては、極々シンプルで修羅場的なモノを抱えているわけではありません。
今後中堅メンバーとして活躍していくにあたり、問題解決手法の型をメンバーに伴走して身に着けさせることです。
文字に起こしてみるとめちゃくちゃ小さい笑
ただ、良い機会なので自分の思考のベースとなくこの本を再読しましたので、改めて良いなという点を残しておきます。
どんな人におススメ?
普段の家庭や仕事で大小いろいろな問題解決をみなさましていると思うのですが、その問題解決を行っている全ての人に読んでいただきたいと思うぐらい良い本です。本当におススメ
2010年1月に発売されているこの本ですが、2024年の今読んでもまったく色あせていません。
これが、1760円で自分のいつでも手を伸ばせば届く範囲に所有できるとおもうと、かなりコスパの良いものだなと思います。
やっぱりこれは大事だねというフレーズ達
・「解決できるか」にこだわる
これは、論点らしきものが目の前に現れたときい、次の3つのポイントで問題を検討すると書かれており、大変学びになりました。
1、解決できるか、できないか。
2、解決できるとして、実行可能(容易)か
3、解決したらどれだけ効果があるか
目の前の課題に対して、着手する前に冷静にこの3つの質問をあてて考えていなかったな。特に2番めに対して拘れていないことに気づけました。
まさに、論点思考の幹となる考えだよなと改めて思いましたので、取りあげました。
・問題意識が論点思考を育む
論点思考の力をつけるために重要な事は「これは本当の論点か」という問題意識をもちながら仕事をすることが重要と書かれている。
そして、上から与えられた大論点に問いを挟まずに問題解決作業に没頭する人との「この大論点は正しいか?」という問題意識を持っている人とでは時間と共に大きな差がついてくる。
この文章を読むと、確かに最近、その問いって正しいの?とDXを推進しているときの課題設定自体に問いを挟んでなかった!とハッとなりました。
やはり大事なのは、「その論点は解けるのか?」「その問いは正しいのか?」を今日を機に再インストールします。
・時には失敗させる
多くの場合は、自分で課題そのものは何かを考えて、その上で時間がかかりすぎたり、間違ったあな(論点)を掘ったり、することがあるだろう。
ただ、この間違った経験が血となり骨となるのが「論点思考」である。
と示されており、自分は課題から考えてもらうことができてないという自己認知ができました(とはいえ、後輩の資料の締めが迫りくるのですが怖)
もう少し長い時間軸で見る事を行動として起していきます。
まとめ
もう、何度も何度も「論点思考」を読んでいても付箋を貼っていない所に、今の自分に刺さる事が書かれていたり、立場や持ち場が変わると、同じ本でも刺さる場所が変わる、または広がったりしていることを実感しました。
本当に懐の深い本だなと思わされます。
自分にとってのベースとなる問題解決手法はトヨタの問題解決手法なのですが、それにプラスしてクリティカルシンキングの問題解決を組み合わせたような感覚があります。
問題解決といえばこの1冊という激アツな本なので、まだ読まれていないかたは是非手にお取りください。
だれかの選書の参考になれば幸いです。
ではでは
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
