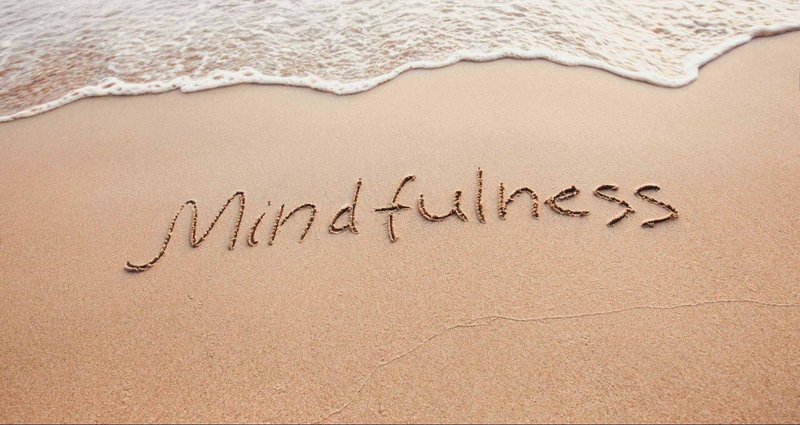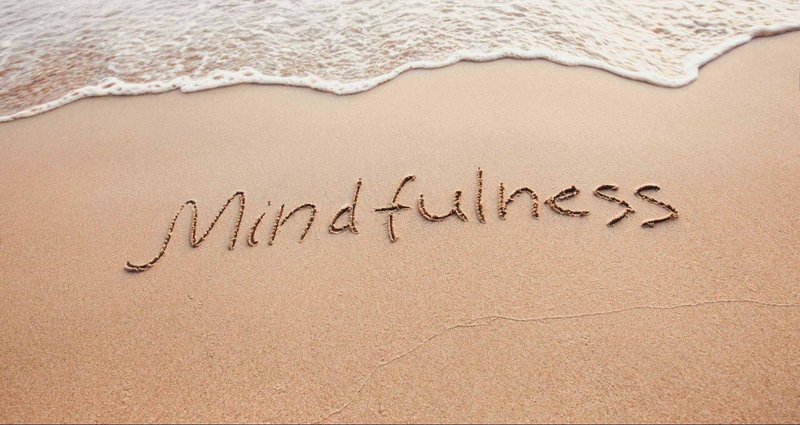サティを入れて思考の後続切断
対象→六門→識→受→想→尋→行
原始仏教が説明する認識のプロセス。
対象と六門(五感+意門(頭の中のイメージや思考を捕える感覚器官があるとブッダは説いている。))と識(認識する作用)が触れ合って受(感受作用)が生まれる。感受した内容から、概念やイメージが想起される。これが「想」。そしてより深く対象にフォーカスし(尋)、対象がなんであるかを知る。カラスの声を聞いたなら、「想」の段階で、「音」と分かり、「尋」の段階で、「カラスの声」だと分かる。そして「カラス嫌だなあ・・・」とい