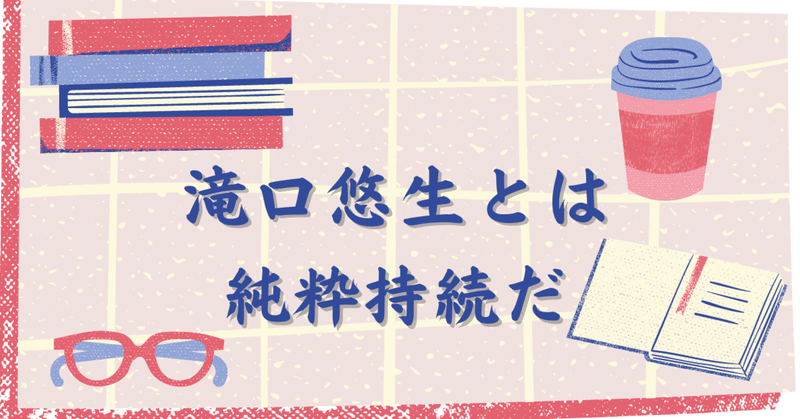
滝口悠生とは、純粋持続だ
最近、滝口悠生の本ばかり読んでいる。きっかけは毎日新聞の2021年の本を選ぶ書評企画で堀江敏幸が滝口悠生の「長い一日」を挙げていたからだ。
僕は小説が読めなくなった
当時、というか恐らくここ3,4年、僕は小説というものが読めなくなっていて、読める小説と言えば、嘗て読んで面白かったものとか、スカスカな文体のものだった。スカスカ、というと響きが粗悪だが、音楽や風景や僕自身の位相が入り込む場所がある、という意味合いで、そういった意味で、堀江敏幸や保坂和志くらいしか読めなかった。
なぜ、小説が読めなくなったのか
そもそもなぜ、小説を読めなくなったのか、と言えば、小説以外の新書や専門書を読むうちに、小説世界の辻褄とか、整合性とかが読んでいるうちにとても気になりだしてしまって、物語以前に文章として読むようになり、そこに齟齬が生じことが多い小説に気持ちがついていけなくなっていってしまった。また、重々しい、もしくは細やかな町や季節や建物の描写に対して、率直に「まどろっこしい」と感じるようになっていた。部屋の間取りとか、段差とか、異世界の構成とか、そういう「設定」の説明文章を読むだけで、圧倒的に眠くなってしまう体になってしまった。そう、小説を読もうとすると、直ぐに眠くなってしまうようになっていた。
それでも、嘗ては小説しか読んでいなかった僕は、小説には憧憬があって、小説家にも、というよりも死ぬまでに1冊は小説を出版できたらな、と高校生くらいから40歳にもなった今でも思っていて、しかも、それはいつか実現するだろうと、今でも思っている。だから、小説を読むと眠くなるんだけど、小説を嫌いになることはなかった。
滝口悠生に出会ったきっかけ
そして、僕は堀江敏幸が薦める滝口悠生の本を図書館で手に取る。手に取った本は、「長い一日」ではなく、「死んでいないもの」だった。読み終わったあとに、この作品が芥川賞受賞作だとしった。そういえば、保坂和志の「この人の閾」とも共振している気がしてきた、記憶の扱い方として。
「死んでいないもの」とはなにか
とにかく、僕は「死んでいないもの」を読んで、驚いた。これは僕がずっと
書きたかった文章だと思った。ちなみにどうでもいいけど、僕は良くある話で10代の頃に詩人になろうと思っていて、でもbright eyesの「perfect sonnet」を聴いて、俺には詩人は無理だ、とあきらめた。
僕はずっと、物語というよりも美しい文章をつなげていけば小説になると思っていた。描写が連関し、そこで全体感として何かの個体を描ければ、何も物語を提示していなくても、それは受け取り手によって変容し、変節が齎せれる小説になるのではないかと思っていた。だから特にストーリー性などない、人が移動するだけの小説を今まで何回も書いてきて、でも結局書き終えられなかった。フック(とっかかり)がないと、ただ文章をつなぎ続けることなど、少なくとも素人にはそれすらできない。となると、小説として成立させることなどできない。小説が何なのかは分からないけれど、でもそれが小説かどうか、ということであれば、僕は小説を成立させることができないものを何回も書いては断念してきた。
しかし、「死んでいないもの」を読んだときに僕は、これは美しい文章だけで構成されている小説だと思った。意味があるのかもしれないし、ないのかもしれないけど、冗長に見えて周到に、しかし援用に文章が複数から張り巡らされていて、実はだらだらというよりも結構緊張感のある文章。主語とか主体とか、丸々と溶けて総体として、何かが語られている作品。この本はいいなあ、とてもいいなあ、と思った。読書メモを書いているサイトで僕の書いた感想は、
「小説が読めなくなった自分が、毎日新聞の堀江敏幸の書評でこの著者の本を今年の一冊に選んでいたので気になって図書館で借りてきた。いやー凄い、なんで今まで読んでいなかったのか、悔やまれる。小説は物語ではないのではないか、と思っている自分にとって、この本のあわいというのか、コンテキストの塊で、意味のなさが逆に日常を反転させる稀有な結晶の結実を示しているこの感じが最高。テキストの縦糸と緯糸によって編まれたこの小説は、永遠に続く誰しもの一日。」(読書メーター)
というものだった。
そのあとも僕は滝口悠生の幾つかの作品を読んだ。良いものもあれば手癖で書かれただけのものもあった。でも、総体として僕は滝口悠生の作品が大好きなんだと思う。肌に合う、というか。
滝口悠生の小説を読んで思ったこと
幾つか読むことで、思ったことが2つある。1つは、小説としては、藤枝静男の死生観というか、生感というのか、死と生をひっくるめたものに近しく、丸谷才一の樹影譚が滝口悠生の小説の母型としてあるのではないか、ということ。死と生をひっくるめたものが、記憶と淡さでもって連綿と繋がれていく感じ。手縫いで、パッチワークみたいに。そして、そこに時制はない。
滝口悠生は、純粋持続について書いているのではないか
この、時制がない、ということで僕は2つ目のこととして、滝口悠生は純粋持続について書いているのではないか、と思った。
純粋持続は、ベルクソンの概念で、正直僕も良く分からない。ただ、シリーズ・哲学のエッセンスのベルクソンという本を読んでから、僕はやたら意識の時間制というものが体に身についていて、僕が勝手に純粋持続だと思っているものがある。
それは、自分の意識は時計とは関係なく流れていて、しかもそれは連綿と流れていて、繋がっている。且つ、いつでも行ったり来たりすることができる、だから今もここにいるけど、例えば10年前の僕もそのなかにいて、それを今取り出すこともできる。という様な感じのことだ。
ちなみに、さっきのベルクソンの本では、純粋持続について
日常生活をおおい尽くす「空間的なかさぶた」をはがしてみると、その下には、我々の常識を覆す「時間」がある。それをベルクソンは「純粋持続」と名づけた。
と書かれている。良く分からないけど、時間とは時計でチクタクと定期的に、コンスタントに刻まれるものではなく、もっと、不可思議なものなのだろう。あなたと僕の時間が違うし、僕の思っている僕の時間も違うのかもしれない。ただ間違いなくそこには、自分の意識があって、流れがあって、存在がある。
滝口悠生の本は、全てで一つの作品となるはずだ。どれもがつながっている。どれもで一つの何かを形作っている。そこには時間もない。どこから読んでもいいし、どこを読まなくても良い。でもできれば全部読んだ方がいい。滝口悠生が書くものは少しずつすべてと連関して、有機的に動き続ける。参照に参照を加えて、相互に補完しあう。そんな小説家というのはなかなかいない。僕はこれからも滝口悠生を読み続ける。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
