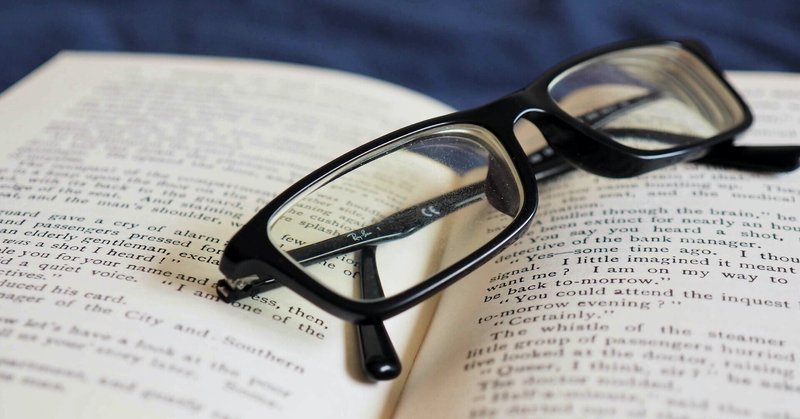
江戸日本の「勤勉革命」は21世紀に「勤勉敗戦」に陥っている 佐々木俊尚の未来地図レポート Vol.706
特集 江戸日本の「勤勉革命」は21世紀に「勤勉敗戦」に陥っている
〜〜平均能力がきわめて高い日本人が経済成長できない理由とは
知能指数を測定できるウェブサイトを運営しているフィンランド企業が、今年の集計データをもとに「世界で最も知的な国ランキング」を発表しています。
それによると、1位は台湾で日本は2位。つづいてハンガリー、韓国、イラン、香港といったランキングになっています。こういうニュースだとすぐ「日本偉い、日本素晴らしい」という誇らしげなコメントが現れますが、本稿の狙いはそこではありません。もう少し先までおつきあいいただければと思います。
このランキング結果について、1位の台湾は受験者数が少なく、スコアの信頼性は低いとか。それに対して日本ではテストを受けた人が多く、正確なデータであると説明。そして以下のように説明されています。
「日本のIQ平均点は世界の平均点よりも高く、標準偏差が小さくなっていることが分かったといいます。また、日本人は問題解決や意思決定に非常にたけているというデータも確認されたといいます」
標準偏差が小さいというのは全体のバラツキが少ないという意味で、つまり平均的に知的能力が高いということです。日本人についてこのような指摘は、以前から言われています。
これは2013年のOECDのレポートで、文章の読解力も数的思考力も日本がトップです。
文章の読解力については5段階で評価し、「簡単な文章を読解するのも困難がある」というレベル1の人は、日本ではわずか5%。逆にレベル4とレベル5を合わせた割合は、日本とフィンランドが高く5人に1人でしたが、スペインやイタリアでは20人に1人もいなかったとか。
また算数でも、ごく基本的な足し算も困難な人は、日本では8%しかいませんでしたが(それでも8%もいるんですね)、なんとフランスでは28%、イタリアとスペインでは30%をうわまわったそうです。
そしてこういう衝撃的なことが指摘されています。
「日本の25~34歳の中卒者は、スペインやイタリアの同年代の大卒者よりもはるかに高い読解力を持っている」
このような平均的な日本人のレベルの高さというのは、いまに始まったことではありません。さすがに中世や古代までさかのぼると他国と比較するのは難しいのですが、近世であれば江戸時代の終わりに日本を訪れた欧米人がさまざまな証言を遺しています。
たとえばトロイア遺跡の発掘で知られるハインリッヒ・シュリーマンは、幕末の慶応元年(1865)に日本を訪れてこう書いています。
「教育はヨーロッパ文明国家以上にも行き渡っている。シナを含めてアジアの他の国では女たちが完全な無知のなかに放置されているのに対して、日本では、男も女もみな仮名と漢字で読み書きができる」
幕末から明治期に訪日した多くの欧米人は、たいてい同じような感想をもらしていますね。男女ともに寺子屋で読み書きを学び、読書に親しみ、江戸には貸本屋が800軒もあったそうです。現在の東京都の書店数が1000店舗ぐらいですから、当時の江戸と呼ばれるエリアの狭さを考慮すると、驚くべき密集率だと思います。
また歴史人口学の故・速水融氏が唱えた有名な「勤勉革命」という説もあります。これは18世紀から19世紀にかけてイギリスで蒸気機関による産業革命が進んだのに対して、同じ時期の日本では人々の勤勉さによる生産性の向上があったというものです。産業革命は英語ではインダストリアル・レボリューションですが、これをインダストリアス(勤勉な)レボリューションと言い換えてるのが上手いですね。
もう少しくわしく説明しておきましょう。当時のイギリスと日本の何が大きく違っていたかというと、イギリスは人口密度が低く、しかも海外にもたくさんの植民地を持っていたので、労働力が圧倒的に足らなかった。この人手不足を解決するために、人が少なくても生産性が向上するように紡績機などの機械が採り入れられるようになったのです。
ところが日本では、新田開発が限界になるまでおこなわれて、余っている土地のほとんどが田畑に変えられていきました。たくさんの作物を収穫するためには、あまっている人員を投下してとにかく「人力」で耕しまくるしかないという方向に進んだのです。
なぜイギリスのように機械化に進まなかったのかと言えば、日本の場合は地形が複雑で棚田や段々畑のような傾斜地が多く、作物の種類もさまざまで、細やかな手入れが必要だったこと。また食糧がつねに足らなかったためウシやウマなどの飼料にまわす余裕がなく、これも大規模化しにくい原因になったようです。ウシにやらせるぐらいなら人間がモリモリ食べて働け!ということですね。
そうした状況では、とにかくみんなが勤勉に農業にいそしみ、たくさんの作物を人力でつくっていくしかない。これがまさに「勤勉革命」で、このような労働に対する考え方が江戸時代は全国に広がり、江戸のような都市にも影響を与え、そして明治以降も労働のモラルとして続いていったと言われています。
この勤勉革命が、冒頭にいくつか紹介したような日本の一般人の平均的なレベルの高さと結びついたことによって、日本の大きな強みになっていったということは言えそうです。つまり「まじめに働く」というこのモラルが、明治維新以降の富国強兵やさらには戦後の高度経済成長を支える原動力になったということなのです。
イギリスで始まった産業革命は初期の蒸気機関による「第一次産業革命」を経て、19世紀終わりごろから「第2次産業革命」がはじまります。この「第2次」の特徴は、ガソリンエンジンによる自動車、高速道路、電力網と家電、ラジオやテレビ映画などの電子的なメディアの出現など21世紀にいたるまでのわたしたちの暮らしをささえるさまざまなテクノロジーが、ほぼ同時に出現してきたということです。
いま挙げたようなテクノロジーの大半が、1890年代のほんの10年間ぐらいのあいだにすべて出そろったと言われていますから、「第2次」のパワーがいかに凄まじかったかがわかると思います。
そして20世紀初頭には悲惨な二つの世界大戦があり、1945年にはそれも終結して、1950年代になると日米欧の先進国ではどこも猛烈な経済成長が始まりました。戦後の復興と人口の急増、そして「第2次」のテクノロジーの普及というさまざまな好条件が重なったのです。
これが日本では「高度経済成長」と後に呼ばれるようになった黄金時代です。1960年代には政府の「所得倍増」計画があり、その通りに所得は倍に増え(物価も高騰しましたが)、みんなが洗濯機やテレビ、冷蔵庫を争って買い求めました。この家電3種のブームを当時「三種の神器」なんて呼んでいましたね。
このような大量生産・大量消費の時代に、企業に必要とされたのは、質の安定した製品をとにかく大量に作りまくることです。原材料を供給できる資本を集め、工場を建てる土地を用意し、工場で働いてくれる質の良い労働者をつのる。カネ・土地・人の3つさえあれば、あとは生産した商品を消費市場がどんどん呑み込んでくれました。
このような大量生産の時代に、日本人が江戸時代から培ってきた労働モラルと能力の平均的な高さは、実にピッタリでした。だから日本は焼け跡の敗戦国からあっという間に世界に冠たる工業国家に返信し、GDP世界2位にまでのぼりつめることができたのです。
最近刊行された『なぜ日本からGAFAは生まれないのか』という本では、こう説明されています。
「産業革命以前は、人々は農村に大家族で暮らしていた。しかし、大量生産のために大量の労働力が必要になると人々は都市の工場に集められた。都市住民が多くなると、家族の単位が核家族に変わる。そして、工場の作業を整然と能率的に進めるために画一的な大衆教育の普及が進められた。その教育の重要な徳目は三つ。一つ目は時間厳守。二つ目は服従。そして三つ目は機械的な反復作業に慣れることである」
「この徳目に最もなじむ国はどこだろうか。そう、それは日本である」
しかしこのような大量生産・大量消費時代はおおむね1970年代までに完了し、「第2次」で生み出されたテクノロジーもあまねく普及し、軟着陸へと向かいます。日本は1980年代にバブル景気があってアメリカやイギリスとはタイムラグがありますが、いずれにせよ90年代後半ごろからは産業構造の改革を求められるようになります。
「構造改革」というのは2010年代のアベノミクスでも使われた言葉ですが、要するに20世紀の大量生産・大量消費が終わってしまったあとに、どのようにして「売れるモノ」をつくるのか、そのためには大量生産に適した従来型の産業構造では間に合わない、という課題から出発しているのです。
アメリカは2000年代、この構造転換に見事に成功しました。その先にいまのGAFAと呼ばれるようなビッグテックのプラットフォーム支配があるのですが、そもそもアメリカがなぜ成功し、日本は成功しなかったのでしょうか。
ここから先は
¥ 600
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
