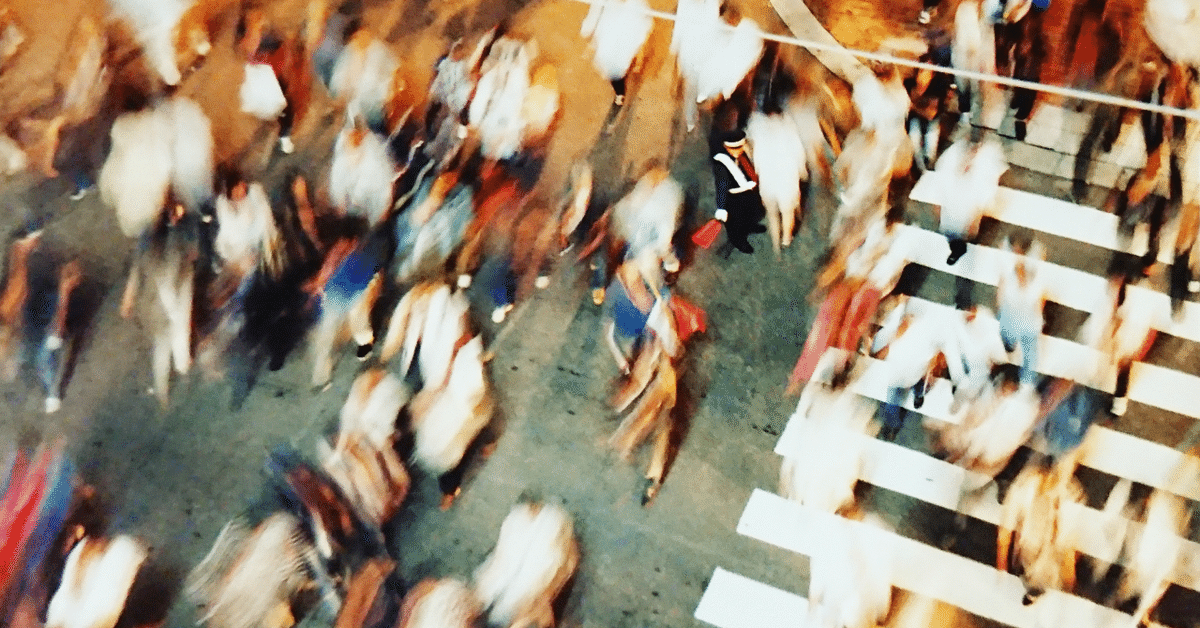
集団作業療法を考える会 さんやまち 第22回定例勉強会 報告
集団の「難しい」を考える~これってホントに「難しい」?Part 2
令和4年6月3日(金)19時から、お馴染みの顔、お久しぶりの顔、初めましての顔が揃い、定例勉強会を開催しました。
アンケート「難しい」の最多得票、「参加人数が多い」をテーマに、意見交換を行いました。
意見交換を行う前に、参加者全員から、「参加人数が多い」と「難しい」と感じる理由を話していただき、グループワークへ。
2回のGWを通して、「難しい」と感じる理由が見えてきました。
”やりたいことの目的が明確にある「この指とまれ!」で集まった集団なら、まとまりやすく、方向性も見えてきやすい”ようです。
でも、利用者様からの希望ではない、”支援者側からの提案などにより集まってもらった、「この指にとまりませんか?」的に集められた集団では、まとまりにくさが生じることもある”ようです。
「そのような集団の場合、利用者様の気持ちにさらに寄り添う必要があるよね」
「利用者様のことを多職種からも教えてもらって、より理解しておかないといけないよね」
「多職種の方と話を重ねることで、利用者様に提供できる支援に多面性が生まれるかも」
こんな話になりました。
他にも「敢えてノーリアクションってどう?」とか、「集団の中に小集団ができて...」などなど、いろんなお話が出ました。
普段から考えているつもりの利用者様のこと、それが共有できていたのかな?
利用者様の思いや、その集団のもつ思い、これらを多職種と共有することを改めて考えたい、という気づきもありました。
「難しい」を言葉に出して、皆さんと意見交換して、共有して、打開策を導き出す。
今回の勉強会で出た意見が、その打開策を導き出せるかどうか、これは参加者全員のこれからの実践でしか答えは見つからないかもしれません。
でも、「難しい」を一人で考えるのではなく、話し合える仲間がいるって、心強いし、嬉しい。
自分だけが悩んでるんじゃない、難しいということを共有できる場にいる安心感も生まれる。
明確な答えがない中、参加者同士の経験から出される打開策が新たな視点になり、臨床の励みにもつながる。
そんなことも感じました。
これからも皆さまといろいろなことを考える場にしていきたいなぁと思える第22回でした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
