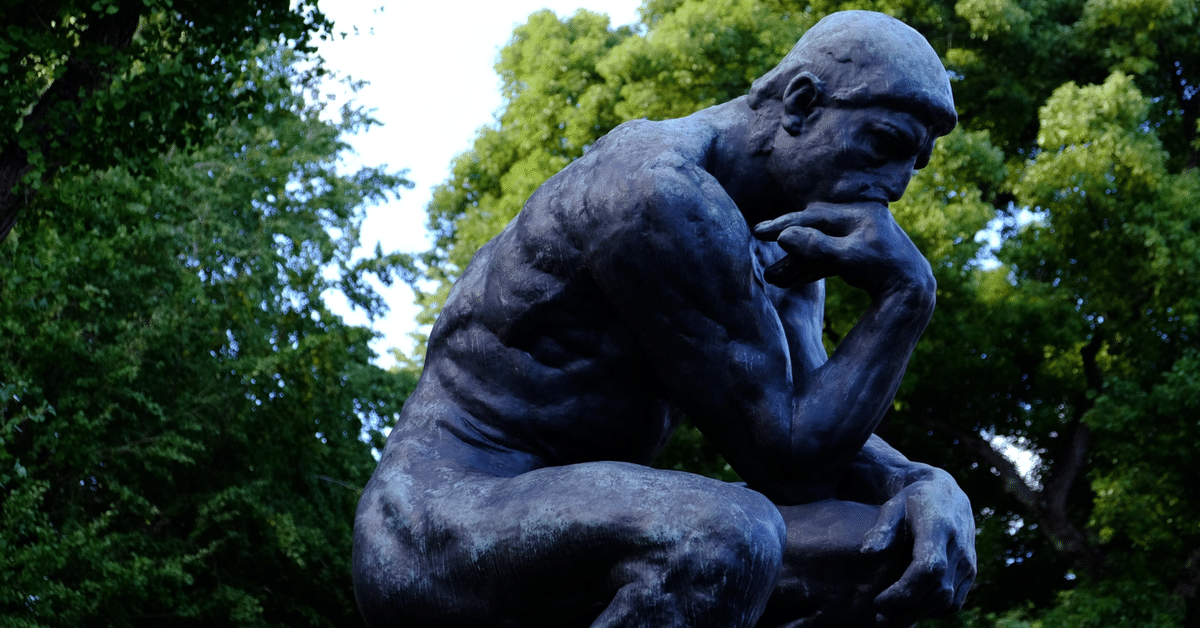
十三人の合議制の成立と崩壊
2022年7月17日、NHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』第27話「鎌倉殿と十三人」が放送されました。
まず、せっかく番組タイトルで算用数字(13)を使っているのに、エピソードタイトルで漢数字(十三)を使っていたことにアンバランス感を感じました。どうせなら算用数字に統一してほしかったなと。
今回は鎌倉幕府の十三人の合議制の成立過程と、それに反発する頼家の五人組体制の成り立ちが描かれています。
実際、この十三人の合議制における「十三人」はどのように選出されたものかがはっきりわかっていません。が、十三人のメンツを見ると次の要因によって選ばれたものではないかと思われます。
1、幕府内の役職を持つもの
2、受領職を持ち、東国武士であること
脚本家の三谷さんは「十三人」の選出理由が不明なところに着目し、幕府を会議体と考えれば、こういうこともあり得るのではないかと考えたのではないかと思われます。
ちなみに「十三人の合議制」は後に鎌倉幕府の「評定衆」の原型となっています。
十三人の合議制
鎌倉幕府の政務の大部分は土地をめぐる訴訟でした。これは平氏政権時代からそうだったのですが、土地に関する揉め事が発生しても公平な裁判機関がなく、結果平氏にゆかりがある者や、国司に縁があるものなどの言い分が通りやすいなどの不公平感があったようです。
鎌倉幕府は朝廷が認めた東国武士の自治政権だと認識しています。その政権を支えるのは御家人や庶民の民意であり、それが公正な裁判にあったのだと私は思います。
そのため、鎌倉幕府には訴訟事務を司る「問注所(問注所)」が設置され、ドラマの中で京都の事情をセッセと頼朝に送っていた三善康信が初代執事に任じられていました。

※出家して「善信(ぜんしん)」と名乗ります。
Copyright NHK (Japan Broadcasting Corporation). All rights reserved.
問注所は訴訟事務を取り扱っていたものの、裁きはあくまでも鎌倉殿が行っていました。頼朝の時代は鎌倉幕府の創設者という事実と征夷大将軍という官位が持つ権威を以って、その裁きが行われていました。
しかし頼朝亡き後、後を継いだとはいえ若干まだ18歳、なおかつ鎌倉殿であってもまだ征夷大将軍ではない頼家が、訴訟案件を自裁できるとは考えにくいと思われます。
そのために作られたのが「十三人の合議制」だと言われています。
『吾妻鏡』(建久十年4月12日)にはこうあります。
訴訟ごとについて、頼家様が直接裁きを下すことは今後は止めることになりました。今後は、全ての訴訟を
北条殿(北条時政/演:坂東彌十郎)
同四郎主(北条<江間>義時/演:小栗旬)
兵庫頭広元(大江広元/演:栗原秀雄)
大夫屑入道三善康信(演:小林隆)
掃部頭中原親能(演:川島潤哉)
三浦介義澄(演:佐藤B作)
八田右衛門尉知家(演:市原隼人)
和田左衛門尉義盛(演:横田栄司)
比企右衛門尉能員(演:佐藤二朗)
藤九郎蓮西(安達盛長/演:野添義弘)
足立左衛門尉遠元(演:大野泰弘)
梶原平三景時(演:中村獅童)
民部大夫行政(二階堂行政/演:野仲イサオ)
達が会議をした上で、判断を下すようにします。その他の者達が安易に訴訟問題を扱うべきではない。と決められました。
これに対して、頼家も御家人たちの意のままにはなるものかと同年4月20日には下記の通達を出しています。
梶原平三景時と右京進仲業(中原仲業)が、政所に張り紙をしました。そこにはこのように書かれていました。
小笠原弥太郎長経(小笠原長経/甲斐源氏小笠原氏)
比企三郎(比企宗朝/比企能員の次男)
同弥四郎時員(比企時員/比企能員の三男)
中野五郎能成(中野能成)
これらは将軍の御側衆であり、鎌倉の中では、たとえ無茶な振る舞いをしたとしても、庶民は歯向かってはいけない。もし彼らの言う事に反していると鎌倉殿の耳に入った者は、罪人として名前を調べて書き出すこと。
これは村や里へお触れを出せ。
また、この五人以外の者は、又特別な仰せがなければ、将軍に目通りは許さない。
これに「五人」とあるのですが、名前が出ているのは四人なので、後一人は誰なのでしょうね。
ドラマの中ではこの四人に江間太郎(頼時/演:坂口健太郎)と北条五郎(時連/演:瀬戸康史)が加わって六人衆になっています。
頼時はともかく、この時の時連は頼家に近い立場にいたということは確かのようです。
幕府功労者の死
ドラマの中で、「十三人」の合議メンバーを加える過程が描かれました。三浦義澄は時政の依頼に応えて合議メンバーに加わります。三浦義村の助言によって和田義盛も加わり、さらに北条方に人数が欲しいと時政が言い出します。
義村「あとは……誰がいたかな」
時政「佐々木の爺さんは?」
義村「もう死にました」
時政「千葉の爺さんは?」
義村「もうすぐ死にます……爺さんは止めておきましょう」
時政の意見に瞬殺で無慈悲で封じる義村が小気味いいですよね。
補足をしておくと、佐々木の爺さんこと佐々木秀義は、1184年(元暦元年)7月から8月にかけて京や伊賀、大和周辺で起きた伊藤忠清ら平氏残党の反乱(三日平氏の乱)の鎮圧のために出陣し、討死しています。
もうすぐ死にますと言われた千葉常胤ですが、実際に亡くなるのはこれから3年後の1201年(建仁元年)です。
なお、千葉常胤が亡くなるまでに以下の2名が亡くなることになっています。
三浦義澄:1200年(正治二年)1月23日
安達盛長(蓮西):1200年(正治二年)4月26日
義村が「もうすぐ死にます」というのは、千葉常胤ではなく、実は自分の父親・三浦義澄のことになってしまいます。
なんとも皮肉な話ですね。
ちなみに「十三人の合議制」は文官トリオの一人である中原親能の出家、そしてこの二人の死によって一気に3人が欠けたことにより、自然消滅していきます。
佐々木秀義、千葉常胤、三浦義澄、安達盛長、これらは幕府創成期の功労者であり、第一世代です。その中でまだしぶとく生き残っているのが北条時政、梶原景時、比企能員です。
そして第二世代である、北条義時、畠山重忠、和田義盛らが後を受けていくわけですが、ここに名前のでているほとんどの人が次々と死んでいくのが鎌倉時代ですね。
結城朝光
今回の話で、琵琶を習いたいという実衣の願いに対し、畠山重忠が推挙したのは結城朝光(演:高橋 侃)という武将でした。
この結城朝光は、下野国の有力御家人・小山政光の四男です。
このドラマには全くでてきませんが、小山政光の妻は頼朝の乳母(寒河尼)で、その子嫡男・小山朝政は、父と共に早くから頼朝の挙兵に参加しています。
朝光も兄と同様に頼朝の挙兵に加わっており、頼朝が烏帽子親になって元服しています。朝光は弓の達人でありながら和歌や音曲にも通じた文武両道の人物でした。
結城朝光はここで唐突すぎる登場になるのですが、これがこの後の梶原景時の変に繋がる布石と認識していただければ幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
