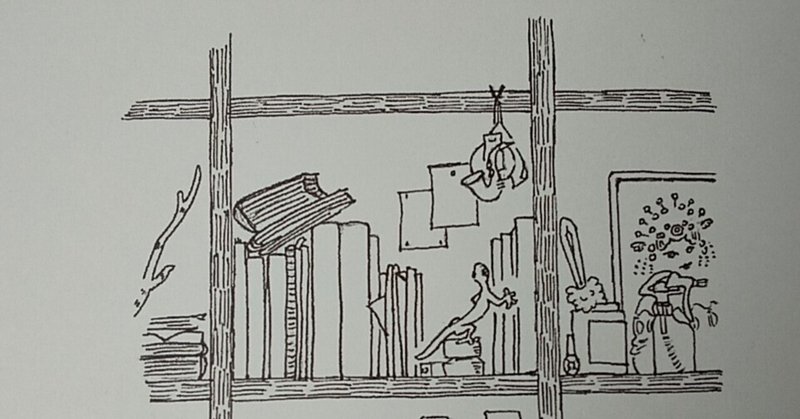
詩誌「三」68号掲載【夕焼けのオマージュ】石山絵里
いつだったか、ヒロシは「きみのこと、好きでなくなった」と言い放った。
あの日の約束をどうしても守れなかった私を、ひたすら謝るしかできなかった私を、アイツはなじりになじった。
仕事で失敗した私に、同僚の吉野さんが「ないわー、ありえんわ」と吐き捨てるように言った。
私の心の中はいつもどんよりとしていて、すっきり晴れることが無い。
「たまには自分の気持ちをハッキリ言ってもいいんじゃない?」
「ハッキリ言わないから、なめられるんだよ」
そんなことを言う人もいるけれど、ハッキリ言えるなら、私の心の中はいつでも晴天なんだろうか。
街に出れば、行き交う人達は白い歯を見せて笑っている。今日は雲一つない快晴。うらめしいくらいの青。太陽の光がまぶしくて思わず目を細めてしまう。
ハッキリ思ったことを言えたなら。どいつもこいつも、ハッキリ言ってくれるよな。あんな言葉も、こんな言葉も、反芻することなくキレイさっぱり忘れてしまえたら。それなのに、どうして私は。
うつむいて歩く私の足。右、左、右、左…。ひたすら足を動かすと、私の体はバス停に着いた。
バスに乗りこんで、バスに揺られて。今日はこの席を誰にもゆずりはしない。どっかり腰をおろして、そのうちに夕焼けでも見られたらいい。年寄りが来ても、赤ちゃんを抱えた母親が来ても、知らないふりして窓の外を眺めていよう。重たそうに沈んでいく夕日を、この目に焼きつけよう。
2022年12月 三68号 石山絵里 作
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
