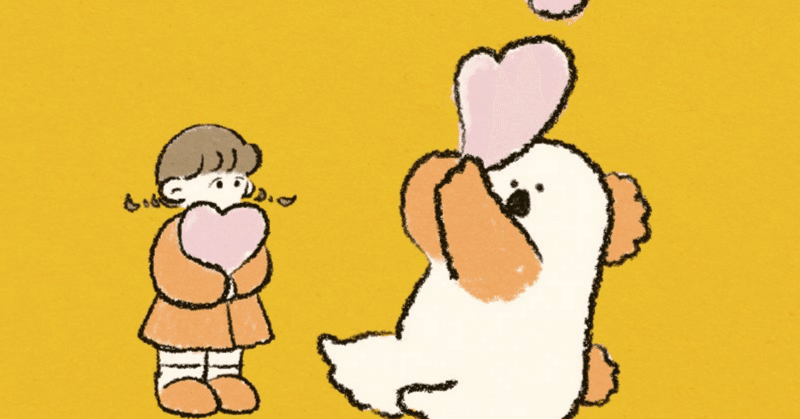
別れ際の『答え合わせ』
「じゃあ、またね」
保安検査場まで見送りに来てくれていた友人が、別れる手前でおもむろにカバンを漁った。
中から出てきたのは、クリーム色のシンプルな封筒だった。
先日「書いてくるね」と約束してくれていた、手紙だった。
彼女とは、音楽の趣味が似ていた。
地元が近く、大学進学で遠方に来ている境遇の近さも相まって、大学在学中のライブ友達としてとても仲良くしてくれた。
ライブと旅行のどちらがメインかわからない遠征も度々一緒に行った。
手紙には、そんな思い出がしたためられていた。
私が就職で上京するにあたり、彼女とは疎遠になる。これまでのように、気兼ねなく気になるライブに誘い合っては、同じ感動を共有する機会も少なくなるんだろう。
潤んだ視界の中で、ある1文に目が止まった。
「私はさむのこと『親友』だと思ってる!」
彼女からの『親友』という言葉に、くすぐったさと安堵感を覚えた。
実は、彼女と「ライブ」という理由なしに会うようになったのは、彼女と仲良くしていた5年のうち、最後の1年半ぐらいだったのだ。
顔を合わせる度に「北海道に行ってみたいね」と言っては、具体的な日程も決めず、やがてその旅行の話すらなくなってしまっていた。
そういう場所が、私たちの間にはいくつかあった。
それは別に彼女が悪い訳ではなく、万年金欠で、彼女と別れたあとにすっかり一緒に行きたい場所のことを忘れて連絡しないでいる私のせいだった。
それなのに「あそこに行きたいね」と言い合う度、いつしか(この話もたぶん、行かずになかったことになって行くんだろうな)と思っている自分がいた。
我ながら卑屈なやつだ。自分で段取りを組めば、行ける場所ばかりだったのに。
そんな自分への後ろめたさが、『彼女に仲がいいと思ってもらえている』ことへの自信を削っていた。
ところが彼女自身は、そんな私を『親友』と呼んでくれた。
いろんな場所に行く算段をたてないことなんて気にしていなかったのかもしれない。あるいは、その事実と『仲がいいかどうか』の判断軸は、別にあったのかもしれない。
なんにせよ、私の気がかりは不毛だったのだと、その1文に気付かされた。
相手に聞いてみて、初めて一方的な感情だったとわかることがある。
一方的だとわかるのは、嬉しいことよりも辛いことの方が多いから、どうしても私たちはその答え合わせを先送りにしてしまうから。
せめてポジティブな感情はなるべく伝えて、そこから相手が自身の感情と照らし合わせてくれたらいいなと。
そんなことを考えながら、私は新しい便箋を机上に出した。
いつも読んでくださってありがとうございます。
