
「私は宇宙人。」第1話
みんなが笑うときに笑えない。
感動映画を見ても一人だけ冷静で、普通の人とは何かが違う。自分は別の惑星からやってきた宇宙人なのではないかと度々考えている木南梨(26)が出逢ったのは「宇宙会」というコミュニティだった。宗教団体の策略や、大企業のステマなどと噂される怪しさ満載の会に参加した彼女は、独特なルールに翻弄されながらも日々奮闘する。互いの素性も明かさないまま「惑星名で呼び合う」「課題に従った行動をする」等、奇妙なルールに従いながら、互いに打ち解けていく参加者たち。そんな中、一人の様子が徐々に不気味さを帯びてきて… 他者とはどこか違うと感じている6人の運命やいかに⁉︎
-人物紹介-






※画像引用元:jewelSaviorFREE
【序章】 とあるうわさ
宇宙会。開催場所や時間帯はバラバラ。
幻の会とも呼ばれ、主催者の情報も、参加者の属性も、その全てが謎のベールに包まれている。
#宇宙会 #plzhmg
“Please help me , grey”の略ハッシュタグをつけ終わり、私はスマホの電源を切る。このアカウントを始めたのは、半年前のこと。後輩で噂好きの美咲が、いつものように私の席にやってきて騒がしく言う。
「木南先輩!宇宙会って知ってますー?なんか、宇宙人と知り合えるかもしれない場所なんですって」
まただ。新しいもの好きで、知ったかぶりを得意とする彼女は、自慢げにそう言った。昨年この会社に新卒で入社してきた時から、イマドキの女の子の権化のようだと感じてはいたが、社内のスキャンダルだけではこと足りず、遂にスピリチュアル方面にまで手を出したかと、半ば感心しつつ、
「うちゅうって、あの宇宙?地球の外のことかな?」
「ですです。惑星とか天体とかの宇宙です。今ネットで少し騒がれてるんですよ。どっかの大学のヤリサーなんじゃないかとか、大手企業のステマとか、新手の宗教団体とか、それはもう色々な。中には宇宙会仲介人なんかも出てきて、宇宙会と志望者を繋げてくれるんですって。なんか、紹介制のバーみたいじゃないですか?」
いかにも美咲がとびつきそうなネタである。多感な20代の女子にとって「特別感」は至高の存在だ。特に、学生から社会人に肩書きが変わり、守られた存在から、大海に、大海原に放り出された彼女らは、特別感を優越感に変換し、拠り所とするしかない。
「私もどうしても入会したくって、裏垢作って運営にアピールしてるんです。しまくったら、突然DMが来るかも…って噂で」
私も特別感に憧れないでもないが、そんな不確かで、不明瞭な存在を純粋に信じられる美咲を羨ましく思う。
「今時の若い子たちの間じゃ、そんな噂あるんだね。宇宙人とお友達にでもなれるのかな?まぁ、新しいものに興味が出る気持ちも分からなくないけど、私には縁のないことだな。あ、そんなことより、今は仕事に集中した方が良いと思うよ。15時までって課長に言われてた資料はもうできてるかな?」
そう言って話を切ると、バツが悪そうに自席に戻っていく美咲。言いすぎたかしらという心配をよそに、私も自分の仕事に戻ると、
「宇宙会って知ってますー?」
美咲の甲高い声が、またオフィスに響き渡った。今度は同期の山下に布教をしているようだ。既に宇宙会に行って、宇宙人にでも洗脳されているのだろうか。見上げるほどの楽観性に呆れつつ、私は彼女の元に駆け寄り静かに諭す。
「み、美咲さん!?」
宇宙会との出逢い
私は宇宙人だ。
そう思うことがある。インターネットでお気に入りのYouTuberの動画を見ているときや、通勤時の電車の中、実家に帰省したときやお風呂の中でさえも。
私はこれを「宇宙症候群」と呼んでいる。発作的にやってくる宇宙症候群の正体はハッキリとは分からないが、私はおそらく、私を人間でない「何か」と思いたいのだろう。思うことで自分という生命体を理解しようとしている。じゃないと不安で押しつぶされそうだから。じゃないと、私は私を保てないから。
発作に自覚的になったのは、大学生の時だ。
当時、仲の良かった清水さん、田中くんという私の友達にしては陽キャに分類される二人に誘われて『命の雫』という、お涙頂戴、小動物映画を観に行った。主人公の実(みのる)が、幼少期に拾った子犬(メロという)を我が子のように育てるも、病気で余命幾許もなくなってしまう。なんとか延命を図ろうと奮闘するも、その甲斐なくメロは死んでしまう。メロを軸に、関わる人々同士が繋がり、成長していく物語だ。
清水さん、田中くんは、メロが亡くなるときには、既にわんわんと号泣していたものの、私の眼から涙が溢れ出すことはなかった。一粒も、一滴さえも。実話をもとに書籍化され、映画化された本作はヒットし、興行収入5億円を記録したようだが、私は未だに、あの映画の泣けるポイントが分からない。
これは私が単に動物嫌いとか、感動映画が苦手とかそういった理由ではない。そんな表面的なものでなく、もっと根源的な「何か」が原因だ。
あたりまえをあたりまえと思えない。
普通のことが普通にこなせない。
みんなが笑う時に、同じポイントで笑えず、みんなが泣くときに、1人だけ客観的に冷めたような分析をしている。能力的でなく、感情的にそれができない私は、たぶん人間として大切な何かが欠落しているのかもしれない。それを人は「冷めた人」と一言で片付けてしまうのかもしれないが、当事者にとって、少なくとも私にとってそれは、一生を添い遂げる伴侶のようなものなのだから、中々どうして割り切ることは容易ではない。
「私は宇宙人かもしれない」
そう思う。きっと私は、太陽系外縁天体からやってきた「人ならざるもの」なのだ。太古の昔に隕石に付着した「何か」が、ホモサピエンスやネアンデルタール人を模し、交流し、真似ぶことで生き延びてきた、人ならざる存在。それが私。
そんな厨二病的な思考をつらつらとしていると、いきつけのカフェ「モンテローザ」に着いた。イタリア・スイス国境に聳える山の名を冠するそのカフェは、私の行きつけの東京都品川区目黒にある。イタリア語で「バラの山」を意味するモンテローザ、という名前の洒落さと、なにより職場に近いという理由で、ランチはここで簡単に済ますことが多々ある。10分ほど注文したパスタを待っていると、隣の席からこんな会話が聞こえてきた。
「先日の件、考えてくれた?」
30代後半に見える小太りの女性と、10代後半か20代前半に見える金髪の青年。親子かと思ったが、こちらにも緊張が伝わるほどのよそよそしい雰囲気を感じる。ママ活を一瞬疑ったが、次の瞬間、その疑念が思い違いだと確信する。
「宇宙会は選ばれた人間しか入ることができないの。この機会を逃したら、あなたを次いつお誘いできるか分からないのよ。巷では、教祖様がいて、変な水を買わせるだとか、そんな噂が流れているけれど、そんなことはないわ。メンバーの私が保証する。宇宙会のメンバーは、みんな面白い人よ。強制はしないけど、私はあなたの力になりたいの。今の自分を少しでも変えたいと思うなら、ここに連絡してちょうだいね」
そう言って、自分の名刺の電話番号欄を強くペンで囲み、彼に手渡す。彼女はそのまま立ち上がり、2人分のお金を置いて立ち去った。残された彼は、1分ほど考えたのち、残った水を飲み干し、何も言わずその場を去った。勢いよく立ったせいで、風は女性の名刺を吹き飛ばし、床に落ちる。私は店内を見回し、接客係を一瞥した後、それを拾い上げた。
「株式会社××× 第二ユニット営業 田中真由美 080-2***-4****」
「今の自分を変えたいなら、宇宙会に」か。思えば私は、何かに熱中したことがあったろうか。いつの時代も「やらなければならないこと」を卒なくこなすことのできた私は、いつしか「やらなくてもよいこと」をしようとするのを辞めた。無駄なことをしないと言えば聞こえは良いが、相手が求めていることしかできない私は至極つまらない人間だなと、自分で思う。
まただ。また「宇宙症候群」が出てしまった。ふと下ろした目線の先には、先ほどの女性が置いていった名刺があった。
「080-2***-4****」
呟きながら番号を押す。
「あ、もしもし」
私の中の中かが躍動するのを感じた。
宇宙会からの誘い
東京都大田区南千束、かの有名な東京工業大学の近くに建つ、緑色の一軒家。まるで北欧の家々を連想させるカラフルなお家に囲まれた家賃7万2,000円(共益費込み)の私の家は、付近では「幸せのお家」と呼ばれている。かと言って、住む人が皆大金持ちになって出て行ったとか、住人の仲が特段良いとか、祈れば子宝に恵まれるみたいな、言うならば一種の呪いのようなタグ付きのお家というわけではない。
摩訶不思議で、怪奇で、世にも奇妙な逸話が特段あるからという理由でなく、単に夏になるとつばめが巣を作るからだ。ちなみに余談だが、私の部屋のベランダには、スズメバチが巣を作ろうとしていたこともあったが、巣が完成する前に、なんとか決死の覚悟で阻止した。
とは言え、私が入居した10年前は、そこにそれはなかった(スズメバチじゃなく、つばめの巣の方だ)。卵が先か、鶏が先か、なんて議論があるか、この場合、つばめの巣ではなく私が先だ。頭からお尻まで読むのに数十分はかかる契約書(その大半が理解不能)に捺印し、電気、水道、ガス等の営業電話に応対し、最後の砦、wi-fi開設を終え、やっとの思いで住み着いたのは私が先だ。その思いを君は知っているのか、つばめくん、そう思う。それと同時に、これがつばめではなく、ねずみやカマキリとかだったならば、スズメバチのように駆除されていただろう。幸せの象徴として崇め奉られる貴重な存在でなければ、駆逐されていたろうに。そんな身にも肉にもならないことをつらつらと考えていると、電話が鳴った。非通知だ。
「木南さんのお電話番号でよろしかったでしょうか?」
聞き覚えのない声に、私は若干たじろぐ。
「はい、木南ですが……」
「モンテローザでお電話いただいた田中です」
私ははっとし、急いでメモを開き、ペンを握りしめる。
「あ!先日は突然すみませんでした、宇宙会の方はどうですか?私は認められましたでしょうか」
半年前にカフェで言われた事は二つ。
①主催がメンバーを直接選抜すること
②最初の勧誘はTwitterのDMで来るため、宇宙会情報や参加の意思をツイートしつづけること。その際は#宇宙会と#plzhmgの2つを必ずつけなくてはならない
小学生以来していなかった「遊び」をしているような、体験型ゲームに参加しているような感覚だった。ただし、私は正直この茶番に終止符を打とうとしていた。なぜなら、田中からの連絡がここ数ヶ月来ていなかったからだ。
「ごめんなさいね、色々あって連絡できていなかったけれど、おめでとうございます。選ばれたみたいよ。今日中にDMをするらしいわ」
田中の覇気のない声を聞くと、少しばかり不安になるが、同時に私はかつてない多幸感を感じていた。何かに選ばれた経験はあっても、結果的に周囲が評してくれていただけで、自分が能動的に行動した結果の功績でないことがほとんどだったからだ。気がつくと、電話は切れていた。電波でも悪いのだろうか、と機内モードをオンにしようとした時、スマホの通知が鳴った。
「おめでとうございます♪ あなたは宇宙会のメンバーに選ばれました。詳しくはポストをご確認ください」
いよいよ宇宙会の始まりだ
下北沢にある一軒家。地方出身者が初めて訪れると、必ず驚くであろう都内でも一風変わった雰囲気を醸し出す駅周辺を抜け、本多劇場寄りに5分ほど進む。閑静な住宅街の中でも、ひときわ立派な一軒家で、第1回宇宙会は催された。到着すると、中から初老の男性に出迎えられる。
「アースです。どちら様でしょう?」
突然の問いに驚きつつも、私は答える。
「あ、ヴィーナスです」
美の女神でもあるこの名を口にすることに多少の抵抗を抱きつつも、彼は何かを理解したように頷き、私を招き入れた。
座敷に案内されると、そこには既にスーツ姿の男性と毳毳しい装いの女性がいた。2人の前には、それぞれ「マーズ」と「ジュピター」の文字が書かれたプレートが置いてある。私が呆然と突っ立っていると、マーズでスーツ姿の男性が立ち上がり、持ち前の営業スマイルと共に歩み寄ってきた。
「こんにちは、俺はマーズです。あなたは?」
「は、はや… あ、ヴィーナスです」
本名を言ってしまいそうになったが、すんでのところで留まった。
「ヴィーナス!俺も彼女も、さっき着いたところなんです。さ、名札の前に座って」
そう言われ、私はヴィーナスと書かれた名札の前に座った。そうこうしているうちに、先程案内してくれた初老の男性が、大学生くらいの男の子と広間にやってくる。彼らもそれぞれ「アース」と「マーキュリー」と書かれた座席に座った。残る空席は、あと「ムーン」だけである。
「ムーン」、最大の衛生であり、英単語の中でも最も知名度が高いと言われている「月」を表す言葉。遠目から見ると、ウサギが餅をついているようだとか、かぐや姫が住んでいるとか、何かと話題の絶えない存在。さぞかしキラキラした女性が来るのではと推測していると、水の流れる音の後に、誰かの足音が聞こえてきた。現れたのは、スラッと細身な女性ではあったものの、ショートカットで色白の女の子だった。高校生くらいだろうか、彼女が「ヴィーナス」の方がよっぽど似合っているのではないか?と思うほど、女の私でも見惚れる透明感を感じた。彼女は、居間に戻るや否や「お待たせしました」と言い、自席に着く。
彼女が席につき、座席が全て埋まったのを確認すると、最初の案内人、初老のアースが立ち上がった。
「本日はみなさん、お集まりいただきありがとうございます。今回の司会を務める、アースです。事前に送られてきた手紙は既にお読みかと思いますが、私の方から再度説明をさせていただきます」
そう言うと、黒い封筒から白い紙を取り出し、机の中心に置く。
1. 互いの本名は伏せ、惑星名で呼び合うこと
2. 提示された課題には各々従うこと
3. 毎週末に一度、必ず集会を開くこと
※会の情報については他言無用
彼は、手紙の内容を上から順に読み上げながら、最後に、
「ということで、今回は私、アースの家で宇宙会、改め集会を開いている次第です」
互いが互いの顔を見合わせ、次の一手を読み合っている。すると、声を上げたのはマーズだった。
「本当にあったんですね、ネットの迷信かと思ってました。ビビりませんでしたか?突然DMが来て、詳細は手紙をみてくださいって。ポスト見たら、本当に手紙入ってて、住所どこで調べたんだーって、怖くなりましたよ」
「ほんとそうですよね!」
同調して応対するジュピター。
「今日はお伝えしなければいけないことがいくつかあるのですが、まず簡単に自己紹介でもしますか?」
主催から届いたであろう他の紙をちらつかせ、アースは問う。どうやら司会であるアースは、私たちより多くの情報を得ていると見て間違い無いだろう。
「では、私から。アースです、今年で53になります。この家で一人暮らしをしています。宇宙には若い頃から興味があって、今も天体望遠鏡で星を見るのが生きがいです。こんな老いぼれですが、活力とやる気は若いもんには負けない自負があります、よろしくお願いします」
見た目の堅苦しさとは裏腹に、柔和で柔軟な考えに関心しながら、私は周りを見回すと、仏壇に男女と子供の写真があるのを見つけた。奥様とお子さんだろうか、なんて考えていると、ムーンが話しはじめる。
「ムーン、高校2年です。この会は、なんとなくワクワクしそうだから参加しようと思いました。以上です」
それ以上聞かれたく無いのだろう。無機質に、端的且つ早口な口調に圧倒されていると、私の番がきた。
「ヴィーナス、30歳で広告系の仕事をしています。えっと、趣味は旅行ですかね」
思わず口をついて出てしまったが、実のところ最近仕事が忙しく、ここ3ヶ月は家と会社の往復しかしていないため、趣味という趣味に時間を割けてはいない。次に、ジュピターが続ける。
「ジュピター28歳です。今は歌舞伎町で夜に働いてます。よろしくです」
「不動産会社勤務のマーズ33歳です。たまにはこうゆう経験もアリかなって、ワクワクして今日は来ました。」
勤め先を暗にごまかす女も、聞いてもいないのに勤め先を誇張する男も、あまり私の周りにはいないタイプで、この会の主催は一体どういう基準でメンバーを選んでいるのだろうと、疑念を強める。
「マーキュリー、25歳、社会人です」
なんとも無気力で、就活の面接なら落とすかもしれない…といった感じの男の子だ。大学生かと思ったが、入社3年目の若手社員といったところだろう。意外と今は、こうゆう寡黙な子がモテるんだろうかと感慨に耽っていると、アースが切り出す。
「みなさん自己紹介ありがとうございます。まさか高校生の方もおられるなんて、ビックリです。年齢も性別もバラバラですね。さて、一通り自己紹介も終わったことですし、交流のお時間としましょうか。今回のお題は『好きな作家』についてです」
なんともまぁ、突飛な展開に一同がたじろんでいると、マーズが代弁する。
「アース。交流の時間とは何でしょうか?」
「あー、これは失敬。私も初めてのことで説明不足ですみません。この歳になると自分が知っていることと、相手が知っていることの差をあまり気にしなくなってくるんです」
「なるほどー」
アースの老害発言に、愛想笑いをすると、気づかず彼は続けた。
「どうやら集会では、それぞれの課題の進捗報告とテーマに沿って、自分の体験、経験、考えを話すことになっているようなんです。テーマも毎回変わるらしいんですが、今回は作家ですね」
迷惑だなと、そう思う。
私は、私のことを話すことが嫌いだ。
まして、どこぞの誰か、赤の他人に話すなんて。
小学3年生の時、レイラという名前の女の子がクラスに転校してきた。帰国子女と紹介された彼女は、父親の関係でオーストラリアのパースという場所に今まで住んでいたのだという。明朗快活とは程遠い私は、皆んなから羨望の目でみられている、一等星の如く輝く彼女とは一生無縁だと思っていた。
ところが、そんな予想とは裏腹に、私と彼女はクラスの誰よりも早く話すこととなる。映画やドラマなんかで見る「〇〇の隣が空いてるから座ってー」なんてことは流石に起きなかったが(毎回あの空席はいつからあったんだろうと思う)、彼女の自己紹介が終わるや否や、先生は席替えを提案した。
視力が悪い私は、1番前の席を学期初旬から固定でキープしていたので、席替えに対する思い入れはあまり無かったが、それでも近くに座る生徒は重要だった。勉強に集中できそうな人が隣だったらな、なんて考えていると、
「はい!よろしくね」
可愛らしくて甲高い声が響いた。例の転校生である。
まさかまさかの展開に思わず唖然としてしまったものの、決まったことは仕方ないと割り切り、その日1日は教科書を隣で見せてあげながら授業を受けた。
問題が起きたのは最後の授業「道徳」である。その日のテーマである「人の気持ち」に関する話し合い。
「あなたが幸せや悲しみを感じる時はどんな時ですか?」
に対して、私は澱みなく答える。
「甘いおかしを食べたときはうれしくて、ピーマンがにがてです」
ペアワーク相手の転校生が微笑み、こう続ける。
「好き嫌いしちゃダメだよ!私はね、ママが笑うとき楽しくて、泣いてる時は悲しいです。あのね、ママはお笑い芸人さんが好きで、笑いながらみてて、玉ねぎきるときとか泣いちゃうから、私いつもヨシヨシしてるの」
今思うとドングリの背比べだが、私は幼心にして劣等感を覚えた。初対面の相手に、こうも明け透けに心の内を話せる彼女の警戒心の無さに驚嘆し、同時に私とその子ではみる世界、生きる場所が違うと悟った。
私はうまく私を話せない。
怖い。知らない人に私を話して、私さえ分かっていない私を知られることが。耐え難い。意図しない方向で理解されることが。憎い。あなたはそういうタイプねと断じ、グルーピングする奴らが。嫌いだ。
「ヴィーナス、ヴィーナス?」
ジュピターの声で我に帰る。
「大丈夫?あなたの番よ。あ、すみません。えっと、好きな作家ですよね。東野圭吾とか、村上春樹ですかね、最近なら湊かなえも」
答えないという選択肢がない中、誰もが聞いたことのあるベストセラー作家を列挙し、私はため息をついた…
ムーン

世の中の人間は大抵バカである。そう教えられて育った。父親は大手コンサル会社の部長、母親は外交官。両親の職種を話すたびにエリートだと羨まれ、妬まれる。
幼い頃から欲しいものは何でも手に入った。
お菓子も、服も、靴も、本も、ネックレスも、カバンも、ゲームだって何でも買い与えられた。ただ、一度だけ叶わなかったことがある。ただ一つだけ手に入れられなかったものがある。
8歳の誕生日、私は家族で旅行をしたいと伝えた。同じクラスで隣の席の美幸ちゃんが、週末の家族旅行の話をしたからだ。それまでも気にならなかったわけではない。ただ、私が起きた時にも寝る時にも顔を見ることがない父と、出張が多くほとんど家にいない母に、そんなことを伝える意味が一体どれだけあるだろうか。幼心に考える。子供心に類推する。
その願いは未だ叶っていない。
当然だ。共働きの家庭には多いこと。ウチだけじゃない、私だけじゃない。そう思い聞かせているうちに、段々どうでも良くなってしまった。親が家にいないだけであって、必ず机上には書き残しがある。枕詞のように冒頭に付く「一緒にいれなくてごめんね」は母の常套句だ。私は可哀想な子なんかじゃない、寂しくない、悲しくない。自分に言い聞かせる。
行ってらっしゃいも、おかえりも言わない生活。
ただ、行ってきますとただいまは欠かさない。
誰もいないリビングに向かって、玄関から大きな声で言う。それを欠かすと、この家が家じゃなくなってしまう気がするから。家族が家族じゃなくなってしまうようだから。
そんなことを考えながら帰路に着く。
ずっと前のことなのに、こんなことを考えてしまうなんて。後悔しながら、右ポケットに手を伸ばすと、一枚の紙に触れた。
「ムーン『家族で過ごす時間を増やすこと』」
宇宙会は思ったよりも胡散臭かった。
まことしやかに噂されていた、大規模団体の関与などは一切感じず、大学のサークルや村の集会にも似た手作り感がそこにはあった。ただ、実態はどうだっていい。私は認められたい。SNSで噂の、宇宙会の真相を暴いてやる。果たして誰が、どんな目的で開催しているのか。尊敬する父や敬愛する母に認められるために……
私にはおよそ友達と呼べる人がいない。
友達の定義がおかしいとか、とは言え少しくらいは話す人もいるだろうと思うかもしれないが、包み隠さず1人もいない。厳密には昔は多少いたのだが、普通の人と異なり、小学、中学、高校と順々に友達の数が増えていく定説は私には通用しない。それはまるで、一次関数のマイナスグラフのように、自我の芽生え、アイデンティティの確立、私が私を自覚すればするほど、私は他人と違う種であるという確信が強まった。
クラスの担任がイケメンだと言われてもピンとこなかったし、勉強が苦手という子の気持ちも理解できない。トイレでタバコを吸って停学処分をうける男子生徒の気持ちも、学校の校則を守らずスカートの丈をまくしたてる女子生徒の気持ちでさえ、全く未知の出来事だ。
私はたぶん一人に慣れてしまったのだろう。孤独を感じないまでに深く。時に思い出されるのは、「そんなバカの気持ちなんか分からなくても良いんだぞ」という厳格な父の言葉と「良くやったわね、あなたは賢いわ。さすがママの子」という母の言葉だけ。私は、嫉妬50%、羨望30%、水と肉でできてる。つまり私を構成する要素の8割は、他人の評価による。
「聡い子。それが月島ラブリだ」
改めて思い直し、実行計画を立案すべく、ランドセルからペンを取り出した。
マーズ
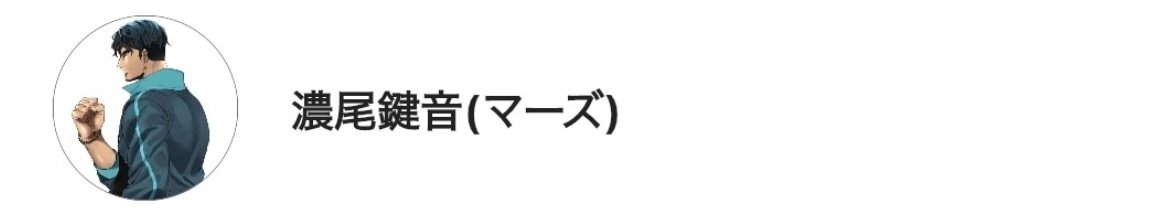
愛用のプロテインシェイカーを振りながら、今日の株価とニュースサイトをチェック。毎朝食べる鶏ささみがバジル風味からカレー風味になったことにも気づかず、7時半に家を出た。今日は、午前中に2件の訪問、1件のプレゼンを予定している。昨日の夜中に作成した資料を、iPadでPDF化した後、電車内でモゴモゴと予行練習をしていると、目の前でお祖父さんがよろけて転倒してしまった。一瞥し、予行練習を続けようとしたが、ふと一昨日の集会の出来事が思い出された。
好きな作家。
普段ビジネス書かNewspicksの記事しか読まない私にとって、小説は縁遠いものである。最後に読んだのはいつだろう。そうだ、1年ほど前、贔屓にしていただいている大手メーカーの部長さんと飲んだ時。小説原作の映画が話題になっているとのことで「興味あります、読んでみたいです」と適当に合わせていたら、帰り際に一冊貰ったのだ。帰宅途中、酔い覚ましにパラパラとめくって抱いた感想は「読みにくい」だった。結論がなく、冗長で、情緒に関する記述が多い。僕はどう思った、彼女はあぁ感じた。彼と別の女が寝た。彼は実は病に伏していた。そんな内容だったと記憶している。陳腐な感想を抱いた自分に少し悲しみを覚えつつも「こんなの分からなくても死にはしない、分かったところで金にも得にもならない」と自分で自分を正当化したことだけを覚えている。
学生時代なら、もう少し楽しく読めていたのかもしれない。「あぁ、あの物語の主人公って結局死んだんだっけか?」と、他愛もないことを考える。冒頭と結末しか読まず、家の棚にしまってしまった本に思いを馳せていると、電車の揺れに気づき、ふと我に帰る。
「あ、大丈夫ですか?つかまってください」
ふと手を差し出すと、初老の男性は手につかまり、謝辞を述べながら、別の乗客が空けてくれた席に座った。
マーズ。火というイメージからか、炎炎と燃えるイメージのある星。だが、あの赤はサビによるものだ。熱々と煮えたぎるマグマではなく、二酸化炭素に覆われた岩石の塊。熱血に見えて、それは虚構か。まるで自分みたいだと思う。そんな私は「1日に2回ありがとうを言われる」というものだった。日に善行を2回も積まなくてはならないのは、純粋に苦労しそうだが、1か月で終わると思うと特に気にならない。
「赤坂、赤坂ー」
そうこうしているうちに、目的地に着いた。
今日も一日気張るぞと思いながら地上に出ると、快晴だったはずの空が薄暗くなっていた。今日は雨が降るかもしれないなと、天気予報の信憑性に呆れながら、やはり会のことを思い起こしてしまう。
一昨日の話題は、特に盛り上がることがなかった。各々が好きな作家の名前を列挙し、当たり障りのない相槌を打つ。まぁ、そんな程度だろう。昨日、私たちは初めて会ったのだから。特に同じ趣味があるわけでなく、共通点が多いわけでもない。私たちを繋ぐものは、宇宙会、ただそれだけなのだから……
朝は必ず6時に起床、20分のランニングと30分の筋トレを行い、シャワーを浴びる。少しゆっくりとご飯を食べた後は、食後のコーヒーも欠かさない無欠のルーティン生活。会社ではある程度の地位にいるし、年収だって周りの同世代に比べると数百万は高い。妻もいるし、友人だって少なくない。金も地位も名誉も伴侶も、可能な限り努力をして手に入れてきたつもりだ。
俺はあいつらとは違う、戦わないやつらとは違う。
自分の未来は自分で決めるし、他人に口出しはさせない。
これが俺の信条だ。
マーキュリー

知らなかった。自由がこんなにも残酷だなんて。
できることならば大学生の僕に、教えてあげたい。
あなたが歩む道は、天国への理想郷なんかじゃなく、魑魅魍魎が蠢く修羅の道ですよ、と。そう思い起こして、やはり辞めようと思った。そうだった、突然未来から数年後の自分がやってきて「逃げろ。ここにいると殺されるぞ」と言われたとしても、僕は信じないし、逃げることはない。そういう人間だ。第一、そんなことを急に言われても、お先真っ暗な絶望をつきつけられても、未来が一層暗くなるだけだ。
子供の頃はこんなんじゃなかった。
物心ついた頃にはノートの切れ端に、パラパラ漫画を書いて遊んでいた。絵を描くことが好きだった。人と関わることなく、自分の頭の中がそのまま現実に浮き出ているようで楽しかった。描いている時は、絵のことしか考えなくてすむ。先生にいつ当てられるか、分からない問題だったらどうしよう、帰ったら宿題をしなくちゃ、テストの成績が良くなかったから怒られるだろうな。頭を空にして、絵に集中する。
僕は人の絵を描かなかった。描けなかった。
どんなに緻密で綺麗に描いたとしても、人間を満足のいくように描けた試しがない。髪の毛の先一本一本、産毛や網膜までいくら繊細に描こうが、やはりそれは単なる絵であり、生命でない。
生命力を表現できないことを知った僕は、代わりに空想の生き物のイラストを描くようになった。自分の思うイメージを、絵にかくことで一つ一つまとめていく。既に頭の中に完成図があるときもあるが、多くの場合思いつきで描く。なんとなくここに翼を足せばカッコ良いんじゃないか、いっそ足を無くして尾鰭をつけよう。目が2個じゃあ不自由だろうから、8個にしよう。そうやって出来た、側から見れば奇怪なキャラクターは、全て僕の引き出しにしまっている。いつかあのキャラクターたちが、世に放たれる日が来ればなんて妄想をしつつ日々を過ごしていた……
両親のような生活だけは送りたくない。
幼心に芯と呼べるものがあるとすれば、それだけだ。
父と母は隣村という距離で結ばれた。唯一の救いは、それが村文化特有のお見合いではなく、合コンという至って世間一般的な出会いからだったことくらいか。明朗快活な母に比べ、荘厳寡黙な父。息子の私からすると「なぜ結婚したのだろう」と疑問が絶えないが、保守的という考えが根底的に2人を繋いでいるのだと思う。彼らは、変えることを恐れ、変わることをしない。床屋や美容院は10年同じところに通っているし、朝はご飯に目玉焼きと味噌汁、寝る前は養命酒を欠かさない。会社の飲み会にだって滅多に参加しないし、自主的に「これがやりたい」と言うのを聞いたことがない。
信頼はしているが、尊敬はしていない。
私にとって彼らは反面教師だ。生物はいつの時代も、変わることで成長し、進化を遂げる。同じ生活を5年、10年続け、今となっては人口減少が著しいこの町に、果たして希望はあるのだろうか。いつか、この町を出て新しい世界にでたいと漠然とした夢は大学生になることで叶うこととなる。
大学3年生の冬。就活をスタートした。
高校での思惑通り、県外の大学に進学したこともあって、就活はとんとん拍子に進んだ。「御社を志望した理由は」「御社の理念のここに共感して」「私はこうゆう社会を実現したいです」満面の笑みで答えた一年前。
当時は人生の佳境だと思っていた就活が過ぎ、社会の酔も甘いも、苦いも辛いも様々なことを知った。知るというより察した。日本人だもの。敷かれたレールの上を、単に走る電車の様な生活の中、脱線に憧れた乗客は、突如降車を迫られ、現れた無数のレールに戸惑い、悩み、急停止した。本当は「何がしたいのか」「どうありたいのか」「どう生きたいのか」飲み会でふと上司から問われるこの難問に出くわす度、自己嫌悪に陥る。立派に明確に生きている人が羨ましい。いつ道を誤ったのだろう……
できない時は、無駄にしたいことを考えるが、いざ出来る時は中々一歩踏み出せない。前者はただの傍観者で、それでいる限り傷つくことはない。最初はそうだ、みんなそう。マイノリティじゃないから恥ずかしくない。ただ、社会人も3年目に差し掛かると、頭ひとつ抜ける人が出てくる。実態は分からないがなんとなくすごそうな団体で社会的意義がありそうなことをしている友人の話を聞くたび、何もしていない自分がみじめになる。このまま、1年、3年、10年経って寿命を終えるのか。
「僕が死ぬ時、泣いてくれるひとはいるのかな」と書き足すが、取り出した紙切れには既に「マーキュリー 『理想の人に会いにいく』」と書かれてあった。
ジュピター

気づくとそこには何もなかった。あると思っていたものがなく、なくても良いものが呪いのようにこびりついて離れない。
いつもそうだ。行動する前には十分考え、すべての意思決定は納得して行う。でもなぜか、毎回、思うようにいかない。それはたぶん「私の見立てが甘いから」ではなく、周りのせいだ。私は私ができる最大限を、精一杯やっている。知らないことはすぐ人に聞くし、理解できないことは夜通し考える。私は努力家だ。
幸せになれると思っていた。
何をするにも不器用で、なにをしても平均以下だった幼少期。今回のテストは簡単だったねと笑う友人の横で、見事平均以下の答案用紙を握ったり、学年が上がるにつれて普通は早くなるはずの50m走のタイムが微動だにしなかったり。私は普通に嫌われている。そう自覚した瞬間、悩んでいた霧が晴れるようだった。折り合いをつけた瞬間、普通なんて気にした方が負けと思う様になった。いや、そう思わないと生きていけなかった。前を向けなかった。
父は暴力的な人だった。
幼い頃の記憶は、部屋の隅っこで母がすすり泣いていることだけだ。大袈裟でなく、本当に。ただでさえない頭の容量の、数十分の一には、いつもこの記憶が刻まれている。腫れるまでこすった目と、枯れるまで泣いた声。身体中の水分が全て霧散してしまったような、ミイラに思える母が繕う不気味な笑顔。大人になった今も、頭にこびり着いて離れない。
物心つく頃には、私も殴られた。母と同じくらい。金の亡者で、女にはだらしなく、酒やギャンブルが大好きなクズ男の要素を余すことなく詰め込んだような父。
せめてもの救いは、私がそこそこ可愛かったということだろう。頭にも才能にも恵まれなかった私にあったのは、多くの人が羨む端正な顔だけだった。
「お前は顔だけはええんやから」
そう言って、殴らないでいてくれた顔。
タバコの跡も、打撲痕も、切り傷も顔だけには作らないでくれた。そのせいか、何度か知らないおじさんに身体を捧げるよう父にいわれ、それをこなした。学のない私にとって、お金を稼ぐ唯一の方法だった。ただ、いつしかそれは不思議と安心できるものだった。男とSEXをしている時。
それは父の拳と、母の顔を忘れさせてくれた。
私は私として、一人の人として求められていると思えるようになった。
私は女磨きに励んだ。
テストで良い点をとれるほどの知性はなく、クラスで秀でて運動ができるわけではない。一度聞いた音を声や楽器で再現できるわけでも、見たものを写真のように描くこともできない。平均以下の私は、平均以上の顔を使って、生きていくしかない。
一度で良いから特別になりたかった。
特別でありたかった。
高校卒業後、上京して歌舞伎町にあるキャバクラで働きはじめた。数万円稼ぐのに苦労した学生時代と比べると、数十万、時には数百万がポンポン飛び交う場所で、私は意外にも愛され、求められた。最初は、ぎこちなかったお酒作りやトークも、続ければ案外サマになった。枕営業は専売特許だ。そもそも行為に抵抗のない私は、他のどんなキャバ嬢よりも右肩上がりで売り上げを伸ばした。
私は特別になった。
お客の特別で、店の特別。
誰かの特別になりたかった。
優越感に浸りながら、メイク直しをしようとポーチに手を伸ばすと紙切れがあることに気づく。
「ジュピター 『嫌いな人に会うこと』」
何度見てもうんざりする課題に憤りを感じながら、丸めてカバンの中に仕舞い込んだ。
ヴィーナス

「何もなし」学生時代はそう呼ばれていた。
名前が梨だからだろう。
ただ、それを悲しいと思ったことはない。いじめられていたという自覚も、いじられていたという感覚もない。そんなのは単なる友達同士のじゃれ合い。そう。人間が猫にねこじゃらしを使うかのようなものだ。「あなたと仲良くしたい」の裏返し。私は笑顔で答える。
「はーい!なにー?」
今日こそはと決意し、私はプラネタリウム会場に向かう。
緊張しながら、チケット売り場に行くと、大学生くらいだろう男のスタッフに声をかけられた。
「どうぞー」
多くの場所がそうであるように、スタッフは流れ作業で仕事をしている。あるのは細やかな気配りなんかでなく、いかにスムーズに問題なく業務を遂行できるかだ。
「どちらのプログラムになさいますか?」
事前に調べていたものを伝えると、
「おひとり様で良かったでしょうか?」
と大きな声で問われた。
そう感じたのは私だけだったかもしれない。
なぜなら私は私が一人ということを気にしているから。
傷口に触れられると痛みを感じるのと同様に、誰しも敏感に感じる話題を持っている。世の中には、独身貴族なんて「孤独」をものともせず、逆に誇らしいと思う人種もいるようだが、私はその人種とは一生相入れることはないだろう。
「はい、1人です」
弱々しい声でそう伝えると、チケットを渡された。
「ヴィーナス 『偽らず、心の赴くまま行動すること』」
これが私に与えられた課題だ。
まるで頭の中を見透かされたかのようなドンピシャなお題に心を痛める。たぶん私は一度として「ありのまま」でいたことがない。「木南梨は中身無し」でもあるのだ。もちろん人である以上、昔から自分を偽っていたわけではない。幼い頃の薄い記憶では、確かに私は私だった。「木南梨は木南有だった。」と言っても良いだろう。ぎっしりと中身の詰まったゼリーのように、余す所なく私の脳みそには私がいた。それがいつしか周りに合わせ、私は私を失った。徐々に、段々と。
硬いことで有名なダイヤモンドも叩けば傷つき、同じ模様が出てくることで名の知れている金太郎飴もいつかは終わりがある。人間は脆い。ダイヤモンドよりも繊細で、金太郎飴よりも短命だ。思い当たる明確な事象は幾つかあるが、大災害レベルの壊滅的な事柄は幸か不幸か私には起きていない。震度2レベルの小さい衝撃が、生まれてから今まで何度も起こり、残酷なまでに無自覚に私は私を失った。「私は亡くなった」と言ってしまっても良いかもしれない。じわじわと血を流し、その間にも別の血が生み出される。細胞レベルで生まれ変わり、新しい私が産まれた。
ただ、それも私だ。
捉え方によってそれは「死」ではなく「変化」かもしれない。いや、きっとそうだ。そう捉えると言って幾分か希望が持てるから。
そんな身も蓋もないことを考えるうちに、プラネタリウムの上映が始まった。孤独を無視し、ずっと行ってみたかった場所に着いてしまうと、案外大したことはないと思う。それはまるでお風呂のように私の心に染み込んだ。
アース

いつからだろう。
得られる楽しみより、失う悲しさに固執したのは。新しい挑戦に胸躍らせるよりも、失敗した時の周知の羞恥しか考えることができなくなった。
おそらくそれはあの日からだ。
私には、人生で愛した人が一人しかいない。
人によっては、一人いること自体が尊く、その人と付き合い、結婚することができた時点で、人生の大半の幸せの量が満たされていると嫉妬するかもしれない。至極その通りだ。
香菜とは、いきつけの喫茶店で会った。
当時、27歳の出来事である。私は、転勤先の宮城から本社のある東京に戻っていた。昔から気に入っていた高円寺のカフェに彼女はいた。地元客がほとんどの、この喫茶店では珍しく若く、隅で小説を読む姿が妙に美しく見惚れた。若者が好きな口達者なマスターのアシストもあり、向こうも20代で若く見える私が珍しかったようで、話すや否や私たちは意気投合した。
イメージ通りの人だった。たおやかで知識があり、お上品。神々しくさえ見えた彼女は、おそらく美の女神アフロディーテの加護を受けているのかもしれない。ただ、美人短命とはよく言ったもので、彼女は5年前、50歳という若さでこの世を去った。
美とは時に人を狂わせる。
恋は盲目とはよく言ったものだ。
彼女には秘密があった。どこで出会ったかは知らない、それが誰であるかも分からない。彼女の葬式の前夜、一通の封筒には「私も彼女を愛していました。愛しいあなたに届きますように」とだけ書かれた手紙と1枚の写真が送られて来た。私の知らない場所と、私の知らない彼女の顔、当然ながら男も知らない顔だった。知っていたはずの、そばにいたはずの彼女が、物理的にも心理的にも遠ざかったような気がした。ただ、それで良かった。私は彼女が何人の男と寝ようが、愛そうが、私と彼女の物語をハッピーエンドで終わらせてくれたのだから。夫という立場で、そのフィナーレを迎えることができただけで幸せだ。
欲張らず、物分かりのいい夫でありたかった。
詮索するつもりは毛頭ない。相手がどこの誰でも良かった。大切で重要なのは、私が彼女を満足させるには不十分だったのではないかという、罪悪感にも似た気持ち。友人からは、思い詰めすぎだ、とか不倫されて怒るべきはずなのに、なぜ悲しんで思い詰めるんだと言われた。だが、そんなことはどうだっていい。私は彼女を愛していた。心の底から好きだった。後にも先にも初めてだ。会う度に心臓が鳴り、頭が冴え、瞳孔が開き、全身がこわばり、笑顔が引き攣るのは。後にも先にも彼女の前だけだ。見えないはずの愛が見えた気がした。
頭では十分わかっているはずなのに、心には届いていない。あれ以降、私は新しく挑戦をしなくなった。何かを得ると、それが大切であればあるほど、無くした時の悲しみが大きい。楽しいことが起きた瞬間、嬉しい気持ちよりも、次はどんな悲しいことが起きるだろうと考えるようになった。楽しいと悲しいは等価交換。人生でその総量はおそらく決まっている。妻との結婚で、その大半を使い果たした私の残りは、おそらく悲哀に満ちたものだろう。
目線を落とした机の上には、
「アース 『やっていなかったことに挑戦する』」と書かれた紙が置いてあった。
いただいたお捻りは一人暮らしの生活費に使わせていただきます(^^)泣笑 本当にありがとうございます! Kiitos paljon. Thank you. เพิ่ตั้งครับ. Teşekkürler ederim.
