
方言と大日向の昔の暮らし
大日向の幼馴染同士の菊池昭雄さんと菊池高明さんに方言手拭いを見ながら、大日向の方言と昔の暮らしについて教えていただきました。お話の一部を印象的だった方言を中心にご紹介します。
おしかけ
意味:ご飯を炊くこと
おざら・ほうとう・おつみこ
意味:うどん
昭雄さん「ここら辺の人は、開田作りで働いてたから忙しくって、『昭雄、おしかけだけやっとけよ。』ってよく言われた。」
高明さん「うどんのことっておざらだな。ほうとうともいった。平べったくして切って。あとおつみこっていうのもあって、ちょこん、ちょこん指でちぎってつまんでいれたからおつみこかな。それにお皿みてえにフライパンでお粉を焼いたのを、お皿焼きって言って食べたな。」
方言から話題は昔の食べ物に。
昭雄さん「なんせ、帰ってきたって、おやつなんてねえんだから。塩でおにぎりにぎるか、味噌つけるか、きゅうりに味噌付けて食べるか。ほとんどねえわ、店が。農協と菊池商店とちょっと売ってるぐらいのもんだから。」
高明さん「後は、たまに下からたまに豆腐屋が売りに来て赤い旗立っとくと止まってくれたよ。」
昭雄さん「あと納豆屋のおばちゃんが、すげえいい声で、『なっと、なっと~』って手拭でほっかぶりしてさ、自転車で売りに来てよくよく買ったよ」
水も現在は上下水道が通る地域だが、昔は一苦労だったそうだ。
昭雄さん「水は、甕なんだよ。だから、農協の前の井戸に1列に並ぶだよ。井戸は、自分ちにある家と無い家とがあっただよ。バケツに入れてな、何べん通ったかわからねえ。」
へっすい
意味:かまど
昭雄さん「風呂や、へっすいへ『ぼや、つっくべろ(木の枝をくべる)』って言われたりした。かまどなんてハイカラないい方しねえよ。へっすいでご飯作って、鍋は、囲炉裏があったから、鍵っ吊るしでやってただよ、天井真っ黒で、古い公民館にも、囲炉裏があって、鍵っ吊るしがあって使ってたよ。」
高明さん「おらち(自分の家)もそうだよ。それで俺が小せぇ時(子どもの時)、転んで囲炉裏に転びおって(転び落ちて)ばさっと灰かぶって真っ白になっちゃって。火傷したっつーわけで、芋を擦ってさ、火傷には、芋だつーことで、顔に芋をべたべた塗って、おやじがバイクで高見沢医院へ連れて行って、医者が芋を剥いでいったら、火傷はしてなかった、灰がついてただけだったって。それで、じいちゃんが、こんなの危ねえって言って、囲炉裏をよしちゃったんだよ。」
ほっかぶり
意味:頭をおおうこと
めた
意味:段々、いっぱい、たくさん
昭雄さん「結局、今みてえにガスがあった訳じゃねえ、何もねえ。炭と薪で煮炊きやって。冬になりゃあ、めた寒くなってきて、炬燵とかさ、全部暖房は、炭だから。部屋にストーブもなけりゃあ、何もない。後は、ほっかぶりしてあたったり、家ン中もマイナスだから、朝になりゃあ、寝てる布団の襟は、息で白くなったり、そこらにある雑巾は、カチカチに凍ってて、家ン中は、バリバリだ。」
高明さん:「それと、田んぼスケート場があってさ おらとうがPTAの役員のときは、夜10時頃集まって良い氷を作るためにマイナス10度以下で水撒いて、その後、焚火で、肉なんか焼いて1杯飲んだよ。」

のっこされる
意味:追い越されること
昭雄さん「そうそう、そん時は、下駄スケートだよな。おら、下駄だい。」高明さん「おらとは最初下駄やってて、すぐ靴になったから買ってもらった。靴だとよく滑れるだもの。のっこされるんだもの」
つっぺった
意味:足が泥にはまったり、車のタイヤが溝などにはまってしまうこと。
高明さん「リヤカーで荷物を運んでたな。リヤカーの後ろに棒を差しとくと、それが、地面に引っかかって、ブレーキにしてたよ。」
昭雄さん「当時(1960年代ごろ)は、三輪車のミゼット、オート3輪の車がでてきただよ。荷台に乗せてもらったことがあるんだけど、前は1輪で後ろは2輪だから、曲がりカーブでバランスが悪くて、ひっくり返ったり、砂利道のくぼみにつっぺって出れなくなったりしてみんなで押したりしたよ。おっかねえやな。」
おふたりにとって子どもの頃の大日向は不便なところではなかった。
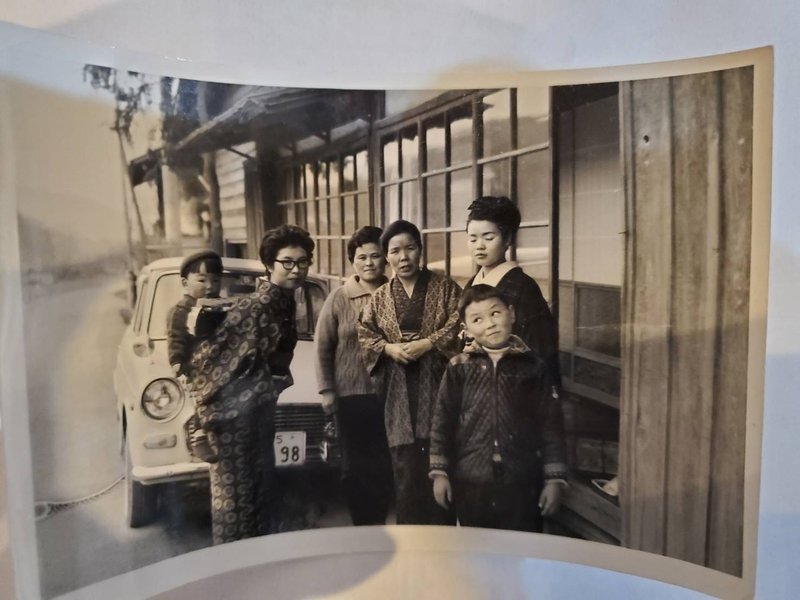
昭雄さん「商店があって、役場があって、農協があって、駐在所があって、郵便局があって、桶屋さんがあって、全部並んでた。」
高明さん「今は、無くなっちゃったな。」
昭雄さん「役場の裏には、保健所があって、頭が痛えっていえば、そこいってな。なんか、練り歯磨きみてえのほらこれっぬれってくるくる巻いてな、そんな適当なあれだったわ。」
高明さんその後、ソウシン電機がここに来て、おらちのお袋もそこで働いてたよ。弱電やってたな。かなり長くやってたよ。小学校の帰りに良くそこへ寄リ道して家に帰ったな。」
昭雄さん「昔は、人口が多くて盛んだっただよ。まさかこんなになるとは、思わなかったけどな。減る一方だよな。」
人口が減って世代も後に続く人がいないことが話題になりました。
お話を伺っていると方言と共に思い出される時代、家族の名前、友人、近所の方たちの顔が蘇えり和やかな空気感になりました。
『方言』は、人の中に生き、人を通して紡ぎ、その土地その土地に残る言葉のふるさとなのだなと気づかされました。
今回話題に上がったその他の方言
ももっけー
意味:くすぐったいこと
しゃらっ~せえ
意味:とても~だ。強調するときに使う。
例:*しゃらっ臭え、しゃらっ危ねえ、しゃらっうるせえ、しゃらっやかましい
らざ・ざ
意味:語尾につけて提案する
例:帰らざ(帰りましょう)、行かざ(行きましょう)
えべや
意味:行きましょう
おつくべ
意味:正座
お手しょう
意味:手のひら
げびてる
意味:卑猥な ケチくさい
おぼさん
意味:ひざこぞう
ちゅっくれん
意味:いいかげん
とんます
意味:かき混ぜる
しんの
意味:疲れた
しこっちょにゃいかねえ
意味:手ごわくてうまくいかない
ぶちゃる
意味:捨てる
とびっくら
意味:かけっこ
つびてえ
意味:冷たい
ひてぐち
意味:おでこ
らっちむねー
意味:つまらない、価値がない
しこってしたもんだ
意味:困ったものだ
文 大波多志保
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
