読みかけのディケンズ
読みかけのディケンズ
お姉さんの名前は「サオリ」という。漢字はわからない。名前を聞いた時、「サオリ」と呼んでね、と言われたけれど、何だか僕は恥ずかしくて、やっぱり最後まで「お姉さん」としか呼べなかった。
いつもお姉さんとは公園で会った。お姉さんはいつも本を読んでいる。そして時々、缶コーヒーを飲む。大事そうに、ゆっくりゆっくり。初めて会った時も、お姉さんは本を読んでいた。その時、僕は友達とサッカーをしていた。僕が蹴ったボールがお姉さんの前に飛んでいった時、お姉さんは軽やかに片手でそれを受け止めた。へえっと僕は思い、ボールを受け取ると、「すごいですね」と声をかけた。お姉さんは涼しい顔をして、「そうでもないさ、少年」と、やはり軽やかに答えた。
それから公園で友達と遊ぶ時に、ちょくちょくお姉さんを見かけるようになった。僕はサッカーやら鬼ごっこやらどろけいやらをやっていたけれど、横目でちらちらと眺めては、パスミスをしたり、壁にぶつかったりしていた。お姉さんとは時々目が合った。シュートを決めた時は、僕に向かってピースサインもしてくれた。
その公園でサッカーが禁止になって、僕たちは別の公園を使うようになった。でも、僕はいろいろ言い訳しては友達と放課後別れて、お姉さんのいる公園を訪れるようになった。いる時もあればいない時もあった。どうやら水曜日にお姉さんはいるようだった。初め僕は、無意味にブランコを漕いだり、鉄棒で逆上がりをしたり、ただ歩き回ったりしていたけれど、お姉さんが「どうした少年」と話しかけてくれて、ようやく隣に座ることができた。
お姉さんは近所の中学校に通っていた。
「小学校のうちに、よく遊んでおいた方がいいよ」
そうお姉さんは言った。来年は受験なのだそうだ。「でも、こうやって公園で君たちみたいな小学生を眺めるのは、楽しいよ」
お姉さんは必ず本を持ってきていた。僕は遠慮してあまり聞かなかったけど、一度だけ何を読んでいるか訊ねると、表紙を見せてくれた。
「ディケンズ」
「ディッケンズ」
お姉さんは穏やかに訂正した。どんな話かと聞くと、「愚かな人間たちが描かれている」という答えが返ってきた。僕はその頃、人間を愚かかそうでないかというものさしで考えたことがなかったので、お姉さんの言葉は新鮮だった。
見るたびに違う缶コーヒーをお姉さんは飲んでいた。僕はもちろん、コーヒーなど飲んだことなどなかったので、どんな味がするのか知らず、「どんな味がするんですか」と素直に訊いてみた。お姉さんはにっと笑い、「飲んでみる?」と、自分の飲みかけを差し出した。僕がどぎまぎしていると、「本気にするな少年」と、また笑った。僕がむっとした顔をして見せると、ごめんごめんと言って公園横の自販機で、缶コーヒーを一本買ってくれた。飲んでみると、やたらと甘ったるかった。
そのうち僕は、宿題も見てもらうようになった。お姉さんは算数が得意だった。「数学ね」と言って、池の周りを走るA君の速さとか、水の中の塩の濃さを一緒に考えてくれた。
「私も小学校の頃は苦手だったんだよ」
お姉さんはそう言った。「でも、今の中学の佐藤先生って言う数学の先生の教え方が上手なんだ。ちょっと癖はあるけど」
そして、地面に数式を書いた。「黄金比って聞いたことある? ピラミッドとかダヴィンチとか。その性質は中学の数学で解くことができるんだよ」
今ならそれはただの二次方程式だということがわかるし、その説明もあまり正確ではなかったのだけれど、当時の僕は魔法の言葉のように思えた。
「お姉さんの学校に行ってみたいな」
僕がそう言うと、お姉さんは、「もっといい学校はたくさんあるよ、少年」と、頭をぽんと叩かれた。
最後にお姉さんを見たのは、中学校の部活見学だった。サッカー部でシュート体験をさせてもらったり、柔道部で背負い投げを見せてもらったり、僕はそこそこ楽しませてもらいながら、お姉さんがどこかにいないかと、きょろきょろしていたが、なかなかその姿を見ることはできなかった。
「サオリ!」
時間が来て、もう帰ろうとした頃だった。下駄箱で、声が聞こえた。振り向くと、お姉さんがいた。何人かの同級生に囲まれている。
「あれ、あれやってよ、サトセン」
お姉さんを囲む一人が言った。お姉さんは恥ずかしそうに笑った後、「オッケー諸君」と大きな声をあげた。どうやら、誰か先生のモノマネらしい。お姉さんは顔を歪め、やたらと低い声で、数学らしい問題を叫んだ。ぎゃははと、笑い声が起こった。「諸君オールライッ?」やべえよサオリ、と誰かが言った。お姉さんは笑っていた。僕は立ち止まり、しばらくその様子を眺めていた。お姉さんと目が合った。お姉さんは目をそらした。とても、とても上手なそらし方だった。
次の水曜日、お姉さんは公園に来なかった。代わりに、いつものベンチに本が置いてあった。ディケンズ。ぱらぱらめくると、しおりのように手紙が挟まっていた。手紙は長かった。僕は半分まで読むと、本に手紙を挟み、またベンチに戻した。自分の口元が歪むのがわかった。この前、ちょっと古い小説を読んだら、「微苦笑」という言葉が出てきて、なるほど、と思った。
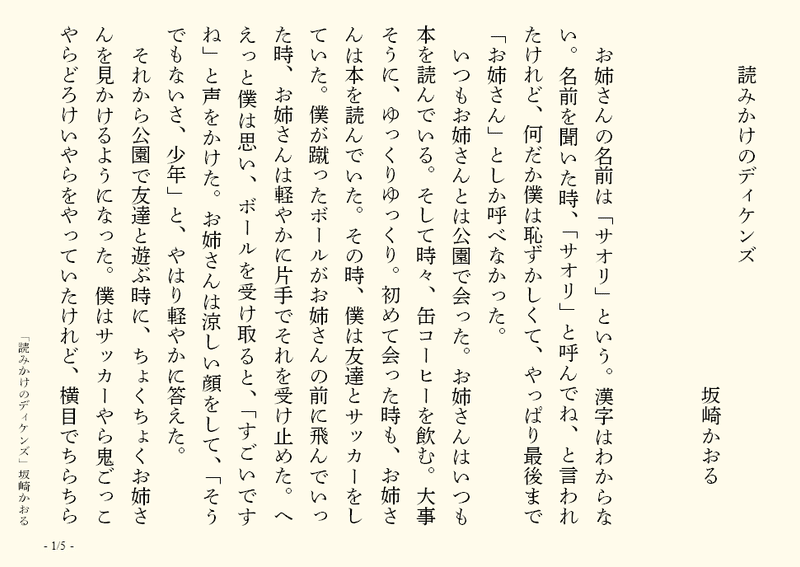
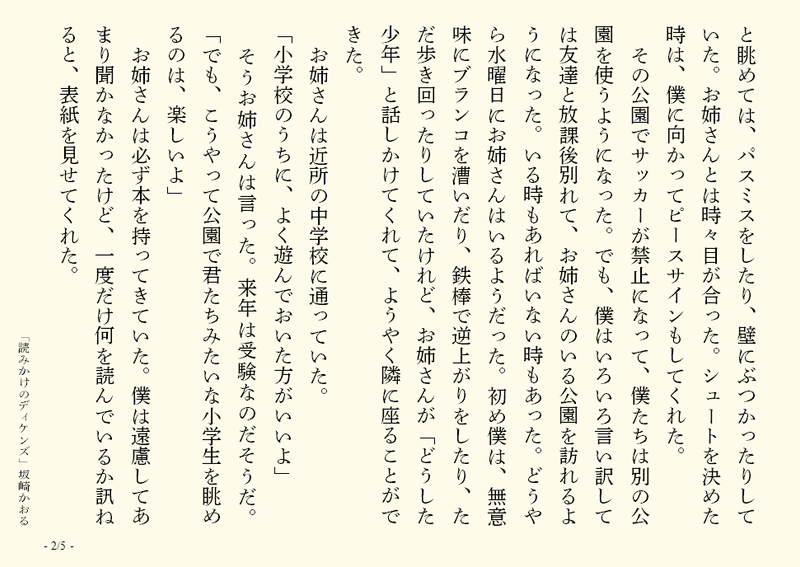
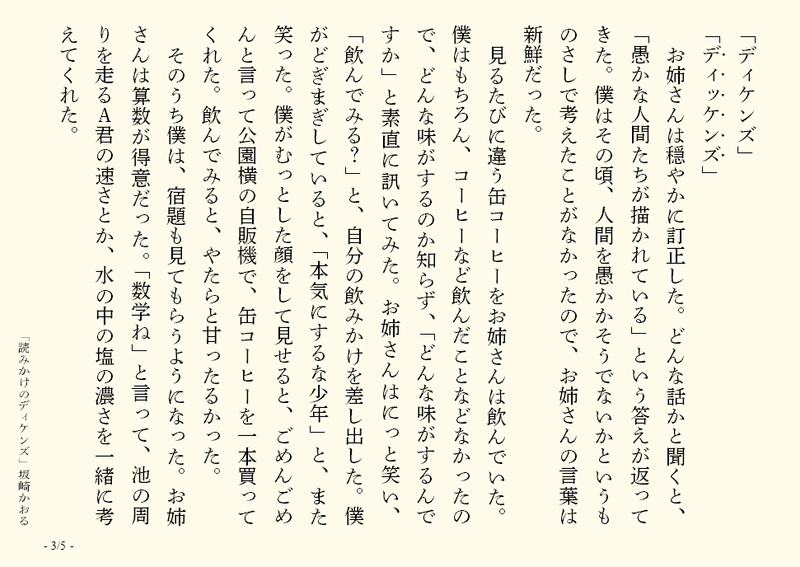
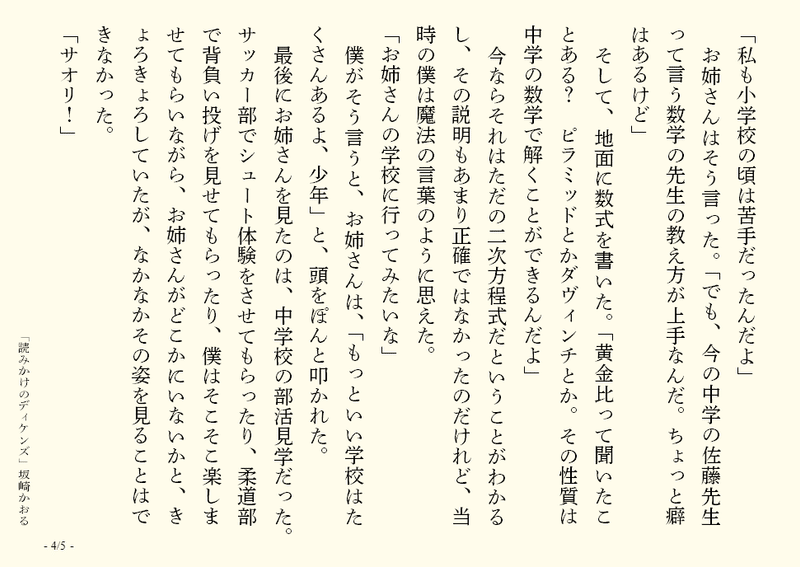
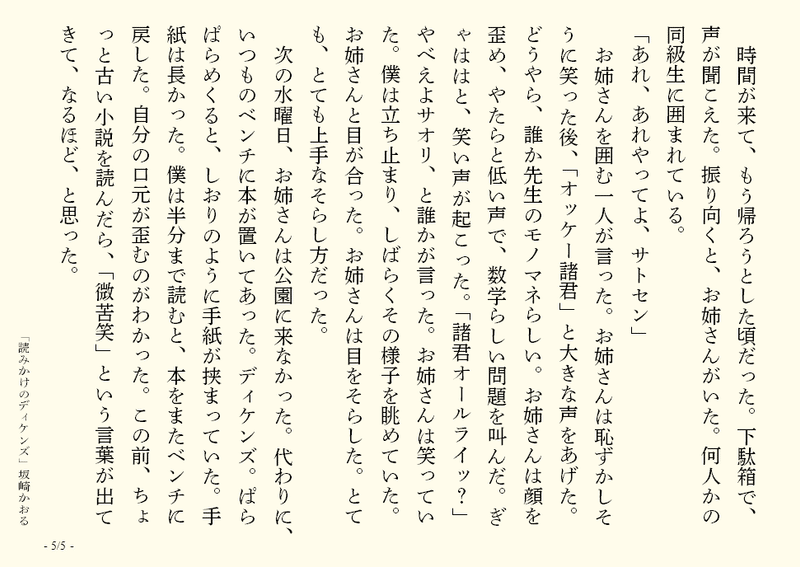
【作者解題(という言い訳)】
横書きは最後の手紙を戻すシーンを書き換えました。縦書きは六枚道場で作っていただいたものをそのままにしています。
正直、下記の佐藤相平さんの読みが、
作者の表層の意図に近いので、そちらを読んでもらえればと思います。要するに黒歴史小説です。思い当たることはありませんか?私はあります。あと、Takemanさんの「残酷」という印象も、意図したかった部分であるので、ありがたかったです。
語り手を一人称にするかどうするか、というのは永遠の課題だと思いますが、私は一人称で書く時はその「語り」があまり信用できないというスタンスで書いています。お姉さんは「軽やかに」ボールを受け止めたわけですが、たぶんたまたまそうなった(見えた)だけで、一番びっくりしていたのは「お姉さん」でしょう。
私は「語り手」が何にせよ、どこに立っているのかを拘るタイプで、物語の「僕」は小学校六年生ですが、実際に語っている現在位置は「お姉さん」より一個上の中三ぐらいをイメージしていました。中二病まっさかりです。
「僕」は、出会った頃の「お姉さん」よりも年上になることで、彼女の存在を少々批判的に(もしくは皮肉的に)眺めています。最後の一文はかなり苦労して、あんまり満足はしていないんですが、「微苦笑」は久米正雄の何かを読んだのだということにしています。国語の教師が、雑談の折に「微苦笑」に触れ、「久米正雄が発明したのか、読んでみるか」と「僕」は読んでみたわけです。
久米正雄にしたのは、念頭に、有名な「私小説と心境小説」の一文「『戦争と平和』も『罪と罰』も『ポヴアリイ夫人』も高級は高級だが要するに偉大な通俗小説だ」をおいていて、久米がディケンズを読んでいたかわかりませんが、ディケンズなんてまさにそんな感じじゃないかな(純文学と大衆文学の間にあるような)と思い、採用してみました(高級と通俗が、お姉さんと「僕」の対比)。ディケンズ、ちょっと背伸びをしてみたい中学生ぐらいに読みやすいのではないかと感じるのですが、どうでしょう。
結局「僕」自身も、現時点では「お姉さん」を客観的に見れている、と思っているわけですが、背伸びして久米正雄なんか読んでわかったふりをしているあたり、それは「背伸び」に過ぎないのです。ちなみに、お姉さんは『大いなる遺産』あたりを読んで、挫折しかけていたことにしています。
