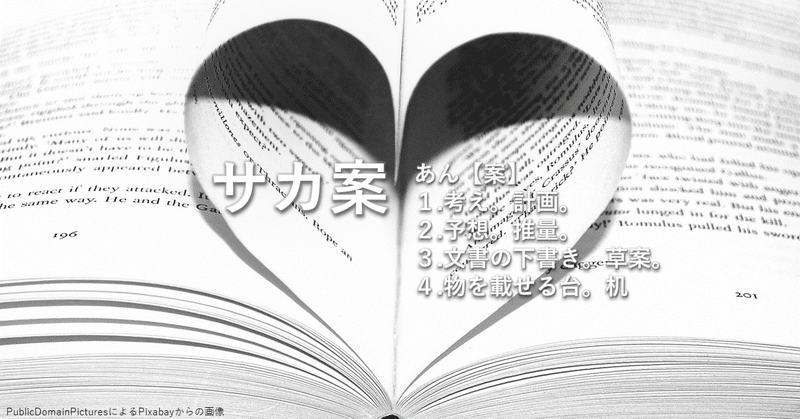
秋春制への移行は愚策:競技レベルは強化ではなく育成で決定する
改めて秋春制には反対
Jリーグのシーズン移行について年内を目処に移行可否の結論を出すとのことなので、議論の声が騒がしくなってきた。
以前、秋春制移行に反対する記事を書いたが、今回改めて秋春制反対の意見を書きたいと思う。
シーズン制移行の主な課題
シーズン移行に対して考えられる課題は主に以下の5つだと思う。
1.降雪地域への対応
2.夏場の試合の回避
3.欧州・ACLとのスケジュールギャップの是正
4.学校教育とのスケジュールギャップの是正
5.国内スケジュールの調整
1.降雪地域への対応
【課題解決難易度 8/10】
コストを掛けることで解決できることと、経済的なことだけでは解決できない問題とに大きく分かれると思うので、完全な課題解決は難しいと思う。
それでもハッキリしていることは秋春制に移行すれば問題が重篤化し、現状の春秋制の方がまだ軽傷の状態で小康状態を維持できるということ。
2.夏場の試合の回避
【課題解決難易度 1/10】
7、8月の試合数を0にすればいいだけなので、極めて簡単に実現可能な課題だと思う。ウィンターブレイクをサマーブレイクに置き換えれば良いだけなので、秋春制移行の理由としては極めて脆弱な理屈だとしか思えない。
3.欧州・ACLとのスケジュールギャップの是正
【課題解決難易度 5/10】
スケジュールギャップがあることがハンデと考えるかどうかで意見が分かれると思う。ここでの課題は主に欧州移籍に関するものになると思うが、個人的にはハンデではないと考える。
理由は南米各国のリーグスケジュールは日本と同時期に行われているが欧州移籍への弊害があるようには感じないからだ。
現状日本人選手への信頼が南米よりも低いために低額の移籍金になっているだけで、今後欧州で実績を残す日本人選手が増加すれば、自然と移籍金は高騰化していくと思う。
個人的な提案としては、移籍金が低額なのは日本人選手に付加価値が付いていないからだと思う。
夏と冬で2回の移籍期間がある。
選手としては欧州開幕に合わせて夏移籍を希望するが、Jリーグのチームはそれではシーズン途中に戦力の低下を招いてしまうというジレンマがある。
なのであれば、Jリーグのみで適用されるローカルルールとして、日本人選手の欧州移籍は冬移籍の年1回しかできないことにすれば良いのではないのだろうか?
年1回しか獲得のタイミングがないのであれば、欧州クラブとしては厳しい判断が求められる。中小クラブの場合1年後の成長によってマネーゲームに参加できない可能性もあるため、より厳格な選手調査が行われることになり、Jリーグのクラブが強気な移籍金設定をしても飲まざるを得ないような付加価値が生まれると思う。
さらに国際ルールを配慮するのであれば、夏移籍に関して移籍契約はできるが身柄の移送はできないことにする。
つまりJリーグの選手に関しては、夏移籍の契約についてはシーズン終了まで現所属クラブにレンタル移籍で残ることを絶対条件として飲まなければいけないことにする。
そうすればシーズン途中での戦力低下は防ぐことが出来る。
シーズン終了までレンタルで残る移籍は、最近は南米から欧州に移籍する選手の移籍パターンになりつつあるので日本でも実現可能だと思う。
どちらにしろ、欧州とのスケジュールギャップはギャップがあるからこそ、上手く活用すれば日本人選手の付加価値の創出が可能なチャンスだと捉えるべきだと思う。
4.学校教育とのスケジュールギャップの是正
【課題解決難易度 10/10】
日本の教育制度は4月に始まり3月に終わるので、どうやっても秋春制とは噛み合わない。調整することで可能になることもあるだろうが、現状で問題のない状況を調整のために改めて労力を割くことは無駄だとしか思えない。
もちろん夏場の部活動に対する対策はしなければならないだろうが、秋春制移行という方法が推進力もしくは抑止力になるというのは考え方として無理があると思う。
5.国内スケジュールの調整
【課題解決難易度 5/10】
シーズン移行する・しないに関わらず、夏場や冬場に試合を行わずブレイク期間を設けるのであれば、活動スケジュールがタイトになることは避けることが出来ない課題だと思う。
そして、この課題解決の方法は以下の2択しかないと思う。
「リーグのチーム数を減らす」
「ルヴァンカップを廃止する」
個人的には国内に3つもコンペティションがある必要はないと思うので、ルヴァンカップは廃止して、リザーブリーグの充実を図る方向に動いた方が良いと思っている。
視界不良なシーズン移行のメリット
以上、課題について書いてきたが、どう考えても秋春制に移行するメリットがあると思えない。
秋春制移行によって得られるメリットは主にトップリーグであるJリーグのクラブだけであり、それ以外のサッカー環境にある人にとって享受できるメリットが感じられない。
どんなスポーツにも普及・育成・強化の3局面があって、強化のためだけの改革が普及・育成の面に良い波及効果を及ばせるとは限らない。
今回の場合であればJリーグの方針に擦り合わせるための調整に膨大な労力が必要となるが、そこまでして変化することで得られるメリットがそれほどあると思えない。
オリンピック競技における日本の実績
確かにJリーグが出来たことで日本サッカーの競技レベルは向上したと思う。
では、なぜ競技レベルが向上したのか?
トップカテゴリーの選手が日常的に競争力の中に身を置くようになったから?
競技環境が改善されてプロ意識を高く持つようになったから?
断じて違う。
日本の過去のオリンピックにおける競技別メダル獲得数は以下の通り。
1位 体操 :98個(31個、33個、34個)
2位 柔道 :84個(39個、19個、26個)
3位 競泳 :80個(22個、26個、32個)
4位 レスリング:69個(32個、20個、17個)
5位 陸上競技 :25個(7個、9個、9個)
6位 ウエイトリフティング:14個(2個、3個、9個)
7位 アーティスティックスイミング:14個(0個、4個、10個)
8位 バレーボール:9個(3個、3個、3個)
9位 射撃:6個(1個、2個、3個)
10位 ボクシング:5個(2個、0個、3個)
1-4位の体操・柔道・競泳・レスリングの4競技がぶっちぎりでメダル獲得数が多いのが分かる。
では、なぜこの4競技がこれほどメダルを獲得できるのか?
答えは、選手育成が民間で行われているからだと思う。
学校体育の延長の部活動で育った選手ではなく、そもそも就学前の幼い頃から民間で競技を始めている選手が多い競技だからだ。
2020年と少し古いデータになるが競技人口は以下の通り
体操 3.1万人
柔道 14.3万人
競泳 12.8万人
レスリング 0.9万人
陸上競技 42.5万人
バレーボール 41.8万人
射撃 0.7万人
ボクシング 0.3万人
※ウエイトリフティングとアーティスティックスイミングは不明
中央競技団体現況調査 2020年度調査報告書
柔道・競泳はそれなりに競技人口がいるが、必ずしも競技人口と競技レベルが一致している訳ではない。ちなみにサッカーは91.9万人で国内最大。
競技レベルの本質
トップ選手の競技環境・待遇などで言えばサッカーや野球の方が恵まれているが、国際競争力の高い選手を輩出する力で言うと、まだまだ体操・柔道・競泳・レスリングの4競技に追いついているとは言えないのではないだろうか。
日本サッカーの競技力が向上したのは、Jリーグのクラブが必ず下部組織を保持しなければならないというルールを作り、選手育成が民間に委託されるようになったからだ。
つまり1993年にJリーグが出来て、やっと体操・柔道・競泳・レスリングと同じレベルで選手育成を行う土壌が整ったのだ。
そこから30年かけて国際競争力がある選手が出現してきたが、では五輪で金メダルを獲得するレベルの選手が日本サッカーからどのくらい排出されているのだろうか?
結論
どんな競技であっても、競技レベルはトップレベルの強化ではなくて育成で決定している。
サッカーより恵まれない環境で世界一の選手を輩出し続けている競技がこの国にはある。
Jリーグの改革は日本サッカーの競技力向上のために行うのではないのか?
秋春制によって育成レベルで得られるメリットが果たしてどれだけあるのだろうか?
第一に育成に軸足を置いて日本サッカーの未来を考えることがJFAとJリーグがやるべきことだと思う。
ハッキリ言って、秋春制への移行は愚策中の愚策だと思う。
(文中敬称略)
サッカーに対して個人的に思うことを発信していきます。サポートしていただけると励みになります。
