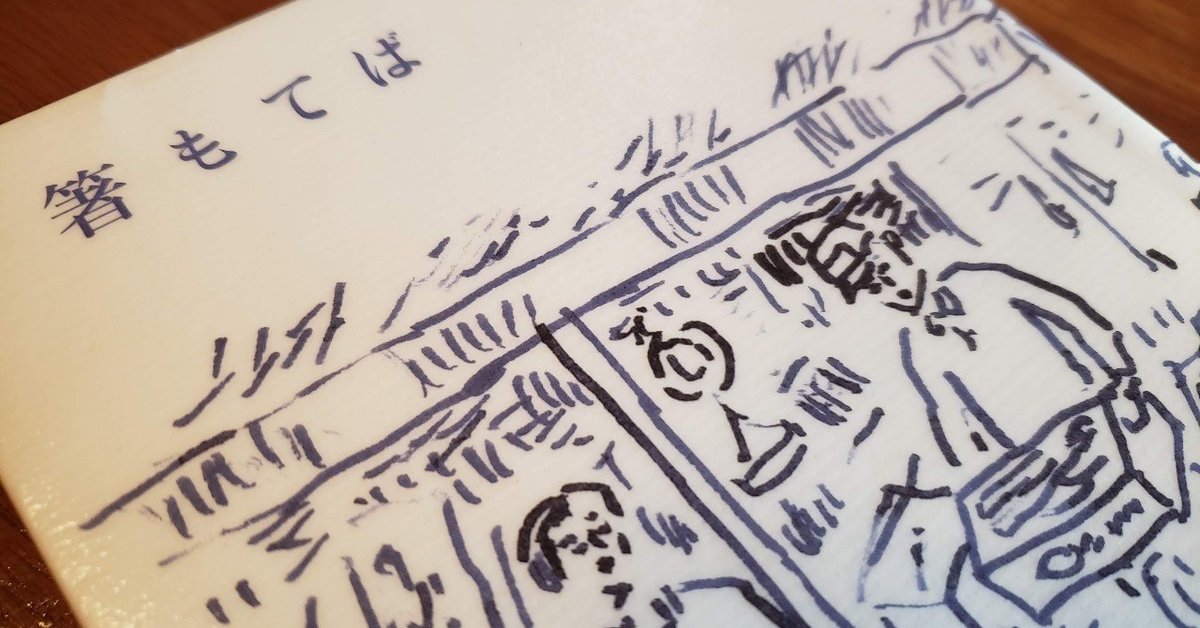
残りつづける食の記憶:石田千『箸もてば』
初めて石田千の文章に触れたとき、私は身も心もボロボロだった。人の世話にばかり追われ、自分の寝食さえも満足にコントロールできない状況で、自分自身をいたわる精神的な余裕もなかった。ただそれでも希望を見つけたくて、貪るように本だけは読んでいた。そんな時期だった。
あの時読んだ本が何だったのかどうしても思い出せないが(最近いつもそうだ)、表紙を開いて最初のエッセイを読んだときに「風が吹いた」と感じたことだけはしっかりと覚えている。
爽やかな風と日差しがたくさん入り、時折カーテンがふらりと揺れる。カウンター付きのキッチンで自然な色のテーブルと壁紙。無駄なもののないシンプルな部屋。窓からは海が見えて、山も近い。この人が住んでいるのはきっとそんなところ。雑踏なんか一切ない、きっと最高に素敵なところに違いない。部屋や街の描写なんてほとんどないのに「見えた」ような気がして、というかそう感じさせる軽やかで爽やかな文体が、忘れられないくらいに衝撃的だった。
今回読んだ本も、その時と同じ食のエッセイだ。
人は食べないと生きていけなくて、生きるためには食べるしかない。私の心は、なぜか喜びよりも悲しみの記憶ばかりストックしてしまうように出来ている。だから「食べると思い出す楽しい思い出」みたいなものがほとんどなくて、見たり食べたりすると暗い気持ちになる食べ物はあるのにその逆がないことが残念でならない。
なんて書いていると我ながら寂しい気持ちになってきてしまうけれど、このエッセイは明るい食の記憶であふれている。親の味、子供の頃の思い出、大切な人と食べた味。誰にだって、箸をもてば思い出すことがたくさんあるだろう。心と体が覚えている味の記憶と今を、あふれるほどに詰め込んだ一冊だ。もはや嫉妬すらしないほどに豊かで、読んでいるだけで満たされてしまった。
