
「ボーナンザ」の感想
以下の文章は全て個人的な見解です。権利者の方々による指摘や、個人的な気付きによって、予告なく変更・削除する可能性があります。
また、視界が狭い人間なので、色々とご指摘いただければ幸いです。
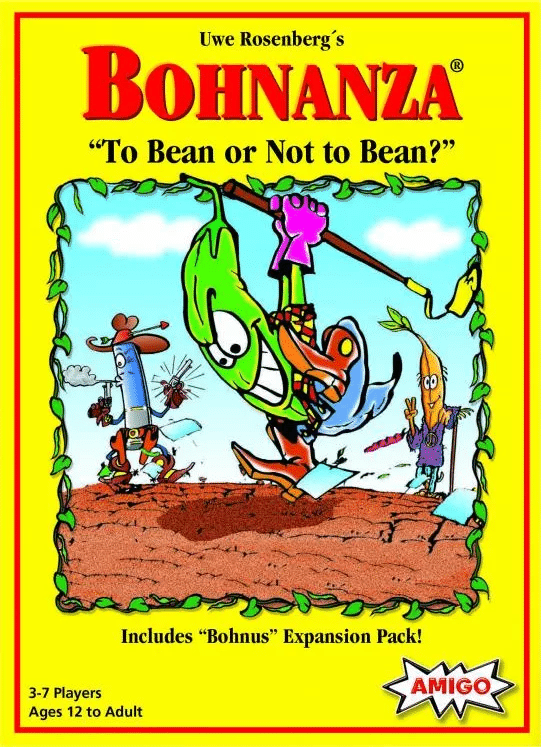
◆0.前提
・基本セットのみ。
◆1.概要
・ゲームの流れ
自分の前に畑があり、そこに豆を植え、育てることで資金を獲得し、その資金が最も高いプレイヤーが勝利するゲームだ。
まず、前提として、このゲームでは、手札の並び替えをすることができない。手札の役割は選択肢ではなく、キューであると言える。
各カードには、豆の絵が書かれており、それがデッキに何枚入っているか(6~20の範囲の偶数になっている)の数字と、何枚重ねることで何金になるのか、という換算レートが書かれている。枚数を重ねるほど、効率が良くなっていく。
各プレイヤーは自分の出番が来ると、手札の一番左のカードを出す(つまり、キューから取り出す)。これは強制で、次のカードも続けて出しても良い。これはオプションだ。
次に、山札からカードを2枚めくり、そのカードを処理しなければならない。誰かに交渉して与える(押し付ける)か、それができなければ自身が植える必要がある。最後にカードを引く(キューに補填する)。
これを繰り返していき、山札が3枚なくなったら、ゲーム終了となる。
各プレイヤーには最初、2つの畑が用意されており、そこに豆を植えていく。1つの畑には、1種類の豆しか植えられないので、最大で2種類までしか植えることができない。それ以外の豆を植える必要がある場合、2枚以上重ねている畑があればそこの、そうでなければ、どちらかの豆を刈って(お金に変換して)植えなければならない。
また、交渉の自由度は非常に高く、手番プレイヤーと様々なレートで自身の豆や、手番プレイヤーの豆と交換することができる。
◆2.考察
・手札という表現方法
このゲームの最大の特徴の1つとして良く挙げられるのが、入れ替えてはいけない手札だ。
上述したように、このルールによって、手札が表現するものは、他のゲームとは大きく異なるようになっている。つまり、一般的なゲームでは選択肢であるものが、キューとなっているのだ。
ただ、先入れ先出しと言ったような概念を説明することなく、手札を入れ替えてはいけない、というルールと、端から使用していき、逆の端に補充するということを伝えれば、それを実装することができる。
手札という概念は、各ゲームで使用されているものだから、カジュアルプレイヤーでも受け入れやすい。このように、表現は汎用的なものと同じものでも、いくつかのルールを導入することによって、異なる概念を導入することができるを示している。
ただし、つい、癖で手札を混ぜてしまう(TCGでは、そのターンに引いたカードをわからなくさせるために、手札をシャッフルすることがある)など、良くある概念を使っているがゆえの欠点もあることに留意すべきだ。
・交渉の自由度
交渉の自由度がかなり高く、本質的にはここで勝負が決まることが多いと考えられる(特に経験者が少ない場合)。
しかし、それゆえに、ある程度ゲームの展開を操作することができ、経験者と初心者が同居しやすいゲームになっているとも言える。交渉の過程で情報が共有されることから、助言のようなこともしやすい。
勝敗を決するゲームとして考えた場合、ここまでの交渉の自由度は間違いなく問題なのだが、一方で、このゲームが人気な理由の1つでもあると感じられる。結局、どのようなゲームにしたいのかを考えて、設計する必要があるのだろう。
・カードという表現媒体
各カードには豆が記載されており、表には必要な情報が書いてあるのだが、裏にはお金のマークが書いてある。そして、豆を育てて、お金に換算する際には、その育てた豆からお金に等しい値の枚数のカードを取り、裏面にして、手元に置くのだ。このルールは多くの作用をもたらしている。
第一に、単純にコンポーネントが圧縮されている。チップのようなものを用意するのではなく、カードだけで表現出来、しかも、別のカードを用意する必要もないので、枚数の圧縮も出来ている。
第二に、カードの価値が変容していく。どういうことかというと、換算された豆は、その分のカードがゲームから取り除かれた状態になるのだ。結果として、その価値が下がっていく。特に顕著なのは、6枚しかない豆(通称6豆)だ。この換金レートは、2枚で2金、3枚で3金という破格なものなのだが、2枚+3枚という組み合わせで換金された場合、1枚だけ6豆が残ってしまう。そうなると、完全に邪魔なカードになり果ててしまう。そういう変化を起こすことができている。
このように、1つのルールにしても、様々な方向に対して、有用な効果をもたらすことができる。
・育てる豆の種類と畑
このようなルールによって、結果として生まれるのは、住み分けであり、競りであり、チキンレースでもある。
誰も育てていない豆を育てることによって、交渉が有利になったりする一方で、伸ばしていきたいがために柔軟性が失われたり、後から他のプレイヤーに参入されたり、と言ったことが起こる。お互いに同じ豆を伸ばしていき、どこで降りるのか、というやり取りも発生しうる。
これらは、畑の数(=育てられる豆の種類)の制限と、重ねた方が有利になる換算レート、自由な交渉と強制的なキューの排出、と言ったような要素から引きずり出されるゲームの展開だ。
しかし、このゲームには、畑を増やせるというルールが存在する。
お金(=勝利点)を消費することで、3枚目の畑が買えるのだ。
これは、強い制限からの解放が感じられる要素ではあるものの、一方で、最初に3枚目の畑を買った人はマークされやすく、交渉が不利になりやすいためタイミングが難しいことや、制限によって生まれる面白いゲームプレイが生じにくくなるという作用があるようにも感じる。
交渉という心理的な側面が重要になり得る要素がゲームの主体になっているゲームで、明確な拡大再生産要素を入れることには、少し慎重になった方が良いのではないか、と感じる。軽んじられても、その要素を獲得したプレイヤーが一気に有利になるし、重んじられても、その要素を獲得したプレイヤーがゲームのコアである交渉にあまり関われないという状態になる可能性があるためだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
