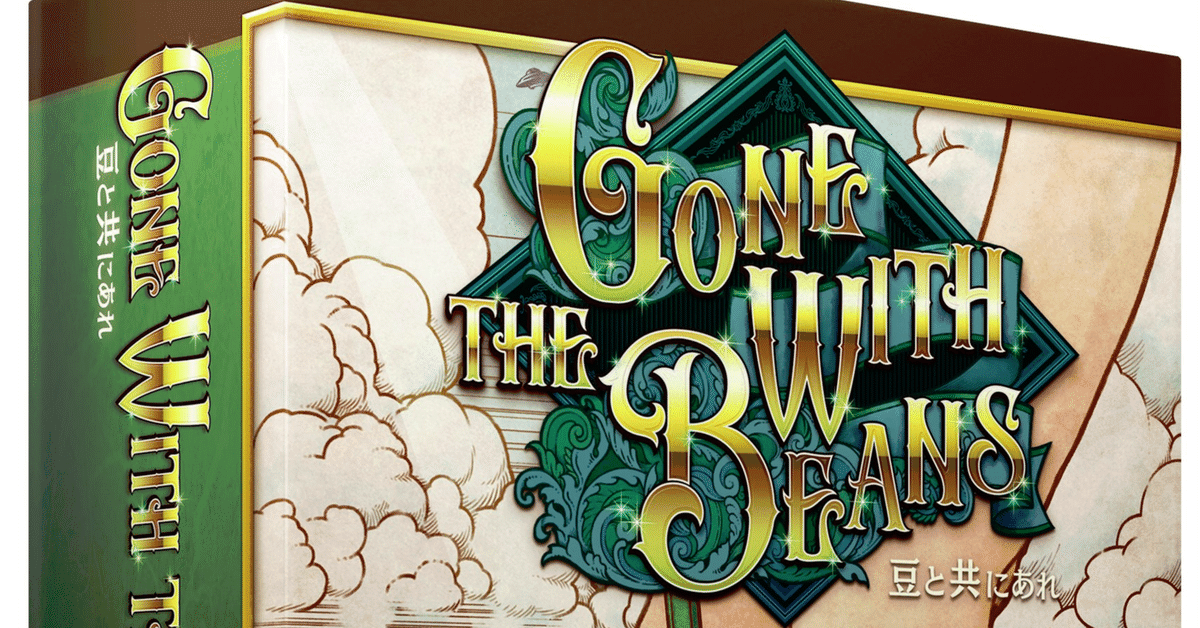
「豆と共にあれ」の感想
以下の文章は全て個人的な見解です。権利者の方々による指摘や、個人的な気付きによって、予告なく変更・削除する可能性があります。
また、視界が狭い人間なので、色々とご指摘いただければ幸いです。
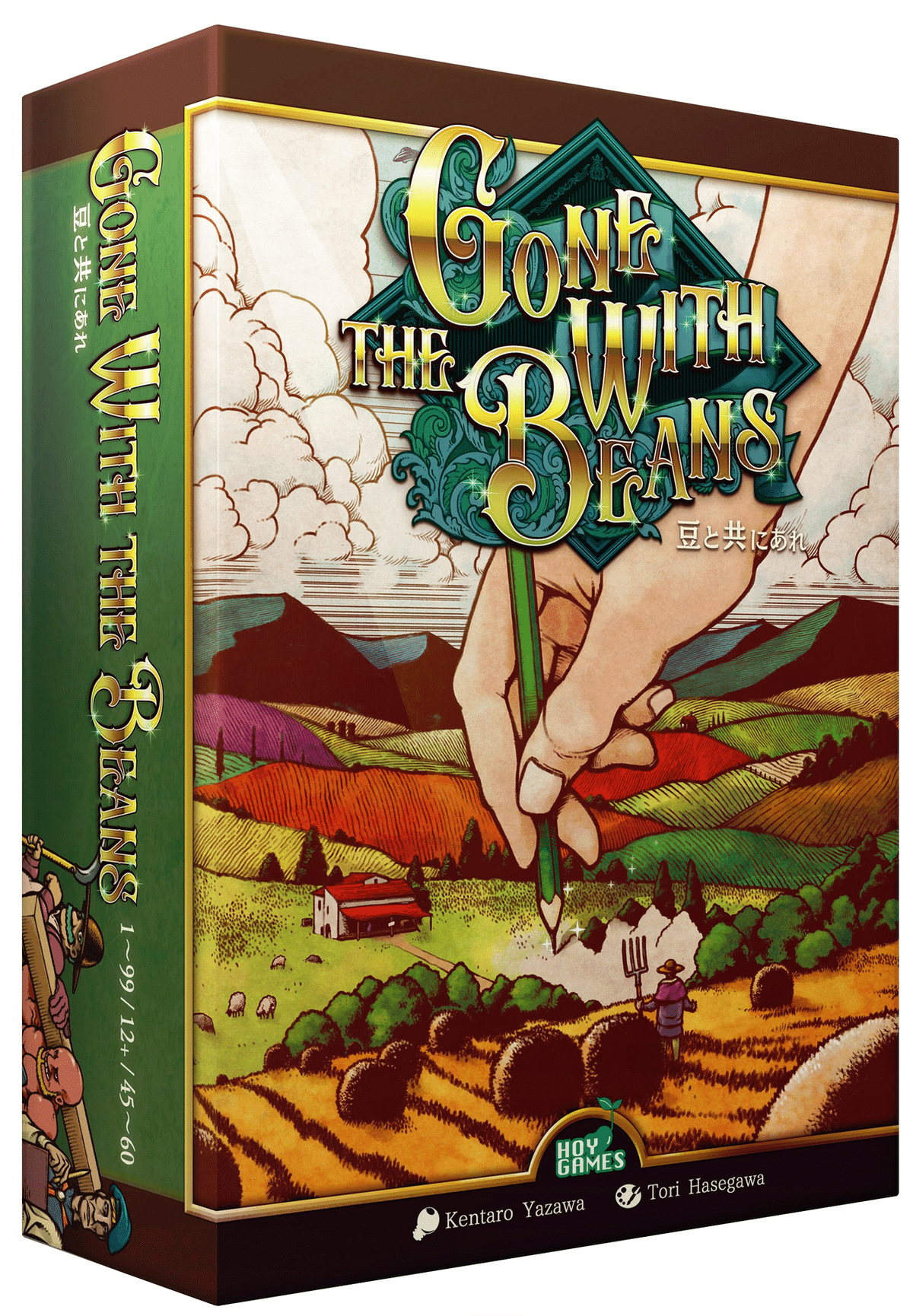
◆0.前提
・A~Dシート、プレイ済み。
Pシートは本稿に含めない。
・1~2人プレイ(とは言っても、ゲーム内容には関係がないが)。
◆1.概要
・ゲームの流れ
大型の紙ペンゲームだ。6つの領地が円形状に配置されており、そこを統治者と呼ばれる駒が時計回りに回っていき、その駒と自身の領地(ゲーム開始時に決定され、ゲーム中は固定)との距離により、建物を建築する制限(シートによるが基本的にはコスト増)が変わっていくのが特徴と言える。
ラウンドの開始時には、カードが捲られ、そこに記された建物の種類に応じて、牧草の資源が得られる。そして、各自アクションを1回行う。
アクションは(シートによるが)基本的には4つだ。
まずは、建築で、建物を選び、その建築コスト+統治者との距離コストを支払うことでチェックすることができる。建物が建つと、上述のラウンド開始時の牧草が多くなることがある他、後述する臨時収入が得られるようになったり、勝利点になったり、距離コストが軽くなったりする。これが主軸のアクションであると言える。
次に、マイルストーンの達成で、これもシートによるのだが、基本的には建物の数が一定以上になっていると達成を宣言できる。大抵は各種資源と勝利点がセットになっている中から1つを選択し、その恩恵を得られる。
他には、牧草アクションがある。これは、牧草を消費することで行えるアクションで、他の資源を得たり、利点が付いた上で建築ができたりする。また、各種類の行える回数に制限がある。勝利点になるシートもある。
最後に、牧草庫の拡張というアクションがある。牧草は(消費した分も合わせて)30個までしか獲得できないので、その枠を広げ(+30個)、追加で2牧草得ることができる。拡張は2回までできるが、それ以降でもこのアクションを打つことができる。その時には事実上のパスに近いアクションとなる。普通にプレイしていれば、30個は優に超えるので、何らかの形で1回ぐらいは打つことになるだろう。
また、統治者が動いていくことで、色々と変化がある。上述の通り、建築に対する制限が変わるというのがまず1点あるのだが、6つの領地は3つずつ大きく左右に分かれており、それを統治者が跨いだ時に臨時収入が得られる。そして、臨時収入で得られる資源の種類や量は建物によって決まる。
資源の種類は、基本的に労働者、豆、金(ターラー)、牧草である。労働者は豆の代替ができ、豆は金の代替ができる、という上位の関係がある。また、牧草はフリーアクションで各資源に変換できる。
ラウンドの開始時の収入で得られるのは牧草だけであり、かつ量もそれほど多くはないため、実体としては、この臨時収入の方がメインの資源供給と見なすことができ、ここで得た資源を建築に費やしていく。
15ラウンドが経過した時点で、ゲームが終了する。インタラクションが一切存在しないため、個々のスコアはレート表と見比べ、どれぐらいのレベルにいるかを確かめるような感じだ。
◆2.考察
・「テラミスティカ」らしさ
このゲームは「テラミスティカ」を自分なりに紙ペンに落とし込み
という記載が説明書にあるように、「テラミスティカ」に影響を受けた紙ペンゲームとなっている。
しかし、筆者としては、「テラミスティカ」らしさを感じることが全くなかった。もちろん、これは個人的な感想である上、「豆と共にあれ」は「豆と共にあれ」固有の面白さが存在するのだが、どうして、「テラミスティカ」らしさを感じなかったのだろう、と疑問に思った。
考えてみると、筆者は『マップ』『インタラクション』『勝利点換算』に「テラミスティカ」らしさ、を感じているらしい。
まず、マップ。「ガイアプロジェクト」との差異にもなっているように毎ゲーム固定であり、あるヘクスにおける価値は、その地形や隣接ヘクスなどによって評価され、他のプレイヤーの種族にもよるし、最終的な広がりを計画する必要もあるので、かなり複雑な価値の見積をしなければならない。
このゲームでは、統治者が回る領地がそれに該当すると思うのだが、土地の価値の見積というような要素はなく(マップがないので当たり前)、単純に統治者が遠い時には建築以外のことをして(するように推奨し)、近づいたら建築をする(ことを推奨する)というゲームリズムの構成要素というように感じた。もちろん、どちらが優れているとか、そういうことではなく、単純に「テラミスティカ」が行っているのは『マップによる価値の見積の難しさ』であり、「豆と共にあれ」が行っているのは『周期的なゲームの構成』であると思った。つまり、ボードか紙ペンか、という表現の違いというより、ゲーム上での役割、本質が異なっている。
次に、インタラクション。個人的にソリティア色が強いゲームにおいて、インタラクションを完全に排除することはあまり気にならない。同じく大型の紙ペンゲームである「Hadrian's Wall」は、その感想でも述べたが、変にインタラクションを導入することによって、ゲームに大きな瑕疵が生じてしまっている。こんなことになるぐらいなら、ない方が断然良い。ただ、「テラミスティカ」を構成しているのは、その強いインタラクション(場所とパワーアクションの早取り、パスによる手番順競り)などであるため、これが欠けていると、「テラミスティカ」らしくないと感じる。
最後に、これが最も大きい(というより、前述の2つは紙ペンゲームでは縮小されるのが一般的だと思うので)と感じられたのが、勝利点換算だ。
「テラミスティカ」は勝利点に換算される要素が少なく、その中でも一定の割合を占めるのが、各ラウンドにおける勝利点ボーナスである。これはランダムセットアップで決まるボーナスで、そのラウンドに指定された建物を建てたりすると勝利点を得らえる、というメカニクスだ。個人的には、これこそが「テラミスティカ」のコアであると感じている。基本的には拡大再生産のゲームというのは、序盤に投資、終盤にそれを勝利点化するという流れが固定化されてしまうものだ。しかし、「テラミスティカ」は、その道中である投資に勝利点を付けている。つまり、なるべく早く拡大再生産を進めるのか、勝利点ボーナスに合わせるために手を歪めるのか、どちらが最善手なのかがわかりにくくなる。これが肝であると感じる。「豆と共にあれ」では、勝利点は比較的単純な計算がされるため、拡大再生産における逡巡はあまりなく、基本的な動きができれば、最高評価ぐらいの点は出る。
もちろん、このような差異は、作者も理解しており、紙ペンゲームへコンバートする際に剝がれてしまった部分だろう。リソースマネジメントの部分など、「テラミスティカ」らしさを色濃く残している部分もある。
・マルチソリティアにおける他プレイヤーとの差異
前述の通り、このゲームにはインタラクションが全くない。その点は特に問題がないと個人的には感じている。
しかし、そうなると難しくなってくるのが、その各プレイヤーの勝利点が何を示しているか、だ。
各プレイヤーは、ゲーム開始時に自身の領土が決まる。統治者のスタート地点はプレイヤー間で共通だから、そことの距離が異なった状態でゲームがスタートする。また、領土に紐づいた能力(VPP)もある。
VPPがある多くのゲームの場合、インタラクションが強めに設定されている。そうなると、強い能力であっても、マークされやすいというデメリットを持つことになり、自然とバランスが調整されることになりやすい。インタラクションがないと、そういったことが期待できない。
また、そもそも、勝利点を他のプレイヤーを見比べる意味がなくなってしまっている。たとえば、「トロワダイス」はインタラクションが全くない状態で、さらに基本ルールではプレイヤー固有の差がなかったはずだ。そうなると、点数は基本的には同じ条件(ラウンド開始時のランダム性など)でのゲームの結果であり、それを見比べることに意味はある。
「豆と共にあれ」の場合、ゲーム内の経過したランダム性が同等であっても、領土が異なる場合では、前提の異なる、インタラクションがない結果なのであって、他のプレイヤーを比べる意味がないように思える。もちろん、「豆と共にあれ」では、一応、全ての条件で同じ指標(ソロゲームでの得点レベル表)を用いるぐらいなので、それでバランスが取れているのだが。
しかし、実際には自身と他のプレイヤーの点数に差があっても、それが自身の領土の差(VPPや初期位置)における影響が強いように感じてしまう。
7人以上であると、領土の数が足りないために、重複ありになるのだが、6人以下でも同じ領土でプレイする方が、個人的にはゲーム終了時の面白さが増すように感じる。ただ、この場合だと、全く同じ条件であり、インタラクションがないので、本質的には最適な回答は一意に決まる(ランダム性はあるが、それは期待値で計算することができ、最も点数が取れる選択肢は原理的には決定される)という問題はあるが、それを人間は計算し得ないし、し得ないからこそ、多くのゲームは成立していて、自然とプレイヤーが取る手順は異なっていくはずなので、それで良い、と個人的には思っている。
ただし、現在の仕様の良い点は(当たり前だが)いくらでもある。
前提条件に差があるということは、もし、完璧にバランスが取れていたとしても、その差のせいにできる、という点でもある。他人の方が点が高くても、領土の差のせいにできる。あるいは、領土ごとに強さの差があると感じられるのであれば、ある種のハンデのような使い方もできる。
また、同じゲームで、他の領土が使われることによって、他の領土でのプレイがしてみたくなり、実際のリプレイが増える、という可能性も大きい。
・ランダム性と勝利点
上記にもあるように、ゲームの点数は、ある表を用いて、ランク付けされる。これは初期領土やシートなどに左右されず、同一のものを用いる。ソリティアのゲーム(「豆と共にあれ」は対応人数に幅はあるが、本質的にはソリティア)には、このハイスコア式とでも呼べるようなゲームがたびたびあるが、この表に関しては、少し難しさを感じている。
なんというか、実情を示していないというか、少し虚しさのようなものを感じやすくなっているように思うのだ。表と見比べて、自身の実力を測ってはいるものの、やはり、各プレイ(1ゲーム)間のランダム性の差は激しく、勝利点の点数帯がプレイヤーの実力を示しているように思えない。
たとえば、このゲームにおけるランダム性の大きな部分を簡単に考えてみる。統治者の初期位置は毎ゲームランダムに決まるのだが、前述の通り6つの領土のうち、ある個所をまたぐ時に臨時収入が得られるというルールがある。そして、1ゲームは15ラウンドで構成されている。つまり、どういうことが起きるかというと、ボーナスが得られる回数がゲームごとによって異なるのだ。具体的には、ある2つの領土から始まると、1ゲーム中に4回しか臨時収入を得られないが、残りでは5回臨時収入を得られる。これは、本当に同じ点数として比較して良いものなのだろうか。
実際、ゲーム内のランダム性によって、全体の点数が上下することは良くある。しかし、そのランダム性をインタラクションにかけた上、最終的にはプレイヤーごとで点数を比べることで、勝利点は意味を成している。一般的なインタラクションと強めのランダム性を持つ中重量級ゲームの場合、本当はゲームごとの勝利点を比べることに意味はなく、その中で他のプレイヤーに勝ることができるか、という点にゲームの焦点がある。つまり、勝利点は多くの場合、相対差にこそ意味があり、絶対量における役割は少ない。
これはこのゲームに限ったことではなく、ランダム性を持つソリティアに共通する課題であるように感じる。
デジタルゲームでは、その特性上から様々な要因を持たせられるのに対し、アナログゲームでは処理に制限がかかるため、インタラクションがなければ、パズルに単純なランダム性が足されたようなものになってしまうことが多い。そして、そのランダム性は剥き出しであり、ともすれば、虚無感を抱かせるような結果を実直に示してしまう。
たとえば、最後にA→Bという順でカードが捲れれば9点だったが、B→Aで捲れたので8点だった、という場合に、その1点差に意味はあるだろうか。
セットアップにランダム性があるだけだとしても、そこで創られた問題(それ以降にランダム性がなかったとすれば、それは純粋なパズル的性質を持つ)の難易度や勝利点の上限に差が生まれてしまえば、単純に他の試行と点数を比べる(表と点数を比べるのも同じ)意味がない。
中重量級の現代的なボードゲームのソリティアに関する試みは最近、急速に行われている試みの一つだと筆者は感じている。そのためか、まだまだ、そこで何を目指すべきなのか、何をさせるべきなのか、という部分が固まっておらず、1人でもプレイ『できる』だけになっていることも多い。インタラクションが全くないマルチソリティアでも、同じような課題を含む。
これらの試みがどう発展していくのか、今後とも追っていきたい。
◆関連記事
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
