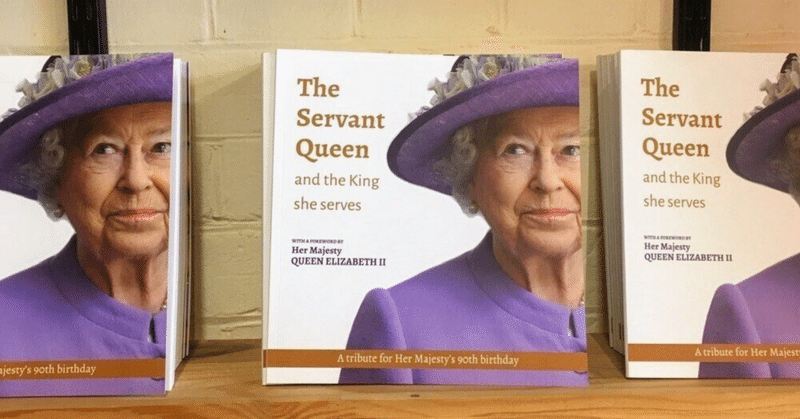
「王朝の支配」を吟味しないブラックバーン教授の調査報告書(令和6年5年15日)
イギリス下院の政治・憲法改革特別委員会の報告書「Rules of Royal Succession, Eleventh Report of Session 2010–12」(2011年12月)に、ブラックバーン教授(キングズ・カレッジ・ロンドン。憲法学)の調査報告書(同年11月)が載っている。
同年10月のパース協定(Perth Agreement)以後、イギリス国内では王位継承に関して、どのような議論が行われたのか、その実態を知るため、とくに関連する部分を拾い読みしてみる。
◇1 楽天的な為政者たち
教授は、パース協定で提案された王位継承ルールの改正案などについて、同委員会から議論と分析を求められていた。12ページにわたる報告書はその回答である。
教授はまず、パース協定の条文を引用して、ふたつの大きな変更点について説明したあと、1772年王室婚姻法を改正する動きに言及している。
Additionally, the UK Government has let it be known that it intends to amend the Royal Marriages Act 1772which requires members of the royal family to obtain the consent of the monarch before they may enter into any marriage.(さらに、英国政府は、王室のメンバーが結婚する前に君主の同意を得ることを義務付ける1772年王室婚姻法を改正する意向である)
200年以上続いてきた王室の婚姻のルールには「君主の同意」という制約があったのだが、個人の自由へと大きく舵を切ったのである。小嶋和司・東北大学教授(故人)が指摘したように、イギリス王位継承には①王族同士の婚姻(父母の同等婚)と②女王即位後の王朝交替という二大原則があったのだが、少なくともこのリポートを見るかぎり、大原則は微塵も顧みられていない。そしてパース協定による王位継承ルールの変更は、王位継承問題だけにとどまらなかった。
教授によると、それだけの大テーマにかかわらず、為政者たちは楽天的(upbeat)だった。
The public statements of key participants at the Commonwealth meeting were upbeat about the reforms and about there being no difficulties about the processes involved. … Mr Cameron was similarly enthusiastic, saying, “If the Duke and Duchess of Cambridge were to have a little girl, that girl would one day be our Queen. The idea that a younger son should become monarch instead of an elder daughter simply because he is a man, …this way of thinking is at odds with the modern countries that we have become”.(コモンウェルス会議の主要参加者の公式声明は、改革について楽観的であり、関連するプロセスについて困難はなかったと述べた。…キャメロン首相も同様に、「ケンブリッジ公爵夫妻に小さな女の子が生まれたら、その女の子はいつか私たちの女王になるだろう。年少の男子が、年長の女子に代わって、単に男だからという理由で、君主になるべきだ…という考え方は、私たちが到達した近代国家とは相容れない」と語った)
◇2 ジェンダー平等の結果
教授が指摘するように、コモンローの世界では男子優先が原則である。
The hereditary principles of monarchy are ones of primogeniture: eldest preferred, sons before daughters.(君主制の世襲制の原則は、長子相続の原則であり、長子が優先され、女子よりも男子が優先される)
しかしいまやジェンダー平等や性差別撤廃が社会の隅々に浸透し、これが王族や貴族の慣習に変革を迫ることとなったのである。小嶋和司教授が指摘したように、君主制は平等原則の例外である。法の下の平等を貫くのなら、君主制は否定されなければならない。けれどもブラックバーン教授はそこには触れない。
Today, the practice is condemned of treating some people less favourably than others on grounds of their gender or sexuality in virtually all matters of a public nature, especially in holding public office. The principle is enshrined in post-war UK statutes, most recently the Equality Act 2010, and in western international human rights treaties such as the European Convention on Human Rights. Clearly, in this context, the present male preference in the law of succession to royal and aristocratic titles looks an anomaly.(今日、この慣習は、事実上すべての公共的性質の問題において、とくに公職に就く際に、ジェンダーやセクシュアリティを理由に一部の人々を他の人々よりも不利に扱うことで非難されている。この原則は、戦後の英国の法令、最近では2010年平等法、および欧州人権条約などの西側の国際人権条約に明記されている。明らかに、この文脈では、王族や貴族の称号に対する継承法における現在の男子優先は、異常(anomaly)に見える」
教授にとっての「王位」とは公職であり、称号なのだろうか。教授は視線を海外に転じる。
Furthermore, most of the other European monarchies have corrected their law to implement gender equality in their royal succession.(さらに、他のヨーロッパの君主国のほとんどは、王位継承にジェンダー平等を実施するため、法律を改正している)
教授は北欧の王位継承とイギリスとの違いには目を向けない。そしてイギリスでも、と教授は論を進めていく。各王国それぞれの王位継承の独自性より、ジェンダー平等が最優先の原理なのである。
Unsurprisingly, therefore, there have been numerous calls to remove this item of sex discrimination, including from parliamentarians in both Houses of Parliament, so that it would become simply the eldest child of the monarch who succeeds to the throne.(したがって、当然のことながら、この性差別の項目を撤廃せよという要求が数多くあった。両院の国会議員を含めてであり、その結果、王位を継承するのは、君主の長子になるだけである)
◇3 女王陛下の承認!?
教授の認識では、要するに、ジェンダー平等の原則に照らして、王位継承者は男子に限られるべきではないということなのだが、それなら王室自身の考えはどうなのか、教授は、エリザベス女王が承認したとする情報を紹介している。
Of special interest is that on one such occasion, where consideration was given by the House of Lords to a Bill presented by Lord Archer, the minister responding on behalf of the Government made it know that the Queen personally approved of the reform.(とくに興味深いのは、アーチャー卿が提出した法案を貴族院が検討した際に、政府を代表して答弁した大臣が、女王が個人的に改革を承認したと知らせたことである)
Her Majesty had no objection to the Government’s view that in determining the line of succession to the throne daughters and sons should be treated in the same way.(女王陛下は、王位継承順位を決定する際に、女子と男子を同じように扱うべきであるという政府の見解に異議を唱えなかった)
教授は、女王の見解が示されることによる憲法上の問題について指摘している。というより、そもそも君主は憲法上、首相の意見に従うこととされている。反対のしようがない。だから、シンプソン夫人の例をも、その文脈で取り上げている。
…in 1936 King Edward VIII was obliged to abdicate in order to marry Mrs Wallis Simpson who was deemed unsuitable by the then premier Stanley Baldwin and dominion governments.(1936年にエドワード8世は、当時の首相スタンリー・ボールドウィンと自治領政府によって不適切と見なされたウォリス・シンプソン夫人と結婚するために、退位を余儀なくされた)
教授は、ここでも王族同士の婚姻という原則については触れず、つづいて、王配の要件について、エドワード8世以後、現国王の事例を挙げて解説しようとする。
It drove Edward VIII into abdication and exile in 1936, and it effectively prohibited Princess Margaret from marrying the divorcee Captain Peter Townsend in the mid-1950s. More recently, the same notion was the underlying assumption driving the extensive public debate and controversy on whether Prince Charles should marry Mrs Parker Bowles, which was eventually resolved with support from the Prime Minister and Archbishop of Canterbury.(1936年にエドワード8世を退位と亡命に追い込み、1950年代半ばにはマーガレット王女が離婚したピーター・タウンゼント大尉と結婚することを事実上、禁止した。最近では、チャールズ皇太子がパーカー・ボウルズ夫人と結婚すべきかどうかについて、広範な公の議論と論争を駆り立てる根本的な仮定が同じ考えであり、最終的には首相とカンタベリー大主教の支持を得て解決された)
チャールズ皇太子とカミラ夫人の婚姻は、王族同士の婚姻という原則に抵触することだが、教授の説明はそうではない。
◇4 歴史と伝統の喪失
The logic behind this idea is that the partnership of the individual who is Head of State is a matter of public interest to the well-being of the Government and the country. The Head of State’s consort is inter-woven into this public interest in good governance, for he or she has considerable de facto official, ceremonial and diplomatic functions to perform, and is likely to be the parent of the subsequent heir apparent. A comparative glance at monarchies elsewhere in the world indicates that similar notions often operate there too. Both Spain and Sweden, for example, have constitutional provisions debarring from the throne those who proceed with a royal marriage which is not approved by the Government.(この考えの背後にある論理は、国家元首である個人のパートナーシップは、政府と国の幸福にとって公共の利益の問題であるということだ。国家元首の配偶者は、この良い統治における公共の利益に織り込まれており、彼または彼女は実行すべきかなりの事実上の公的、儀式的、外交的機能を持っており、見かけ上の次の相続人の親である可能性が高いからだ。世界の他の場所の君主制を比較検討すると、同様の概念がしばしばそこでも機能していることが分かる。たとえば、スペインとスウェーデンの両国には、政府が承認していない王室の結婚を進める者を王位から追放する憲法の規定がある)
王族同士の婚姻(父母の同頓婚)という大原則の喪失について、教授はまったく関心を示していない。つまり、「王朝の支配」についての認識が完全に欠けている。
王位継承ルールの変更はかなり広がりのあるテーマとなることを教授は指摘している。しかし「世襲」が適切か否かが教授のテーマであり、なぜ「世襲」なのか、なぜ男子継承なのかには教授は関心がない。せいぜい貴族社会への影響を見渡している程度である。
Similarly, the proposed reforms raise the operation of the hereditary principle, and whether removal of male preference in succession to the throne should equally apply to the rest of the aristocracy in the UK.(同様に、提案された改革は、世襲制の原則の運用を提起し、王位継承における男子優先の撤廃が英国の他の貴族に等しく適用されるべきかどうかを提起している)
ブラックバーン教授の報告書では、長子優先主義についてのくだりは正味1ページにも満たない。教授の報告書の大半はカトリック排除問題、国教会の首長としての問題、個人の信仰に割かれている。父母の同等婚と女王継承後の王朝交替という二大原則についての検討もなく、王朝の支配についての吟味もない。歴史と伝統という視点はすでに失われており、歴史と伝統を重視する立場からは参考にしようがない。
日本にはこうしたイギリスほか、ヨーロッパの「改革」を見習って、女性天皇容認どころか、過去の歴史にない女系継承容認にまで踏み出すべきだという意見がいまなお多数派を占めているが、承認されるべきことだろうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

