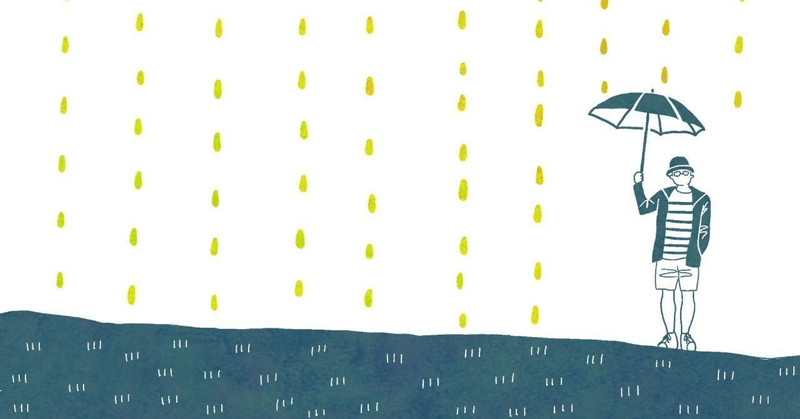
第2回_活動記録①まち歩き_2023.06.17
第2回の活動内容は、「まち歩き」と8月の西都夜市に出展する「屋台ワークショップ」と記録は2本立てです^^
1.まち歩きの全体概要
西都市には、西都原古墳群という年間100万人の観光客が訪れる宮崎県内随一の観光地があります。
西都原古墳群には、こんなに沢山の人が西都市を訪れているにも関わらず、西都原市街地への活性化に繋がっていません。
そのため、西都原古墳群に訪れる100万人の観光客が西都市街地でも時間を過ごしたくなる仕掛けを考えることが市の課題の一つとも言えます。
そのため、SAITOBASEのまち歩きでも、①西都原古墳群の見学と②中心市街地の2つのルートを回りました。
2.西都原古墳群のこと
西都原古墳群は、西都市のシンボルと言っても過言ではありません。歴史的には古墳群であり、現在は、春に桜と菜の花、夏はヒマワリ、秋にはコスモスが咲き渡り、四季折々の風景を楽しめる観光地として有名です。
現在まで西都原古墳群が形を留めているのは、地域の人たちが何千年ものあいだ、この場所を語り継ぎ、守ってきたからだと言えます。
■西都原古墳群の歴史
西都原古墳群は、文化庁が古墳や城址等、遺跡の広域保存を目的として指定した「風土記の丘」の第1号として指定された場所でもあり、公的にも長らく守られ整備されてきました。

鬼の窟の中には入ることもでき、神秘的な場所です。
また、西都原古墳群には、男狭穂塚(おさほづか)・女狭穂塚(めさほづか)も重要な場所です。古事記や神話に登場する夫婦の神様である、ニニギノミコトは男狭穂塚、コノハナサクヤヒメは女狭穂塚がそれぞれのお墓だと言い伝えられており、2人は日本の初代天皇である神武天皇の曾祖父母にあたると言われています。
西都市は、この2人の神様がひとめぼれをして結婚まで至った出会いの場とされる逢初川や、のちに天皇へと繋がる子どもをもうけ、仲睦まじく暮らした古代の恋物語の舞台として今もなお語り継がれています。
天皇に繋がる場所であることから、男狭穂塚・女狭穂塚は今も宮内庁に管理されており、一般に開放されていません。しかし、11月の古墳祭りの時だけは特別に一般公開されており、実際に入ることができます。
※厳しい警備下での公開となります
■西都原古墳群と西都市民の繋がり
このように西都原古墳群は、風土記の丘に認定された昭和40年代頃から西都市民にとって「保全する場所」であり、観光地としての意識が生まれにくかった背景が考えられます。そのため、観光客は訪れているのに、観光客向けのお店の売り込みなどが得意ではなく、今まで観光資源として活用されにくかった背景が考えられます。
その一方で、こうして西都原古墳群が今も立派に保全されているように西都市民は歴史や伝統を守り、語り継いでいくことが上手な市民性も読み解くことができます。
3.中心市街地のまち歩き
西都原古墳群の見学を終え、中心市街地のまち歩きでは、3つのグループに分かれ、それぞれ別のエリアを歩きました。
皆さんには、まち歩きに伴う①ミッションと、②まち歩きの着眼点を事前に共有しました。

■中心市街地まち歩きのミッション
中心市街地のまち歩きでは、グループで各エリアを歩きながら、通りの名前を考えるというミッションを設定しました。
これからまちづくりに取り組むうえで、まちにある資源を発見し、そのエリアの価値を再編集する練習と考えてもらうと良いと思います。
■まち歩きの着眼点


まちにある資産は、建物だけでなく、環境も含まれます。その雰囲気までもが資産と考えられます。
その場所が昔はどんな場所だったのか?は各グループに西都市出身の参加者が必ず入っているので、「昔から住んでいる自分にとってはこういう場所だった」という話を聞くことができます。
昔の姿を聞いたり、これからどんな場所にしたいか?と未来への想像をしながら街を歩きます。
また、着眼点+αとして、

グループ内でコミュニケーションを取りながら、感じたことや疑問点は遠慮なくシェアすることで、自分には見えていないものや他の人が見ると自分と違う視点で見えるものに気付くことができます。
■各グループで回ったエリア
グループ①(オレンジ):小野崎商店街~桜川添い~ゾウさん公園~市役所
グループ②(青):小野崎商店街~平助通り商店街~御舟町~市役所
グループ③(ピンク):妻線跡地市営駐車場~妻町~小野崎商店街~市役所

■各グループのミッションのシェア
まち歩きから戻り、各グループの中でまち歩きをしながら受けたコースの印象や発見したものをシェアしました。全体的にワークの設定時間が短く、「〇〇通り」とつけるところまで到達しなかったのですが、新たな視点を発見することができました。
グループ①(オレンジ):小野崎商店街~桜川添い~ゾウさん公園~市役所
歩いた短い区間・エリアの中で、ここだけで生活が成り立つ環境が整っており、生活圏がてきている。シャッターが閉まっていても懐かしさを感じるビルや、桜川添いにきれいな花が地域の人で整備されており、地域の人の温かさや優しさが感じられた。川と木々、整備された花が多く、歩いてみたくなる街、景観を見たくなる街だと感じた。
グループ②(青):小野崎商店街~平助通り商店街~御舟町~市役所
シャッターが下りていたり空き物件になっている古い建物と新しいマンションやお店が混在しているエリアで、古い建物を見てタイムスリップしたような感覚を楽しめた。レトロを生かして、大分県豊後高田市の昭和の町のような打ち出し方もありそうだと感じた。
グループ③(ピンク):妻線跡地市営駐車場~妻町~小野崎商店街~市役所
レトロな雰囲気の飲食店・お店が多かった。昭和レトロな雰囲気をうまく生かしきれていないのではないか、という仮説が考えられる。レトロな写真や映えを意識することで、地元の人だけでなく、外からも人を呼び込むことができ、外の人が増えることでもっと明るい雰囲気が生まれると感じた。

短い時間でのまち歩きとグループワークでしたが、西都市街地に残るお店にレトロな味わいのあるお店が多く、全体として昭和レトロな雰囲気・強みを発見したという意見が多く出ました。
個人のお店が昔から頑張って今も営業を続け、昔からのお店が今も残り続けてくれたからこそ、「レトロ」なエリア全体の価値に繋がっているのだと思います。
今は空き物件になってしまい、パッと見で価値が無さそうに見える建物も、このエリアの文脈に沿って考えると、新たな使い方が生まれるかもしれません。
6月17日の活動記録は後半の屋台ワークに続きます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
