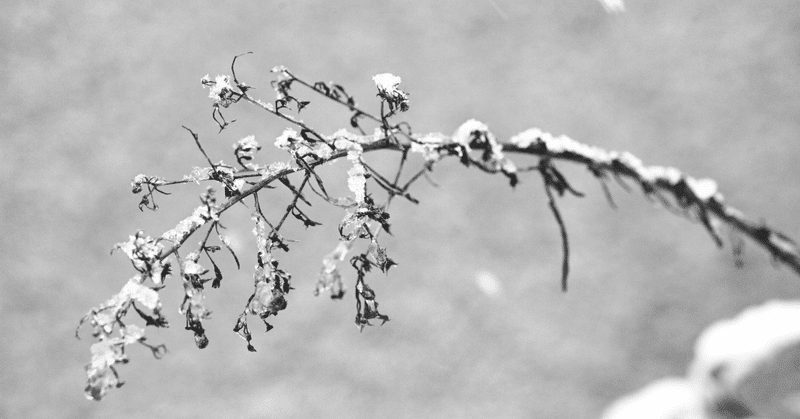
雪の結晶はなぜ六角形なのか?
先日都心は雪が降った。年齢が上がると雪が降っても憂鬱な気分になると思うが, 気を取り直して, 雪についての化学を考えよう。

氷の化学
タイトルの疑問。これは氷の構造を考えることである程度解決できる。
雪は氷を主成分としている。氷は水の固体で, 個々の水分子のあいだには水素結合がはたらいている。水素結合には方向性があり, 正四面体の結晶構造を形成する。隙間の多い結晶であり, これは水が例外的に固体の方が液体より密度が小さくなる理由である。正四面体が連結した結晶構造は六方晶構造となっている(酸素原子だけに注目して見るとわかりやすい)。五角形でも七角形でも六角形なのはここに原因がある。

様々な説明
実は, タイトルの疑問はすでにたくさん本になっている。
ただ, 意外なことにも着眼点は著者によって様々である。フラクタルに着目したものもあれば, 低温環境, 結晶形成に着目したものもある。
結晶形成
さて, 今回, 追って話題にしたいのは結晶形成についてである。というのも, 結晶形成は雪の話だけではなく, ナノ粒子合成, 鉱物, 生体内においても重要な話題だからである。結晶形成の一般論としては, 核形成(核生成)と結晶成長の2段階があることは知って損はない。
核形成は, 分子あるいはイオンが集まり, クラスターを作る段階である。熱力学的に, 全体の自由エネルギー変化が負になるときに起こる(※)。これまでミクロでのメカニズムは把握されておらず, シミュレーションなど理論的研究, マクロ系でしか把握されていなかったが, 近年顕微鏡による核形成の様子の観察も行われた。必ずしも無秩序な状態から秩序のある状態に一方向に進むわけでは無いみたいである。
(※) 体積増加に伴い, 単位体積あたりの自由エネルギー変化(および弾性歪みエネルギー変化)は減少するのに対し, 単位面積あたりの界面エネルギーは増加する。以上を差し引いた, 全体の自由エネルギー変化は正から負に符号変化する。
雪の場合, 水滴が集まった雲の中, それも気温が−40℃以下となる地上10kmの上空において, 氷の粒が形成される。これが結晶の核(氷晶核)となっている。
一方, 結晶成長は, 過飽和状態あるいは過冷却状態(氷晶の場合はこちら)のときに起こる。 氷晶核形成の後の成長において, 雪の結晶の形を決定する基本因子は温度・水蒸気量である。温度は成長の際の結晶面を左右し, 水蒸気量は枝分かれ構造の成長のしやすさと関係する。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
