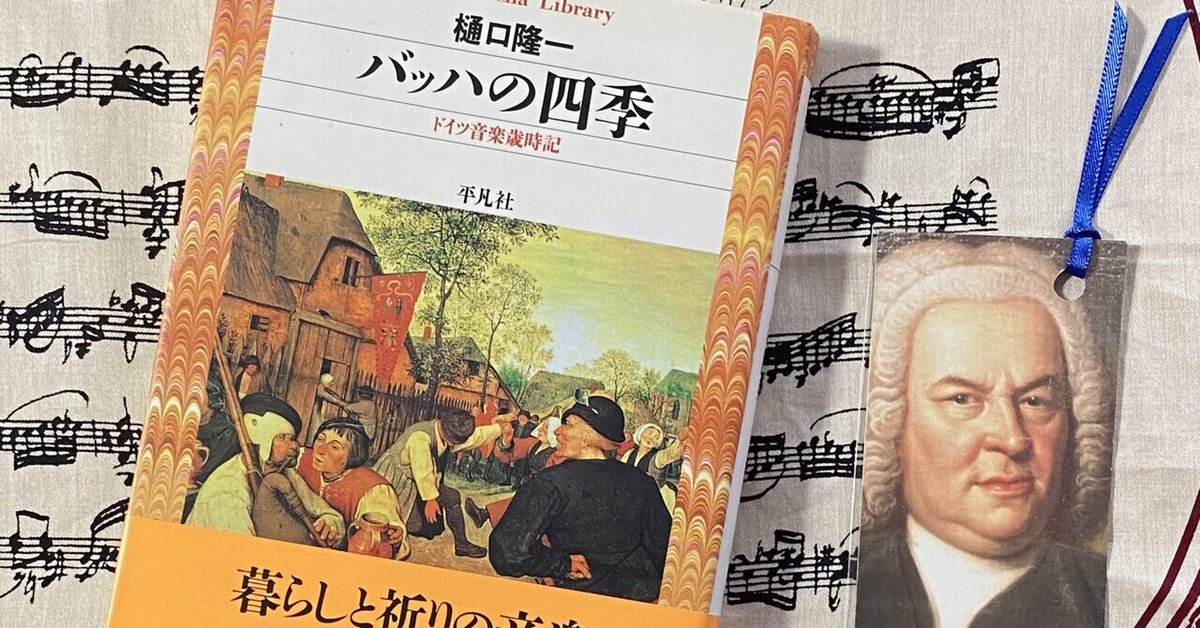
宗教改革記念日に思う。
宗教改革記念日。
宗教改革の果たした歴史的重要性は、特に基本的人権の普及など、キリスト教に無縁な世界にも無視できない歴史の流れの源流であり、その動きのエネルギー源であるから、どれだけ高く評価しても仕切れないと思う。
しかし、その一方で、抜き差しならぬ対立を生み、それは時に数十年に渡る戦争ともなってしまったのも歴史的事実である。
それは、今日、なお、人類が直面する問題でもある。
それ故に、その根源的解決を願い、「宗教的寛容」のために、文字通り人生をかけて声を上げた二人の先達を想い起こしたい。
一人はカルヴァンの指導下にあったスイスの改革運動で、異端視した再洗礼派の指導者を火刑に処すことに反対し、声を上げたセバスティアン・カステリョである。
古典に精通した、カルヴァンにも信頼された学者でありながら、信念ゆえに出世の道から外れ、家族を養うために肉体労働に携わり、病人の介護に従事しながら、学問をコツコツと続けた苦労人でもある。
彼の信念こそ、「宗教的寛容」、宗教、信条によって差別、断罪し生命を奪ってはならないというものであった。
もうひとりは、ロジャー・ウィリアムズである。彼については20年ほど前に書いた文章があるのでそのまま掲載する。
「宗教的寛容の精神」のパイオニア、ロジャー・ウィリアムズ
「人権」、今では我が国も『日本国憲法』により高らかにうたわれ、認められてきたこの当然の権利は、決して「当たり前」ではない。
70数年前の日本にはなかったものであり、今日でも、権利意識は高まり、時に過剰なほどの「人権」の権利主張が横行しているが、しかし、本来の「人権」の意義をはっきり自覚的に受け止めている人は、一体どれだけいるのだろう。
「人権」意識の由来をめぐる論争で欠かせない論文がある。
イリネックの『人権宣言論争』だ。そこには、こう書かれている。
「個人のもつ、譲り渡すことのできない、生来の神聖な諸権利を法律によって確立せんとする観念は、その淵源からして、政治的なものではなく、宗教的なものである。従来革命の成せるわざであると考えられていたものは、実は、宗教改革とその闘いの結果なのである。宗教改革の最初の使徒はラファイエットではなく、ロジャー・ウィリアムズである。彼は力強く、また深い宗教的熱情に駆られて、信仰の自由に基づく国家を建設せんと荒野に移り住むのであり、今日もなおアメリカ人は深甚なる畏敬の念をもってその名を呼んでいるのである。」
(イリネック著 初宿正則訳『人権宣言論争』みずず書房 99ページ)
一般に、特に我が国では、「人権」の起源はフランス革命を引き起こした理知的な啓蒙主義に由来すると教えられているが、そうではなく、歴史的事実として宗教改革由来であることを説いたものだ。
その中で、忘れてはならないのが、「こんにちもなおアメリカ人は深甚なる畏敬の念をもってその名を呼んでいる」という、「ロジャー・ウィリアムズ」である。
彼については、我が国ではほとんど認知されていない。日本でも本格的な評伝がやっと出版され、少しずつ知られるようになったばかりだ。
『ロジャーウィリアムズ ニューイングランドの政教分離と異文化共存』(久保田泰男著 彩流社、1998年)である。
ロジャー・ウィリアムズの生涯は非常に魅力的で、とてもひと言では言い表せない。1603年(江戸幕府開幕の年)にイギリスで生まれ、ケンブリッジの大学を卒業後、エリート聖職者として活躍できたにもかかわらず、栄達の道を捨てて、自らの信仰の純粋を保つため、結婚後、イギリスを離れ、北米のニューイングランドへ移住した。
しかし、初期ピューリタン植民地でも彼は受け入れられず、結局自らの理想を実現するためにプロビデンス(「摂理」という意味、現在のロードアイランド州プロビデンス)という町を開墾した。しかし、そこでも創設者である彼の理想は孤立し、最後まで孤高の人として生涯を貫いたそうだ。
彼の主張は、徹底的な「政教分離」であり、「信教の自由」の立場だ。それは、「宗教的寛容」を最も大切にする精神でもあった。
それは彼の生き様にも現れている。彼は大学を卒業した正規の牧師だったが、その立場を顧みず、生涯、いち「シーカー(Seeker : 真理探究者)で通し、結局どの宗派にも属することがなかった。
もちろん、宗派を越えて、互いを尊重する立場を貫いたため、彼が築いたプロビデンスには宗教的に迫害を蒙った者たちが集まり、結果として、ロジャー・ウィリアムズを異端視した正統派ピューリタンたちが危惧したような政治的混乱がプロビデンスに生じ、ウィリアムズ自身、そこを追われる身となった。それでも、彼は決して宗教的寛容を譲ることはなかった。
また、彼はアメリカ原住民をも全く差別することはなく、むしろ深い尊敬をもって接していた。それは開拓者として、自然の猛威と闘いつつ共同体を建設する作業に自ら従事し、農民として、商業者としても最大のタレントを発揮し、現地語をマスターし、彼らの生活に溶け込んでいく態度にも表れている。
後に彼はその経験を生かし『アメリカ現地語案内』をイギリスで出版した。その中で彼は、先住民の礼儀正しさを褒め称えている。
「奇妙に思えるかも知れないが、多くのキリスト教徒と自称する人々の間にいるよりも、一般に、これらの未開な人々のなかに身を置く方が、一層おおらかな気持ちをゆったりさせるもてなしを受け、気分が爽やかになるのは、本当なのである。」
このようにウィリアムズの目は、他の正統派ピューリタンたちとは異なっていた。その点をこの著者久保田氏は次のように指摘している。
「ウィリアムズの所見は、先住民の生活や習俗の表面的な観察に止まらず、その根底にある彼等の人間性や精神に関する洞察にも及んでいる。ウィリアムズは、深い異文化理解に基づいて、自己の属する西欧文化への批判と反省も試みている。ここに、異文化理解・異文化への洞察のあるべき姿が提示されていると思われる。相違を超えて、自分と同じ人間である、という厳粛な人間観を体得することであろう。」
こうしたロジャー・ウィリアムズの生き方は、同時代人のピューリタンたちにとっては、時には信念のない、矛盾だらけの存在に写ったようだ。
しかし、彼は現地人にも深い尊敬を勝ち得、また同じく心あるピューリタンたちにも信頼される行動の人だった。
それは現地人同士の激しい部族抗争や、たびたび起きた植民地の市民と現地人との紛争も、再三、命がけで和解交渉の任に当たったことにも現れており、彼がいかに双方に人望が厚かったかが伺える。
彼の思想についてはまだまが十分探求されたとは言えないそうだが、そうした生き方を通して、また、彼の残した言論を通して、やがれ「宗教的寛容」が「政教分離」として「アメリカ合衆国憲法」に結実していったのは事実のようだ。その歴史的事実を、まずは知ること、また、彼の発言や行動に耳を傾けることからスタートしなければならないのではないか。そうしなければ、いつまでも似非「人権」に取り憑かれた偶像崇拝者に陥ったままではないかと思う。
「ロジャー・ウィリアムズ」、まずはその名を覚えることから出直さねばならない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
