
【愛されるキャラクターの作り方】シナリオライターが使用するキャラ設定書を大公開!
シナリオライターがキャラクタ―設定で一番意識しているのは、いかにキャラぶれを減らすかということです。
キャラぶれとはすなわち、そのキャラクターが一貫性のない言動をとってしまうことを意味します。
極端な例を挙げると、魔王討伐を目指している勇者が急に「魔王とかどうでもいいから俺はのんびり暮らす」と言い出すようなことをキャラぶれと言います。
そういったぶれが多くなればなるほどキャラクターの魅力は下がるため、なるべく減らすようにしなければいけません。
しかし、創作の経験値が低いとどうしてもキャラぶれが発生してしまいます。物語序盤では問題なくても、中盤から終盤にかけてキャラクターがまったく別人になってしまうというのはアマチュアによくあるパターンです。
すべては、キャラ設定がしっかり作りこまれていないことが原因。設定段階からキャラクターのイメージを固めておけば、ぶれることを防げます。
そこで今回、キャラぶれが激減する上手な設定書の作成方法を解説。
この記事を読めば必ず、あなたの作品は何段階もレベルアップしますので、ぜひ最後まで目を通してください。
※この記事は読破するまでに10分以上を要する長文コンテンツとなっています。ブックマーク代わりに「スキ」を押していただき、あとで読み返せるようにしていただくことを推奨します。
♢この記事を書いた人:さーくん♢
シナリオライターとして3年間活動し、20作以上のゲーム開発に携わる。
現在はサイト制作、WEBマーケティングをこなすクリエイター。
詳しいプロフィールはこちらから→自己紹介
1.魅力的なキャラクターとは
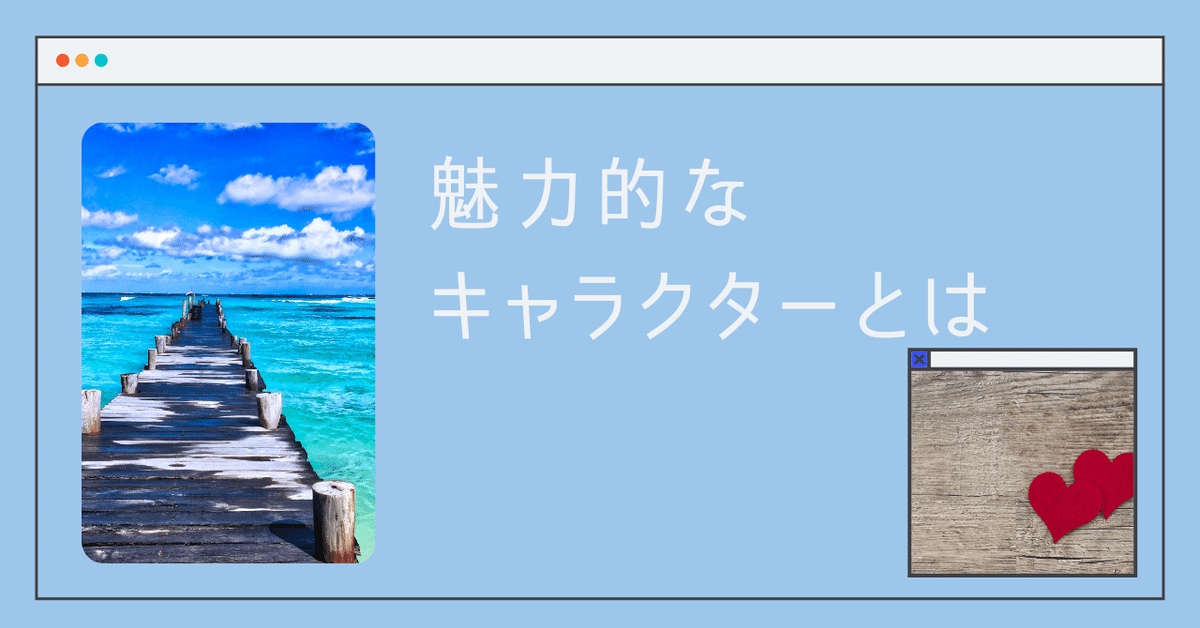
繰り返しになりますが、プレイヤーが魅力を感じるのはキャラぶれが少ないキャラクターです。現実世界でも同じことが言えます。
たとえば、ひたむきに頑張っているアスリートを見たときに応援したくなるはずです。彼らには一切ぶれがなく、勝利というただ1つの目標に向かって行動しているからです。
では、キャラぶれを抑えるためにはどうすれば良いのかというと、設定書をしっかりと作り込むことです。
次の項目からさっそくキャラ設定書の作り方を解説していきましょう。
2.キャラ設定書の作成方法

キャラ設定書を作るにあたり、次の項目は誰でも記載するでしょう。
・名前、性別、年齢、体型、性格、趣味
この項目はもはや説明不要だと思いますので説明しません。
プロはこれに加えて、次のような項目を作成します。
・学歴/職歴
・家族構成と関係性
・主要人物たちの関係性
・これまでの生い立ち
・生きる上での信念
・ギャップ
・セリフの特徴
人によってはさらに項目を追加しますが、まずはこの7項目はマストだと思ってください。
では、各項目について説明していきます。
2-1.学歴/職歴について
キャラクター設定書に、学歴や職歴を書く必要があるのか疑問に思うかもしれません。
ただ、学歴や職歴というのはキャラクターのパーソナリティーを形成する大事な要素の1つのためしっかり記載しましょう。
具体的な書き方としては、次のようになります。
〇最終学歴
高校中退
〇現職
正社員3年目。地元では有名なメーカーの工場勤務。ピッキング担当。
給料は低く、仕事内容もあまり面白いとは感じていない。
しかし、前職よりも休日は多く、勤務も不規則ではないため不満はない。
〇前職
契約社員として5年勤務。キャバクラの客引き担当。
優秀な成績を継続して収めていたが、急遽退職した。
好きな女性と結婚したいと思い、まっとうな職に就こうと思ったのが理由。
この設定だけでも、キャラクターの人間性が見えてくるはずです。
・愛する人のために頑張れる人間
このようなパーソナリティも、設定書をしっかり作っているからこそ形成されるのです。
2-2.家族構成と関係性について
物語に家族が深くかかわるのであれば、家族構成についての設定はとうぜん必要になります。しかし、物語にまったく関与しない場合でも設定をしっかり練っておく必要があります。
少し、私たちに当てはめて考えてみましょう。
私たちは普段、生活しているなかでふと家族との思い出が脳裏をよぎることがあるでしょう。
たとえば、スーパーで買った肉じゃがを食べたとき、「お袋が作ってくれたやつのほうが美味しいな」と思ったりするような感じです。
このようにして、私たちは長い時間をともに過ごした(あるいは過ごしている)家族との記憶を何ともなしに思い出したりするものです。
それは、キャラクターにおいても同様であるべきです。作中、いっさい家族のことが話題に上がらないのは不自然です。
家族についてはあえて触れないというのは問題ありませんが、なんの理由もなく話題に上げないのは違和感を覚えます。
キャラクターに人間味を与えるという意味においても、家族構成をしっかり練っておき、必要な場面でその設定を活かすようにしましょう。
2-3.主要人物たちの関係性
作中に登場するキャラクター同士、お互いのことをどう思っているのかを設定段階から考えておくべきです。
そうすることにより、キャラクターの会話がより自然になります。
たとえば、恋愛ストーリーに当てはめて考えてみましょう。ここでは分かりやすく、主人公とヒロインの2人によるラブストーリーにします。
〇主人公から見るヒロイン
ヒロインに対する第一印象は最悪で、さながら女王のようだと感じた。知り合ってから1か月ほど経過した今も、上から目線の物言いに不快感を覚えている。なるべく関わりたくないと思っており、どうしても話をしないといけないときは他人行儀な喋り方になる。
〇ヒロインから見る主人公
主人公に対する第一印象は、不思議な人。自分の美しさをもってすれば、どんな男もなびくはずなのに主人公はそうではないからだ。知り合ってから1か月ほど経過した今では「不思議」から「面白い」存在となっている。何を言ってもそっけない主人公が、どうしたら自分に好意を向けるようになるのか試している最中。
このような設定があるだけでも、主人公とヒロインの掛け合い(=会話)がスムーズに思い浮かぶはずです。たとえば、次のような具合です。
【主人公】
「あの、何かご用ですか……?」
【ヒロイン】
「あらあら、用がないと話しかけちゃいけないのかしら?」
【主人公】
「用事がないのに話しかけられても困ります。それじゃあ」
【ヒロイン】
「つれないわね、本当。それじゃあこうしましょう」
【ヒロイン】
「あなたに用事があるの。それも、すごくすごく大切な用事」
【主人公】
「……と、言いますと?」
【ヒロイン】
「ずばり、あなたの女性の好みを教えてちょうだい!」
【主人公】
「あなたと似ているところが何一つなくて、あなたとはまったくの正反対な女性がタイプです」
設定があれば、このように自然と会話が浮かんでくるものなので、ぜひキャラ同士の関係性を設定に盛り込んでみてください。
2-4.これまでの生い立ちについて
誰しもが、生まれたときから今日に至るまで色んな経験をするものです。そして、さまざまな経験を通じて人格が決定づけられます。
なぜ、そういう性格になったのか。なぜ、そういう考え方をするのか。すべてには必ず理由があるはずです。ためしに、あなたの人生を振り返ってみてください。いまのあなたを形作ったのは、これまでの色んな経験があったからではないでしょうか。
キャラクターにおいても同じことが言えます。さまざまな体験をしたからこそ、いまの性格・価値観があるのです。
それにも関わらず、キャラクターの設定段階で「冷たい性格」「優しい性格」などと一言で簡単にまとめてしまったらどうなるでしょうか。キャラクターから人間味がなくなり、プログラムを組み込まれたロボットのようになってしまいます。
キャラクターは、シナリオを進行させるために必要な駒ではありません。彼らもまた、私たちと同じように物語のなかで生きているのです。
だからこそ、キャラクターにも生い立ちは必要になるわけです。彼らの人生にしっかりと焦点を当ててあげなければいけません。
2-5.生きる上での信念について
キャラぶれを防ぐために、一番重要なのがこれです。つまり、そのキャラクターが生きる上でなにを信念としているのかということです。
分かりやすく、極端な例を挙げてみましょう。主人公が政治家の物語があるとします。
〇主人公の信念
主人公は新人・政治家である。父親が誰なのかも分からぬまま主人公は誕生し、母親の手一つで育てられた。母は主人公に立派に育ってもらいたい一心で連日働きつづけ、稼いだお金はすべて主人公のために使った。しかし、あまりのハードワークに身も心もボロボロになった母は自らその命を絶った。主人公は、自分たちのように生活困窮者を救済する法制度がもっと整っていたら違う結末が待っていたのではないかと悔やんでいる。そして、「貧困層に救いを」をモットーに政治家となり、法整備に取り組んでいる。
この設定で考えると、主人公は自分と同じような境遇にある人々を救うことを信念としています。信念がこのように明確になっていれば、主人公の言動がぶれることは少なくなるはずです。
その一方で、たとえば、「政治家として日本を良くしたい」というふわっとした設定ではどうでしょうか。
日本を良くするといっても色んな方法が考えられますし、そもそも、日本の何をどう変えたいのかが分かりません。そうすると、キャラクターの言動に一貫性がなくなりぶれが発生する可能性が高まります。
2-6.ギャップについて
ギャップとは、簡単に言えば「意外な一面」といった意味合いになります。
では、キャラクター設定にギャップがなぜ必要なのでしょうか。その理由は、次のようになります。
・ギャップはキャラクターの個性を強める
たとえば、見た目はギャルだけど実は料理がすごく上手で家庭的な一面を持っていたりすると魅力に感じますよね。
そのため、個性を強めるためにもキャラクターにはギャップをもたせるべきなのです。
ただ、ギャップには2種類あり、良い印象を抱くプラスギャップと、悪い印象を抱くマイナスギャップがあります。
キャラクターによってプラスギャップを設定に組み込むか、マイナスギャップを設定に入れるか使い分ける必要があります。
たとえば、次のようなパターンで考えましょう。
容姿端麗な女性キャラクターですが、コミュケーション能力に難があるとします。人間を前にすると「あ……あ……」としか言えなくなり、会話相手はもっぱら動物です。
これがまさしくマイナスギャップで、「美人が台無し」状態。しかし、このマイナスギャップこそが魅力となり得るわけです。
人前ではまったく話せなかったキャラクターが、主人公と触れ合うなかで堂々と喋れるようになる。そういうマイナスギャップを用いた物語も良いでしょう。
プラスギャップもしかりです。超絶・元気娘の女性キャラクターですが、実は誰よりも繊細な性格をしていて傷つきやすいというのも良いと思います。
あなたの作品に登場するキャラクターにあわせてプラスかマイナスかを考えるようにしましょう。
2-7.セリフの特徴について
意外と抜けがちですが、キャラクターがどのように喋るのかを設定書の段階からしっかり決めておくのが鉄則です。
そうしないと、物語終盤になった頃には話し方がまったく変わっているという事態も起こり得ます。
これに関しては複雑に考える必要はなく、ただセリフの一例を書き上げていくだけで良いでしょう。
3.この記事のまとめ

ここまでの内容を、最後にまとめていきます。
〇キャラクター設定書で考えるべき項目
・学歴/職歴
・家族構成と関係性
・主要人物たちの関係性
・これまでの生い立ち
・生きる上での信念
・ギャップ
・セリフの特徴
以上になります。
この記事に関してや、シナリオに関して何かご質問等ございましたらお気軽にお問合せください。
お問い合わせ先:Twitter
では、最後までお読みいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
