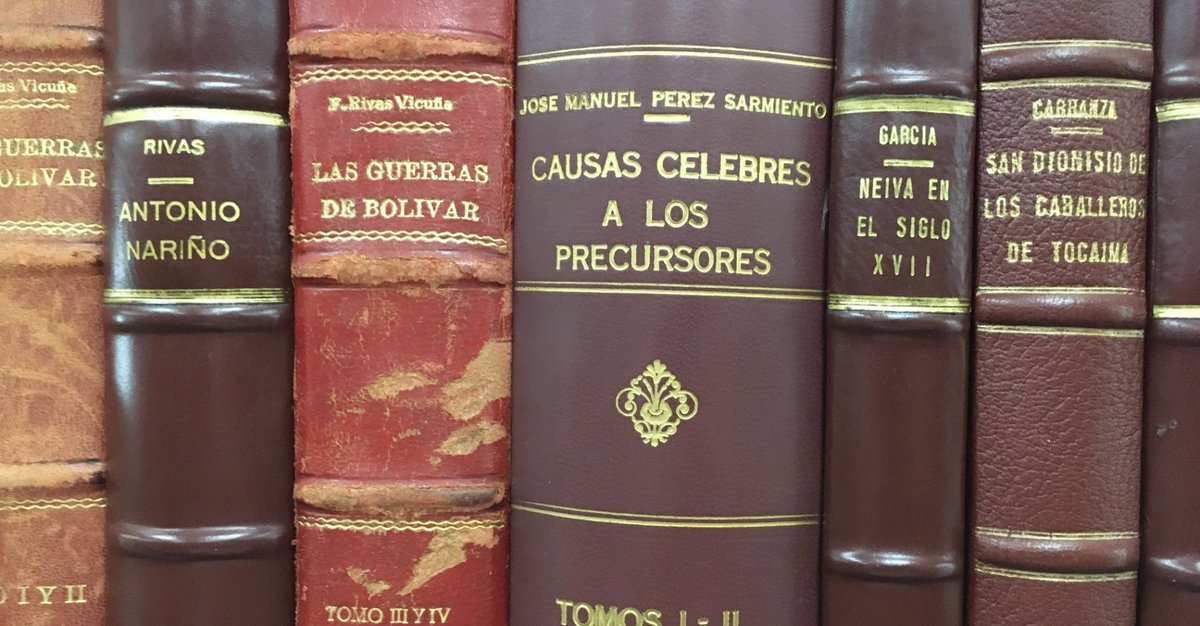
【読書メモ】首都圏に生きるアイヌ民族―「対話」の地平から
『首都圏に生きるアイヌ民族―「対話」の地平から』関口由彦著、草風館、2007年。
本書は、文化人類学者の関口由彦さんによる、首都圏で暮らすアイヌ民族の人びとのライフストーリーの語りを集めた本です。著者は、アイヌ料理店のレラ・チセでアルバイトをしながら調査を行い、本書をまとめたそうです。
僕は、本書の中で言及される「見る者のまなざし」に着目しました。着目するきっかけとなったのは、次の一文です。
多様なズレを伴った意味づけを生じさせる歩く者の柔軟な日々の営みを、見る者のまなざしが押し付ける固定的なアイデンティティの中に閉じ込めるようとすることは、大きな抑圧となる(pp.235-236)。
本書では、フランスの哲学者ミシェル・ド・セルトー(Michel de Certeau)の言葉を引用しつつ、ある特定のコミュニティ集団に身を置きながら、その中で日常を暮らす人びとを「歩く者」と表現し、そのコミュニティや人物を、ある程度の距離を持って俯瞰して理解しようとする立場の人びとを「見る者」と表現しています(pp.11-12)。これを踏まえた上で、本書は徹底して「歩む者」を描く立場を貫いています。
この「歩く者」「見る者」の齟齬は、アイヌの事例に限らず、日常のあらゆる場面で生じていると思います。
海外のニュースを日本で見る私たちは「見る者」であり、出来事が起こっている現場の人びとは「歩く者」です。報道であっても、カメラが切り取る場面、そこに流されるBGM、キャスターやコメンテーターの発言などによって、見る者の印象が変わるということはよくあります。ましてや、海外情報もののバラエティー番組であれば、視聴者ウケする「面白く見せよう」という演出がさらに加わります。
あるテレビ番組でミャンマー人の紹介の仕方があまりにも偏向していたとして、在日ミャンマー人団体が、オンライン署名サイト「チェンジ・ドット・オーグ(change.org)」で、番組を放送したテレビ局に是正を求める署名活動を行ったことがありました。
このように「見る者のまなざし」には、本人が純粋に「歩く者」を見ていると思っていても、実際には、意図的にしろ意図せずにしろ、幾重にもフィルターがかかっています。
このことが顕著に表れるのが、「らしさ」や「べき」というようなステレオタイプに基づく言葉です。
本書の中でも、周囲から、時には同集団内でも「アイヌらしさ」「アイヌはこうあるべき」ということを求められ、それに悩む人びとの様子が描かれています。これこそが「見る者のまなざしが押し付ける固定的なアイデンティティの中に閉じ込める」行為です。そしてこの行為は、悪意を伴って行われるだけでなく、「その文化を守りたい」という一見すると、やさしさや善意のように見える気持ちから行われることも多々あります。ただ、そこに「やさしさや善意のようなもの」があるだけに、非常に厄介でもあります。
本書の中でも、アイヌ研究者の大谷洋一の言葉を引用し、次のように痛烈に批判しています。
『アイヌに同情することによって、善人としての自己存在をアピールする場』を見つけたと考えて喜んでるシャモ(和人)が多い(p.9)
こういった見る者のまなざしは、決して「歩く者」を見るものではなく、自己満足のためであり、歩く者以外の別の他者にアピールするためのものと言えます。これは、障がい者の頑張りを見せて感動を誘う、いわゆる「感動ポルノ」に対する批判とも関連すると思います。
アイヌであれ、障がい者であれ、いわゆる「マイノリティー」とされる人びとが、マジョリティー側(にいると思っている)人びとによって、ある種の「消費」をされている状況があります。
ともすると、その状況に加担しかねない「見る者のまなざし」から脱却して、「歩く者」と同じ目線を持とうとする「共に歩く者のまなざし」を身につけることが必要です。
よく「真摯に向き合う」という言葉が用いられますが、僕はそれだと、自己と他者が向かい合う目線となり、向かい合っていては「共に」歩けないと思います。そうではなく自己と他者が同じ方向、前を向いて歩いていき、そして歩きながら対話が生まれていく、それこそが「共に歩く者のまなざし」なのではないかと思います。
真心こもったサポートに感謝いたします。いただいたサポートは、ワユーの人びとのために使いたいと思います。
