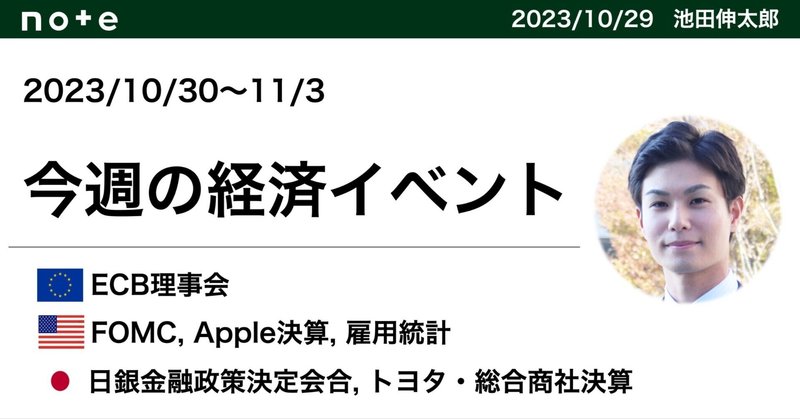
【今週の予定】主な経済・投資イベント(2023/10/30〜11/3)
イスラエルがハマスへ地上作戦を拡大するという旨の報道から、本格的な地上侵攻への警戒が強まり日経先物は大きく下落しています(約400円下落、1.42%安)。週明けの金融市場も神経質な展開が続きそうですが、もともと今週はビッグイベントが複数重なっており毎日話題に事欠かない一週間になるでしょう。
この記事では、重要なイベントについてその見通しをサクッと解説します。あまり冗長にならない程度の文章量にまとめましたので、最後までご覧ください!
この記事へのスキマークがこの活動を続ける活力になるので、是非応援のほどよろしくお願いいたします🙏
<読了目安時間:10分>
【今週の要点】
日銀会合では「YCCの再修正」と「物価見通しの引き上げ」に注目
ユーロ圏GDPは再びのマイナス成長に警戒
FOMCは消化試合濃厚、パウエル議長会見でのタカ派発言に警戒
米雇用統計は雇用者数変化弱含み&平均時給伸び率減速なら利上げ停止期待で株価にプラスか


日米の中銀会合
🇯🇵日銀金融政策決定会合
7月会合でYCCの運用方針を変更し、長期金利の実質的な上限を1.0%にして以来、長期金利はジリジリと切り上げており直近では0.8%後半での推移となっています。そもそも上限を0.5%から1.0%に引き上げたのは、長期金利に上昇圧力がかかる中で政策的な余裕を持たせたいという意図から先手を打ったものでした。しかし、既に余裕が無くなりつつある点は、植田総裁をはじめ日銀執行部としても「金利の上昇スピードが思ったよりも速い」という印象を持っているのではないかと推察します。米国のFRBが思いのほかタカ派姿勢を強めており早々の利下げに至らないと目されることや、米国債の大量発行と中国の米国債売却などが重なり、需給の緩みから米国債利回りが上昇していることなどが主な要因です。
その中、今会合でYCCの更なる修正があるのでは?と一部の金融メディアで取り沙汰されています。具体的には、1.0%の実質的な上限を例えば1.5%に引き上げるというものです。7月会合でYCCの枠組みを残した以上、早々に撤廃することは出来ず、順当な引き上げを行うという予想なのでしょう。
一度撤廃してしまうと再度導入するのは難しいという視点からすれば、仮にズルズルと上限を引き上げることで制度自体が形骸化したとしても、YCCという枠組み自体を残す意味はありそうです。日銀としては「米国の利上げが終了し、利下げ局面に入った際の物価動向を見たい」という気持ちがあり、それを待ち続けている状態だと考えられますので、しばらくYCCの延命措置が続いてもおかしくはないでしょう。
ただ、延命する場合には「先手を打つ」と言いつつも、市場動向に左右されるため実際には対応が後手に回ることになります。その場合、「一体全体、日銀は長期金利をどの水準に抑えたいのか?2%や3%でもYCCをやる意味があるのか?」という疑問について説明がつかないでしょう。
そもそも異次元の金融緩和はデフレ感を払拭するために「国民の気持ち」に影響を与えるための政策(簡単に言えば、社会の雰囲気を変えることが目的)であり、もともと数字の根拠には乏しいという見方もありますが…。
一方で、もし今会合でYCCを撤廃するならば、私見ではむしろ天晴れと感じるほどです。ここで撤廃するということは、7月会合やこの間の見通しが甘かったことを認めることになります。もちろん「日銀の見通しが甘い」という事実は全く褒められたものではありません…が、経済は常に変化し予測が難しい事象ですから、その予想精度をひたすらに問いただしても事態は解決しません。もし見立てが異なるのであれば、早々に軌道修正を図る方が建設的です。日銀執行部の気概を確認する機会にもなります。YCCはそもそも相当に異例の政策であり撤廃自体のハードルはそこまで高くないとみられますが、撤廃するならばその後の方針に注目が集まります。
なお、マイナス金利の解除はまだ早いのではないかと見られていますが、来年になれば早々に議論の的になると目されます。従って、解除の判断基準に関する植田総裁のコメントに注目すると良いでしょう。これまでの発言を見る限り賃上げが重要な判断項目であり、特に来年の春闘で企業がどの程度の賃上げを実施するのか?が大きなポイントになります。その点、昨年はファーストリテイリングが、今年はサントリーが他社に先んじて賃上げを声高にしており、来年の賃上げ機運を高めている印象です。春闘の動向が徐々に明らかになるのは来年1月から2月頃ですので、引き続き動向を確認しておきましょう。
また、10月会合では四半期に一度の展望リポートが公表されます。これは物価見通しなどを示したものです(前回公表は7月会合)。今回のリポートではおそらく物価見通しが引き上げられ、来年の物価が2%を上回るのではないか?と見られています。その場合、2022年、2023年、2024年と3年連続で2%を上回ることになるため、金融政策の正常化に近づくのは間違いありません。YCCの取扱も含めて政策決定の論拠になるデータであることから大きな関心が寄せられます。
メガバンクなどの銀行セクターが金融正常化をどの程度株価に織り込んでいるのかは分かりませんが、業績的には追い風になるでしょう。
🇺🇸FOMC
今回のFOMCでは、フェデラルファンド金利(政策金利)誘導目標が据え置きになるとの予想が支配的であり、会合の結果自体は消化試合になると思います。市場の関心は既に12月会合での利上げ有無に移っており、FOMC終了後に予定されているパウエル議長の会見でも「次回、利上げをするのかしないのか」を探るための質問が記者から多くなされると想定されます。
十中八九、パウエル議長は「データ次第」との姿勢を崩さず、利上げの選択肢を残しておくでしょうから、基本的にはタカ派寄りの発言になるでしょう。一方、12月会合では利上げがあったとしても、2024年の利上げ可能性が相当に低いと感じさせる発言がある場合には、「年内タカ派&来年ハト派」として株式市場は後者を好感する可能性があります。
と…ここまで書きながらも、他人の発言を正確に予測することなど出来ませんので、少なくとも上記2パターンのシナリオを頭の片隅に置きつつ、実際にどのような発言がなされるかウォッチしておくと良いでしょう。私のXでも解説する予定です。
経済指標
🇪🇺ユーロ圏7-9月期GDP速報値
前回は前期比+0.1%の伸び率となり、からくもリセッションを回避しました。今回は前期比+0.0%あるいは▲0.1%と予想されており(媒体によって異なる)、再びマイナス圏への転落が警戒されます。中央銀行に相当するECBは、先週の理事会にて11会合ぶりとなる主要政策金利の据え置きを決定しており、景気減速への警戒感を強めている様相です。GDP発表前日には、欧州の雄であるドイツのGDPが発表されますので、その結果がユーロ圏GDPの予測材料になるでしょう。
🇺🇸雇用統計
前回、非農業部門雇用者数変化が思い掛けず強い結果となり、金融引き締め長期化への懸念が増した雇用統計。今回は非農業部門雇用者数変化が弱含みと予想されているほか、インフレに関係するとされる賃金動向も前年比で伸び率減速が予想されており(前月比ではやや加速)、この通りであればインフレ鈍化を連想させる材料になるでしょう。
前回の非農業部門雇用者数変化では、その中身を見ると多くはパートタイマーの増加によるものであり、数字の印象よりも強いものではありませんでした。労働参加率が上昇しており(既に潜在労働参加率に近しく、今後は急激な改善は見込めないと考えられる)、求人件数は漸減傾向にあることから今後は労働市場が徐々に緩んでいくと想定できます。
雇用統計発表前には、別日にJOLTSやADP雇用統計が予定されており市場が多少なりとも揺れる可能性があります。ただ、本番は雇用統計であることからいずれにしても市場は様子見の状態を崩すことはできず、本格的なポジション取りは金曜になるでしょう。東京市場は金曜が休場ですので、雇用統計前に持ち株を整理したい方は木曜日までに行うように注意してください。
企業決算
🇯🇵トヨタ登場、個人投資家に人気の総合商社も
今週はトヨタが場中決算を行うほか、伊藤忠を除く総合商社大手4社も場中発表を予定しています。いずれも市場の関心は「為替レートの円安修正などによる業績予想の上方修正、配当の増額」であり、期待値が高い状態にあることは間違いありません。Q2決算の数字自体は良くても売られる銘柄(例えば先週のカプコンなど)があるため、期待値を超えてくるかどうかがポイントになります。

トヨタは生産台数が回復する中で前年同期比での伸び率拡大は確定的であり、より重視したいのは対前期比での業績動向でしょう。前期営業利益の大躍進を支えた日本国内の販売状況や、利益面での苦戦がみられる中国事業が焦点です。
総合商社は資源価格や円安の状況から業績上方修正や配当予想増額に期待がかかります。特に、今期配当予想を前期と同額に据え置いている丸紅は、配当増額期待が相対的に高そうです。また、丸紅や三井物産、住友商事は自社株買いの新規設定にも関心が寄せられます(三菱商事は実施中)。
伊藤忠の決算は11月2週目に予定されているため、次回の見通し解説で取り上げます。

また、先週、特に注目を集めたのは中国関連銘柄です。信越化学やキーエンス、オムロンは減益となり、月曜日の動向に注目が集まるほか、同様の傾向にある企業として今週ではファナックや村田製作所が挙げられます。
🇺🇸ビッグテック決算のトリ、Apple
日本時間の金曜午前5時頃にAppleの決算発表が予定されています。市場コンセンサスは前年同期比で増収増益。7-9月期のため、9月に発売されたiPhone 15の影響は部分的にしか反映されませんが、市場の大きな関心はiPhoneに向けられるでしょう。iPhone 15の販売初速はiPhone 14を超えてiPhone 13と同程度になっているとの報道もある一方、中国においてはHUAWEIの新機種にシェアを奪われているという報道もあります。
このところApple株は下げ基調が続いているほか、単純に市場の地合いが悪く、他のビッグテック決算でも市場の反応は渋いです(純粋に評価されたのはAmazonくらい。Microsoftは決算の翌々日に下げている)。私見では、今の状況だと「決算発表で株価急騰!」というイメージがなかなか湧かないのが正直なところですが、iPhoneの販売動向に加えてサービス部門の伸びに注目しています(市場からすっかり忘れられているVision Proにも注目しています)。また、日本時間10月31日午前9時からAppleの新製品発表イベントが予定されており、新たなチップを搭載したMacが発表されるのではないか?と予想されています。

以上が今週の主なイベント見通しでした。よい一週間をお過ごしください🙌
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
