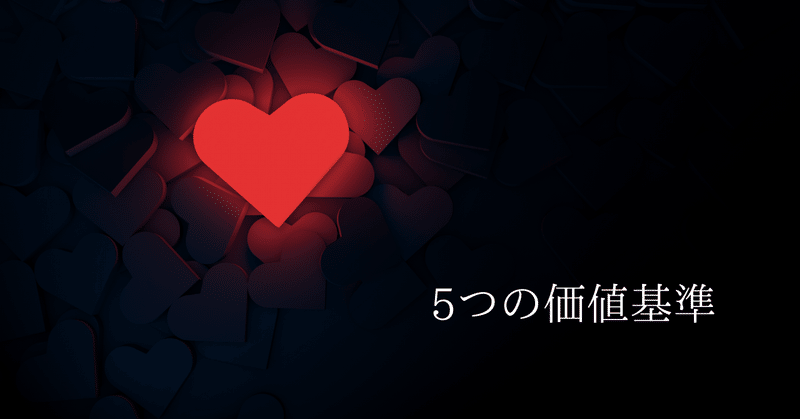
いまさらだけど、Scrumの価値基準に向き合いたくなった
2022年ももうすぐ終わりですね。そんなタイミングで書いています。
最近の自分の傾向として、
Scrumの中心からどんどん外に向かっているような興味の状態から
Scrumの中心にどんどん向かっていくような興味の状態になったので
せっかくなので価値基準から考えてみようと思います。
(そこは「3つの理論」じゃないんかーーーい)
Scrumには「3つの理論」と「5つの価値基準」がある
私は特に違和感なく受け入れていたんですけど・・・
スクラムは、複雑なプロダクトを開発・提供・保守するためのフレームワークである
スクラムとは、複雑な問題に対応する適応型のソリューションを通じて、⼈々、チーム、組織 が価値を⽣み出すための軽量級フレームワークである
"フレームワーク"ってなんだか使っておけば良さそうなイメージではないですか?
なのに、そこに理論と価値基準という抽象度の高い概念が入れ込んである・・・。
枠組みとして「こうやっておけばいいよ」と書いてくれたらいいのに・・・。
となる気がします。
■「This Is Lean」に見る、価値・原則が必要な意味
この書籍の中で大庭さんが伝えていることは
抽象度が極めて高い”価値観”を体現するために”原則”がある
ちょっとだけ具象度が上がったけれども・・・
まだまだ抽象度の高い”原則”を行動や仕組みに落とすために”メソッド”がある
というものです。

■「エクストリームプログラミング」に見る、価値・原則が必要な意味
この書籍中では
価値とプラクティスのギャップを埋めるのが”原則”
だと言われています。

■ザクっと要点
「This is lean」にしても「エクストリームプログラミング」にしても、具体例もなく概念だけバスっと書いてしまいましたが・・・。
つまりは
Scrumにおいても、
スクラムの理論である「経験主義」「リーン思考」と
その柱である「透明性」「検査」「適応」
を具体的な行動と仕組みに落とすために
各種のイベントやプラクティスがあるのではないかと思うわけです。
「価値基準」を見つめ直す
上記のことから
「なんちゃってアジャイル/スクラム」や「ぬるいチーム」は価値・原則を体現できてないからこそ、そのようなレッテルを貼られてしまうのではないかと思ったわけです。
今回は、Scrumの価値基準を中心に考えていきます。
価値基準があることによる良さと、その価値基準が蔑ろにされるとどのようなことが起こるのか考察します。
せっかくなので、日本語版のScrumの価値基準を貼っておきます!

5つの価値基準
■確約(Commitment)
スクラムチームは、ゴールを達成し、お互いにサポートすることを確約する
正しく運用されると、スクラムチーム(PO/SM/Dev)がゴール達成に向けてチームで協力している姿が想像できる気がします。
しかし、強すぎる納期へのCommitmentは自分たちを苦しめる気がします。
次第にチームよりも部分最適な自分の作業を終わらせることを優先していくかもしれません。
逆に弱すぎるCommitmentは、いつまでも何も達成せずに平気ないわゆる”ぬるいチーム”に成り下がる気がします。
技術に詳しくないステークホルダーやPOに対して、ぬるぬると開発者が生活するような「アドバース・セレクション問題」のようなことが起こりうる・・・
■集中(Focus)
スクラムチーム は、ゴールに向けて可能な限り進捗できるように、スプリントの作業に集中する
正しく運用されると、スプリント中にフロー状態にあるようなチームの姿が想像できる気がします。
しかし、強すぎるFocusは予定外を一切受け付けないような頑なさを感じます。スクラムチームが集中するために孤立するようなイメージがあります。
逆に、弱いFocusは仕事が手につかず、自分たちでコントロールできることがあまりにも少ない疲弊したチームになっていく気がします。
集中できない(マルチタスク)ことによる弊害はここに・・・
■公開(Openness)
スクラムチ ームとステークホルダーは、作業や課題を公開する
正しく運用されると、スクラムチームとステークホルダーが1つになり、価値創出のためにお互いが納得している姿が想像できる気がします。
強すぎるとかあるのかな・・・。
強すぎるをこの流れで書くとすると・・・。
公開を強要され、心理的安全性が下がり始めるのかもしれませんね・・・。
弱いOpennessは、何をやっているのかわからず、顧客とベンダーのような関係になる可能性がある気がします。
■尊敬(Respect)
スクラムチームのメンバーは、お互いに 能⼒のある独⽴した個⼈として尊敬し、⼀緒に働く⼈たちからも同じように尊敬される
この価値基準は、チームの幸福度に影響する気がします。
自己効用感などの社会的欲求が満たされる気がします。
Respectをしすぎることもよくない側面があります。
そこに、迎合やその人の意見を汲み取りすぎて自分の意見の主張ができません。
Respectがなさすぎても意見が出てこなくなり、チームとしての協業は立ち行かなくなってきます。どちらの意見が勝っているのかが焦点になり、正しく価値を追求することがおろそかになります。
■勇気(Courage)
スク ラムチームのメンバーは、正しいことをする勇気や困難な問題に取り組む勇気を持つ
VUCAが当たり前の時代において、様々な要因からくる困難な状況に対して正しく向き合うチームの姿がある気がします。
Courage(勇敢さ Brave)とは強すぎると、無謀で向こう見ずな状態(Reckless)になるかもしれません。いきすぎた勇気は人を傷つけることもあります。尊敬と共にでる必要があります。
Courageの少ないチームは、自分の手の届く範囲の意見やアイディアや挑戦を選ぶ気がします。
いわゆる、コンフォートゾーンから抜け出さずに成長する機会を逃していくような状態です。
まとめ
ダラダラと書いていきましたが・・・。
どんなに、イベントやプラクティスを知っていても価値を生まない時があります。
それは、スクラムが経験主義であり、実践を大切にしているからです。
スクラムの価値観に真摯に向き合わずに、単なるフレームワークとしてスクラムを使ってしまうと・・・それは「なんちゃって」と言われる可能性が出てきてしまいます。
原理原則・価値基準を実践するためのメソッドやアクティビティとして、
価値・原則に寄り添えているかに対しても透明性・検査・適用を持って日々活動をしていく必要がありそうです。
