
ウォーズ五段までの道のり(級位者編)
先日、本当にありがたいことにウォーズでオール五段になることができました!
(普通は10分が五段なら、3分や10秒は六段くらいかと思いますが、やっぱり早指しは苦手です)
長い間、10分五段は目標にしていましたので、ものすごい達成感がありますが、現在は立派に沼生活をしております(笑)
そこで今回から備忘録も兼ねて、自分が今までどのような勉強をしてきたのかと、もっとこんな勉強をしていればよかったなーということについて書いていきたいと思います。
級位者の頃の勉強
私は子供のころから観る将だったので、指す将になったのは5~6年ほど前になります。逆に観る将歴は約20年ほどでしょうか。
観るだけではありましたが、駒の動かし方や囲いの名前などは覚えることができました。
つまり、何もかも手探り状態の初心者ではなく、少し基礎のあった状態からの指す将スタートでした。
さて、級位者の頃に勉強していた主な内容は以下の4つです。
①詰将棋
②手筋の勉強
③観戦(可能なら棋譜並べ)
④対局
ひとつずつ解説していきます。
①詰将棋
当たり前ですが、詰将棋は大切です。
というのも将棋は最後には相手玉を詰まさなければいけません。
どんなに優勢を築けても、相手玉を逃してしまっては何の意味もありません。詰将棋は大切なので、必ずやりましょう。
私がやったことは、3手詰ハンドブック1冊、5手詰ハンドブック1冊を繰り返し繰り返し解きました。見た瞬間に解けてしまうくらい繰り返すことが重要です。
ここはかなり賛否両論あるところだと思います。ただ誤解しないでいただきたいのは、難しめの詰将棋をしっかり考えることに意味がないということではありません。あくまで級位者のときは基礎トレーニングが大切だということです。
個人的な感覚ですが、九九をイメージしていただければと思います。皆さんも小学生のときに「3×1=3、3×2=6………」と何度も暗唱して覚えたでしょう。
ちゃんと頭で計算できることは素晴らしいことではありますが、九九のような基礎については何も考えなくてもスラスラと言えるように覚えてしまったほうが早いです。それと同じように3手詰や5手詰くらいなら、何も考えなくても詰み筋が頭の中に浮かぶことが重要です。
また、声を大にして言いたいのですが、本当に初心者の方や、3手詰に少し苦戦している方はちゃんと1手詰からやりましょう!
どんなに長い詰将棋も最後の1手が指せなければいけません。1手詰を馬鹿にする者は1手詰に泣きます。
※ハンドブックシリーズはKindle版はないと思います。どうしてもKindle版がいいという方は高橋道雄先生の「3手詰将棋」「5手詰将棋」もおすすめです。
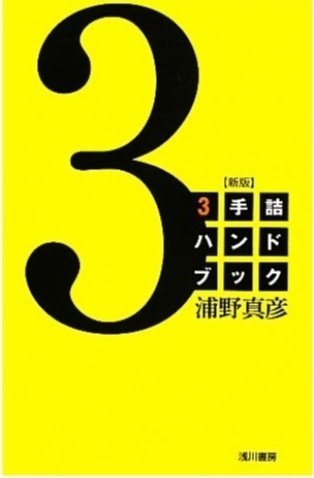

②手筋の勉強
手筋の勉強はかなり早めにしておいて損はありません。
皆さんも経験があると思いますが、将棋の強い方と対局すると、相手に合わせて自然な手を指していたはずなのにどんどん劣勢になっていきます。
これは強い方ほど対局の中で手筋を活かしているからです。
しっかりと手筋をマスターすることで、かなり効率的に実力をUPさせることができます。
おすすめの棋書は
「羽生の法則1 歩・金銀の手筋」
「羽生の法則2 玉桂香・飛角の手筋」
の2冊です。
駒の特性を活かした手筋が収録されていますので、かなり分かりやすいと思います。これも何度も繰り返し解いて、身体に覚え込ませます。
手筋においては特に「歩」の使い方が大切です。将棋の駒の半分は歩なので、歩をどう使えるかが勝敗を分けると言っても過言ではありません。

③観戦(可能なら棋譜並べ)
次に観戦です。
将棋が上手くなるには、上手い人の真似をするのが手っ取り早いと思います。
個人的にはプロの棋譜はかなり難しいと思うので、級位者の方は初段~三段くらいの方の将棋をYoutube等で観ることをおすすめします。
私も将棋系Youtuberのクロノさんの動画をよく観ていました。内容としては自分が指す戦型と同じものを観たほうが効率はいいでしょう。
観戦する際には、自分だったらどう指すかと考えながら観るようにしましょう!
※別にプロの棋譜を楽しむをことを否定はしていません。あくまで上達にフォーカスした場合には自分より少し上手い方の将棋を観たほうがよいのではないかということです。
また、私の勝手なイメージですが、棋譜並べはかなり苦痛だという方も多いような気がしています。私は好きだったので、観戦した棋譜を実際に並べたりしていましたが、棋譜並べが苦手な方は無理をしないほうが無難だと思います。余裕があったら並べてみようかなくらいのほうが気楽で長続きすると思います。
④対局
これは皆さん当たり前のようにやられていると思いますが、やはり実戦は大切です。ただ、上達という観点では「ある程度戦型を固定」したほうが効率はいいと思います。
私も昔は四間飛車党でしたので、対抗形なら四間飛車、相振りなら向かい飛車をよく指していました。
また、実戦の後には必ず振り返りを行いましょう。
最新のソフトで振り返りを行ってもよろしいですが、あまりに強すぎるので、ぴよ将棋くらいでも全然問題ありません。
もし振り返りが苦痛なら、一局の中でほんの1つでもいいので、「ここではこう指したけど、こういう手を指したほうがよかったのか~」と反省し次に活かすようにしてください。
個人的な意見ですが、上達のためにはある程度持ち時間がある対局のほうがよろしいと思います。ウォーズなら3分や10秒は止めて、可能な限り10分を指したほうがしっかりと考えることができます。
まとめ
以上が私が級位者の頃に行っていた主な勉強です。
個人的には「繰り返すこと」に苦痛を感じない体質でしたので、繰り返しというのがひとつのポイントになってしまってますね(笑)
楽しく将棋を続けることが何よりも大切ですので、楽しくない勉強なら止めてみるというのも一つの手です。
「序盤の勉強は棋書でしなくていいの?」という質問が飛んできそうですが、なかなか級位者の頃に棋書で勉強するのはかなりハードルが高いのではないかなと思います。もし詳しく序盤を勉強したい場合には、一問一答形式で序盤を勉強できる棋書(四間飛車でいえば「四間飛車を指しこなす本」)がおすすめです。私も最初はこれで四間飛車を勉強しました。
棋書での勉強のハードルが高い方は、やはりYoutube等の動画で勉強するほうがよろしいと思います。

上記はあくまで私個人が行ってきたことですので、参考にしつつ自分なりの上達法を考えていただければ幸いです。
次は初段~二段編を書きたいと思います。
(消えないでくれ俺のモチベーション!笑)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
