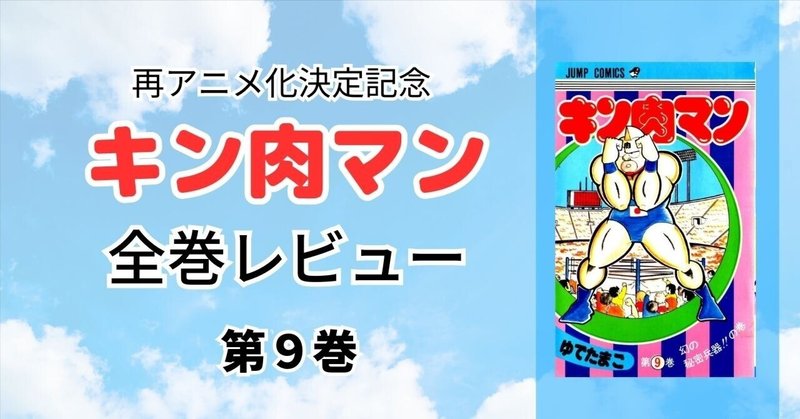
第9巻:幻の秘密兵器!!の巻
第9巻データ・アナリティクス
危険水域からのV字回復・前夜

「掲載順=人気」とは一概に言えないが、人気を測るバロメータのひとつとして参照する。
1号あたりの漫画作品の掲載本数は15〜17本。
単行本9巻の発行日は1982年7月15日。
『キン肉マン』人気の推移は、大雑把に言えば、「アメリカ遠征編」で低迷し、「超人オリンピック ザ・ビッグファイト編」の決勝戦で盛り返し、続く「7人の悪魔超人編」で不動のものとなる……というものだが、掲載順の動向は必ずしも人気推移と同期しているわけではなく、少し遅れて反映される。掲載順の平均値がもっとも低いのはこの第9巻であり、じつは「アメリカ遠征編」よりも低い。
36〜38号にかけて3週連続で14番手となっているが、この3週のあいだに『キン肉マン』より掲載順が後ろだったのは、『スーパーポリス』(原作:篝一人、作画:谷村ひとし)、『ガッツトライ』(田中つかさ)、『フォーエバー神児くん』(えだまかつゆき)の3作品。それぞれの掲載順は以下のとおりである。
・『スーパーポリス』:「15,16,15」40号で終了
・『ガッツトライ』:「16,15,17」38号で終了
・『フォーエバー神児くん』:「17,17,16」46号で終了
後ろ3つがほどなくして連載終了になっていることを考えると、次の改編期には連載可否が判断された可能性は高い。
入れ替わりで始まった新連載陣は、40号『キャッツ♥アイ』(北条司)、41号『コブラ(※連載再開)』(寺沢武一)、45号『ストップ!!ひばりくん!』(江口寿史)、46号『ブラックエンジェルズ』(平松伸二)と大ヒット作が続くので、もし「キン肉マンvsウォーズマン」戦での人気回復がなければ……と考えると、連載終了もありえた話だろう。
危険水域からV字回復を成し遂げたのだから、『キン肉マン』は作品そのものが「奇跡の逆転ファイター」だったと言える。
第9巻収録話の連載期間の出来事
およそ5年弱連載が続いた『リングにかけろ』(車田正美)が44号で連載終了を迎えた。車田正美は愛読者賞で描いた『実録!神輪会』の第2弾「リングにこけろ」(1980年18号掲載)の冒頭で、「わたしの人気のおかげで入口の階段を改装できたわたしの集英社…」「“リンかけ”人気で300万部突破できたアホばっかりの少年ジャンプ編集部」と諧謔的にネタにしているが、事実、『リングにかけろ』が「少年ジャンプ」躍進を支えた大看板であったのは間違いない。そうした功労者に報いるためか、『リングにかけろ』の最終回は巻頭カラーであった。これは異例のことである。
ストーリー漫画としての『キン肉マン』の方向性
キン肉マン=マスクマンという設定
「幻の秘密兵器!!の巻」では、今はもう閉園してしまった豊島園(正確には1980年から「としまえん」表記)プールで超人オリンピック決勝戦の調印式が行われる。この回は1981年33号(7月27日発行)掲載なので、学生はちょうど夏休み直前だからプールが舞台、という季節感が漂う。
この回では、突如として「キン肉マン=マスクマン」との設定が明かされ、決勝の「キン肉マンvsウォーズマン」戦は覆面はぎデスマッチ(マスカラ・コントラ・マスカラ)になる。
このマスクマン設定には、タイガーマスクの影響を抜きには語れまい。初代タイガーマスク(佐山聡)のデビューは1981年4月23日。蔵前国技館でのダイナマイト・キッド戦である。
このタイガーマスクのギミックは、アニメ『タイガーマスク二世』とのタイアップだった。アニメ『タイガーマスク二世』はテレビ朝日系列で1981年4月20日〜1982年1月18日にかけて月曜19時〜19時30分枠で放映された。
もともとの『タイガーマスク』(原作:梶原一騎・作画:辻なおき)は1969年から1971年にかけて「ぼくら」「週刊ぼくらマガジン」「少年マガジン」(いずれも講談社)に連載された漫画作品で、1969〜1971年に日本テレビでアニメ化され、「プロレスを題材にした漫画・アニメといえば『タイガーマスク』」といえるほど、世間に広く認知されていた作品である。
梶原一騎と新間寿(新日本プロレスの営業本部長)は親交があり、雑談のなかから、タイガーマスクを現実のレスラーとしてデビューさせる企画案が浮上したという。
この80年前後は『仮面ライダー(スカイライダー)』(1979〜1980年)や『サイボーグ009』(1979〜1980年)、『ウルトラマン80』(1980〜1981年)、『鉄腕アトム』(1980〜1981年)、『鉄人28号(太陽の使者)』(1980〜1981年)のように、過去のヒット・シリーズが作品展開を再始動するのが盛り上がった時期であった。こうした時代背景も、テレビ朝日がアニメ『タイガーマスク二世』にGOサインを出す追い風になったと思われる。
アニメ化と同時に漫画版(原作:梶原一騎、作画:宮田淳一)もスタートし、少年画報社「月刊少年ポピー」(1980年8月22日号〜1981年6月27日号)と講談社「増刊少年マガジン」(1981年9月11日号〜1983年1月6日号)に連載された。
アニメ『タイガーマスク二世』の放映開始は4月20日(月曜)なので、その3日後の23日(木曜)に新日本プロレスのリングでタイガーマスクがデビューしたことになる。ただし、新日本プロレスを中継するテレビ朝日の番組「ワールドプロレスリング」でこのデビュー戦が放送されたのは、さらに8日後の5月1日であった。
裏番組が『あしたのジョー2』(日本テレビ系列)だったせいか、アニメ『タイガーマスク二世』の視聴率は振るわず、33話で打ち切りとなってしまったが、レスラーとしてのタイガーマスクは「四次元殺法」と呼ばれる空中技を武器に大ブレイクし、「ワールドプロレスリング」は視聴率が毎週25%を超えるほどになった。昭和のプロレスブームは、タイガーマスクによって牽引されたものであったのは間違いない。
こうしたタイガーマスクブームの初期段階に、「キン肉マン=マスクマン」設定が出てきたのである。
なお、原作者の梶原一騎は、1983年5月25日に「月刊少年マガジン」副編集長への傷害事件で逮捕される。その後、余罪を追及され、第一線から姿を消す。この事件を受けてレスラーのタイガーマスクの改名騒動があり、しかしそれとは別に目標とするレスリングの方向性の違いから、佐山聡は1983年8月4日の寺西勇戦を最後に、新日本プロレスとテレビ朝日に契約解除通告書を送付し、プロレスからの引退を宣言してしまう。
この頃には『キン肉マン』はアニメ化して大人気となっており、ポスト・タイガーマスクとして『キン肉マン』に白羽の矢が立った。
80年代初期、新日本のリングではタイガーマスクが一大ブームを巻き起こしたが、内部のいざこざから1983年には引退してしまっていた。新日本はその後釜として、人気絶頂だったボクたちの『キン肉マン』に目をつけたのである。
ボクたちは断った。
どうせ出すなら、大好きな馬場の全日本のほうがいいと思っていたからだ。
だが馬場は、ギャグテイストの『キン肉マン』に難色を示したという。結局、『キン肉マン』を諦めた新日本プロレスでは、新しいマスクマンとしてストロング・マシーン(平田淳二)をデビューさせ、タイガーマスクは権利関係をクリアしたうえで、1984年に全日本プロレスで二代目(三沢光晴)がリングに上がることになる。
ちなみに、新日本プロレスでの初代タイガーマスクは、マスカラ・コントラ・マスカラを行っており、その最初の相手はマスク・ド・ハリケーン(1981年10月8日/蔵前国技館)。この当時は「敗者マスク剥ぎマッチ」と銘打たれ、試合はタイガーマスクが完勝した。「キン肉マンvsウォーズマン」の覆面はぎデスマッチは、それより3カ月も前に行われたことになる。
ビビンバの気づき
のちにキン肉マンの妃となるビビンバは、この時点ではまだ正式な妻ではなく、立場的には曖昧であったが、「超人オリンピック ザ・ビッグファイト編」ではキン肉大王やミートくんらと行動を共にしているので、“暗黙の了解”を得た存在であったともいえる。少し先の話になるが、キン肉マンがバッファローマンと戦っている最中には、キン肉大王はビビンバに「お前もキン肉族の女なら だまってスグルの勝利を信じるんじゃ!!」(「パワーの限界!?の巻」第13巻収録)と諭すシーンがあり、本来はホルモン族のビビンバをキン肉族扱いしているあたりからも、この時期のビビンバがスグルと婚約状態にあったとも推測できる。
ビビンバは「魔性のリング!!の巻」(第8巻収録)でウォーズマンの心根が本当は優しいことを見抜き、「幻の秘密兵器!!の巻」の調印式ではウォーズマンサイドにつく。寝返ったように見せて、ウォーズマンにベアークローを使わないように要請したり、ウォーズマンとバラクーダ(=ロビンマスク)のパートナーシップに亀裂が入るように働きかけたりする。
これは物語のロールにおいては⑥トリックスターの役割を担っており、「グレートマザー」や「誘惑する異性」とは異なる。ただ、誰も気づかないようなウォーズマンの心根の優しさに、いち早く気づくあたりに、のちに「グレートマザー」の役割を担う素養を見せている。
倒した敵は、なぜ味方になるのか?
①主人公の⑤好敵手として登場したウォーズマンは、キン肉マンとの死闘を演じた結果、次シリーズの「7人の悪魔超人編」では正義超人の仲間になる。このような「倒した相手を味方にし、より強い相手に立ち向かっていく」構図は、俗に「トーナメントバトル」と呼ばれ、「少年ジャンプ」のバトル漫画のお家芸とされる。
一般的なバトル漫画/喧嘩漫画の場合、勝敗を決めるルールは存在しないので、本人が負けを認めなければ決着はつかない。しかし、それでは不毛な報復合戦が続くことになってしまうので、物語を前に進めるには、読者にわかるかたちで決着をつける必要がある。
どうすればいいか。
「この人には敵わない」「もう逆らいません」と、相手が心服すればいい。そのためには主人公が「度量を示す」とか「男気を見せる」ことが大事である。つまりバトル漫画における戦いの本質は、力比べではなく、器量比べにほかならない。主人公のバトルの強さは、さほど重要ではないのだ。
このような構造に立脚しているからこそ、少年漫画では、負けた相手が仲間になるという図式が成り立つ。
『キン肉マン』における超人プロレスの場合、デスマッチルールが採用されているので、明確に勝敗が決着するものの、このウォーズマン戦からは「ただ勝てばいい」とは異なるレイヤーに移行している。
この構図の最初の例は、前回の超人オリンピックにおける「キン肉マンvsラーメンマン」戦であった。しかしながら、「心服させる」要素がはっきりとは描かれていないので、なぜラーメンマンが「選手入場の巻」(第4巻収録)で「ほこりたいんだよォ〜〜〜っ キン肉マンとの戦いを〜〜っ」と血の涙を流したのか、いまひとつ読者の理解が追いつかない。キン肉マンとの戦いには、当事者にしかわからない、何か感ずるところがあったのだろう、と。
しかし、このウォーズマン戦の場合、ベアークローの上にウォーズマンを叩きつけて再起不能にするように「おとせ」コールが場内に響き、ビビンバも「それがウォーズマンのため」と涙ながらに訴えるが、キン肉マンは以下のように応じる。
わたしが残虐ファイトで対抗してどうなる それではいつまでたっても 泥試合だ…
できることならクリーンファイトで戦いたい!
試合に勝利した結果、不毛な報復合戦になっては意味がない。キン肉マンは自分のファイトスタイルの方針を明確に定義し、それに感化されたウォーズマンもクリーンファイトに目覚める、という一連のシークエンスによって「心服させる」要素が描かれている。
戦いを通じて心を通わせる……という、『キン肉マン』の最大のテーマが読者にわかるかたちではじめて描写されたのであり、ここにおいて本作品は、ストーリー漫画として語るべきテーマを持ち得たのである。
それは「友情」だ。
このテーマ性と方法論が確立する以前に描かれたロビンマスクとのグランド・キャニオンでのリマッチでは、ロビンマスクがキン肉マンの友情に涙するシーンはあるものの、完全決着できなかったせいか、心服するまでには至っていない。そのため、「不毛な報復」として、キン肉マンへの復讐を誓うバラクーダなるキャラクターが誕生した。
この失敗ケースを踏まえたうえでウォーズマンとの決勝戦があると考えると、『キン肉マン』という作品がストーリー漫画化するうえで大きな役割を果たしたのが「ロビンマスクの失敗」であったといえよう。
なお、「天の声!?の巻」では、植物超人となったラーメンマンがキン肉マンに心の声で語りかけ、再び「火事場のクソ力」のワードがフィーチャーされる。「キン肉マンvsウルフマン」戦でもミートくんが「火事場のクソ力」の語句を用いている(「土俵際にかけろ!!の巻」第8巻収録)し、意味自体は明示的なものであったが、作中で初めてその言葉を使った(「奇跡のホールドの巻」第4巻収録)ラーメンマンから再び発せられることにより、何か特別な意味を帯びたミステリアスな響きが付与されている。
「友情」と「火事場のクソ力」、『キン肉マン』を支える重要な要素が定義づけられたのがこの決勝戦であり、いわばストーリー漫画としての方向性を定める重要な一戦であったといえる。
キン肉マンの新必殺技と、白黒反転の演出
「キン肉マンvsウォーズマン」戦では、ウォーズマンがキン肉マンを場外まで放り投げたり、場外のキン肉マンにウォーズマンがプランチャ(作中ではブランチャー表記)を仕掛けたりと、前回超人オリンピック決勝でのロビンマスク戦をなぞるような試合展開が描かれているので、比較してみると面白い。
また、「タイム・リミット30分!!の巻」では、キン肉マンの代名詞ともいえる必殺技「キン肉バスター」が初お披露目となる。「48の殺人技」のなかでは、正式に技名があるものとしては「風林火山」以来であり、「風林火山」の初出が「超人太平洋戦争終結の巻」(1980年30号、第5巻収録)なので、1年以上ぶりとなる「48の殺人技」であった。
キン肉マンに必殺技が備わったことで、以降のシリーズでも話を展開しやすくなったものと思われる。
なお、「タイム・リミット30分!!の巻」では、ウォーズマンにキン肉バスターを決めたコマ(「ガキ」の効果音のあるコマ)は白黒反転されていた。「アメリカ遠征編」におけるアメコミ風劇画路線を脱したあと、『キン肉マン』の作画は主線が太くなっていき、であればこそ白黒反転をしても主線がツブれることなく明確に視認できるため、こうした効果的な演出が可能になっている。
このような白黒反転は印刷所で指定するものなので、おそらく生原稿は通常の作画と同様であると推測される。コミックスでは旧版・新装版ともに雑誌掲載時の演出(白黒反転)が施されていないのは、元原稿をそのまま掲載しているからだろう。デジタル入稿が可能になった現在であれば、雑誌掲載時の演出を再現するのも難しくないと思うので、カラー(4色および2色)原稿ともども、このような演出部分も再現してほしいところだ。
『エレファント・マン』の影響?
1981年43号(10月5日発行)に掲載された「勝利をわが手に!!の巻」では、試合後にウォーズマンの過去が明かされる。ロボ超人のウォーズマンはズタ袋をかぶって素顔を隠して生きてきたのだが、その来し方は映画『エレファント・マン』からの着想ではないかと推測する。
デヴィッド・リンチ監督の映画『エレファント・マン』の日本公開は1981年5月23日。この年の国内の映画興行収入は24.5億円で、『007 ユア・アイズ・オンリー』を抑えてランキング1位になった。
日本公開日から近いところでは、1981年29号(6月29日発行)に掲載された「魔性のリング!!の巻」(第8巻収録)において、「ラーメンマンvsウォーズマン」戦の前、包帯姿のラーメンマンが棺桶を担いで入場する際に、キン肉マンが「よっ! ミイラ男 エレファントマン!」とヤジを飛ばしているシーンが見受けられるので、作者が『エレファント・マン』を意識していたのは間違いないはずだ。
映画『エレファント・マン』は、外見のせいでサーカスの見せ物にされていた青年ジョン・メリックの生涯を描いた物語である。ジョンの外見に興味を抱いた外科医のトリーヴスは、サーカスからジョンを保護する。ジョンはトリーヴス医師との交流により、閉ざしていた心を少しずつ開いていき、社会性を身につける。また、舞台女優のケンドールは、ジョンが優しい心の持ち主であることを見抜く。
しかし、ジョンを商売道具にしていた興行師のバイツがジョンを誘拐して、サーカスに連れ戻してしまうのであった。
それぞれの役どころを『キン肉マン』に当てはめると、興行師バイツはバラクーダ、ケンドール夫人はビビンバ、ジョン(=エレファントマン)はウォーズマンとなる。映画『エレファント・マン』(および興行師バイツ)の影響があったとするならば、この「超人オリンピック ザ・ビッグファイト編」におけるバラクーダ(=ロビンマスク)が過度に嗜虐的に描かれるのも納得がいくのだが、はたしてどうだろうか。
よろしければサポートのほど、よろしくお願いします。
