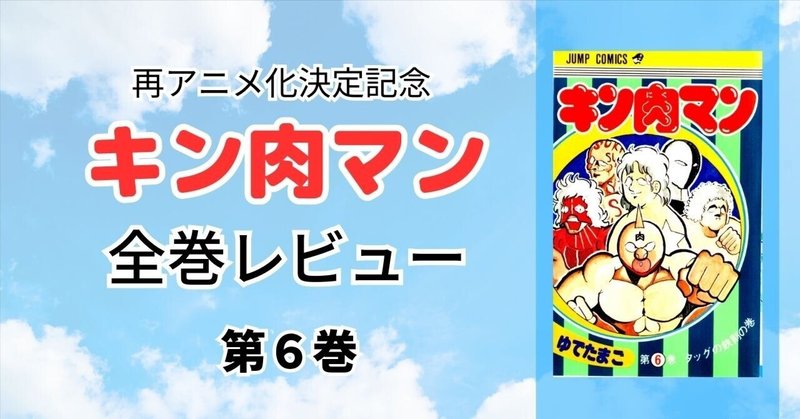
第6巻:タッグの鉄則の巻
第6巻データ・アナリティクス
依然として「ギャグ漫画枠」

「掲載順=人気」とは一概に言えないが、人気を測るバロメータのひとつとして参照する。
1号あたりの漫画の掲載本数は16〜18本。
単行本6巻の発行日は1981年4月15日。
第6巻は「アメリカ遠征編」の後半パートにあたる。
前回引用したように、このシリーズは「人気の急落具合は半端ではなかった」との作者の証言があるが、上記の第6巻収録話のデータを見る限り、まだ「人気の急落」が掲載順には反映されていない模様。46号から49号まで4号連続で2ケタ順なのは従前には見られなかったことだが、全体的な掲載順はまだ高い。「アメリカ遠征編」クライマックスの50〜52号は、3号連続で掲載順2番、2色カラーだった。
この頃の『キン肉マン』はまだギャグ路線の名残で1話13ページのままである。45号の表紙は「ギャグ陣のバトルロイヤルちゃ!」と題し『Dr.スランプ』(鳥山明)、『こちら葛飾区亀有公園前派出所』(秋本治)、『すすめ!!パイレーツ』(江口寿史)とともに『キン肉マン』が描かれているので、いわば「ギャグ漫画大集合」的なテーマ性がうかがえる。このことからも、編集部では「『キン肉マン』=ギャグ漫画」の認識がまだ変わっていないことがわかるだろう。
こうしたギャグ漫画枠の集合表紙は定期的に行われ、その際にはギャグ漫画枠の作品が上位に掲載される。
第6巻収録話の連載期間の出来事
この時期は『Dr.スランプ』人気が圧倒的で、40号から47号まで8週連続で「ほよよカードスペシャル」という本作のカラーカードが付録でついた。だが『Dr.スランプ』の人気はまだ序章で、翌年のアニメ化でさらに拍車がかかり、社会現象にまで発展する。
41号からは『3年奇面組』の連載がスタート。のちに劇中の主人公たちの高校進学を機に『ハイスクール!奇面組』と改題し、80年代の「少年ジャンプ」メディアミックス戦略の一翼を担うヒット作品へと成長していく。
なお、1981年1号では荒木利之が読み切り『武装ポーカー』でデビューしている。作者はのちに「荒木飛呂彦」と改名し、『ジョジョの奇妙な冒険』を生み出す。
「行きて帰りし物語」の構造
通過儀礼を構成する三幕
本稿では、「アメリカ遠征編」とは一体なんだったのか、あらためて省察したい。
少年漫画において、俗に「王道」と呼ばれる連載型のストーリー漫画は、主人公が冒険の旅に出るのが常だ。そして、自分の知らない世界に行き、自分を知っている人が誰も居ない場所で友人や知人をつくり、目的を成し遂げて、帰る。「行きて帰りし物語」の構造である。この物語構造は、神話の英雄譚などで古来より用いられてきた。
映画ではよく「三幕構成」という言葉が使われるが、この「生きて帰りし物語」も同様で、内容を分解すると「Ⅰ:旅立ち」「Ⅱ:冒険」「Ⅲ:帰還」の3パートにわかれる。
主人公の冒険の目的は、何でもいい。敵を倒す、お宝を探す、指輪を捨てに行く、ドラゴンボールを集める、海賊王に俺はなる、スポーツの大会に優勝する、などなど……。そして、その過程において、主人公の目的達成を阻害する敵対者が出てくる。
主人公が目的を達成後、元の世界に帰ってきて日常を回復すると、妻をめとったり、出世をしたり、旅立つ前より自分の立場がよくなって、元の共同体に迎え入れられることになる。無名だった主人公が、英雄になるわけだ。「桃太郎」や「一寸法師」はその典型例といえる。
つまりこの定型は、みずからが所属する共同体の構成員(=大人)として迎え入れられるための通過儀礼を意味する。「生まれ育った故郷を後にして冒険に旅立つ」という行いは、みずからを守ってくれていた環境を離れることであり、すなわち親の庇護下を離れることを意味しており、文学的な意味においての「父殺し」が旅の本来的な目的といえるだろう。子供としての自分と決別し、大人として社会の構成員になるのだ。
要するに「少年が大人になる物語」なのである。
少年漫画はこの構造を繰り返しており、その成長過程をどう描くかにかかっている。それが時代に即したものであれば、その時々の読者に受け入れられる。それゆえに、少年漫画は、つねに現代性を反映したものとなる。
また、この構造から逸脱した箇所にこそ、その作品や作者の「いびつさ」とか「個性」「オリジナリティ」が読み取れる。
「Ⅰ:旅立ち」・主人公の境遇
では三幕をもう少し具体的に見ていこう。それに際し、登場人物たちが作中で担う役割(ロール)についても同時に説明していく。この物語構造が「定型」であることを示す意味でも、他作品(代表的なビルドゥングスロマン)を引き合いに出していく点についても了承してほしい。

「Ⅰ:旅立ち」において重要なのは、①主人公の境遇である。少年漫画の①主人公には、読者が自分を投影しやすいキャラクターが望ましい。想定読者層と同世代が望ましく、『ドラゴンボール』の孫悟空は12歳である(最初は14歳を自称しているが、数の数え方を間違っていたので、のちに12歳であることが判明する)。『HUNTER×HUNTER』(冨樫義博)のゴンも物語冒頭では12歳。「少年ジャンプ」の想定読者層を意識した年齢設定になっている。
キン肉マンは1960年4月1日生まれなので、連載開始時点では20歳。少年漫画の①主人公としてはやや年長だが、これは作者のゆでたまご(嶋田隆司、中井義則)と同学年、ということだろう。
この物語構造では、冒頭、①主人公の恵まれない境遇が語られる。もしくは、平穏な日常が破壊され、恵まれない境遇に陥ってしまう。こうした状況から脱却するために、①主人公は冒険の旅に出る。
映画『スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望』(1977年)を例にすると、ルーク・スカイウォーカーは砂漠の惑星タトゥイーンで農作業の手伝いをしていて、彼は士官学校に行くつもりだったが、育ての親である叔父夫婦に反対され、途方に暮れて夕陽が落ちるのを眺める……というところから物語の幕が開く。自分はこのまま何もない田舎に骨を埋めることになるのだろうか……と。とても印象深いシーンであり、『スター・ウォーズ エピソード7/フォースの覚醒』(2015年)でもセルフ・オマージュされた。
『ドラゴンボール』の孫悟空は、都から数千キロ離れた山奥に、ひとりで暮らしている。育ての親のじいちゃん(孫悟飯)と死に別れ、平穏といえば平穏な、しかし外界から隔絶された世界で生活していたところにブルマがやってくる。平穏な日常に闖入者が訪れ、そこから悟空はドラゴンボールを探す旅に出る。
『キン肉マン』の場合、連載開始当初は1話完結型のギャグ漫画なので、「行きて帰りし物語」のような物語構造をとっていない。ストーリー漫画へと移行するには、“大きな物語”を動かす装置を用意する必要がある。そのための準備段階が、この「アメリカ遠征編」であった。
超人オリンピックで優勝したキン肉マンは、全世界サーキット(世界タイトル防衛旅行)に出る。日本で怪獣退治をしながら馬鹿騒ぎをしていた日常は失われ、チャンピオンとしての責務を背負わされるのだ。
つまり「アメリカ遠征編」では、ギャグ漫画の主人公だったスグルを、ビルドゥングスロマンの①主人公へと再定義するために、「冒険の旅に出る」というプロセスを踏ませる必要があったわけである。
「Ⅰ:旅立ち」・チカラの獲得と②付与者
①主人公は冒険に出る使命を受けた際に、いったんは拒むこともあるが、使命を受け入れることで、超自然的なチカラを発現できるようになる。もしくは、あらかじめ使命に耐えうるチカラを授けられていることに、第三者によって気付かされる。このチカラを与える存在を、②付与者とする。
②付与者は矮小な姿で描かれる傾向にあり、老人、老婆といった姿をとることが多い。『ドラゴンボール』では、①主人公・孫悟空に付与されるチカラは、じいちゃん(孫悟飯)に鍛えられた体術である。②付与者は孫悟飯、ということになる。大ザルに化ける能力も天与のチカラであり、これはのちにサイヤ人が生まれながらに持つ特殊能力だと、あとづけ的に判明する。
『DRAGON QUEST -ダイの大冒険-』(原作:三条陸、作画:稲田浩司)では、かつて魔王ハドラーを倒した勇者アバンという②付与者によって、①主人公ダイの潜在能力が見出される。なお、この作品も貴種流離譚の形式をとっている。
ダメ超人だったキン肉マンは、超人オリンピックで優勝するだけの潜在能力を秘めていた。それはラーメンマンによって「火事場のクソ力」と説明されるが、その具体性は示されない。キン肉マンのチカラは、超人として老境の域に差し掛かったプリンス・カメハメの特訓によって「48の殺人技」という形で読者に可視化される。キン肉マンにとっての②付与者はプリンス・カメハメであった。
なお、②付与者は、⑦敵対者から阻害されるケースが多い。⑦敵対者というのは、要するにボスキャラである。『ダイの大冒険』の冒頭において、勇者アバンは魔王ハドラーからダイを守るためにメガンテの呪文を唱えて力尽きる。このボスキャラというのは、ラスボスでなくとも構わず、当面のシーズンにおけるボスと思っていい。
『キン肉マン』においては、「夢の超人タッグ編」ではぐれ悪魔超人コンビの「呪いのローラー」を受けたり、「キン肉王位争奪編」で知性チームに利用されたりするくだりは、カメハメが②付与者であればこそ、ともいえる。
「Ⅰ:旅立ち」・目的と③対象物の違い
①主人公の冒険の目的は冒頭で提示される。しかし、物語自体は③対象物を手に入れようとして進展していく。目的と③対象物は、似ているようで異なるものなので区別をつけておきたい。
その違いは『ONE PIECE』(尾田栄一郎)を例にするとわかりやすい。①主人公ルフィの物語全編を通じての目的は「海賊王に俺はなる」ことだが、訪れる島ごとに「海軍大佐モーガンの圧政から島の平和を取り戻す」とか「道化のバギーから“偉大なる航路”の海図を奪う」と、目標となる③対象物は変化する。
『ドラゴンボール』では、「ドラゴンボールを7つ集める」とか「天下一武道会で優勝する」などが③対象物といえる。『キン肉マン』では「ベルトを防衛する」とか「超人オリンピックで二連覇を達成する」などがこれに該当する。
シリーズが変われば、その都度、やるべきこと(=③対象物)はリニューアルされ、④友人や⑤好敵手といった存在もセットで入れ替わっていく。入れ替え可能なものであるから、さほど重視されず、場合によってはマクガフィン化することもある。
「Ⅱ:冒険」・④友人について
冒険に出た①主人公は異界へと越境する。いままで自分が暮らしていた世界を捨て、未知の世界へと足を踏み入れ、そこで④友人と⑤好敵手に出会う。まずは④友人について。
④友人は①主人公と同世代に設定される。その役割としては、①主人公に未知の世界を案内する水先案内人である。世界についての情報保持という点において優位性があるので、①主人公と同年代だが、少しだけオトナの側に近い(上図の位置参照)。このため、わかりやすく「主人公より少し年上」となる例は多い。とはいえ、ここでは年齢そのものが大事ではなく、①主人公よりも世慣れしている点が重要である。
『ドラゴンボール』で孫悟空を外の世界に連れ出したブルマは、自称14歳の悟空に「ふたつしか違わない」と言っていたので16歳。彼女は世間のことだけでなく、ドラゴンボールについての情報も持っている。
そしてシリーズが進み、③対象物が「ドラゴンボール集め」から「天下一武道会」へと変化したあとは、ここのポジションにはクリリンが入る。クリリンは悟空より1歳年上の13歳だ。亀仙人に弟子入りを志願するときに袖の下(エロ本)を渡していたように、悟空に比べて世間擦れしている。
ブルマとクリリンは、ふたりとも悟空より社会性があり、世の中のことを知っていて、少しだけオトナに近いぶん、「よいこ」しか乗れない筋斗雲には乗ることができない。
『ダイの大冒険』のダイは12歳で、先にアバンの弟子入りをしていたポップは15歳。兄弟子としてダイを導き、最後まで旅を共にする親友となる。
『HUNTER×HUNTER』のゴンは、島育ちで外の世界を知らなかったが、12歳になる少し前にハンター試験を受けるために島を出る。外の世界で知り合う④友人・キルアは、ゴンと同い年だが、暗殺者としての英才教育を受けているので、ゴンよりも世間のことに詳しく、ゴンにとって世界の導き手となる。
キン肉マンにとっての④友人(ロールとしての)はテリーマンである。キン肉マンとテリーマンは同い年で、テリーマンのほうが世間擦れしている。「アメリカからきた男の巻」(第1巻収録)で初登場したときには、怪獣を退治したあとに日本の首相に報酬を要求したり、父親の救助を求めてきた子供に「ボーイ おとなをからかっちゃいけないよ!」と言い放ったりするなど、世間擦れしている様子が見て取れる。
「怪獣退治編」からキン肉マンと旧知の仲で、「アメリカ遠征編」ではコンビを組み、タッグチーム「ザ・マシンガンズ」を結成。タッグとしての戦い方をキン肉マンに教えながら、切磋琢磨していく。このシリーズを通じて、読者はテリーマンという④友人を再発見することになる。
①主人公と④友人の関係で面白いのは、①主人公が強くなるにしたがい、立場が逆転していくところだ。④友人は、はじめは①主人公に対して優位性を保っているが、そのうち庇護される対象となる。『ドラゴンボール』のクリリンは、いつの間にか、悟空に守られるようになるのがその典型例だ。
①主人公が広い世界を知り「オトナ側への近さ」の序列が変わるから、そういった逆転現象が起こるのだ。④友人を尺度に①主人公の変化(=成長)を測れるわけで、いってみれば④友人とは「①主人公の成長を可視化するメジャー」としても機能するわけである。
そうした例を念頭に置いて、この先のキン肉マンとテリーマンの関係性の変化を見ていくと面白いだろう。
また、④友人は①主人公の身代わりになることがある。もっとも主人公に近い存在だから擬似主人公たり得るわけで、たとえば①主人公が怪我をした際や、修業中で不在の状況などで、①主人公のかわりに戦う……といったケースが想定される。
『ドラゴンボール』のクリリンはピッコロ大魔王に生み出されたタンバリンやフリーザと戦って死亡するし、『HUNTER×HUNTER』のキルアは「キメラアント編」で念能力を30日間封印されたゴンのかわりに戦う。
テリーマンはキン骨マンのライフルに撃たれて左脚を失う(「氷上のキャメルクラッチの巻」第3巻収録)し、負傷したキン肉マンになりすましてブラックホールと戦おうとする(「キン肉マン参上!!の巻」第10巻収録)。
これは「失敗パターンを提示する」という役割を担っている。主人公のかわりになれるからこそ、みずからの失敗によって、①主人公に多くのメッセージをもたらすことができるのだ。そして読者も、④友人と同じ轍を踏まないでくれと、①主人公に深く感情移入できる。
いずれにせよ、「自分を知っている人が誰も居ない場所で友人や知人をつくる」ということは、物語上、ものすごく重要だ。それは、①主人公が社会性を獲得する、ということを意味するからである。
「Ⅱ:冒険」・⑤好敵手について
一方で、④友人と対になる存在が⑤好敵手だ。①主人公と③対象物を奪いあう、直接のライバルである。敵というよりは、競争相手、といったほうがいいかもしれない。①主人公と同世代だが、④友人同様に世間擦れしているので、上図では少しオトナ寄りにプロットした。
⑤好敵手はオトナではないものの、①主人公よりはオトナに近い。つまり、オトナの姿が仮託されている、と見ることができる。
ものすごくわりやすい例でいえば、⑤好敵手は①主人公より体格が優れている。パッと見の外見で、①主人公よりオトナ側の人間であることがわかる。かつての少年漫画では、ライバルは①主人公より大きく描くのがセオリーだったという。
『あしたのジョー』(原作:高森朝雄、作画:ちばてつや)では、①主人公・矢吹丈の⑤好敵手・力石徹はジョーと同世代だが、ひとまわり体が大きく、白木財閥の援助を受けている。立場的にもオトナの側の人間であり、まさしくオトナの姿が仮託されている。
なお、ちばてつやは『あしたのジョー』の連載を始めた当初は、あまりボクシングに詳しくなかったという。従来の定石に従ってライバル・力石の姿を大きく描いたところ、ボクシングには階級があるので、原作の高森朝雄(梶原一騎)は「矢吹と力石が同じ階級に見えない」と悩んだ末、力石がジョーと同じバンタム級に階級を落とすために過酷な減量をする、という作中でも屈指の名エピソードが生まれた。
なお、競争相手である以上、③対象物が変われば、必然的に⑤好敵手も変化する。「超人オリンピック ザ・ビッグ・ファイト編」ではウォーズマン、「7人の悪魔超人編」ではバッファローマン、「キン肉星王位争奪編」では運命の5王子……といった具合である。
⑤好敵手は④友人に転じることが多く、両者はオトナ側に完全に踏み入れていない点で、①主人公や④友人と近い存在ともいえる。
「Ⅱ:冒険」・グレートマザーの存在
冒険が進むと、①主人公は未知なる異界の、さらに深い領域へと足を踏み入れていく。いわばここからが「試練の門」であり、通過儀礼のキモとなる。
より深い領域へ、闇に向かって航海を進めていく段階の例としては、『ピノキオ』でクジラの王・モンストロに飲み込まれるシークエンスが象徴的で、これは胎内回帰とも考えられる。
この胎内回帰の段階では、女神、グレートマザーとの遭遇がある。
といっても、自分の母親に会いにいくわけではなく、母性を象徴するようなキャラクターと出会うことを意味する。あらゆる物を包み込み、慈しむ存在であり、いわば「象徴としての母」。神話では、そういった聖なる母との「聖婚」、神と人の婚姻が行われることもある。
物語における「母」には、優しさやぬくもりといったポジティブなイメージが割り当てられるが、その一方で、子供を支配したり束縛したりするネガティブな面もあわせ持つ。
人間はみな母から生まれてくるものだから、グレートマザーとはすべてを生み出す地なる母であり、それと同時に、すべてを飲み尽くしてしまう死の神でもある。生と死の両面を象徴する存在だ。
自立するためには母の影響力から逃れなければならない。精神的に乳離れするために、グレートマザーと対決することになる。グレートマザーの姿としては、年長の女性、老婆、魔女、女神などの例が挙げられ、ネガティブなイメージとしては鬼婆、化け猫、メスの猛獣などが挙げられる。
少年漫画の場合、物語のヒロインがグレートマザー的な役割を担う。『ドラゴンボール』ではチチが相当するだろう。彼女は「おらの心は水洗便所みたいに綺麗」と言うように、筋斗雲に乗れるくらいに心が綺麗だ。まさしく聖女であり、そして実際に悟空と結婚して母になる。
チチは悟空に一途だが、裏を返せば独占欲が強く、嫉妬深い。天下一武道会で悟空とチチが戦うのは、①主人公を追っかけてきたグレートマザーと対決しているわけであり、ここでのチチは、黄泉比良坂のイザナミのようだ。チチのネガティブ面は、とくに息子の孫悟飯が生まれてからは顕著になり、息子を束縛する母親のイメージを強くしていく。
一般的に少年漫画のヒロインは、このようなネガティブな面はスポイルされがちだが、『ドラゴンボール』ではきちんと表現されている。
また、『チェンソーマン』(藤本タツキ)では、マキマがグレートマザーの役割にあたる。作者の藤本タツキはマキマについて、『有頂天家族』(森見登美彦)の弁天というキャラクターを引き合いに出して、次のように発言している。
底が知れなくて人間より上位の存在でありながら、上位者なりの悲しみがあって、しかし下々の僕らではその悲しみに寄り添えない……といったところが好きなんですよ。マキマでもそういうところが出せればいいですね。ちなみに、チェンソーは本来は木を切る道具じゃないですか。「マキマ」から「キ」を切り取ると「ママ」になるんですよね。デンジはずっと母性的なものを求めていますから
このことからも、作者がきわめて自覚的に「母性」を描いていることがわかる。とくに物語終盤、マキマがチェンソーの悪魔に対して発揮する執着心は常軌を逸しており、グレートマザーの両面性が過剰なまでに横溢している。この部分が『チェンソーマン』において、もっとも「いびつ」で、個性的でオリジナリティが出ている部分だろう。
『キン肉マン』では、この「アメリカ遠征編」のあとの「怪獣退治編(第二次)」の「初地球の出の巻」(第7巻収録)でホルモン族の少女ビビンバと出会う。彼女はキン肉マンに片思いし、地球までついてきて、キン肉ハウスに押しかけて裸エプロン姿になったりする。
じつは神話には、「誘惑する異性」という存在もいる。①主人公を誘惑する異性であり、遊女や娼婦として出てくることが多い。いったん女神による回復を経験した①主人公は、誘惑者の快楽を断れなくなっているもので、順番的にはヒロイン(グレートマザー)のあとに出てくる。
少年漫画では、この「誘惑する異性」が出てくるケースは少ない。そのため上図には、「グレートマザー」、およびそれと対になる「誘惑する異性」はプロットしていない。
『ドラゴンボール』は物語構造の優等生というか、実に抑えるところを抑えた作品であり、だからこそ世界的に受け入れられたと思うのだが、この部分においては、ある種の「いびつさ」が出ている。
「ぱふぱふ」とか「ギャルのパンティおくれ」とか、下ネタはたくさんあるし、天下一武道会でナムと戦ったランファンのようなお色気キャラも出てくるものの、真にセクシャルな部分はスポイルされている。悟空とチチの結婚や出産も、「コウノトリが子供を運んできた」レベルの描写で、とても記号的である。「子供向けだから」との作者なりの配慮もあるのだろうが、おそらく本人が苦手で描きたくなかったのだろう。
ビビンバは、はじめは「誘惑する異性」のような印象を受ける(その場合は二階堂マリがグレートマザー)が、ウォーズマンの心根の優しさに誰よりもいち早く気づくなど「女神性」を発揮していき、やがて正式にキン肉マンの婚約者となる。『キン肉マン』でのグレートマザーは、ビビンバである。
「グレートマザー」と「誘惑する異性」はほとんどセットのようなもので、物語中に果たす役割や機能性ばかりが際立つと、「この作品には聖女と娼婦しか出てこない」といった評価をされがちだ。ただ、物語構造的に両者は本来的にはセットなので、本当に精査しなければいけないのは「聖女と娼婦(のロール)が同一の機能を果たしてしまっているかどうか」である。
「Ⅱ:冒険」・父親とアナザーワールド
このように、③対象物を奪い合う展開を繰り返すことで、少年漫画の物語は進んでいく。
そして物語が深化すると、今度は父親の姿を確認することになる。父親の真の姿、もしくは父親が外界でつくった世界(アナザーワールド)を知る、という段階に至るわけだ。かいつまんで言えば「実は父親は○○でした」。
『スター・ウォーズ エピソード5/帝国の逆襲』(1980年)でダースベイダーが「アイ、アムユアファーザー」と明かすのは、その代表例である。
『ダイの大冒険』では竜騎将バランがダイの父親であることが判明するし、『BLEACH』(久保帯人)では黒崎一護の父親は実は死神であり、『幽☆遊☆白書』(冨樫義博)では魔族大覚醒をした浦飯幽助の“魔族としての”父は魔界最強クラスの妖怪・雷禅である。
『ドラゴンボール』では、孫悟空を育てたじいちゃん(孫悟飯)は、占いババの館で登場し、狐面で正体を隠して悟空と戦う。正体を明かしたあと、悟空が「じいちゃーん」と駆け寄っていくところは、作中でも屈指の名シーンであろう。じいちゃんは、悟空が友人に囲まれているのを見て、安心して、あの世に帰って行く。友達がいることの重要性が、ここで示されている。
「父親が外界でつくった世界(アナザーワールド)」というのは、一見するとわかりづらいが、父の事績、生きた足跡を知るということだ。
『HUNTER×HUNTER』のゴンは最初から父ジンの姿を追っていて、『オデュッセイア』(ホメロス)のテレマコスが女神アテナに導かれて父オデュッセウスを探す旅に出るのと似ており、この構造がわかりやすい。ゴンは父がつくった世界(グリードアイランド)で冒険する。ラストでカイトと再会した際に多くの読者が肩透かしを感じたのは、無意識化にこの構造を意識していたからである。父のつくった世界をクリアしたら、その報酬は父との再会でしかるべきだろう、と。
『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』でポカパマズの足跡をたどったり、『ドラゴンクエストV 天空の花嫁』でグランバニアを訪れたりするのも、この例にあたる。
通過儀礼においては、「父親を超える」ということが重要な要素となる。このため、「実は父親はすごい人でした」と設定すると、この「父親超え」の要素をわかりやすく提示できるが、あまりやりすぎると、血統主義に見えてしまう危険性がある。
いわゆる文学的な意味における「父殺し」というのは、単に「能力的に父を超える」ということではない。親の影響下を離れ、父親を畏怖の対象ではなく、等身大の人間としてフラットに評価することを意味する。父親との力比べではなく、主人公の自己超克が本義である。
『キン肉マン』における自己超克については、該当箇所の巻の記事で詳述することとする。
なお、『キン肉マン』では、スグルがキン肉星の王として戴冠するにあたり、天上の100人の超人神と出会い、みずからの出生に隠された秘密に直面し、5人の邪悪超人神から試練を与えられる。
「己のルーツとの対峙」というテーマは、連載再開後の「完璧超人始祖編」以降にも引き継がれており、キン肉族のルーツ、正義・悪魔・完璧超人の起源などが解き明かされていく。
「Ⅱ:冒険」・⑥トリックスターと⑦敵対者
上図において少し特殊な立ち位置にいるのが、⑥トリックスターである。このロールは④友人と⑤好敵手の両属性をあわせ持つ。
敵サイドの人物として出てきたのに、紆余曲折を経て①主人公と一緒に行動するようになる。あるいは味方として登場したのに、①主人公を嫌っていたり裏切ったりする。
利害によっては敵にも味方にもなり、舞台を引っかき回す道化役であり、無垢な者、無知な者、粗暴な者として描かれる。
⑥トリックスターは、トラブルメーカー的な役割を担うものの、①主人公の立場では知り得ない情報をもたらす。あるいは無知ゆえに、先入観がなく、気づけたことを①主人公に知らせる。そして、⑥トリックスターのもたらす情報が、ラストへの推進力となるのだ。
『ドラゴンボール』のミスターサタンがこの典型例で、魔人ブウを倒すきっかけはミスターサタンによってもたらされる。
ギリシア神話のプロメテウスは、神に反抗し、神を欺いて人類に火や穀物をもたらした文化英雄である。性格や行動などにおいて善悪二面性を持つ存在であり、⑥トリックスターの性質を持っている。
日本神話の『記紀』では、荒ぶる神として悪行を働く一方で、ヤマタノオロチ退治などで活躍するスサノオが⑥トリックスターだ。
『キン肉マン』においては、キン肉アタルがトリックスターの役割を担う。スグルの兄アタルは、キン肉王族の教育に反発して家出し、本来のキン肉マンソルジャー(傭兵超人ソルジャーマン)を襲ってマスクを奪い、残虐の神を欺いて、正義超人と悪魔超人の混成チーム「超人血盟軍」を結成。スグルには、馴れ合いではない真・友情パワーを示唆し、さらにマッスルスパーク完成の手がかりを提示し、キン肉マンスーパーフェニックス打倒の糸口をもたらす。アタルは『キン肉マン』におけるスサノオなのである。
こうした段階を経て、この「Ⅱ:冒険」のラストの段階で、⑦敵対者を打ち負かす。⑦敵対者というのは、いわゆるラスボスである。
少年漫画では③対象物、④友人、⑤好敵手、⑥トリックスターのセットを入れ替えながらシリーズを重ねていき、ファイナルシーズンでは⑤好敵手がそのまま⑦敵対者へとスライドする。
それゆえに、「7人の悪魔超人編」などシリーズが変わるごとに、各セットについて見ていくとしたい。
「Ⅲ:帰還」・拒絶からの祝祭
ラスボスである⑦敵対者を倒すまでが「Ⅱ:冒険」であり通過儀礼であるなら、物語構造の最終段階、「Ⅲ:帰還」とは何を表すパートなのか。
そもそもの問題として「Ⅲ:帰還」には困難がつきまとう。「ラスボスを倒したら元の世界に戻って大団円」と思いがちだが、その手前に困難さがあり、すんなりとは帰れない。その困難さの種類のなかには、①主人公自身による拒絶、というものもある。
なぜ①主人公は、冒険からの帰還をいったん拒絶するのか。
冒険は辛く苦しかったが、反面、楽しかったからだ。みずからの手で「夢のような時間」を終わらせたくない、という無意識の欲求である。たとえばロール・プレイング・ゲームで、ラスボス手前まで順調に進めておいたのに、最後の戦いだけ手をつけず、未クリアのまま放置……なんて話はよく聞くが、これも物語を閉じたくない潜在意識の表れといえる。
こうした拒絶反応により、主人公は報酬から逃走する。具体例を示していこう。『ドラゴンボール』では、天下一武道会でマジュニア(ピッコロ)を倒した悟空は、神様から「わたしにかわって神になってくれぬか…」と提案されるが、それを拒否する(「其の百九十四 ドラゴンボールの贈りもの」第17巻収録)。そしてチチと結婚し、一緒に筋斗雲で飛び去っていく。
『ドラゴンボール』は物語構造上、この時点で「あとはエピローグを残すのみ」の状態まで進んでいる。そして、このエピソードの最後には、亀仙人の「最終回じゃないぞよ もうちっとだけ続くんじゃ」とのセリフがある。鳥山明はストーリーテリングの天才であり、直感的に物語の構造を理解しているからこそ、あの場面で、こうしたメタ的なセリフを書けるわけだ。
ただ、諸般の事情により、『ドラゴンボール』の連載はさらに続くことになり、③対象物、④友人、⑤好敵手、⑥トリックスターのセットを入れ替えながら「サイヤ人編」「フリーザ編」「人造人間セル編」「魔人ブウ編」と、さらに6年間も物語を続けていくことになる。
困難さの描き方としては『チェンソーマン』が白眉で、ラストバトルに勝利したあと、ある方法によって、ラスボスを処理しなければならない。その処理方法が判明する回が「少年ジャンプ」2021年1号に掲載されたときには、SNSで驚異的なバズり方をした。2020年12月7日のツイッターのトレンドワードに入った「生姜焼き」が『チェンソーマン』の関連ワードとは、リアルタイムで連載を追っていた読者でなければ気づけなかっただろう。
ともあれ、⑦敵対者打倒後のこうした「拒絶」や「困難さ」のプロセスを経て、①主人公はようやく元の世界に戻り、平穏な日常を取り戻す(エピローグ)。『スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還』(1983年)のラストでイウォーク族の村で祝賀会が開かれるように。なぜ『スター・ウォーズ』サーガのラスト(当時)に、熊の愛くるしいダンスを見なければならないのかと訝しんだ向きもいるだろうが、あれはジョージ・ルーカスの演出というよりは、「物語構造が要求した」と考えたい。
『キン肉マン』では、この「拒絶」「困難さ」のシークエンスは描かれない。⑦敵対者のキン肉マンスーパーフェニックスとの戦いに勝利したあと、邪悪超人神をのぞく100人の超人神が現れ、スグルの大王継承任命を行う。その際に「勝利者の権利」としてスーパーフェニックスの超人預言書を燃やすように勧められるが、スグルはこれを拒否するあたりが「拒絶」に相当するだろうか。だが、「Ⅲ:帰還」のシークエンスが満足に描かれず、足早に物語を終えた印象は拭えない。
このため、連載終了後から数年後には、この「Ⅲ:帰還」部分を補完する物語が描かれた。『キン肉マンII世』連載時に特別編として描かれた「キン肉マンvsテリーマンの巻」(集英社「週刊プレイボーイ」2000年19・20合併号〜22号掲載)、さらに「週刊少年ジャンプ40周年特別記念企画第11弾」として「少年ジャンプ」20008年29号に掲載された「キン肉マンの結婚式!!の巻」は、いずれも「キン肉マンvsキン肉マンスーパーフェニックス」戦のあと、キン肉マンがキン肉星に帰還して大王位を継承するまでのミッシングリンクを埋めるストーリーであり、「拒絶」と「困難さ」から祝祭に至る一連のエピローグ・シークエンスを描き切った。現在、この2エピソードは、どちらも単行本第37巻に収録済みである。

このように物語構造の面から見ると、少年漫画は同じ物語構造を使って、同じような物語を繰り返しているように思えるだろう。これは少年漫画に限った話ではなく、物語(とりわけ成長譚)を紡ぐ際に、人類が神話の時代から繰り返してきた営みなのである。
物語構造とは音楽でいえばコード進行のようなものであり、そこにどのようなメロディや歌詞を乗せるかは、時代に応じて、あるいは作者によってオリジナリティが出る。読者はそこに時代性や自己同一性を見出し、「これは自分の物語だ」とか「自分について書かれた物語だ」と感じるわけである。
では、このコード進行を用いて、人類は何を表現してきたのか。何を繰り返し語ってきたのか。人間は眠りと覚醒、死と再生、此岸と彼岸を行き来する生き物であって、われわれの来し方行く末を物語で追体験していることになる。われわれは物語を娯楽として享受しているが、物語を通じて、この世界を認識しているわけである。物語は世界を認識する手だてにほかならない。
「アメリカ遠征編」は、産みの苦しみ
話を『キン肉マン』の「アメリカ遠征編」に戻す。
冒険に出る、師に出会う、チカラを獲得する、対象物(アメリカ超人界統一)が提示される、友と出会う、強敵を倒す……と、「アメリカ遠征編」にはキン肉マンを英雄譚の主人公たらしめる要素が凝縮されている。
宇宙怪獣を相手に連戦連敗していたダメ超人のキン肉マンが、ラッキー以外の要素で勝ち上がっていくために強さの裏付けが求められ、潜在能力を開花させ、ストーリー漫画の主人公としての資質をその身に宿した。
つまり『キン肉マン』という作品は、この「アメリカ遠征編」を通じて、ギャグ漫画ではなくストーリー漫画としてのリアリティラインを引き直したわけである。『キン肉マン』がストーリー漫画へと生まれ変わるためには「アメリカ遠征編」は必要であり、ここを経ずしてのちのストーリー漫画路線の成功はあり得ない。
しかし、「必要」と「面白い」は同義ではなく、読者に受け入れられるかどうかはまた別の問題である。それは産みの苦しみをともなった。
では、それだけ物語構造的に正しく、必要な作業であったのにも関わらず、なぜこのシリーズは「人気の急落具合は半端ではなかった」のか。
その要因のひとつは、前述した「作者が読者から離れてしまった」感である。
そしてもうひとつは、シンプルな理由として、主役のキン肉マンがあまり活躍しなかった点にある。この「アメリカ遠征編」でのキン肉マンは、プリンス・カメハメには7秒でフォール負けし、ジェシー・メイビアにこそ完勝するが、ロビンマスク戦は技らしい技を見せないままノーコンテスト(無効試合)となり、超人タッグ選手権での活躍はキン骨マン・イワオ組という「勝って当然の相手」にピンフォール勝ちしたのみ。ラストはテリーマンのカーフ・ブランディング(作画的にはブルドッキングヘッドロック)でフィニッシュしている。
主人公が目立たない、という点で読者は消化不良だったようにも思う。カメハメに鍛えられ、強くなりすぎたキン肉マンをどう活躍させればいいか、持て余していたような印象さえある。
結局、「アメリカ遠征編」のシリーズは、凶悪怪獣ブルゴラスの退治に日本に向かったキン肉マンが、試合時間に間に合わなくなりタイトルが剥奪され(「ベルトか日本救出か!?の巻」)て終了。
この回をもって「怪獣退治編(第二次)」へと移行する。
後世の視点で見ると「タッグが難しい」「団体抗争が難しい」などの理由は腑に落ちるのだが、ここで原点回帰ともいうべき怪獣退治路線に舵を切り、主役を立たせようとするあたりは、この当時は「タッグがダメ」「団体抗争がダメ」ではなく、「プロレス路線」に難色を示されたのではないかとも推測できる。
なお、コミックスでは第6巻ラストで「怪獣退治編(第二次)」がスタートしているので、シリーズの区切れ位置としては印象がよくない。しかし、雑誌連載時の掲載号を見ると、この回は(表示上の)年が明けてからの1号に掲載されており、「新年から新シリーズ」という体裁をとっている。雑誌で連載を追っていたか、コミックスでまとめて読むかによって、新シリーズに対する印象がかなり異なるだろう。
「アメリカ遠征編」後半
エリックとは何者?
「アメリカ超人界の首領の巻」では、アメリカ超人界の創始者であるゴッド・フォン・エリックが登場する。モデルは「鉄の爪」フリッツ・フォン・エリック。1954年にプロレスデビューとの記録があるから、ジャイアント馬場より6年もデビューが早い。AWA世界ヘビー級王座に君臨し、NWAの会長も務めた。『キン肉マン』連載時にはすでに大ベテランの域に達していたレジェンドレスラーである。
このゴッド・フォン・エリックが登場するたびに、キン肉マンは「E・H・エリック」と言い間違えるネタが差し込まれる。E・H・エリックは日本の俳優であり、同じく俳優の岡田真澄の実兄にあたり、いわゆるハーフ・タレントの先駆者的な存在だ。日本の芸能史に残る人物なのは間違いないが、1980年時点での子供たちにどれだけの知名度があったかは不明。いま再読するにあたっては、なかなかわかりにくいネタといえる。
人気投票がすぐに反映
「車いすの少年の巻」は、トビラでキャラクター人気投票の結果を掲載している。「応募総数625名」というのは、現在の価値観からすると、いかにも少ないが、なにせキャラクター人気投票自体が当時は珍しい企画であった。
そして、キャラクターの人気投票をやったのも『キン肉マン』が一番最初だった。これも中野さんのアイデアで、今では当たり前のように各作品でやっている。
(※注:「中野さん」とは『キン肉マン』の初代担当編集氏のこと)
この証言のファクトをチェックするのは難しいが、たしかに前例をあまり聞かない。この人気投票は、主役のキン肉マンは投票対象外であり、「人気超人の部」と「悪役超人の部」にわかれていた。
人気超人の部は「1位:テリーマン、2位:ロビンマスク、3位:ラーメンマン、4位:スカイマン」、悪役超人の部は「1位:デビルマジシャン、2位:スカルボーズ、3位:ラーメンマン、4位:ブロッケンマン」と、どちらも4位までが発表された。ラーメンマンが両方の部門で3位に入っているのが印象的である。
このうち、この回から始まる「ザ・マシンガンズ(キン肉マン、テリーマン)vs宇宙一凶悪コンビ(スカルボーズ、デビル・マジシャン)」戦に参戦しないのはラーメンマン、スカイマン、ロビンマスク、ブロッケンマンの4人。生死不明のロビンマスク、死亡済みのブロッケンマンをのぞくと、浮いている超人はラーメンマンとスカイマンだけであり、この優勝決定戦を裁くレフェリーとして、この回からラーメンマンが登場する。
さらに、翌週の「最大の弱点の巻」ではスカイマンが登場。自分の得意技「フライング魚雷」を、かつて超人オリンピックで戦ったテリーマンに使用されて、「おお! みろ オレの必殺技だ!!」と喜んでいる。
人気のあるキャラクターはすぐに作品に出してもらえる、というのはファンからしても嬉しいことで、しかも掲載順2番目の2色カラーの際にこうした企画をあわせてくるところは、さすがに如才ない。ラーメンマンは続く「怪獣退治編(第二次)」にも登場することになるが、このランキング結果の影響かもしれない。
なお、ラーメンマンは、のちに(モンゴルマンとして)「キン肉マンvs悪魔将軍」戦でもレフェリーを務める。
この「車いすの少年の巻」では、会場のマジソン・スクエア・ガーデンに『リングにかけろ』の高嶺竜児のコスプレをした観客がいて、応援するチームを聞かれて「凶悪コンビにきまってるだろ!」と答えている。
この頃の『リングにかけろ』は、「ギリシア十二神編」が終了して「阿修羅の挑戦編」に突入。依然として人気は高く、この2週前の48号では巻頭カラー、翌51号では表紙を飾っている。
人気作品のパロディは、少なくとも「田端義夫」や「浜田幸一」などの時事ネタをやるよりも、はるかに読者寄りのスタンスである。人気低迷を知らされた焦りに起因するのかもしれないが、こうしたギャグにせよ、キャラクター人気投票をすぐ作品に反映することにせよ、『キン肉マン』が従来の想定読者層を再び強く意識した証左といえる。
タッグチームの入場曲
タッグチームの入場曲についても触れておく。
ジ・エンペラーズ(ビューティー・ローデス、スティムボード組)はベートーベンの「ピアノ協奏曲第5番」。宇宙一凶悪コンビ(スカル・ボーズ、デビル・マジシャン組)はムソルグスキーの「はげ山の一夜」で、ジ・エンペラーズ戦ではベートーベンの「葬送行進曲」を用いている。
そしてザ・マシンガンズは、映画『荒野の七人』(1960年)のテーマ曲。『荒野の七人』は黒澤明の『七人の侍』(1954年)を西部開拓時代に翻案したもので、エルマー・バーンスタインの楽曲は1961年の第33回アカデミー賞のドラマ・コメディ映画音楽賞にノミネートされた。
最後に評ではなく感想になって申し訳ないが、『荒野の七人』のテーマ曲はザ・マシンガンズの入場シーンの絵(「開会セレモニーの巻」)に合っていて、とても格好いい。『キン肉マン』はアニメやゲームなど、あらゆるメディア展開がされているが、どうにか権利的な問題をクリアして、原作内で設定された入場曲を使用できないものだろうか。
よろしければサポートのほど、よろしくお願いします。
