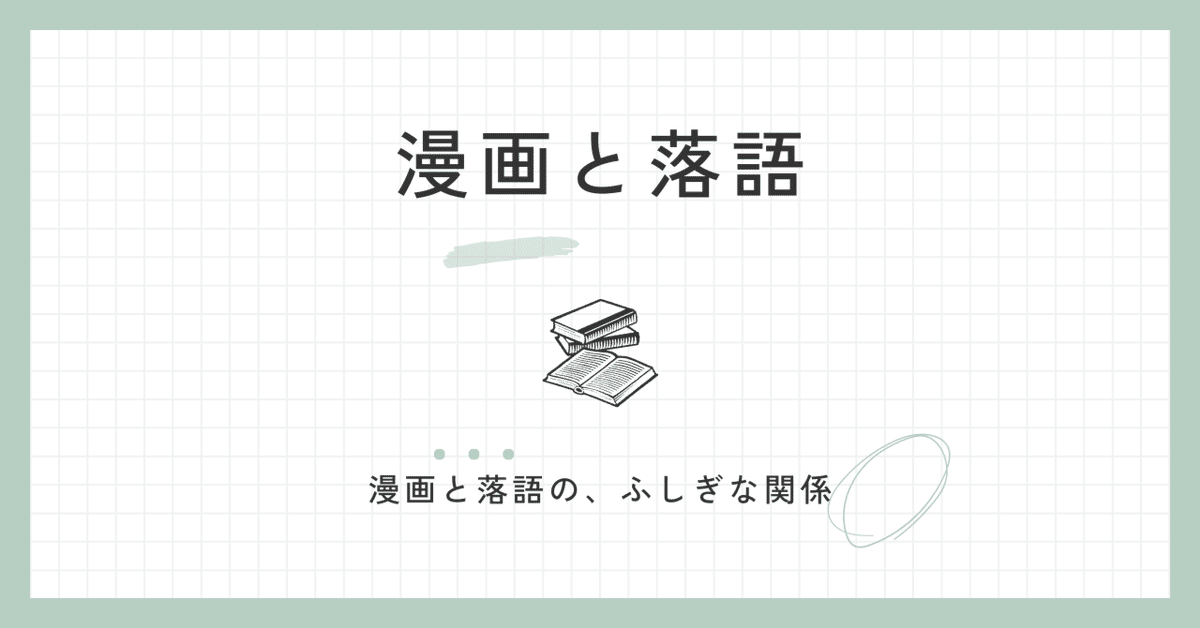
漫画と落語:田河水泡『のらくろ』 6
仲太郎の小僧修行
1914(大正3)年、仲太郎は実父のもとに戻された。 家業を学ぶために、今度は神田のメリヤス屋へと奉公に出されることになったのである。仲太郎は画家になりたい夢を、それとなく父に打ち明けたものの、「世迷い言を言うな」と取りつく島もない。
仲太郎としては不本意な時期であった。仕事に熱が入るわけはなく、店主が店を空けると、これ幸いと、店番をしながら絵の練習をしていたという。とはいえ、絵の具を店先に持ち込むわけにはいかない。店番中の仲太郎は、Gペンを使って落描きをしていた。
Gペンとは、いわゆる「つけペン」の一種だ。インクをペンの内部に格納する種類のペン(万年筆やボールペンなど)とは異なり、ペン先にインクや墨汁をつけて描くもので、Gペンは英字を書く際や製図用に用いられた。筆圧によって線に強弱をつけやすい特性が漫画の作画には向いており、やがてGペンは丸ペンと並びアナログ作画における主要な画材となる。
北澤楽天や岡本一平といった最初期の漫画家には、日本画をルーツとする作家が多く、筆で漫画を描いていたが、田河水泡が漫画家になる頃には徐々にペン画が主流となっていく。小僧修行時代の落書きでGペンの扱いに慣れていたことが、のちに漫画を描く際に奏功するのであった。
また、仲太郎は配達に出ると、佐賀町(現在の江東区佐賀)に住む従兄・遠治のもとに寄り、美術雑誌をもらったり、絵画や美術について色々教わったりしていた。そうした日々のなかで「絵描き」への憧れを募らせる。
1917(大正6)年1月15日、仲太郎が18歳のときに父が脳卒中で死去する。仲太郎がこの日を「藪入り」と記憶していたのは、奉公人ならではの覚え方だろう。
育ての母である伯母こそ存命であったが、実母、伯父、実父と死に別れ、「行き場を失った」感覚が仲太郎の胸に宿る。天涯孤独の「のらくろ」は、こうした仲太郎の境遇によって生まれたものであった。
このとき仲太郎に声をかけてきたのが、従兄の高見澤遠治であった。仲太郎に転機が訪れる。
フランク・ロイド・ライトの激怒
村幸は高見澤某なる者と相謀り、江戸錦繪を贋造し、米國建築技師ライトといふ者に賣渡せし所、後日に露見し、ライトより二十萬圓の賣價取戻しの掛合を受けたりと云ふ。
これは永井荷風の『断腸亭日乗』巻之五にある大正15年7月21日付の日記だ。荷風は9年前の1917(大正6)年に起きた事件を回想して書き記している。
要約すると「村幸(浮世絵商の村田久吉)が高見澤という男と共謀し、アメリカの建築技師ライトに江戸錦絵の贋作を売ったところ、のちに悪事が露見し、総額20万円の売買契約のキャンセルを求められた」とある。
ここに名が出てくるライトとは、帝国ホテルの新館(千代田区内幸町、現在は愛知県犬山市の博物館明治村に移築)を建築したことでも有名な建築家フランク・ロイド・ライトである。ライトは熱烈な浮世絵コレクターとして知られており、彼を介して海外に流出した浮世絵は2万点を超え、ライトの収集したコレクションは現在はボストン美術館に収蔵されている。
谷川正己の『フランク・ロイド・ライトの日本 浮世絵に魅せられた「もう一つの顔』(光文社新書)によると、ライトの来日は合計7回におよび、三度目となる1917年の来日時は1月9日から4月21日までの103日間。おそらくこの期間で起きた出来事なのだろう。
ライトに詐欺を働いた人物は、荷風の日記では「村幸」と記されているが、関係者の証言から、林旧吾という別の浮世絵商であると判明する。ただし、この「高見澤某」は、仲太郎の従兄・高見澤遠治その人であった。浮世絵版画の職人となっていた遠治は、保存状態の悪い浮世絵の直し(修復)に才覚を発揮し、同業者から「直しの遠ちゃん」と渾名されるほどの腕前を持っていた。
遠治の「直しもの」を、件の浮世絵商がさも掘り出し物であるかのように偽り、ライトから大金をせしめたのである。しかし、ライトの審美眼は、この浮世絵商の企みを見抜く。
ライトは林をホテルの一室に閉じ込めて鍵をかけ、拳銃を突きつけて一部始終を白状するように迫った。恐れをなした林はすべてを告白した。遠治の名も林の口からもれたのである。怒ったライトは直ちに検事局に関係者を訴えた。

永井荷風は「賣價取戻しの掛合を受けたり」と穏当な表現を用いているが、拳銃を額に突きつけて白状させたとあるから、かなり物騒な騒ぎであった。
この事件では、遠治は自分の仕事を悪用されたに過ぎない。もとより遠治は芸術家肌というよりは、それこそ落語に出てくる大工の棟梁のような、職人気質の仕事人であった。酒が入ると喧嘩っ早いところはあったが、「江戸っ子は五月の鯉の吹き流し口先ばかりではらわたはなし」を地でいくような男であったから、刑事から事情聴取されたり、検事局までが動いたりする騒動には、ほとほと嫌気が差した。結果、遠治は「直し」の仕事をやめてしまったのである。
複製浮世絵頒布会
だが、遠治の腕を惜しむ声は多かった。
遠治を高く評価していた者たちは、彼の技術が埋もれてしまうのを懸念し、「複製浮世絵頒布会」を発足させたのである。これは協賛者から浮世絵の名品(写楽、歌麿、春信など)を提供してもらい、遠治が模写して複製したものを会員に提供する会であった。いわば遠治にレプリカをつくらせる会である。
会の賛助員には、泉鏡花や永井荷風なども名を連ねた。
遠治はこの会で制作した複製画に、小さな葵の印を付けた。これは悪用されることを恐れ、複製品であることを示すためであった。先のライト事件が、よほど懲りたのだろう。この印がついた複製画は、のちに「遠治版」と呼ばれるようになる。
そうした仕掛けを施す必要があるほど、遠治の複製品は精巧を極めた。「文藝春秋」誌上で菊池寬の司会による「浮世絵座談会」が開かれた際には、藤懸静也(帝大教授)が「高見澤が入念に作つたものは眞物か、贋物か鑑別がつかなゐ。あれは一寸分かりませんでしたね」と証言しているように、遠治の複製版画はプロですら原画との区別が難しかった。それが春信だろうが写楽だろうが、である。まさしく天才である。
だが、大正6年に複製浮世絵頒布会が発足した当時は、まだ会が本格的に始動する前の段階であった。複製品の制作に取りかかるには、彫師や刷師のもとに使い走りをする「小僧」が必要だった。まさに猫の手も借りたい状態である。
そんな折に、仲太郎が父を亡くしたことを知る。かくして遠治は仲太郎に声をかけ、仲太郎は「複製浮世絵頒布会」で使い走りをするようになる。
居場所を失った仲太郎と、人手が欲しい遠治。両者のタイミングが奇跡的に合致したのである。
遠治宅には、頒布会の協賛者から預けられた一級品の浮世絵があり、日常的に鑑賞眼を養える。また、遠治の収集した美術書は好きなように見ることが許されていた。さらに遠治からは油絵の道具一式を譲り受け、仕事のかたわら、遠治から絵の指導を受けた。天才・遠治の手ほどきによって、仲太郎は美術の基礎を学ぶのであった。
このとき仲太郎、18歳。店番をしながらGペンで落書きをしていた日々から、環境が一変した。
永井荷風と正岡容
これは余談だが、永井荷風の落語との関わりについて触れておきたい。荷風は若かりし頃、落語家の六代目朝寝坊むらくに弟子入りしたことがある。朝寝坊むらくの師匠である四代目三遊亭圓生は初代三遊亭圓朝の弟子であり、三遊派の総領を務めた。つまり、六代目むらくは、初代圓朝の孫弟子ということになる。
わたしは朝寝坊夢楽という落語家の弟子となり夢之助と名乗って前座をつとめ、毎月師匠の持席の変るごとに、引幕を萌黄の大風呂敷に包んで背負って歩いた。明治三十一、二年の頃のことなので、まだ電車はなかった。
永井荷風は1897(明治30)年に官立高等商業学校附属外国語学校清語科(現在の東京外国語大学)に入学し、1899(明治32)年に中退するので、むらく門下になったのはちょうどその時期だ。
一応、「三遊亭夢之助」という高座名をもらっているが、演芸評論家の矢野誠一は『荷風全集 月報10』(岩波書店)に寄稿した「正岡容の荷風信奉」という評論文(日本経済新聞出版社『昭和の東京 記憶のかげから』収録)のなかで「師のむらくは一向に噺を教えてくれなかったという」と記しているから、見習い修行はしていたものの、高座に上がったかどうかは実際のところわからない。
結局、荷風は寄席に出入りしているところを実家の使用人に見つかり、家に連れ戻されて落語家になる道を閉ざす。
なお、荷風が見出した谷崎潤一郎も後年に落語について述べていたり、晩年の荷風に私淑した正岡容は演芸評論家として大家となるなど、荷風の落語好きは後世に影響をおよぼしていく。
よろしければサポートのほど、よろしくお願いします。
