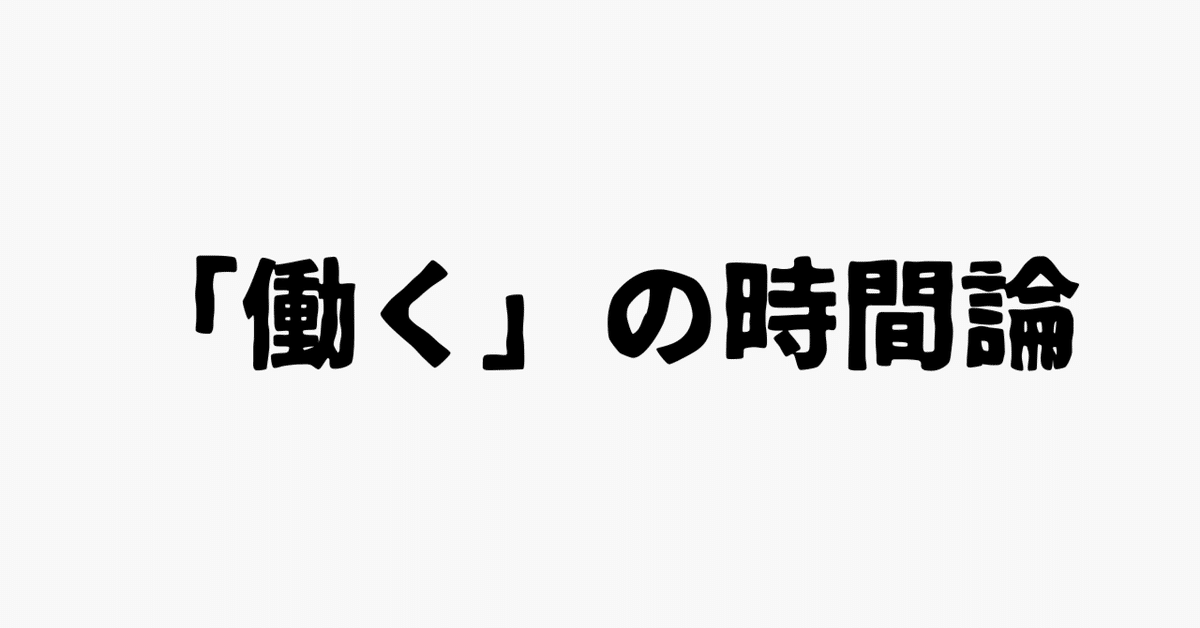
「働く」の時間論⑦ 他者のために、自分のために
何のために働くのか。まず自分が生きるために、自分のために働く。それがまず前提である。では、何のために、自分のために働いているのだろうか。それはレヴィナスになぞらえて答えると、他者のために、自分のために働く、となる。
自分はまず食べるために働かなくてはならない。そのことを通して自分のために生きている。だが、同時に働くことを通して他者のために贈与できるものを生産している。自分のために働くことが、他者のために働くことにつながっている。
「働く」という時間は、「他者のために」、「自分のために」、この二つの軸が矛盾せずに両立する結節点である。
レヴィナスの言うことに耳を傾け、もう一つ言うと「働く」ということは、そのこと自体を享受して幸せに生きることも実現している。
レヴィナスはホロコーストという虐殺から生き残ったユダヤ人である。そのことがどれほど影響を及ぼしているかわからないが、生きていることは幸福であると言い切っている。何のために生きるのか、という問いに対して、幸福のために生きる、と答えられることもある。しかしレヴィナスにとって生きることそのものが幸福をすでに叶えているから、それは答えにはならない。
私たちは食べ物を食べたり、仕事で道具を使いこなしたりして生きている。レヴィナスは人間がいつもこの世界にあるものを「享受」することで生きていると考えた。仕事をすることも享受のひとつである。
レヴィナスの享受論からすると、幸せに生きることはすでに実現している。私たちは、幸せに生きるために仕事をしているのではなく、仕事をしているというそのことで幸せに生きているのである。仕事をして生きることは、仕事を享受して健康に楽しく生きることである。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
