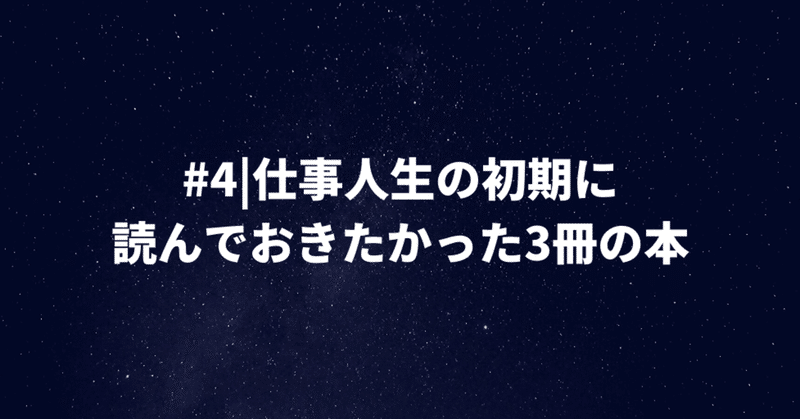
#4|仕事人生の初期に読んでおきたかった3冊の本
「仕事とは何か?」
この問いに皆さんなら何と答えるだろうか。色んな答えがあると思うが、今の自分なら「課題解決である」と答える。
自分の仕事人生は高校生から始まっていると認識しており、スーパーの品出しやゲームアイテムの販売、塾講師、イタリアンレストラン、インターネット上で物やスキルの販売、タイと日本を繋ぐメディア、子育てメディア、就活コンテンツ、アプリマーケ支援、コールセンターなど、未熟ながら様々な仕事をしてきた。職種としても営業からマーケティング、ライター、経営企画など、一部かじった程度ではあるが様々な分野に携わってきた。
その中で自分が感じたことは、世の中にはたくさんの仕事があるが、どれも根本部分は変わらないということ、またその根本部分とは「課題解決」であることである。課題解決とは、「①課題特定」→「②課題の深堀」→「③解決策の創出」の一連の流れであり、前半の①課題特定と②課題の深堀が課題解決の9割以上を占めると考えている。起業家であれば顧客の潜在ニーズを見つけ出し、それにあった解決策を提供する、営業であればクライアントの課題を引き出し、それに自社の知見を提供する、アイドルであれば顧客の心に空いた穴を探し、自身のパフォーマンスを通じて動かす。どれも必要なスキルは多少異なるが、共通の根本の部分が強ければ強いほど、そのスキルがより活きてくる。これはある種「センス」のようなもので、無意識的にできている人もいれば、後天的に不断の努力をして身に付けた人もいるだろう。この力においては後天的に身に付けられるものであり、その力が強ければ強いほど、他のスキルにレバレッジをかけられると自分は考えている。
その「課題解決力」を身に付ける上でもっと早くから出会い、何度も繰り返し読んでおきたかった本をここでは紹介したい。自分のチームメンバーには最低限これは読んでもらいたいと思っている。職種、業種関係なく、これから仕事人生をスタートするという方はこれを読んでおくと、仕事に対しての理解が深まり、より人生を有意義に過ごすことができるのではないか。
1.「イシューからはじめよ」
ヤフーのCSO,安宅和人さんの著書。
先日の記事には安宅さんのブログを紹介させていただいたが、こちらでは書籍を紹介したい。
「イシュー」とは、「2つ以上の集団の間で決着のついていない問題」であり「根本に関わる、もしくは白黒がはっきりしていない問題」の両方の条件を満たすもの。
あなたが「問題だ」と思っていることは、そのほとんどが、「いま、この局面でケリをつけるべき問題=イシュー」ではない。
本当に価値のある仕事をしたいなら、本当に世の中に変化を興したいなら、この「イシュー」を見極めることが最初のステップになる。
多くの人は正しい「イシュー」を設定できておらず、そのために時間を無駄に使用している。世の中の事象は課題解決を試みる際に、Howに焦点が当たっていることが多いが、本当に重要なのは課題であるWhatを見つけること、また、なぜそれが課題なのかのWhyを見つけることだと個人的に考える。WhatとWhyを正しく特定することができれば、自ずとそれを解決するHowは見えてくるだろう。
「頑張っているのに結果が出ない」と思っている人は「本当にそれは正しい頑張り方なのか?」を常に問いかけ、「何がイシューなのか」を常に探索して欲しい。(圧倒的自戒を込めて)
安宅さんは最近、「シン・ニホン」という書籍も出されている。「イシューからはじめよ」が知的生産性を向上させるための書籍だったのに対し、この「シン・ニホン」は、現在の日本の状況と、今後どのようにしたら良いかが書かれている書籍である。まだ私自身読めていないためこちらも読んでみたい。
2.「考える技術・書く技術」
本書は物事をうまく人に理解してもらう/自分でも理解するためにどうしたら良いか、言語というアウトプットツールを用いて書かれている本である。前述の通り、課題解決には、「課題を正しく捉えられているか?」がもっとも重要であり、事象を整理し、正しく認識するに当たって、言語は非常に強力なツールである。これができると、状況が全く異なる人に対してもある程度の説明ができ、共通認識を持つことで理解してもらいやすくなる。(根本のバックボーン(インプット環境の差)により、いくら整理して伝えても理解してもらえないケースもあるだろう)SCQAの筋道に沿った説明はストーリーを作り、相手の中に入ってきやすくなる。
3.「意思決定のための『分析の技術』」
さて最後はこの書を紹介したい。先ほどの書籍が言語を用いた、事象の正しい捉え方、正しい伝え方を伝えていたのに対し、本書では実際にどのように物事を分けて考えるのかといったユースケースが数多く記載されている。分析をする際、よく目的を見失いがちだが、本著を読んで一通り分析方法をインプットし、正しく応用すれば大体の事象は正しく分析できるのではないかと考える。下記が各項目となっており、項目ごとに事例つきで考え方が記載されているので、参考にして欲しい。
・大きさを考える
・比較して考える
・変化、時系列を考える
・わけて考える
・ばらつきを考える
・過程を考える
・ツリーを考える
・不確定を考える
・人の行動、ソフトの要素を考える
以上、仕事人生の初期に読んでおきたかった本を紹介した。かく言う自分も圧倒的にまだまだこの力が足りないと思っているので、前述の書籍を参考に今後もトレーニングを重ねていく。
この記事が参考になったら、スキやフォローしていただけるとありがたいです。Twitterもやっているのでよろしければご覧いただき、フォローをお願いします。
この記事がためになったと感じたらサポートいただけるとありがたいです。コンテンツ作成費用として使用させていただきます。
