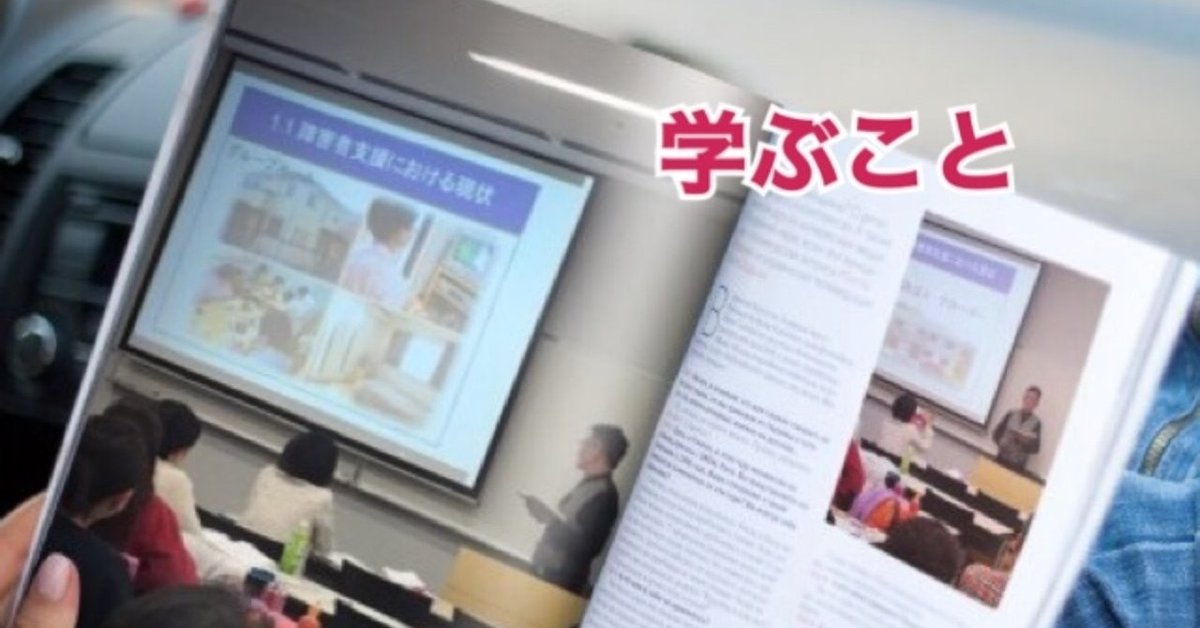
転移/「教える技術」を「支える技術」へ (教える技術のふりかえり)
01月10日から02月14日まで、早稲田のエクステンションセンターで開催された向後先生の「教える技術」について書いてきました。今回はこの講座のまとめ、その4、最終回です。
今回の講座では、教える技術を障がいのある方への支援場面で活かすにはどうすればよいか、それを私のテーマとして参加しました。
講義内容は以下のとおりでした。
01月10日 第1回 教えるとはどういうことか
01月17日 第2回 運動技能の教え方
01月21日 第3回 認知技能の教え方
01月28日 第4回 態度技能の教え方
02月07日 第5回 コースの設計
02月14日 第6回 コースのデモンストレーション
前回は5回目のロケットモデルについてふりかえりました。今日は最終回、6回目の講義についてふりかえります。
6回目 コースのデモンストレーション
最終回の講義では、受講生それぞれが教えたいコースを考え、プレゼンをしてそのコースについてふりかえりを行いました。そこで学んだことはことは学習者が教える人を評価するという考えです。
1)お金をもらうということ
講義では、教えるときにはお金をもらった方が良いというお話がありました。私は、地域でお話をしたとき、一度だけ思った以上の謝礼をいただいてびっくりしたことがあります。あとから、あの内容で良かったのか、期待に応えることができただろうかと不安になりました。先生がおっしゃることは、お金をもらうことで、このふりかえりの意識が変わり、自分も成長していくということなのではないかと思います。相手が満足してくれたかどうか、この問いかけは常に必要です。
私たちの支援も同じです。障害福祉サービスは、障がいのある利用者さんたちが利用してくれることで成り立っています。福祉事業所はサービス提供した分だけ行政に請求をあげます。サービス内容に応じて利用者さんから対価をいただきます。
しかし、残念なことに支援者の意識は、「支援をした」という実績を作るだけで、「利用者の満足」というところに到達していません。ゆえにふりかえりは、利用者さんが満足できたかどうかではなく、支援ができたかどうかで完結しています。
このお話は、対価としてお金をもらうということを意識するきっかけになりました。
2)教える人と学習者は対等である
インストラクショナルデザインにおいては、教える人が学習者を評価し、学習者が教える人を評価します。教える人は、学習者が最終的にできるようになったかどうかパフォーマンスを確認することで評価できます。逆に学習者は教える人のコースが面白いコースであったか、役に立ちそうだと思えたか、終了後に自信が持てたか、やって良かったと思えたかこの視点で評価ができます。これはARCS動機づけモデルといわれています。ゆえに、教える人と学習者は対等だと言えるのです。
このARCS動機づけモデルも支援内容や支援者を評価するのに役立ちそうです。
支援者は利用者さんやそのご家族から評価されることを嫌がります。利用者さんが支援内容に意見をすると、わがままだと言われたり、あの人は人によって言うことを変えるからと言われることがあります。またご家族からの申し出に対しても同様です。あの親は口うるさいと思ってしまいます。なぜなら、支援者は良いことをしていると思っているので、自分の良い行動を否定されたと思ってしまうからです。
利用者さんと支援者は対等です。これは大原則です。しかし、本当に対等になるまでにはまだ距離があるようです。福祉サービスに評価の意識を導入することを進めていかなければいけません。
3)最後に
学習者を評価するには、転移できたかどうかで判断することができます。今回でいえば、「教える技術」を「支える技術」に転移できたかどうかで私が学習できたかどうかがわかります。来年の「教える技術」までに実践で活かし、報告できるようにすることを目標にして今回のコースのまとめとします。
ありがとうございました。
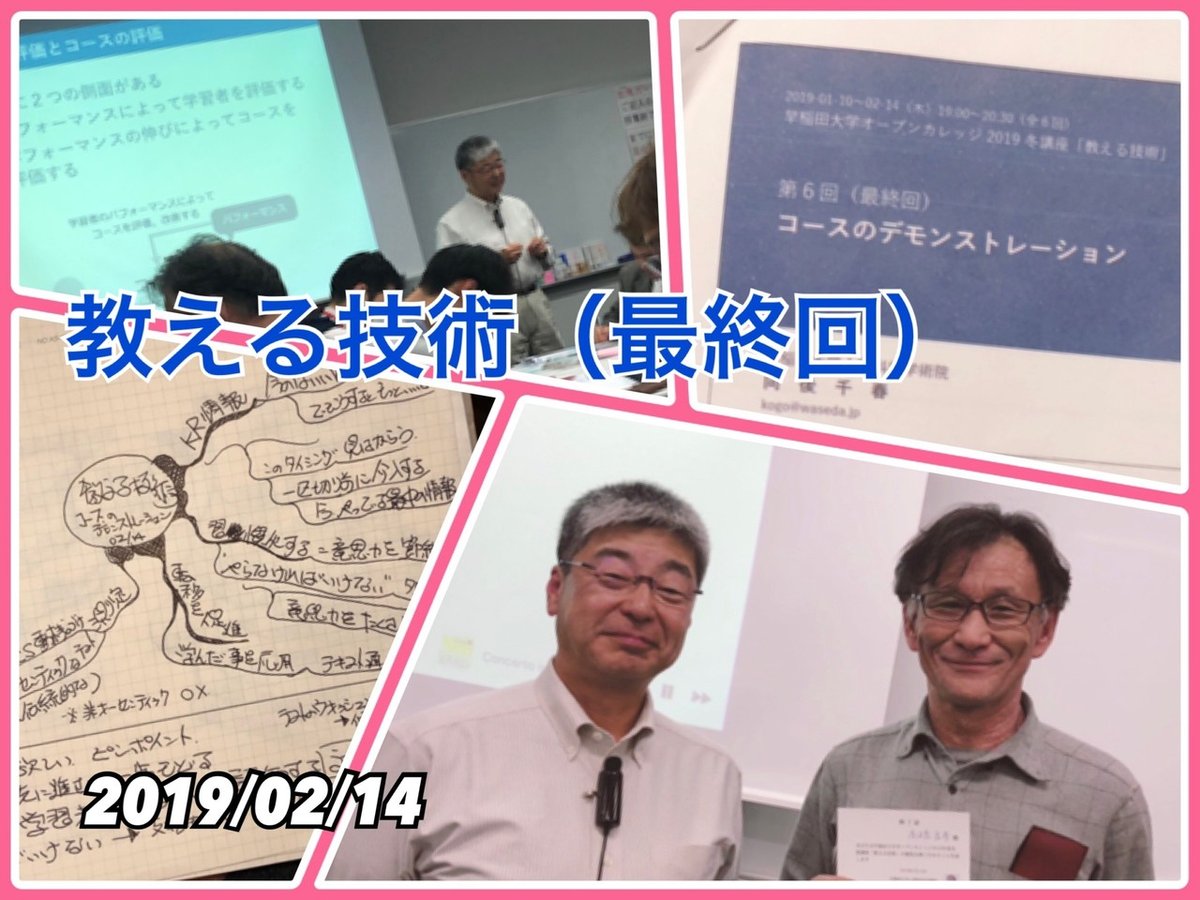
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
