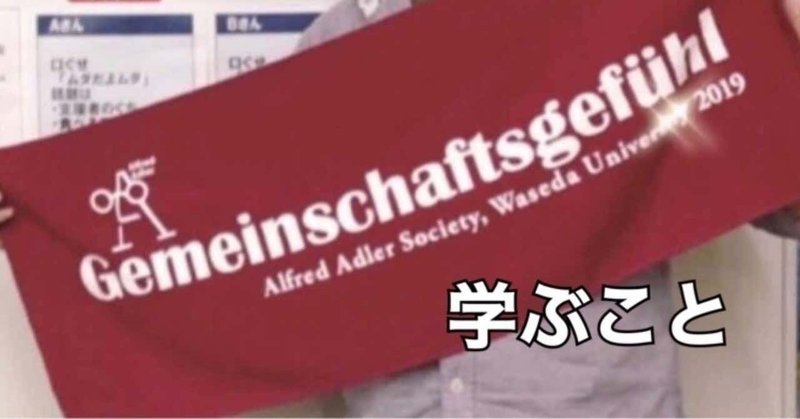
間違いを繰り返す人とのかかわり方いろいろ(アドラー心理学実践講座 第7回目より) ②
10月03日(木)から早稲田大学のエクステンションセンター中野校で向後千春先生の「アドラー心理学実践講座」が始まりました。今回もそこで学んだことを障がいのある方への支援場面でどのように活用できるか実践報告を交えて考えていきます。
11月14日、第7回目のテーマは「感じられたマイナスとその反応」でした。今日は、昨日に続き、質問会議に挙がった質問に関連したことを書きます。
質問は、職場で間違いを繰り返す同僚、その同僚は記憶に留めることなく初めて間違えたかのように平然と間違いを繰り返す、そんな同僚についての対応についてでした。
向後先生からはアドラー派の解釈として、この同僚には間違える目的がある。それは間違えることによって、指摘してもらえる、相手をしてもらえると思っているのではないかという、ねじれた承認欲求でした。
障がいのある人の支援において、同様のことを感じたことがあります。それは支援者のかかわり方が、利用者の不適切な行為を強化しているのではないかということです。支援者が、その行動は問題だと思い過度にかかわることによって繰り返されているように思います。たとえば、何十年も同じ方法で注意されている利用者がいます。何十年も同じ方法で注意しているのに変わらないということは、その注意の仕方は効果がなく、かえって目的を達成していると言えます。
利用者の中には、他害行為と言って他者を攻撃してしまう人がいます。私がまだ現場にいた頃、ある一人の利用者を受け入れました。そのとき、その人が在籍していた養護学校の先生から暴れたときの押さえ方というのを教えられました。当時の私は、その利用者が暴れると教えられたとおりに押さえつけていました。そのかかわりはいつまでも続きました。その利用者にとっては私は格好の遊び相手だったのかもしれません。
また、ある男性利用者は、他人の家のピンポンを押してしまいます。その人がガイドヘルパーと外出するときの様子を見ていたら、ガイドヘルパーがしっかり腕を組んで出かけて行きました。その利用者が急に走り出してピンポン押さないためです。そのガイドヘルパーさんはかわいい若い女性のヘルパーでした。その様子を見ているとうらやましく思います。それも、アドラーの目的論で考えると、若くてかわいい女性ヘルパーにかまってもらうために突発的な行動に出ている言えます。ただ残念なことは、ガイドヘルパーはいつも同じとは限りません。別の日は、ご年配の男性ヘルパーが同じように腕を組んでいました。
いっけん同じに見える行動にもそれぞれ目的があります。その目的を考えず、ただ注意ばかりしているとその行動が強化されたり、利用者との関係が悪くなります。
バスの中で降車ボタンを押したがる人がいます。一般的には、目的地ではないところで降車ボタンを押すとイタズラや問題行動として注意されます。あるときガイドヘルパーがその対応で困っていたので、降車ボタンを押したらバスを降りたらいかがですか、と提案をしました。それを試したところ、その利用者はそれから30分歩いて、目的まで行きました。もしかしたら本当にバスを降りたかったのかもしれません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
