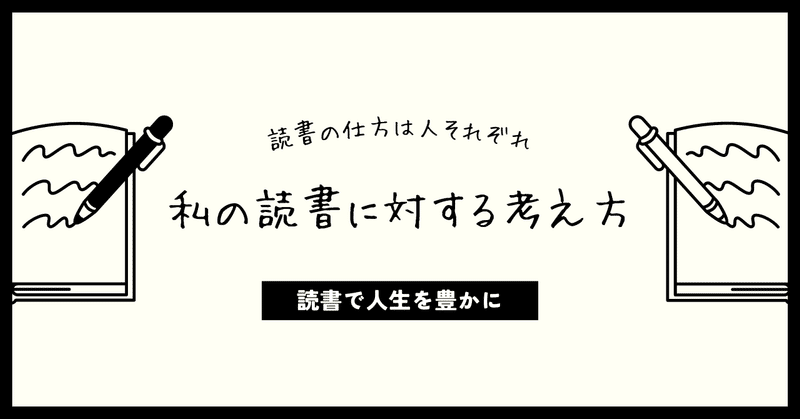
私の読書に対する考え方を書いてみます。
ども、スマレジの新垣です。
スマレジは、高機能かつアプリで自由に機能を拡張できるクラウドPOSレジです。
本日は、私の読書に対する考え方を述べつつ、最近読んだ本について簡単にまとめてみます。
読書は読み終えるのが目的ではなく、人生や仕事に役立てるのが目的
これが、私の読書に対する考え方です。
なぜこの考え方に行きついたのか?それは、20代までは本を読むのが苦手だったからです。読み終えることができない自分はダメだと思い込んでいましたが、読み終えるのが目的ではなく、仕事や人生に活かすのが読書をする目的であると定義したとたんに、本が読めるようになりました。
私の本の読み方
数冊同時進行で読むのが私の読み方です。
いま同時に読んでいるのは、
営業関係:4冊
思考関係:3冊
分析関係:1冊
人種問題:1冊
小説:1冊
エッセイ:2冊
です。
必ずしも通読(最後まで読む)するのではなく、必要な情報を摘まみながら読み進めています。進めるうちに通読する必要がありそうな本は通読し、必要がなさそうな本は、読み残しのままいったん本棚にしまいます。でもって、半年くらい読み返さなかったら廃棄します。古本屋に売ることもありますが、読み返さない本はほぼ廃棄です。なぜなら、めっちゃ本に書き込みますので。
※さすがに小説は通読します。
同じカテゴリーの本には、同じようなことが書かれていたりします。照らし合わせながら読むことで、自分ならどうするかを思考を深めることに役立ったりします。
年中こんな読み方をしてます。ので、「新垣さんって年に何冊くらい本を読みますか?」と聞かれると、めっちゃ返答に困ります。最後まで読み終える本と、つまみ読みだけで終わる本もありますので。
読書は読み終えるのが目的ではなく、人生や仕事に役立てるのが目的ですからね。
最近読んだ本は(摘まみ読みして、面白かったので最後まで読み終えた本たちです)
↓
「場当たり的」が会社を潰す 著者:北澤幸太郎
「場当たり的」の反対は「戦略的」です。
この本は「戦略的に考えられる組織をつくるには」という問いに対して、著者の考え方がまとめられています。
会社は「強い思い」を持つ必要があり、「強い思い」とはすなわち「大きな目標」であると書かれています。会社内のすべての行動は、この大目標を実現するためのものでなければならないと書かれています。
ビジネスパーソンなら読んで損はない本です。特に、リーダー以上の方にお勧めです。戦略がなく場当たり的になっていないか?そんな不安を感じているなら、読んでみてください。
ビジネスマンのための「読書力」養成講座 著者:小宮一慶
これは、読み返した本です。
2008年の本ですが、何度か読み返しています。私はこの本を読んで人生が変わりました。人生が変わるなんて大袈裟な!と思いでしょうか?
具体的に言うと「私はこの本を読んで、本の読み方を変えました」それにより「人生が変わりました」となります。
以前、このnoteでも「私は、良い本だ!と思った本は読み返す前提で惜しげもなくラインを引きます。ガンガン書き込みます。なので、読み返すが楽です。ラインを引いた箇所を読み返せば、容易に内容を思い出すことができますので。
速読についてもこの本で学びました。この本では「速読とは求める情報を素早く得る読み方」とされています。これに超ガッテンいきまして。それ以来、情報を素早く得るために速読を実践しています。
読書を仕事につなげる技術 著者:山口周
これは、最近読んだのではないですが、私の読書方法にかなり影響を与えた本ということでピックアップしました。Kindleで読んだので、古本屋で出会えば購入しようと思いつつも、まだ購入はできてない本です。
恐縮なのですが、私は以前から、この本に書かれている読み方とほぼ同じ読み方をしていました。この読書法にたどり着いたのは、先にあげた「ビジネスマンのための「読書力」養成講座なのですが。
読書力養成講座と合わせてこの本も読むことで、ビジネスパーソンとしての読書法が劇的に変わりますよ。読書が苦手である、あるいは、読書してもなかなか仕事に活かせないという方には、この2冊は超オススメ本です。
アイデアのつくり方 著者:ジェームス・W・ヤング
1988年の本です。
この本はもはや古典といってもいいかもしれません。
本のタイトルに「つくり方」とありますが、具体的な作り方が書いてあったとは思っていません。私は、アイデアを形にするための下準備について書かれていると解釈しました。
著者が広告畑を歩いた方なため、広告を作るという観点で書かれている箇所があるのと、全体的に翻訳が解りにくいなーという印象があり、少し読みにくい本です。
ある程度の社会経験をつけた方なら解釈できると思いますが、高校生や大学入りたての若者が読むとチンプンカンプンかもしれません。あと、最近の本がいかに読みやすく書かれているかを再認識できます。今、1983年に書かれた別の本も読んでいますが、その本もじっくり読まないと内容を理解するのに時間がかかります。が、それが古い本の良いところだと思っています。
最近のビジネス本は「○○する方法」のように、すぐに答えを教えるような本が多く、どれも似たり寄ったりな内容だと思うのは私だけでしょうか?
モノを売るバカ ~売れない時代の新しい商品の売り方~ 著者:川上徹也
古本屋で100円で見つけました。
著者曰く「商品を売って飛ぶように売れる時代はとっくに終わった。普通では売れない時代だからこそ、新しい売り方が必要だ」と説き、商品に人を加えることで、物語で売る方法が書かれています。事例が多く取り上げれ荒れており、示唆多い本でした。
読書っていいですね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
