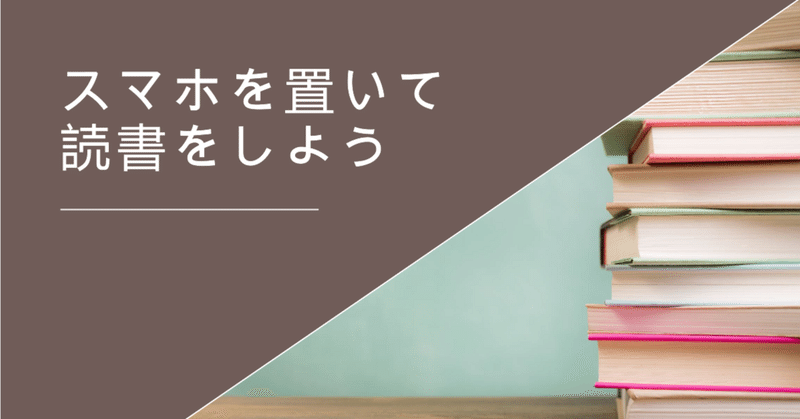
【読書】「おっ!」を共有します。(読んだ本:数学的に考える力をつける本)
ども、スマレジの新垣です。
スマレジは、高機能かつアプリで自由に機能を拡張できるクラウドPOSレジです。
私は人並みに本を読みます。
最近は本屋に行くときは、いつも立ち寄りがちなビジネス書や新書コーナーとは違うコーナーに立ち寄ります。哲学、心理学、化学、教育、児童書、これらのコーナーに行くと、普段は読まないような本と出合えるから楽しいです。
いつからでしょうか、本が好きになったのは…
実はわたくし、高校2年ごろまでは、ほとんど本を読まずに過ごしてきていました。サッカー一筋です。本も読まず、授業もろくに聞かず、部活をしに学校に行っているような生活でした。
がしかし、
とある友人から、シドニィ・シェルダンの「真夜中は別の顔」を薦められてから本を読むことができるようになり、これまで多くの本を読んできました。
ビジネス書:8割 小説やドキュメント:2割
こんな感じで読んで気ました。
この割合は今でも変わらないと思いますが、ビジネス書8割の中身が変わってきたと思っています。というのも、毎回新しいビジネス書を読むかというとそうではなく、気に入ったビジネス書を繰り返し読むようになっています。多くのビジネス書は、ほぼ同じことが書いていることに気づき、それからは、自分自身が考える普遍的な内容が書かれている本をストックするようになりました。
よって、
ビジネス書:8割 小説やドキュメント:2割
この割合は、読んでいる時間の割合であり、冊数の割合ではありません。
前置きが長くなりましたが、最近読んだ本で「おっ!」と思った箇所を共有したいと思います。
読んだのは「この本」
↓
数学的に考える力をつける本 著者:深沢真太郎
本のタイトルに「数学的」と書かれていますが、この本の中で計算については、ほとんど書かれていません。あくまでも数学的に考えることを重点的に書かれています。具体的に言うと「本質をつかむ力」「考えをまとめる力」「説明上手になる」ことなどが書かれています。
たまたま本屋で目に入り、立ち読みしたら、私自身がよく使う「なぜなら」「一方で」「よって」「ゆえに」などのコトバを使て説明することを「数学的に考える」と定義しているようで、なんか面白そうだなーと思い購入しました。で、結果、まぁまぁ面白かったです。
帰納法や演繹法についても書かれているのですが、最後のページのほうにあた帰納法を使ったフレーズが「わかるー」と超納得、超共感だったのでシェア致します。

この「納得」という箇所について
私的には「納得≒疑問のない状態」とも思っています。
ビジネスや仕事をする上で、まったく疑問のない状態ってあまりないと思いますので、疑問の少ない状態といってもよいかもです。
つまり、
納得とは、疑問が極力少ない状態とも言い換えることができると思います。
数字を使って説明すれば、疑問が少ない状態を作ることができ、ゆえに人は納得して動く。こんな感じでもあるかと思います。
例えば①
過去のデータを時系列で分析した結果、○○率を5%伸ばせば、売上が15%伸びることが解っている。だが、今期の○○率の伸びは3%にとどまっており、目標の15%増に届いていない。○○率をあと2%伸ばすために、あらたに○○○施策を立案し、来月からアクションを起こしてくれ!
→ はい!(納得のイエス)
例えば②
なんかわからんけど、売上を伸ばす目標に対して伸びが悪いので、○○○施策を考えたので、来月からやってみてください。
→ は・・・はい(納得してないイエス)
①は納得、②は納得していない(疑問満載)
こんなことって、案外あるよねーって思いました。
数字は納得をつくる。
納得できるから人は動く。
ゆえに数字で人は動く。
いいこと書いてるなーっと思った本でした。
ビジネス書以外で、教育関係の本を読んでてで気づいたことに関しても書こうと思いましたが、すでに1,500文字も書いてしまっているので、またの機会に致します。
ではまた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
